|
| ◆ 側款(そっかん)(作者のサイン等) |
側款の拓本は古典の篆刻作品のページにも多数収録しました。 古典の篆刻(てんこく)印の側面(右手で印を押すときに、 親指があたる面)には、作者のサインや制作年月、 誰のため或いは何のためにはんこを刻したのか、 はたまた”窓の外には雨が降っていた”とか ”暑いので汗をかいた”等、作者の感想が刻されています。 側款だけでも楽しめるものです。 中にはよっぽど言いたい事があるのか、 一面だけでは足りず三面四面にもわたっている印鑑も有ります。 ちょっと古典のはんこの側款を見てみましょう。 1、誰が刻したのか ・姓、名または号のみ。 ・それらに”作”等の文字を加えたもの。 例えば ・○○作 ・○○刻 ・○○製 ・○○制 ・○○篆 等。 ちょっと変わったところでは・○○刊・○○治 ・年月日を数字で記したもの。 ・干支で記したもの。 ・四季を記したもの。他 例えば、二千一年四月 ・平成十三年春 ・辛巳端午 (五月五日)等。 拡大 参考側款画像(拓本) 趙 之謙 刻。(ちょうしけん・号:悲あん、冷君、無悶など)1829-1884。  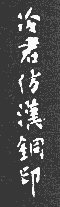 均初先一年至其年八月 冷君 左は双入刀法(一画の両面に刀を入れて刻す)、 つまりあらかじめ書かれた文字を忠実に刻したもの。 それに対して右は単入刀法(一画の片面に刀を入れて刻す)によるもの。 単入刀法は布字をせず、直接石に切り込んでいきます。 店主もこの刀法に依ります。 呉 昌石 刻。(ごしょうせき・字:蒼石、号:缶廬、苦鉄など)1844-1927。 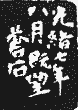 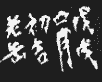 光緒七年八月既望(十六日)蒼石 戊戌四月初吉(ついたち)老缶 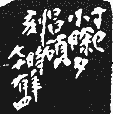 丁巳小除(二十四日)夕(夜)昌碩刻時年七十有四 |
