|

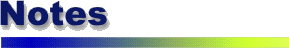
父のいない正月 2004年1月1日
沢木耕太郎の「無名」(幻冬社)を読んだ。
実は昨年(2003年)の冬、私も静かに父の最期を看取った。その2ヶ月前に転倒して腰椎を骨折し、「これで肺炎でもなったら最後かもしれないので覚悟はしとけよ」と私に言い聞かせるように話していたのが現実になってしまった。
父は97 歳という高齢にもかかわらず、西上州の地方都市で一人暮らしをしていた。私が毎週土曜日に東京から関越道を利用して帰ると、父は一緒に外出し、昼飯にてんぷらや鰻、寿司などを食べ、スーパーで買い物をして、しめくくりに喫茶店でコーヒーを飲んで帰るのが週末の日課であった。
こういう生活がここ5年くらい続き、その間には胃炎や風邪で入退院したり、一人で老人保健施設に入ったりして、必ずしも満足はしていなかったみたいだが、意気軒昂に暮らしていた。
その父が新年になると、町にあるお諏訪様と浅間様という二つの神社に初詣に行くのが恒例であった。もう足もそんなに丈夫ではないのに、人前ではステッキを持たずに、カシミアのオーバーを着て、二十段くらいの石段を登り、参拝するのである。
私は小さかった頃父と一緒に初詣に行った記憶がないし、家族も一緒に行ったことはなかったはずである。父は決して神仏を信じているわけではないのだが、おそらく年中行事の一つの決まりごととして一人でこのように欠かさず行っていたのだと思う。
ところが昨年の正月は父は骨折で動けなくなり、私が代わって参拝をしてきた。晩年は一緒に行くことが多かったのでもう父と一緒はないのかとその時思った。
父が亡くなって初めて迎える正月である。東京にいる限りはいつもの正月と変わりはない。お雑煮とおせちを食べて、静かに一日が終わる。父も近くのスーパーでおせち料理を求め、よく一人で正月を祝っていた。孫たちにお年玉を用意し、「おじいちゃん」らしさを見せてはいたが、一方では皆に早く引き上げてもらって静かな正月を送ろうともしていたのだ。かってのそんな姿を思い浮かべながら父のいない故郷の家で正月のひと時を過ごそうと思っている。
2004年1月1日 oggi


|