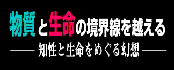
E.T.Shimizu
第六章 宇宙生命体
−− SETI幻想 <人類は孤独か?> −−
生命の本質を考えてくると「人工生命(AL)」を提唱していた、クリス.
G.ラングトンの言うように「地球上の生命は、一例にすぎない」という主
張が真実味を帯びてきます。
では、地球外にいるかも知れない生命体を検討してみましょう。
 SETIとは?
SETIとは?
今回は、少々地球を飛び出して、宇宙の彼方の生命に思いを馳せてみたい
と思います。
 SETIとは、Search for ExtraTerrestrial Intelligence の略です。
つまり「地球外文明探索」です。UFOの観測もその一つといえるかもしれ
ませんが、現在の方法は主として、異星の知的生命体から宇宙に送信されて
いるかもしれない、なんらかの意図を含んだ電波信号を想定して、これを受
信解読しようとするものです。
SETIとは、Search for ExtraTerrestrial Intelligence の略です。
つまり「地球外文明探索」です。UFOの観測もその一つといえるかもしれ
ませんが、現在の方法は主として、異星の知的生命体から宇宙に送信されて
いるかもしれない、なんらかの意図を含んだ電波信号を想定して、これを受
信解読しようとするものです。
地球上に生命が発生したメカニズムを考えると、地球に似た天体上でも、
やはり生命が発生しているのではないかと考えることは自然です。
1951年、著名な宇宙物理学者、オットー・ストルーブはコーネル大の
講義で、銀河系の恒星は半数ほどが惑星を持っており、そのいくつかには、
生命が存在するであろうと述べました。これを受講していた、当時21才の
電子工学専攻生、フランク・ドレーク(Frank Drake)は、それがかねて自分の考えていた予
想とピタリだったので、大いに触発を受けたそうです。
その後、天文学も修めたドレークは、1958年 WestVirginia に新設
された国立電波天文台(NRAO:National Radio Astoronomy Observatory)
に籍を置きました。
そして、1960年、彼の手による最初のSETI、「オズマ計画」が開
始されたのです。といっても、電波望遠鏡を使って信号を調べた期間は2週
間、探索された恒星は、くじら座のτとエリダヌス座のεの2つだけでした。
結果は、1回の誤警報以外、何も発見されなかったのですが、こういうプ
ロジェクトが動き始めたことが各方面に衝撃を与え、新たなプロジェクトの
起爆剤となっていったようです。
 異星文明はいくつあるか
異星文明はいくつあるか
これは、まったくの謎ですが、1961年、オズマ計画の翌年開かれた、
第1回国際SETI会議で、ドレークは以下のような推定式を示しています。
N = N* x fp x ne x fl x fi x fc x fL
ここで、N は異星文明の数です。また、N* を含む7つの変数は以下の
ようになっています。
ドレークの概念 C.セーガンの話
N* : 銀河系内の恒星の数 1千億 4千億
fp : その内、惑星を持つ率 1/5〜1/2 1/4
ne : 生命に適した惑星の数 1〜5 2
fl : 生命発生率 0〜1 1/2
fi : 文明発生率 0〜1 1/10
fc : 通信手段と必要性を持つ率 1/10〜1/5 1/10
fL : 文明寿命と惑星寿命の比 1/10の8乗 1/10の8乗
〜1/10の6乗 又は1/100
この式で、ドレークはNの数値を具体的に述べてはいませんが、近年、亡く
なったコーネル大のカール・セーガン博士は、N=10(文明寿命が戦争や環
境汚染で自己破壊することが必然的である場合)と、N=1千万(文明が危機
を乗り越える自浄能力を持っていて、それに成功する文明が1%はある場合)
の2つの数値を例示しています。
しかし、銀河系内で、N=10では少なすぎて、まず絶対に相互認識を持ち
得ないと言ってよいでしょう。ということは、もし地球外の文明が1つでも存
在することが確認されれば、それはセーガンの後者の仮定である「生命体は危
機克服能力を持つ」ことが証明されるとも考えられます。
 距離の壁
距離の壁
ここで、現在の我々が探索できる範囲を考えてみましょう。
銀河系宇宙は直径20万光年ほどの円盤状をなしていると言われています。
しかし、地球から観測する異文明の電波は、新星爆発時に発生するような、巨
大電磁波ではなく、一般信号電波ですから、その減衰を考えると検知可能な発
生源は遠くても、100光年のオーダーと考えられます。
 そこで、体積比を考えて見ます。例えば銀河系の直径を20万光年、観測期
待範囲の直径を200光年とすると、面積比は1/百万です。次に銀河の厚さ
の代表値を1万光年とし、観測領域の厚さをやはり200光年とすると、厚さ
の比率は、1/50です。すると体積比は、1/5千万 となり仮に、N=
1千万だったとしても、この観測領域に異文明が入る確率は低いと言えます。
そこで、体積比を考えて見ます。例えば銀河系の直径を20万光年、観測期
待範囲の直径を200光年とすると、面積比は1/百万です。次に銀河の厚さ
の代表値を1万光年とし、観測領域の厚さをやはり200光年とすると、厚さ
の比率は、1/50です。すると体積比は、1/5千万 となり仮に、N=
1千万だったとしても、この観測領域に異文明が入る確率は低いと言えます。
ということは、現在の技術では、異星からの信号が何も観測されなくても、
まだ、絶望的になることはありません。
 でもやはり、知的生命体はいるだろう
でもやはり、知的生命体はいるだろう
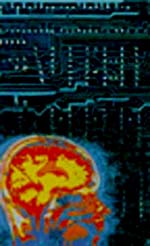 ここで、翻って地球に生命が誕生した経緯を考えてみましょう。
ここで、翻って地球に生命が誕生した経緯を考えてみましょう。
いままでの考察をさっと振り返ってみます。
まず生物の基になる素材ですが、分子結合にはエネルギーレベルの大小が
あるので、放置しておくとなるべく低エネルギーレベルの結合に遷移していこ
うとします。
例えば酸素は原子単独でいるよりも、2個くっついて、O2 となったほう
が安定だし、そこに水素があれば、これとくっついて、H2Oとなりたがるわ
けです。
では、どこまでくっつけば一番安定なのかというと、実は単純な法則はなさ
そうです。いたるところにエネルギーの盆地があるので、その底に遷移してい
こうとするのはわかりますが、それが全盆地中の最低である保証はないわけで
す。
やがてそれらを素材にして、細胞という生命体の基本構造物ができてくるわ
けですが、その作りは、単に複雑な有機構造をしているほうが、エネルギーレ
ベルが低いから盆地の底に遷移していった結果できた、というだけでなく、時
にその進化においては、より低い盆地を知っているみたいに、エネルギーの峠
越えをすることまであるのです。
このメカニズムは、非生命体の分子を律するエネルギー則とは異なるもので
すが、無理に例えれば、ある特定条件下で、エネルギー系が発振を起こした時
と似ています。その限りにおいては、奇跡的な現象とは思われません。
従って惑星など、中心となる恒星からエネルギーがいつも得られる環境で、
生命が発生する確率は、自然界に自励発振系が発生する程度(例えば間欠泉が
自然に形造られる程度)はあるだろうと考えられます。これはかなり高い確率
と言えます
つまり、生命誕生の確率(上記式のfi、fl)は比較的高いけれど、それら
が相互に認知しあえる確率のほうがずっと低いというモデルが描けます。
 異星からの信号が発見される時
異星からの信号が発見される時
しかし、確率が低いといっても、0ではありません。 0でなければ運命
のいたずらというものは、奇跡的な所産を見せることもあるものです。
地球外知的生命体からの信号が発見されるケースは、多分、それが地球人宛
に送信され、ちょうどよくそれが受信される、というような形ではないと思わ
れます。
ありそうな発見のケースのついて想像してみると、次のようになるかも知れ
ません。
*************************
20XX年、COBE−4というセンサー衛星を使って、宇宙背景輻射の精
密マップを作成していた、エリー・アロウェイ博士は、信号に混じったノイズ
に悩まされていた。彼女はこの性質を把握するため、超高速、超長周期、超高
分解能のフーリエ変換装置でノイズの分析をしたが、そのスペクトラムが一定
せず、ノイズ源の特徴も判定できなかった。
彼女は、このスペクトラムが分散しているため、ホワイトノイズという、も
っとも平凡なノイズだと考えていた。ある時、彼女は念のため、その分散性が
完全なものかどうかを調べてみた。
だが、結果は完全ではなかった。非周期性の超短時間パルス列の信号が、ホ
ワイトノイズとよく似たスペクトラムを発していたのである。非周期性とはい
いながら、そのパルス間隔は数十分から、数時間に及ぶものであった。従って
測定時には、直観的に把握できなかったのである。
その間隔時間は、ある数列に乗っていることから、頻度分布を取ることがで
きた。その分布形は、自然画像を構成する画素の隣接輝度差分の分布に等しか
った。つまり、パルス間隔を使って、画像が伝送されていたのである。
彼女は記録してあったノイズ信号を使って、伝送画像を再現してみた。
そこには、地球外知的生命体連合が発行する、日常的報道画像が鮮明に現れ
たのであった。
− 第六章 完 −
約半年間にわたって連載してきました、「物質と生命の境界線を越える −知性と生命をめぐる幻想−」も今回をもって終了することとなりました。 御読みいただきました皆さまには、篤く御礼申し上げます。
生命体を情報処理主体の一種として捉えようという視点は、近年、急速に高まっていることは周知のことと思われます。いままでSF的な仮説と思われていることが、すぐに通説となっていくことも、この世界では珍しくないようです。生命体の一員である我々も、柔軟な発想でこの世界を考究しながら新たな自画像を創っていくことを迫られているのかも知れません。
E.T.Shimizu
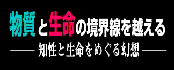
 SETIとは、Search for ExtraTerrestrial Intelligence の略です。
つまり「地球外文明探索」です。UFOの観測もその一つといえるかもしれ
ませんが、現在の方法は主として、異星の知的生命体から宇宙に送信されて
いるかもしれない、なんらかの意図を含んだ電波信号を想定して、これを受
信解読しようとするものです。
SETIとは、Search for ExtraTerrestrial Intelligence の略です。
つまり「地球外文明探索」です。UFOの観測もその一つといえるかもしれ
ませんが、現在の方法は主として、異星の知的生命体から宇宙に送信されて
いるかもしれない、なんらかの意図を含んだ電波信号を想定して、これを受
信解読しようとするものです。 そこで、体積比を考えて見ます。例えば銀河系の直径を20万光年、観測期
待範囲の直径を200光年とすると、面積比は1/百万です。次に銀河の厚さ
の代表値を1万光年とし、観測領域の厚さをやはり200光年とすると、厚さ
の比率は、1/50です。すると体積比は、1/5千万 となり仮に、N=
1千万だったとしても、この観測領域に異文明が入る確率は低いと言えます。
そこで、体積比を考えて見ます。例えば銀河系の直径を20万光年、観測期
待範囲の直径を200光年とすると、面積比は1/百万です。次に銀河の厚さ
の代表値を1万光年とし、観測領域の厚さをやはり200光年とすると、厚さ
の比率は、1/50です。すると体積比は、1/5千万 となり仮に、N=
1千万だったとしても、この観測領域に異文明が入る確率は低いと言えます。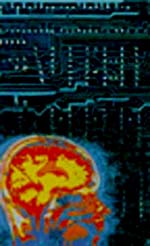 ここで、翻って地球に生命が誕生した経緯を考えてみましょう。
ここで、翻って地球に生命が誕生した経緯を考えてみましょう。