世阿弥の謡曲にうたわれる通り、富山県との県境にある。
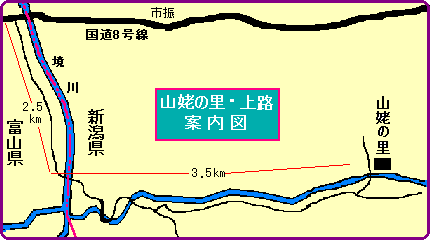
渡り、川沿いの道を数キロ登って、再び、新潟県側に戻る橋を渡らなければ
ならない。一番近い集落からも約3.5キロ離れている。
細く曲がりくねった道を登って行き、心細くなった頃、山の懐に囲まれた小さ
い集落が見えて来る。・・・・・ 杉を育て、炭を焼いて生計を立てていたが、
今は農業が中心だ。昭和初期まで、250〜300人が暮らしていたと言う
上路も、今では、29世帯、人口約52人。住民の六割を超える人が、65歳
以上という高齢者と過疎の集落である。
伝説の地にふさわしく、集落の周辺には、「山姥が日向ぼっこをしていたと
言う岩」や、「山姥神社」など山姥にまつわる物が随所に残る。
山姥は、一般に伝わる昔話では、道に迷った旅人を食べてしまう「鬼女」で
ある事が多い。・・・ 白髪を振り乱し、顔色は真っ赤な鬼瓦のようで、口は
耳元まで裂け、赤い舌を出した化け物として描かれている。
「上路の山姥は村人にとって優しい、ありがたい存在だった!」
そう話すのは、山姥伝説を調べている 元公民館長の上原さん、
地元に伝わる言い伝えでは、上路に居を定めた山姥は、人を騙したり迫害
したりせず、日向ぼっこをしたり、里の人に踊りや機織を教え、貧しい人達
には金を与えたと言う。
「山姥神社を信奉して いた庄屋の娘が青海の回船問屋に嫁いだところ、
その店は瞬く間に商売繁盛になった」と言う話が江戸時代から伝わる。
明治時代末期には、「材木商の男が、山姥神社近くの友人宅で昼寝を
していたら、夢の中に山姥が現れ、金銀財宝を授けられた。・・・ 男は
その後、富山まで商売を広げる大商人となった」と言う噂も出たと言う。
「山姥さま」は、地元では、金儲け ・商売繁盛の神様となっている。
年に二回、四月と十月の九日は「山姥さまの日」。
上路の人たちは農作業を休み、祠にお神酒やおはぎを供える。上路を離れ
た人たちも「お盆と山姥さまの日には戻って来る」という。帰省した人たちは
集まり、ささやかな懇親会を開く。
小さな里の人々は、今も、山姥さまでつながっている。・・・・・
人里離れた集落も、雪が消えると、「山姥の里を一目見よう」と言う民話
フアンや観光客で賑やかになり、人に優しい山姥さまも、少しずつ外の
世界に知られようとしている。