分布図を掲載しています。

地名と方言の分布(愛知県を例として)
方言の有り様は地名と同一であります。即ち「方言は一つの土地の言葉である。その土地の中から生まれ、少しずつ
変化しながら、各世代の日常生活を支えてきたものである。方言の中には、その土地で生活をした人達の共通した生
活体験が積み重ねられていると言ってもよい。」愛知県の方言 平成元年愛知県教育委員会刊
と述べています。
かって私が豊橋市内の或る企業に務めて居た時岡崎出身の同僚がいました。彼の方言の内次ぎの語彙が特に印象
に残っています。
標準語 どこへ行くのですか。 何をやっているのですか。
豊橋方言 何所へいくだん。 何をやっとるだん。
岡崎方言 何所へいかっせる。 何をやっとらっせる。
尾張方言 何所へ行きゃーす。 何をやっとりゃーす。
この語彙一つをとっても愛知県内に3っの方言帯の有る事が分かります。
愛知県教育委員会では上掲書(愛知県の方言)の中で非常に良く似た語彙として「書きますか」と言う語彙の方言の
分布図を掲載しています。

此処には三つの地域差が明確に提示されています。
即ち
1・カキャースに代表される尾張方言
2・カカッセルに代表される西三河方言(特に岡崎・豊田地域)
3・カクに代表される東三河方言
であります。之は又各々異なった文化圏が存在した事の証ででもあります。
この様な方言文化が地名に反映する事があるのでしょうか。?
|
尾張地域 |
西三河地域 |
東三河地域 |
合計 |
尾張地域 |
西三河地域 |
東三河地域 |
合計 |
||
|
1 |
三昧 |
22 |
1 |
2 |
25 |
88 |
4 |
8 |
100 |
|
2 |
大日 |
15 |
3 |
2 |
20 |
75 |
15 |
10 |
100 |
|
3 |
ナガレ |
47 |
15 |
1 |
63 |
74 |
24 |
2 |
100 |
|
4 |
イシズカ |
27 |
5 |
5 |
37 |
72 |
14 |
14 |
100 |
|
5 |
白山 |
15 |
4 |
2 |
21 |
71 |
19 |
10 |
100 |
|
6 |
ハチマン |
52 |
20 |
10 |
82 |
63 |
24 |
13 |
100 |
|
7 |
花ノ木 |
35 |
15 |
6 |
56 |
62 |
27 |
11 |
100 |
|
8 |
稲荷 |
30 |
25 |
8 |
63 |
56 |
40 |
14 |
100 |
|
9 |
熊野 |
16 |
11 |
2 |
29 |
55 |
38 |
7 |
100 |
|
10 |
薬師 |
24 |
16 |
4 |
44 |
55 |
36 |
9 |
100 |
|
11 |
観音 |
44 |
33 |
9 |
86 |
51 |
38 |
11 |
100 |
|
12 |
コウシン |
11 |
10 |
2 |
23 |
48 |
43 |
9 |
100 |
|
13 |
シャグチ |
16 |
13 |
6 |
35 |
46 |
37 |
17 |
100 |
|
14 |
地蔵 |
46 |
46 |
11 |
103 |
45 |
45 |
10 |
100 |
|
15 |
十王 |
9 |
6 |
5 |
20 |
45 |
30 |
25 |
100 |
|
16 |
若宮 |
15 |
6 |
13 |
34 |
44 |
18 |
38 |
100 |
|
17 |
平均 |
26.5 |
14.3125 |
5.5 |
46.313 |
59.375 |
28.25 |
13 |
100 |
|
18 |
ヤマノカミ |
29 |
62 |
9 |
100 |
29 |
62 |
9 |
100 |
|
19 |
山伏 |
5 |
9 |
4 |
18 |
28 |
50 |
22 |
100 |
|
20 |
花立て |
3 |
9 |
0 |
12 |
25 |
75 |
0 |
100 |
|
21 |
天白 |
7 |
15 |
6 |
28 |
25 |
54 |
21 |
100 |
|
22 |
サイノカミ |
6 |
10 |
12 |
28 |
21 |
36 |
43 |
100 |
|
23 |
キリヤマ |
3 |
12 |
2 |
17 |
18 |
71 |
11 |
100 |
|
24 |
イワクラ |
2 |
15 |
1 |
18 |
11 |
83 |
6 |
100 |
|
25 |
ハマイバ |
1 |
24 |
19 |
44 |
2 |
55 |
43 |
100 |
|
26 |
イシガミ |
0 |
17 |
9 |
26 |
0 |
65 |
35 |
100 |
|
27 |
ウトウ |
0 |
15 |
3 |
18 |
0 |
83 |
17 |
100 |
構成比に於ける相関係数
| 尾張地域対西三河地域 −0.64120 |
| 尾張地域対東三河地域 −0.48056 |
尾張地域対西三河、東三河夫々マイナスの相関関係にあり、西三河により顕著に見る事ができます。
この関係をグラフ化致しますと下図の様になります。
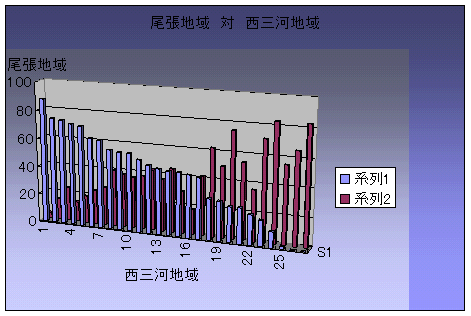
系列1 尾張地域 系列2 西三河地域
マイナス相関の典型的な図式を示しています。
特に土俗的信仰にもとずく地名と後代仏教・神道の延伸に伴い出現した地名との間にプラス・マイナス逆転の
様相が見てとれます。これはどう言う事なのでしょうか。
言うまでも無く当初は土俗的信仰にもとずく地名で覆われていました。後代流行神にもとずく地名や、仏教に
もとずく地名が異文化受容に寛容な平地部に展開したのではと考えています。
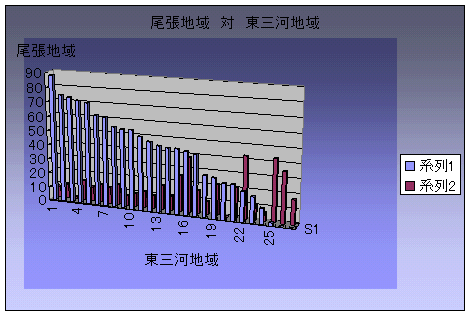
系列1 尾張地域 系列2 東三河地域
東三河地域と尾張地域の相関関係はうんと薄れて来ています。
西三河地域は東三河地域と尾張地域の緩衝地域で両文化の激突の地域で有った訳でありますが、
東三河地域は西三河地域の影に隠れ後代まで異文化の流入を拒んだ地域だったのではと考えます。
ここに尾張地域・西三河地域・東三河の三つの地域相が見てとれます。
地名は方言と同じ位地域相を反映しています。是非地名を一度考えて見てください。そこから何かが見えてきます。
最後に非常によく似た地名でありながら、その分布がまるっきり異なるイシガミ・イシズカと言う地名の分布地図を
お目にかけます。
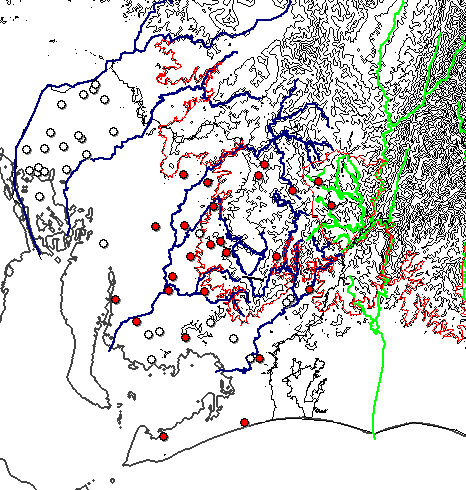
● イシガミ ● イシズカ
地名表&所在地標高
|
標高 |
標高 |
|||
|
石神 |
石塚 |
|||
|
1 |
津具村下津具字石神 |
690 |
豊田市大津 |
159 |
|
2 |
稲武町富永字石神 |
659 |
音羽町長沢字石塚 |
132 |
|
3 |
設楽町納倉字石神 |
655 |
新城市八束穂字石塚 |
79 |
|
4 |
足助町連谷字石神 |
589 |
新城市竹広字石塚 |
73 |
|
5 |
下山村東蘭字石神 |
487 |
犬山市楽田 |
45 |
|
6 |
東栄町古戸字石神 |
462 |
春日井市下原新田 |
41 |
|
7 |
下山村東大沼字石神 |
453 |
犬山市上野 |
37 |
|
8 |
下山村花沢字石神 |
395 |
犬山市高雄 |
35 |
|
9 |
鳳来町愛郷字石神 |
367 |
大府市共和 |
26 |
|
10 |
足助町野林字石神 |
306 |
江南市山尻 |
26 |
|
11 |
岡崎市駒立字石神 |
185 |
西尾市須美字石塚 |
23 |
|
12 |
藤岡町深見字石神 |
129 |
豊川市市田字石塚 |
18 |
|
13 |
鳳来町富栄字石神 |
127 |
幡豆町鳥羽 |
11 |
|
14 |
足助町広岡字石神 |
112 |
岩倉市大山寺 |
9 |
|
15 |
豊田市古瀬間字石神 |
88 |
一宮市西浅井 |
9 |
|
16 |
岡崎市蓬生字石神 |
78 |
小牧市熊之庄 |
9 |
|
17 |
豊橋市豊南字石神 |
61 |
西尾市善明字石塚 |
7 |
|
18 |
蒲郡市柏原字石神 |
49 |
熱田区馬場 |
7 |
|
19 |
豊田市本地字石神 |
40 |
熱田区田中 |
7 |
|
20 |
豊橋市玉川字石神 |
24 |
豊橋市東下条字石塚 |
5 |
|
21 |
岡崎市伊賀字石神 |
21 |
稲沢市井ノ口 |
5 |
|
22 |
岡崎市六ッ名字石神 |
12 |
稲沢市次郎丸 |
5 |
|
23 |
高浜市高浜字石神 |
11 |
西区比良 |
5 |
|
24 |
渥美町石神 |
7 |
稲沢市三宅 |
4 |
|
25 |
西尾市鶴城字石神 |
5 |
一宮市南高井 |
4 |
|
26 |
中川区中之郷 |
3 |
||
|
27 |
甚目寺町上萱津 |
3 |
||
|
28 |
祖父江町島本 |
2 |
||
|
29 |
佐織町勝幡 |
2 |
||
|
30 |
津島市蛭間 |
1 |
||
|
31 |
尾張部なし |
佐織町町方新田 |
1 |
|
|
32 |
佐織町町野 |
1 |
||
|
33 |
佐織町南河田 |
0 |
||
|
34 |
佐屋町大井 |
-1 |
||
|
平均 |
207.07 |
平均 |
23.06 |
標高差グラフ
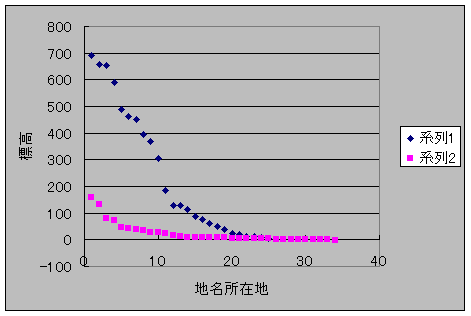
系列1 石神 系列2 石塚