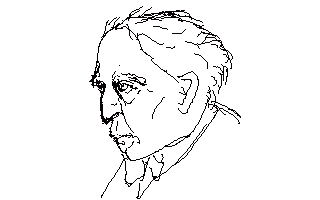 でそのあまりにも美しい天上のような世界は
でそのあまりにも美しい天上のような世界は1998年11月14日のはまり音楽
ブルックナー交響曲第9番とバッハ、管弦楽組曲第3番よりエア。
今週、というよりここ半年ほどはまりっぱなしなのが、ブルックナーの9番です。ブルックナーに親しむように
なったのはまだここ3年といったところなのですが、(それまで買ったのはははずれが多かったもので(^^;))
最初にブルックナーにはまったのは今となっては不満が多い(最新盤欲しいです)朝比奈・新日フィルの5番でした。
で、その後、主に5番と8番にはまっていたのですが、(最近は6,7番にはまり気味です。9番以外では。)今年、
個人的に色々あってやや落ち込んでいるときに、正に天上の深淵をのぞき込んでいるような
9番がしっくりきたのです。僕はギュンター・ヴァントの5番が好きだったので、ミュンヘンとの9番が出てすぐに
購入しました。(下図:ヴァント)
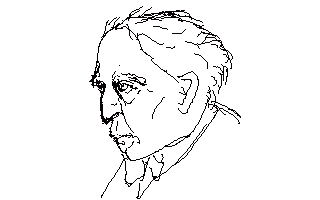 でそのあまりにも美しい天上のような世界は
でそのあまりにも美しい天上のような世界は
同時期に聞いたチェリビダッケのチャイコフスキーの5番とともに僕の心を鷲掴みにしました。(下図:チェリ)
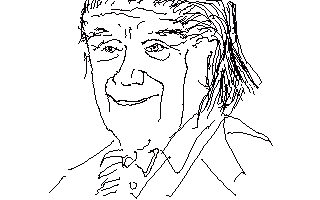 で、チェリビダッケのチクルスを買ってしまったのです。
で、チェリビダッケのチクルスを買ってしまったのです。
これも心の深淵をのぞかせるようなすばらしい演奏でした。で、kuniさんのブル9のページをのぞくようになり、
更にはまってシャイー(下図)、ムラヴィンスキー、カラヤン(下図)などを手に入れまいした。
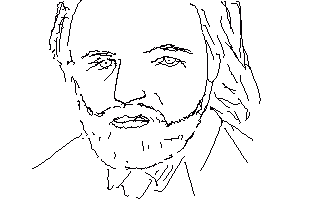
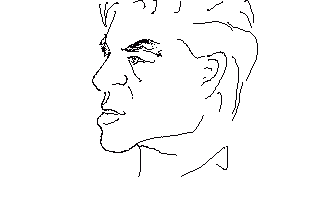
これもなかなか味のある面白い演奏でした。そしてついに世評高いヨッフム(でもミュンヘン)とシューリヒトを
入手したのです。朝比奈さん(下図)やアイヒホルンなどまだまだ魅力的な物はありそうですが。
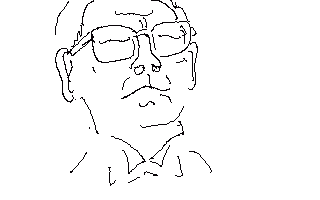
と、ここまでが前振りでそれぞれの特徴と違いについて簡単に書きますと、
シューリヒト・ヴィーン盤はよく、あっさりとした枯淡の風味とされていますが、弦が叫ばないと言うだけで、
壮絶な掛け合いは凄まじい物がありますし、管も良く鳴った実に良く歌い込んだ演奏です。
大きな流れもさることながら隅々までが主役となって掛け合う姿はなかなかのすごみがあります。
ヨッフム・ミュンヘン盤は正に正統的な演奏で、曲の姿を良く現しており、音楽の裏の意味よりも音そのものに
浸るに良い演奏です。(曲から恐ろしいすごみという物は引き出してないのですが)
しかしながら十分な歌もあり、決して近年の指揮者のような無機的な演奏というわけではありません。
この曲になじみの薄い人にとっては持っても良い道しるべとなるのではないでしょうか。
ヴァント・ミュンヘン盤はロマンティックにも見られたのですが、曲から凄まじいまでの美しい音と歌を
引き出した演奏です。正に天上世界を描き出した様なもので、ブルックナーと神の世界がくっきりと映し出されます。
ベルリンフィルとの今年の演奏の方がやや寂寥感に富み、響きもバランスされてないところが見受けられ、
違った味わいとなっているのは面白いものです。簡単に言うならば、ミュンヘン盤の方は天上的、
ベルリンの方は真実的、という感じでしょうか。
チェリビダッケ・ミュンヘン盤はとても遅い演奏で、気合い十分でないと聞けないです。(9番は全体に
そういうところがありますが。)寂寥感、諦念感では随一で、色即是空、諸行無常の、年老いた老人の
深い虚無感に満ちた心の世界が描かれてます。
シャイー・コンセルトヘボウ盤は対照的に明るい農村のようなブルックナーです。
うーん。もっと具体的に一つ一つの演奏について書きたいのですが、長くなるので、次回から機会があれば
徐々に書いていきたいと思います。(この項次回以降に続きます。)
と、ブルックナーばかり聞いていたのですが、最近ちょっと落ち込むことがありました。そのとき、色々聞いた上で
たどり着いたのがバッハの管弦楽組曲第3番から第3楽章、エアでした。いわゆるG線上のアリアです。
といってもG線上のアリアとして演奏された奴ではなくて、ジョン・エリオット・ガーディナー指揮
イングリッシュ・バロック・ソロイスツの古楽器演奏盤です。近代オーケストラやヴァイオリンソロでの演奏は
ややもすると甘ーーーーい陶酔的な歌になりがちですが(それはそれでいいですが)、これは全く逆で
清浄な、真っ白な透き通るような演奏です。時々古楽器演奏の癖のようなフレージングが入りますが、
かえって曲を良い意味で軽快にしています。僕は気分がとてもブルーの時にはこれを何回か繰り返して
再生にして聞いてます。そうするといらいらした気分や不安がいつの間にか消えていきます。
後はそのまま寝るもよし、同じCDに入っているバディヌリ聞いて元気になるもよし、といったところです。
今週のはまり音楽に戻る
音楽のページに戻る