 スパークプラグについて(その2)
スパークプラグについて(その2)4.スパークプラグの熱価
5.正しい熱価を選ばないと・・・
6.プラグを交換しましょう
WAO! WebShop TOPへ戻る 技術資料室TOPへ戻る
スパークプラグについて(その1)
1.はじめに
2.スパークプラグとは
3.スパークプラグの種類
 スパークプラグについて(その2)
スパークプラグについて(その2)
4.スパークプラグの熱価
5.正しい熱価を選ばないと・・・
6.プラグを交換しましょう
4.スパークプラグの熱価
「熱価」とは、スパークプラグが熱を発散する度合いを数字で表したものです。
エンジンが始動してガソリン混合気が正常に燃焼すると、エンジン内部は常に高温状態になります。エンジン内の温度は走行状態・走行環境・キャブレータの状態などに影響を受けますが、この熱を適切に外部に逃さないとスパークプラグの電極部に様々な影響が出てきます。
スパークプラグはそれ自身が火花を飛ばし且つエンジンの燃焼熱を受けるので温度が上昇します。
この熱は、電極部-->プラグ本体-->シリンダヘッドへ と拡散していきます。
この熱の発散度合いが「熱価」ですが、
*熱の発散度合いが小さいものを「低熱価型(焼け型)」
*熱の発散度合いが大きいものを「高熱価型(冷え型)」 といいます。
熱価の違うスパークプラグは下図のように「絶縁体(ガイシ)」の脚部の長さが違っており、この長さによって熱の伝達具合が変わってきます。
「低熱価型(焼け型)」絶縁体(ガイシ)の
脚部の長さが違うぞ
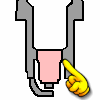
「高熱価型(冷え型)」(例) BR6ES ← ← BR7ES → → BR8ES 絶縁体(ガイシ)脚部が熱を受ける表面積が大きく、また熱の発散経路が長いので熱をためやすく、中心電極の温度が上がりやすい。
熱価の数字が小さい。絶縁体(ガイシ)脚部が熱を受ける表面積が小さく、熱の発散経路も短いので、熱を逃しやすい。中心電極の温度は上がりにくい。
熱価の数字が大きい。
つまりエンジンの燃焼状態(走り方やエンジンのコンディション等)に見合った熱価を選ぶ必要が出てきます。
冬場に極低速でしか乗らない走り方をする場合。
炎天下で高速走行をする場合。
マフラーやキャプレータを替えて燃焼状態が変わった場合。
原付車両をイジって走行速度域が変わった場合。
このような場合にはスパークプラグを選定する必要が出てきます(必ずしもではありません)。
5.正しい熱価を選ばないと・・・
スパークプラグには、使用可能な温度的制約があります。
下限の温度域を「自己清浄温度」(約450度)、
上限の温度域を「プレイグニション温度」(約900度)といいます。
スパークプラグは中心電極の温度がこの範囲にあってこそ正しく機能します。
実際のトラブル例でいうと、
中心電極の温度が約900度を越えてくると、電極部が熱源となって混合気が勝手に着火しちゃいます。これがプレイグニション(過早着火)です。
-->電極の焼損、絶縁体(ガイシ)の破損
---->ピストン・シリンダの破損
中心電極の温度が450度位から低くなると、燃料の不完全燃焼で発生するカーボンがプラグに付着し、このカーボンを伝わって高電圧が漏電(リーク)して失火の原因となります。しかし中心電極がこの温度以上になると、カーボンが焼き切れてプラグ表面が正常に戻ってきます。
この下限温度が自己清浄温度です。
-->プラグ電極の汚損、着火ミス
---->エンジン停止、始動困難等
(その1)夏のある日、カブが来ました。エンジンが止まりません。キーを抜いてもエンジンがかかりっぱなし! お客様自身はムチャクチャ心配&恐がってました。
プラグキャップを外してもエンジンが止まりません。そこでプラグレンチでプラグを少しずつ緩めていったところ、やっとエンジンが止まりました。小排気量車は注意。
(その2)ワンデイツーリングの帰路、まだ山中にてDT200がぶるるぅーと止まりました。その場の誰しもがエンジン焼きつきだーと思いました。仕方が無いので搬送トラックを出動して車両を回収してみると・・・。
プラグを外してみると先端が真っ黒。交換したら何の問題もなく治りました。
ただのプラグくすぶりです。「2サイクル、出かけるときは、忘れずに」 プラグの格言です。
6.プラグを交換しましょう
スパークプラグは(2サイクル車を除いて)意外と丈夫です。
しかし「意外」と丈夫なだけで、知らず知らずのうちに確実に消耗しています。
たかが数百円のために、楽しいツーリングを棒に振れますか?
念のために交換しましょう。
いま。すぐ。ほら。億劫がらずに。
プラグメーカーの推奨交換時期は、二輪車の場合3000キロから5000キロだそうです。
まあ推奨なので2倍に見積もっても(なぜ2倍だか自分でもわからんが)、
7000キロから8000キロ使えば、充分に元はとったと言えるのでは無いでしょうか。
いけないスパークプラグ いろいろ 良好なプラグと比較。外側電極に注目。
自然消耗で厚さが半分以下に!
とりあえずエンジンはかかるが、低速から高速まで全域に渡ってすこぶる調子が悪かった。
(車両)ホンダ カブ50。約25000キロ走行。
むむ、丈夫だ。突然エンジンがかからなくなったとのことで修理を受託。
外してみると、あれ?電極間に小さなカーボンが。
ここまで見事にハマり込むもんですね。
(車両)どっかのスクーター。なんだか忘れた。高速・高負荷走行に耐え切れずにエンジンが焼きついた2サイクル車。
まずはプラグを外してみると、げげ、電極が無い。
異常燃焼のため、高温になり過ぎて焼損した典型例。
(車両)RGV250ガンマ。かわいそー。
もちろんエンジンも無事ではありませんでした。(番外)
これも2サイクル車。プラグ電極付近が汚れきっています。原因は粗悪なエンジンオイル。
この場合ある程度以上に汚れ始めると、失火 --> 汚損 --> 失火 --> 汚損 となり、
エンドレス絶不調地獄に陥ります。やでしょ?こんなの。
たかがプラグ、されどプラグ。古(いにしえ)より今にいたるまで、数多くのライダーがスパークプラグのトラブルに悩まされてきました。まじです。
今一度プラグ点検してみませんか?
WAO! WebShop TOPへ戻る 技術資料室TOPへ戻る