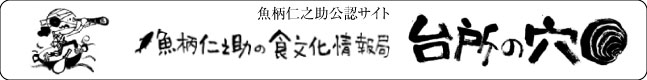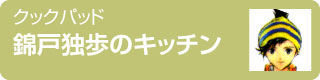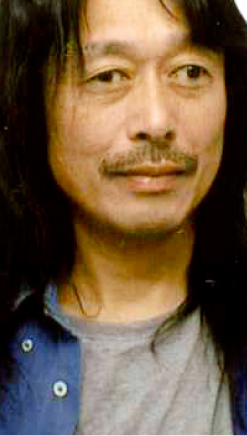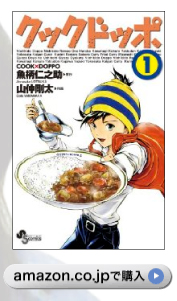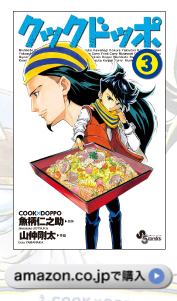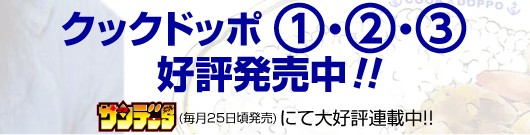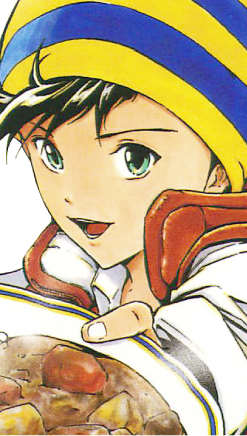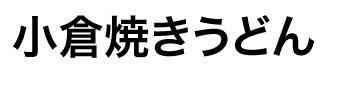これは昭和20年代に誕生した料理です。日本中が食糧難で飢えていた頃、飢えをしのぐための主食といえば、GHQから放出される小麦粉でありました。だから昭和20~30年代には、全国いたるところで、焼きそば・焼うどん・お好み焼きなどの「粉もん(コナモン)」料理が食べられていたのです。
小倉焼うどんは保存の効く「乾麺うどん」を使うのが特徴でした。当初は固ゆでにしたうどんとキャベツなどの野菜をラードで炒め、地元で作られた日本製ウスターソースで味付けをしていたようです。その後、鯨のベーコンや北九州生まれの魚肉ソーセージ、天かす、豚肉などが加わるようになっていったそうです。
昭和20~30年代、私の生まれた家も食堂をやっていましたから、家でよく食べておりました。戦後しばらくは、豚肉なんざとてもじゃないが使えない。ダイコン葉などのくず野菜をラードで炒めたのが「具」だった。
しかし下関が捕鯨基地であったので、鯨は市場でもたくさん売られておりました(昭和21年には南氷洋捕鯨が復活していた)。鯨のベーコンはたぶんなかったと思われますが、ほぼ同時代に登場した食べものだったので漫画の中では使ってみました。やってみますと豚肉と豚脂のこってりした焼うどんとは違い、あっさり味に仕上がるんですね。また、肉よりもずっと安く買えたので、焼うどんなどの「炒めもの」にはよく使われていたのです。
その鯨ベーコンのお株を奪う勢いで市場を席巻し始めたのが「魚肉ソーセージ」だったんだ。魚肉ソーセージ自体は、すでに戦前には開発されていたものの、商品化され市場に流通しはじめたのは昭和27年以降です。小倉焼うどんで魚肉ソーセージを「売り」にしたら、低カロリーで今風かもしれません。
小倉魚町銀天街から枝分かれした「鳥町食堂街」が発祥の地と言われておりますが、今日ではいろいろなバージョンが作られておりまして、「小倉焼うどん協会」のような組織もあるそうです。錦野独歩君がなぜ連載第1回目で小倉焼うどんを作ったのか? 実は原作者にも「ワカラン」のだ。料理ミステリーまんがは、こうしてスタートしたのであった……。



[材料]
茹でたうどん麺、魚肉ソーセージ(うどん麺位の細切り)、
薄く細く切った野菜類→キャベツ、玉葱、その他の残り物野菜、
削り節(鯖節や鯵節)、ラード
- フライパンか中華鍋にラードを敷いて火にかける。
- 魚肉ソーセージ、野菜等を炒め、薄塩をしておく。
- 茹でたうどん麺、削り節、そして杯一杯程度の酒を加えて炒める。
- 甘辛いソースで味を整える。