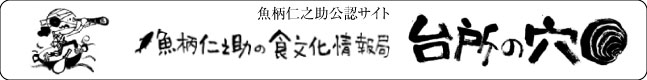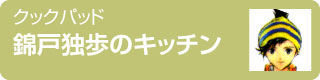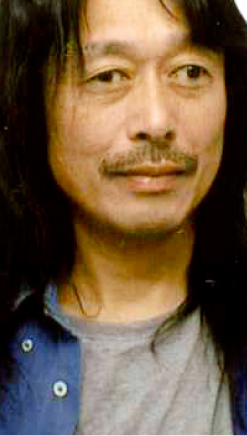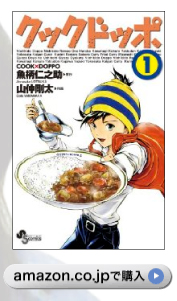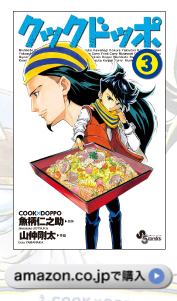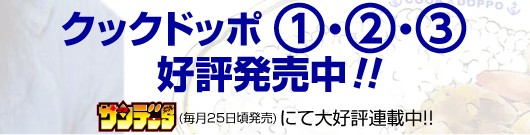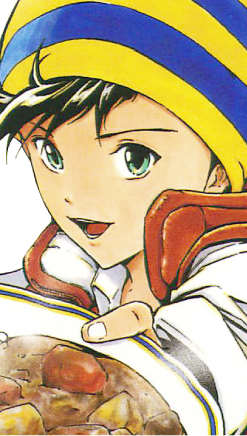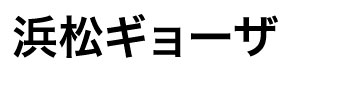今日、日本で食べる餃子は、中華料理ではなく、「和食」でしょう。もともと中国では点心の一つでした。白菜や挽肉などの具を、小麦粉と水で練った生地で包み、蒸籠で蒸したものが餃子だったんですね。それが日本に入ってきて、戦後、主に焼き餃子の形で普及しました。
中国餃子は分厚い皮に包まれていて、皮が主食・中の具がおかずとして成立していましたが、日本餃子は具を包んだ薄い皮まで含めておかずとなりました。有名な宇都宮餃子、浜松餃子、福島餃子なども、皮を薄くして具をたっぷり入れる方向で進化してきたのです。
本場中国では蒸し餃子か水餃子がほとんどで、揚げるとか焼くという調理はしなかったらしいのですが、日本では圧倒的に焼き餃子が広まります。外食産業や食品加工産業では差別化を図って、餃子の具のバリエーションをあれこれ工夫していった。挽肉、白菜、葱などの定番をベースにしつつ、チーズ、トマト、フルーツ、魚介類、餅、納豆、などなど、なんでも餃子の具にしていったのです。ここまで来ると、たとえB級グルメとはいえほぼ出尽くし状態であります。具のバリエーションは出尽くした、皮だって「ホウレンソウねりこみ皮」みたいなものもたくさんあって、そうそう珍しいものは無い。とするとこの先差別化できる餃子と言えば……。
浜松餃子のアイデアを練っている時、ここが悩みの種だったんです。そこで、一つは浜松らしく蒲焼のたれで味付けをした具を使うことにしまして、もう一つが生春巻きにヒントを得た「生餃子」だったんです。蒸す、焼く、揚げる、と言う加熱をしないと、餃子・点心の定義から外れそうですが、具を皮で包むという点だけで押し通してしまいましたの。
荒唐無稽なマンガの世界……と言うなかれ。これがアナタ、パーティー向きのおつまみになるんですな。特に生の魚介類――刺身やたたきなどを具にすると、文句なしに旨いのです。言ってしまえば「手巻き寿司」に近いものですね。生春巻きの皮を沢山用意しておき、指に水をちょいと付け、アジのたたきを包んできゅきゅっと餃子を巻く……よっ! 粋だねっ。こんな掟破りの料理を展開しながら、錦野独歩の逃亡旅は続くのだ。


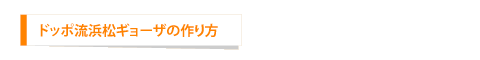
小さめの春巻きの皮を用意する。無ければ大きめのを4つに切る。
具は火を通さなくてもそのままで食べられるものにする。
(例)・醤油か味噌で和えた刺身 ・キムチ ・マヨネーズで和えたサラダ ・切ったチャーシュー ・細切り焼肉 ・漬物 などなど
具に味が付いているのでたれは不要。