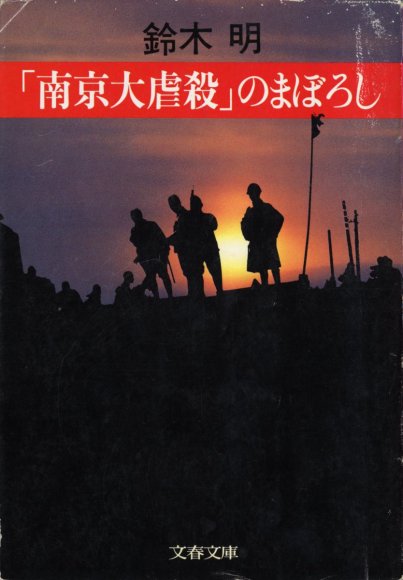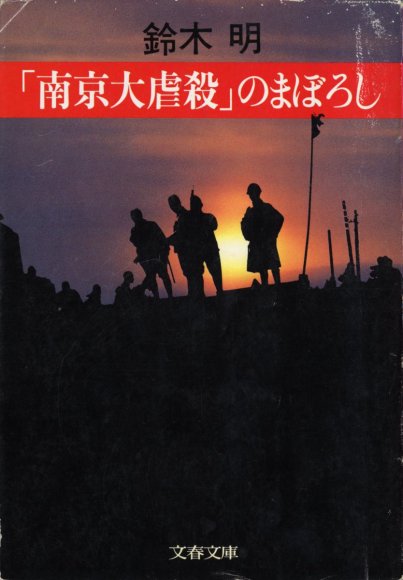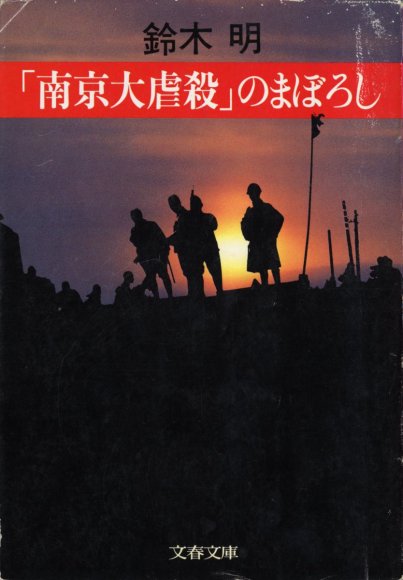
昭和十二年十二月、日本軍が中国で行った最も恥ずべき行為として世界に知られた南京大虐殺と百人切り競争。それは「何時」「どこで」「どのように」「どういう理由で」起きたのか。
なぜか報道されなかったその真実を、南京攻略戦に参加した兵、将校、従軍記者など目撃者の証言から明らかにした。第四回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した話題作。
一九八三年十一月二十五日 文春文庫 三百六十円
ISBN4-16-719702-2
殺人ゲームは平時か戦時か
ちょっと待てよ、と思った。昭和四十六年十一月五日、「朝日新聞」に掲載された本多勝一氏の「中国の旅」のうち、南京事件における「競う二人の少尉」のくだりである。原文のままを引用する。
「『これは日本でも当時一部で報道されたという有名な話なのですが』と姜さんはいって、二人の日本兵がやった次のような《殺人競争》を紹介した。
AとBの二人の少尉に対して、ある日上官が殺人ゲームをけしかけた。南京郊外の句容から湯山までの約十キロの間に、百人の中国人を先に殺した方に賞を出そう──。
二人はゲームを開始した。結果はAが八十九人、Bが七十八人にとどまった。湯山に着いた上官は、再び命令した。湯山から紫金山まで十五キロの間に、もう一度百人を殺せ、と。結果はAが百六人、Bが百五人だった。今度は二人とも目標に達したが、上官はいった。『どちらが先に百人に達したかわからんじゃないか。またやり直しだ。紫金山から南京城まで八キロで、今度は百五十人が目標だ』
この区間は城壁に近く、人口が多い。結果ははっきりしないが、二人はたぶん目標を達した可能性が強いと、姜さんはみている」
このエピソードは、僕に直ちに洞富雄氏が書いた『南京事件』の中の一節を思い出させた。洞氏の『南京事件』は、僕が読んだ限りでは、日本でかかれた物のうち最も史実に肉薄した真摯な労作で、本多氏も朝日の連載をはじめるに当たっての推薦資料に入れている。
この中で、大森実氏が南京を訪れた際、同地の中国人民対外文化友好協会からきいた話として、次のようなことが書かれている。孫引きだが、引用させて頂こう。
「南京入城に先立ち──どちらが先に軍刀で百人斬るか争ったのだ。郊外の湯山に着いた時、城門まであと二キロだったが、向井少尉が八十九人、野田少尉が七十八人斬っていた。上官の許しを得て湯山から競技を再開し、二人が中山陵にたどりついたとき、向井は百七人、野田は百五人。しかしこれではどちらが先に百人斬ったか証拠がないというので延長戦をやり、目標を百五十人にエスカレートした。まったくお話にならない暴虐行為だったが、日本人に大虐殺の模様をくわしく話したのは、私たちが初めてのケースだという」(『天安門炎上す』十八〜十九頁)
この二つの記事の微妙な違いは、誰にでも一見してお判りであろう。まず、大森氏が伝える話は、「南京入城に先立ち」とあるように、戦闘中の手柄争いの話である。 しかし、本多氏の話は、平時とも戦時とも受けとれるような微妙な表現がなされている。「この区間は人口が多く」という言葉は、多分に、平時のことを類推させる表現である。いうまでもなく、平時と戦時とでは、基本的に「残虐」の受けとられ方が違う。「戦場で百人殺せば英雄だが、平時に一人殺したら死刑」というチャップリン映画のテーマではないが、この殺人がもし戦闘中のことならば、少なくとも昭和十二年当時の日本人の心情には「許される」残虐性であろうが、いかに戦時中の日本といえども、戦闘中以外の「殺人ゲーム」を許すという人はいないだろう。では何故、本多氏は敢えてこのような記事の書き方をされたのだろうか?
本多氏はこの連載の途中、読者へのお断りとして特に一回分を割き、
「かりに、この連載が中国側の《一方的な》報告のように見えても、戦争中の中国で日本がどのように行動し、それを中国人がどう受けとめ、いま、どう感じているかを知ることが、相互理解の第一前提ではないでしょうか」
と書いている。つまり、本多氏としては、姜さんが話したことと、かつて大森氏が伝えたこととのギャップを、文章上どう表現するかで苦心されたに違いない。本多氏の文章をよく読むと、微妙に、戦闘中とも平時ともとれるような苦心のあとがみえる。つまり、姜さんの勘違いを、このような形でしか表現できなかったのであろう。この場合、もとより、姜さんの勘違いを責めることはできない。第一、姜さんは被害者の側である。ただ、同じ南京の中ですら、これほどの話のズレを生ずるとすれば、そのモトの話とは、いったいどんな物なのだろうか。「有名な話」とあるからには、当時の大新聞を見れば直ちにわかることであろう。僕は昭和十二年十二月前後の新聞をしらみつぶしに調べにかかった。
事実が変貌する過程
この話は、当時の「東京日日新聞」のマイクロフィルムから、直ちに発見することができた。この記事は、三回にわたって「後日譚」として掲載されており、「東日」の特ダネらしく、他紙にはいっさいみられない。これも、原文を引用させて頂く。
昭和十二年十一月三十日の記事
「(常州にて廿九日、浅海、光本、安田特派員発)常熟、無錫間の四十キロを六日間で踏破した○○部隊の快速はこれと同一の距離の無錫、常州間をたつた三日間で突破した。まさに神速、快進撃、その第一線に立つ片桐部隊に『百人斬り競争』を企てた二名の青年将校がある。無錫出発後、早くも一人は五十六人斬り、一人は廿五人斬りを果たしたといふ。一人は高山部隊向井敏明少尉(二十六)=山口県玖珂郡神代村出身=。一人は同じ部隊野田毅少尉(二十五)=鹿児島県肝属郡田代村出身=。柔剣道三段の向井少尉が腰の一刀『関の孫六』を撫でれば、野田少尉は無銘ながら先祖伝来の宝刀を語る。
無錫進発後、向井少尉は鉄道線路廿六・七キロの線を大移動しつつ前進、野田少尉は鉄道線路に沿うて前進することになり、一旦二人は別れ、出発の翌朝、野田少尉は無錫を距る八キロの無錫部落で敵トーチカに突進し、四名の敵を斬って先陣の名乗りを上げ、これを聞いた向井少尉は憤然起つてその夜横林鎮の敵陣に部下とともに躍り込み五十五名を斬り伏せた。
その後、野田少尉は横林鎮で九名、威関鎮で六名、廿九日常州駅で六名、合計廿五名を斬り、向井少尉はその後常州駅付近で四名斬り、記者が駅に行つたとき、この二人が駅頭で会見してゐる光景にぶつかった。
向井少尉 この分だと、南京どころか丹陽で俺の方が百人くらゐ斬ることになるだろう。野田の敗けだ。俺の刀は五十六人斬って刃こぼれが、たつた一つしかないぞ。
野田少尉 僕等は二人共逃げるのは斬らないことにしてゐます。僕は○官をやつてゐるので成績があがらないが、丹陽までには大記録にしてみせるぞ」
昭和十二年十二月十三日の記事
「(紫金山麓にて、十二日浅海、鈴木両特派員発)南京入りまで『百人斬り競争』といふ珍競争をはじめた例の片桐部隊の勇士、向井敏明、野田巌両少尉は、十日の紫金山攻略戦のどさくさに、百六対百五といふレコードを作って、十日正午両少尉はさすがに刃こぼれした日本刀を片手に対面した。
野田『おいおれは百五だが、貴様は?』向井『おれは百六だ!』・・・・・・両少尉《アハハハ》結局いつまでに、いづれが先きに百人斬ったかこれは不問、『ぢやドロンゲームと致そう、だが改めて百五十人はどうぢや』と忽ち意見一致して十一日からいよいよ百五十人斬りがはじまった。十一日昼、中山陵を眼下に見下す紫金山で敗残兵狩真最中の向井少尉が『百人斬りドロンゲーム』の顛末を語つてのち、
『知らぬうちに両方で百人を超えてゐたのは愉快ぢや。おれの関の孫六が刃こぼれしたのは、一人を鉄兜もろともに唐竹割りにしたからぢや。戦ひ済んだらこの日本刀は貴社に寄贈すると約束したよ。十一日の午後三時、友軍の珍戦術、紫金山残敵あぶり出しに、おれもあぶり出されて、弾雨の中を『えい、ままよ』と刀をかついで棒立ちになつてゐたが、一つもあたらずさ。これもこの孫六のおかげだ』
と飛来する敵弾の中で、百六の生血を吸つた関の孫六を記者に示した」
(昭和十二年十一月三十日及十二月十三日付「東京日日新聞」〈現在の毎日新聞〉から)
もとより、今の時点で読めば信じられないほどの無茶苦茶極まりない話だが、この話が人づてに中国にまで伝わっていくプロセスで、いくつかの点がデフォルメされていった。第一には、戦闘中の話が平時の殺人ゲームにされていること。第二に原文にはない「上官命令」という形が加えられたこと。第三に、百人斬りが三ラウンドくり返されたように作られてしまっていること、などであろう。そして、これは僕が思うのだが、この東京日日の記事そのものも、多分に事実を軍国主義流に誇大に表現した形跡が無くもない。確かに戦争中はそういう豪傑ぶった男がいたことも推定できるが、トーチカの中で銃を構えた敵に対して、どうやって日本刀で立ち向かったのだろうか? 本当にこれを「手柄」と思って一生懸命に書いた記者がいたとしたら、これは正常な神経とは、とても思われない。
この記事には「浅海光本両特派員発」というクレジットがついている。この浅海とは、あるいは、毎日新聞の大記者として著名であり、また新中国の理解者として昨年『新中国入門』を書いた浅海一男氏のことではないだろうか?「諸君!」編集部のたしかめたところによると、このクレジットにある「浅海」とは、まさに浅海一男氏のことなのだが、実際これを取材したのは光本氏の方であり、しかも光本氏はすでに死亡しているとのことで、この件についてのこれ以上のことをたしかめる余裕はなかった。
事の真相はわからないが、かつて日本人を湧かせたに違いない「武勇談」は、いつのまにか「人斬り競争」の話となって、姿をかえて再びこの世に現れたのである。
やや皮肉めいていえば、昭和十二年に「毎日新聞」に書かれたまやかしめいた「ネタ」が、三十四年の年月と日本、中国、日本という距離を往復して「朝日新聞」に残虐の神話として登場したのである。いわば、この「百人斬り」の話によって、ある「事実」が、地域を越え、年月を経ることによって、どのように変貌してゆくかという一つのケースを、われわれは眼前に見せつけられたわけである。
ともあれ、現在まで伝えられている「南京大虐殺」と「日本人の残虐性」についてのエピソードは、程度の差こそあれ、いろいろな形で語り継がれている話が、集大成されたものであろう。被害者である中国がこのことを非難するのは当然だろうが、それに対する贖罪ということとは別に、今まで僕等が信じてきた「大虐殺」というものが、どのような形で誕生したのか、われわれの側から考えてみるのも同じように当然ではないのか。無論、僕個人がこの事件を解明するなどということはもとより不可能なことだろうが、それにもかかわらず、敢えて自分の眼で見た「南京」のイメージを綴ってみようと思い立ったのは、実は冒頭の、「ちょっと待てよ」というあの瞬間が動機となったことは事実である。
意外に少ない資料
「南京事件」を語る場合、意外な盲点が一つあることに気が付いた。それは、当時の南京攻略戦の模様が、案外はっきりしていないということである。むろん「忠勇美談」風の戦記なら、いくらでもある。しかしながら、実際にどのような軍隊がどのような装備で、そのような中国軍と戦ったのか、ということになると、資料は意外に少ない。
とくに、中国側のものは、戦った主力が現在の「人民解放軍」ではなく国民政府軍であり、中国側に「敗けいくさ」の正確な記録がないこともあって、実態がつかみにくい。
いわゆる「中支」に戦乱が飛び火したのは、一九三七年(昭和十二年)八月十三日のことであって、これは「日華事変」勃発から数えて一ヶ月六日たった時のことである。ただ、中支に戦乱が飛び火することは雰囲気としては既に予期されていたことで、八月五日には南京市内における日本女性の引揚げがはじまっており、七日には漢口から、全日本人五百人が引揚げを開始している。
上海で日本軍が行動を起した直接の動機は、八月九日大山勇夫中尉が上海共同租界モニュメント路で「何者とも知れぬ中国人」に惨殺されたことだが、十三日に日本上海陸戦隊が八字橋で行動を起すと、翌十四日には直ちに蒋介石軍の飛行機が上海全市を空襲している。いわば、双方とも「機熟していた」とみるべきであろう。この国府軍の空襲は内外の反感を呼び、被害をうけたカセイ・ホテルに、折から観光旅行に来ていたエセル・ルーズベルト夫人が投宿していたことから、アメリカから宋美齢に対して「即時盲爆を中止するように」勧告が送られたりした。この空襲でアメリカの宣教師フランク・ローリンソンが即死し、上海の繁華街である南京大世界だけで、四百四十五名が死亡したと当時の新聞には伝えられている。
日本政府が「東洋平和のために、上海で兵を起す」と声明したのは、翌八月十五日のことである。当時、上海には三万人の日本人が居住しており、いうまでもなく、ここは各国租界を含めて東洋の一大繁華街であった。
この地域を防衛した国府軍は、翁照垣のひきいる、国府軍随一の精鋭第十九路軍で、五年前の「肉弾三勇士」で有名な第一次上海事変の際、数ヶ月にわたって必死の日本軍を一歩も寄せつけなかった有名な部隊である。
中国に近代的な軍隊が誕生したのは、一九二四年、黄埔に国民革命軍養成のための学校がひらかれたことからはじまるというのが通説である。
この校長であった蒋介石は、この「軍」を掌握して国民政府主席を確保したわけであり、当時は国共蜜月の時代だったから、教頭には周恩来がおり、この生徒の中には林彪、羅瑞卿、陶鋳など、後の中国の歴史を担った有名人が、ズラリ勢揃いしている。
よく知られているように、民国十六年、つまり、一九二八年、いわゆる「国民革命」が成功して蒋介石は南京を首都と定め、新政府主席の地位についたが、実際には各地に軍閥は蟠踞し、党内には反主流勢力がおり、また「中国共産党健軍記念日」が一九二八年八月一日の日付であるのをみても想像されるように、共産党も数は少ないながら、蒋介石の強力な敵側の一角に廻っていた。毛沢東が有名な井崗山にたてこもって、最初のソビエト地区を作ったのが一九二七年十月。この、最初一千名に過ぎなかった軍隊が、七年間にわたって、何十倍かの国府軍といかに効果的な戦いを行ったかは、あらゆる「毛沢東伝」にくわしい。
蒋介石のひきいる国民軍は、五度にわたって「剿共軍」を繰り出して紅軍を攻めたてたが、最後の第五回を除いては、いずれも数少ない紅軍に逆に散々な目にあった。この時の紅軍の勇将が林彪だが、国民軍の中にあって、最も紅軍を悩ませたのが、蔡廷楷のひきいる第十九路軍である。
真相はわからない
僕は取材の末期、ある老人が僕に悲しげな眼を向けながら、「この間、中国にいってきた若い組合の青年から、あなたたちが南京であんな悪いことをするから、いまわれわれがお詫びをしてるんですよ、といわれましてねえ・・・・・・」と訴えたことを思い出す。この人は大正の末期二等兵として応召し、家の貧しさのゆえにそのまま軍隊に残り、ひたすらに戦い続け、二十何年かかかって少尉で終戦を迎えた。「社交一つできない」彼は、鍛えた体だけを資本に「自分の食うものを減らして子供に食わせ」今度はひたすらに「戦後の日本のために働いてきた」。
しかし彼は息子のような年の青年にそういわれたとき、何の反撥もしなかった、という。おそらくあの、悲しげな表情をチラと見せたまま、青年を見つめただけであったろう。僕は無論、この青年個人を難詰しようとは思わない。彼の態度は日本の「マスコミの姿勢」そのままであり、「殺された側」の同情者として、その論は大手を振って歩くことができる。
しかし「殺した側」の老人の過ぎ去った「三十五年間」は、どのマスコミにも認められず、頭を垂れて、ただ「時効」を待つだけの時間に費やされた。
僕は最後に、
「もう一度南京に行ってみたいですか?」
と彼にきいた。それは、僕が多くの人たちにきいたのと同じ質問だった。彼はそのときだけ、一瞬眼を輝かせ、
「そりゃ、行ってみたいですよ」
と答えた。それは僕が同じ質問をしたすべての人と、全く同じ答えであった。
*
僕はここ半年にわたって、とにかく僕なりの方法で「南京事件」をわが心の問題として、自分流に育ててきた。僕の集めることのできた「事件」の素材は、「事件全体」からみれば、あるいはほんの一握りほどのものであるかも知れない。しかし、僕はそれが一九七二年に、日本の一市民として生活する僕にとって重要な素材であると思えばこそ、育ててきたのである。僕の集めてきた素材をみて、人はまたそれぞれに、自分の「南京事件」を心の中で育てるかもしれない。
そしていま、もし請われて、僕がどうしても「南京事件」について記述しなければならないとしたら、僕はおそらく、次の数行だけを書いて筆を止めるだろう。
「〔
南京事件〕昭和十二年十二月、日本軍が国民政府の首都南京を攻め落とした時に起きた。このとき、中国側に、軍民合わせて数万人の犠牲者が出たと推定されるが、その伝えられ方が当初からあまりに政治的であったため、真実が埋もれ、今日に至るもまだ、事件の真相は誰にも知らされていない・・・・・・」
あとがき
昭和四十七年一月十五日のことである。それが一月十五日であったということは、車の中から見る若いお嬢さんたちが、恒例の和服に着飾って、鎌倉八幡宮の周辺に群がっていたことで、鮮やかに記憶している。
僕は知人から紹介を受けて、逗子に住む藤井さんという方を訪ねていった。藤井さんは「南京攻略戦」に戦車隊の隊長として従軍し、それからかなりの期間南京に滞在されていた、ときいたからであった。僕が藤井さんをお訪ねした動機は、まったく単純であった。昭和四十六年夏頃から、朝日新聞に本多勝一氏の「中国の旅」が連載され、僕もいろいろ心に掛かるものが残りながらも読まされてしまったのだが、「南京攻略戦」に参加した人ならば、これらの記事についてかなりの「真相」を語ってくれるに違いないと、いわば、フラリと出かけたのである。
藤井さんはその時「南京攻略」のアウトラインと「南京が陥ちれば凱旋できる」とほとんどの兵が信じていた当時の心理状態などを細かく語ってくれたが、「虐殺」については「私の見聞した範囲では、東京裁判などで伝えられている暴行については、見たことも聞いたこともないので、何ともいいようがない」とだけいった。
僕は実はこの時まで、当時「南京攻略戦」に参加した将兵にとっては、「大虐殺」の事実は「常識」になっているのではないか、と漠然と感じていただけに、藤井さんに「見たこともきいたこともない」といわれたことは、かなり意外であった。
最初は、藤井さんは旧軍人の立場から、当時の日本軍人の立場を守る意味で「知らない」といわれたのかとも思ったが、同じような「旧軍人」の方二、三名にきいても、返ってきた発言は、ほぼ藤井氏と同じようなものであった。
その頃になって、僕はようやく、いくつかのことに気が付きはじめた。一つは、当時のコミュニケーションというものが、今から考えれば想像もできないほど狭かったということである。多くの将兵は、自分が現実に見た眼の前のことしか知らない。同じ連隊はおろか、同じ中隊のことでも、残りの小隊のことは詳しくわからない、というほどの情報量の乏しさである。それ以外の余計なことは全く知らされなかったし、知らすべき機関もなかったし、知る必要もなかった。だから、知らないのである。つまり、極論すれば、「南京事件」なるものの全貌を知ろうとすれば、当時南京にいた数万といわれる将兵が今も全部現存していて、その全部について厳密な事実調べが行われなければ、それを知ることは出来ないわけである。そして、いうまでもなく、それは百パーセント不可能なことである。
だが僕が、この、ちょっとした見聞と動機によって、伝えられている「南京事件」について、「ある種の疑問」を持つようになったのは事実である。ある事件が起きたとき、人間は誰しも、それが「何時」「どこで」「どのように」「どういう理由で」起きたかを知りたいと思う。まして「南京大虐殺」のような歴史的な事件に対して、被告側である日本人がそれを思うのは当然であろう。
しかし、どういう訳か、僕が読んだどの本にも、この四つの疑問符に対して僕を納得させるようなものは、ただの一冊もなかった。僕はこの時、初めて、当時の日本のマスコミに対して、ある怒りを感ずるようになった。
今考えると、これも全く錯覚だったわけだが、僕はこの時、当時の大新聞の従軍記者は、皆事件の真相を知っているのに、その勇気のなさから、真実をひた隠しにして、今日まできたのだと考えていた。そして、その怒りは同時に、今日陸続と中国に出かける記者が、当時の従軍記者と同じように何の真実も報道していないのではないかという「疑い」にもつながっていった。この種の「疑問」は、あるいは余りにも素人臭い書生論なのかも知れないが、僕は殊更に「素人が当然感ずる疑問」だけを取り上げ、「『南京大虐殺』のまぼろし」なる一文を「諸君!」昭和四十七年四月号に書いた。僕の書きたかったことは「南京大虐殺はまぼろし」ではなく「南京大虐殺」を《まぼろし》にしたのは、真実を語る勇気のなさであり、それは「昭和四十七年にも、また同じようなことが繰り返されているのではないか」という恐怖であった。
ところが、この一文に対して、全く予期しないところから反響があった。「南京大虐殺の真犯人」と世上伝えられてきた「百人切り」の少尉の未亡人からの投書である。僕はこの向井少佐の遺書を読んでいるうちに、どうしても関係者を歴訪したい衝動に駆られた。それは、僕が真相を知りたいという興味の他に、マスコミが当然伝えなければならないことを知らせてはいない、という抗議の意味の方が強かったかも知れない。
「向井少尉はなぜ殺されたか」を考えることは、僕にとって「南京事件の真相」より、むしろ、過去現在のマスコミのあり方に対する怒りの方が遙かに問題であるはずであった。
だが、これを書き終わった頃、僕はもう「南京」の魅力から抜け出ることが出来なくなっていた。僕が古い南京の地図を手に入れ、これを睨み付けながら、様々な空想に思いを馳せたのもこの頃である。僕が手にした昭和八年の「上海―南京」間の列車時刻表には、上海を朝八時に出発する「特別快車」が、蘇州、無錫、常州、丹陽、鎮江を通って、午後二時半には南京に着く、と記してある。そこには、蒋介石が精魂を込めて作りつつあった「中華民国」の首都があった。北には揚子江が流れ、東には紫金山、玄武湖と風光明媚な行楽地があり、南は広く沃野が展けている。この首都で、昭和十二年の日本人が、「途方もない残虐事件」をやったと、皆が信じている。しかし、本当は何があったのか?「事件」があったからには、必ず「目撃者」がいるはずである。それは今、日本のどこに潜んでいるのか・・・・・・?
「『南京大虐殺』のまぼろし」を書いていた頃、僕は「大虐殺の真相を知ることなど、全く不可能」と、深く心に念じていたはずであった。しかし、このようなかつての考えは簡単に頭の片隅に追いやられ、いつの間にか、僕に与えられた時間のほとんど全てが、「南京事件」を考えることに費やされていた。
僕は戦史の専門家でもないし、文筆を専業としているわけでもない。だから、僕自身が頼りに出来るのは、僕自身が持つ「平凡な常識」と、ささやかな推理力と実行力だけである。僕はこれを唯一の武器として関係者を訪ねて歩き、その進行のままに、その状況を雑誌「諸君!」に分載していった。
今度一冊の本としてまとめるに当たって、本来ならば、当初書いた部分と最後に書いた部分との前後相矛盾する部分を整理し、重複する部分を削り取って、統一された体裁を整えるべきであろう。しかし僕は敢えて、それをしなかった。何故なら、僕が当初感じた「素人っぽい勘違い」や「怒り」は恐らく大部分が同じように「素人」である昭和四十八年に生きる日本人の「勘違い」に近いものであると考えるからである。そしてその「勘違い」が、どのような形で是正され、より「事件」の内部に踏み込んでいったのかという僕のプロセスを、僕はそのままの形で現在に生きる人たちに感じていただきたい、と念願したからである。
だから、いくらか不体裁であることは覚悟の上で、雑誌掲載時の論旨、取材経過などについては、そのまま一切書き改めるということをしなかった。実際にはこの本をまとめるに当たって、発表当時より百枚ぐらい内容が増えているが、それは、「第三章 南京への道」を書き加えたのと、当時書きながら、頁数の都合などで割愛した部分を追加していったもので、本筋には筆を加えていない。また、数字の表記などで不統一な部分が随所にあると思うが、これも、書いている僕自身、こう書く方が自然で理解し易かったので、無理にそう書かして頂いたのである。
ある種の仕事を終えたとき、普通誰しも、なにがしかの安堵感と解放感に浸れるであろう。だが、僕の気持ちは今でも、書いているときと同じように、重く、暗い。この重さは、僕が日本人であることを、同じく人間であることを止めない限り、ずっと付き纏うような、そういう重さである。僕はその重さと戦おうと思う。しかしこれは所詮、絶対に勝つことのない戦いである。
この本は、たくさんの偶然と、数多くの友人、知人の協力で出来上がった。そのほとんどの方が名前の表記を希望されなかったので、ここではただ、心からの感謝の念だけを表明するだけに止めたい。最後に、執筆中、癌にその生命を奪われた友人津留達児に、本書を捧げたいと思う。
昭和四十七年十二月
鈴 木 明
文庫版のためのあとがき
「あとがき」にも書いたように、この作品の取材は、昭和四十七年一月十五日から始まった。
今にして思うと、歴史の歩みというものは、如何なる「もしも」も許されずに、大河の流れのように、着実に下流へと向かって流れていることを実感せずにはいられない。本多勝一氏が「中国の旅」を朝日新聞に連載を始めたのは、昭和四十六年八月末から十二月にかけてのことであった。この連載に、いわば挑発されるような形で、僕は「南京大虐殺」について取材を始めたわけである。それは誰に頼まれたわけでもなく、誰に協力を頼んだ訳でもなかった。確かに、当時、「諸君!」編集長をしていた田中健五氏と相談の時間は持ったが、当時僕は田中氏の顔をわずかに知っている、という程度のお付き合いであり、文筆とは全く別の世界にいた。
唯、「百人斬り」に素人っぽい疑いを持ち、暇だけはやたらに持っていたので、思いつくままの小文を田中氏のところに持ち込んだに過ぎなかった。
何回か、表現の稚拙な部分を指摘された後、この本の第一章である「《南京大虐殺》のまぼろし」は「諸君!」昭和四十七年四月号に掲載された。そしてその四月号が書店に並んでいるその最中に、第三十一回世界卓球選手権大会が名古屋で開かれ、「中国卓球選手団」が手に手に真っ赤な「毛語録」を振りかざしながら、羽田空港に降り立ったのである。
僕はこの時も興味につられて名古屋まで出かけていったが、その警備の物々しさや、選手と日本人とを交流させない監視の厳しさは、異常という他はなかった。「友好第一、勝敗は第二」というスローガンとは裏腹に、中国選手団は歓迎パーティーにすら姿を見せなかった。大会運営費一億二千万円のうち、朝日新聞社だけが一千五百万円もの協力費を出していたのも異常であった。念のためにきいてみると、地元最大の企業であるトヨタ自動車ですら、協力費は百五十万円であるとのことであった。
この時に来日した最大のスターが荘則棟であったことも忘れられない。荘則棟は後に「江青の後押しによって成り上がった」と噂されて「四人組追放」とともにスポーツ英雄の座から滑り落ちるが、当時は「四人組」こそは中国の揺らぐことのない主流と考えられていた。「文化大革命」による経済発展はめざましく、昭和四十六年、つまり本多勝一氏が中国を訪れた年の中国における鉱業機械の成長率は、実に六二%であると発表されていた。
第二章である「向井少尉はなぜ殺されたか」がそれから四ヶ月経って、同じく「諸君!」に掲載されたとき、日本の政界では世人の予想を裏切って田中角栄内閣が誕生した。しかし、僕自身は田中内閣には何の関心もなかった。一度興味を持ち始めた「南京大虐殺」の取材に夢中で、佐藤栄作であろうと田中角栄であろうと、所詮は自民党内閣のやることに変わりがあるはずはない、と頭から決め込んでいた。それよりも「文化大革命」の最中にある中国の不可解な実体を、何の疑いもなく礼賛し続けている日本の多くのマスコミの姿の方に、僕は遙かに強い関心を持っていた。
田中内閣の手によって、突如劇的な「日中国交回復」が行われたのは、田中内閣誕生からわずか二ヶ月あまり後のことである。三ヶ月前、「台湾との関係を守る」といっていた佐藤栄作を総裁とする自民党国会議員が、選挙の洗礼もなしにわずか二ヶ月で全く逆の決定に踏み切った裏に何があったのか今でも僕は知らない。しかし、いまふりかえってみれば、昭和四十六年の「中国の旅」から「ピンポン外交」へと進んだ歴史の流れは「田中内閣誕生」「日中国交回復」へと着実に歩を進めていたのであろう。そして「日中友好」は誰もが必要と思い、これと不可分の関係のものとして「南京大虐殺」は日本人に再認識されることになった。田中元首相は、このことを象徴するかのように、日中国交回復に当たって「過去において、日本が中国に行ったことについてお詫びをする」といった。
それからしばらく経って、台湾で「南京大虐殺」という本が発行された。その序文には「我々は中日戦争後、恨みに報ゆるに徳を以てする精神を貫いてきたが、今回田中政府の暴挙によって、三十年前の日本人の「獰猛」な面目が蘇ってきた。だから、敢えて三十年前の日本人の暴挙を再現するものである」と書かれていた。
この本の内容は、基本的には本多勝一氏の伝えた「中国の旅」における日本軍の存在と暴行事件と同じである。但し、この本には「南京裁判」における論告求刑の全文が掲載されている。僕は単行本となった「《南京大虐殺》のまぼろし」で、谷中将の申弁書、いわば被告の側からの弁護だけを紹介し、検察側の論告を掲載しなかった不公平を心の中で感じていたので、この論告求刑における「事実」と書かれた全文を、改めて詳しく読んでみた。
この全文をここでご紹介することにやぶさかではないが、歴史家が資料として残すならともかくとして、その直訳を改めて書き綴ることは余り意味はない。大要は、「東京裁判」で述べられたものと同一である。主文の中には、時として「十九万余」という漠然とした数字を使ったかと思うと、時には「石霸街五十号石筱軒が四つの木箱に古元二千件、木器四百件、衣服三十余箱を盗まれた(webmaster注・石霸街の霸はつちへんに霸、古元二千件の元は元を二つ並べたもの)」というように、突如具体的な名前が出てくる。谷寿夫の申弁書の中にある「殊更に・・・・・・不可能事なり」(138ページ11〜12行)などの字句は、これら不統一な内容に対する抗弁の一端であったと思われる。
もう一つ、この「論告求刑」を読んで初めて気が付いたのは、谷寿夫を被告とする「南京大虐殺事件」において、日本軍士官の二人(向井、野田両少尉)の「殺人競技」が意外に大きく取り上げられていることである。出版された本には、昭和十二年の「毎日新聞」の写真が大きく掲げられ、「これは、日本軍が大量虐殺をした鉄の証拠である」と書かれている。既に拙著をお読みになった方はおわかりのように、向井、野田の両名は谷寿夫の部隊とは何の関係もなく、「殺人競技」は日本の一人の新聞記者によってのみ伝えられたものであって、中国人側からの被害届、ないし見聞の証人があったわけではない。
しかし、谷寿夫を銃殺するに当たって、二人の「殺人競技」は「南京大虐殺とワンセット」の中に納められていたことが、よくわかる。
日本軍は、中国に対して理不尽な理由で侵攻作戦を開始した。作戦が拡がり、兵站線がのびるに従って前線は混乱し、それに伴う略奪、暴行も増えていったであろう。特に南京作戦は、その作戦的背景、地理的条件から考えて、予期しなかったいろいろな出来事が起こったことは想像できる。
しかし、中国側の「論告求刑」では、「大虐殺」の背景などについて触れる部分は、全くなかった。日本軍は唯ひたすらに南京の全地域で暴行虐殺を行ったことがすさまじい形容詞で描かれ、特に「二人の士官による殺人競技」は、「南京大虐殺」に欠かすことの出来ない「明白な証拠」のある事件と認定された。これらの「虐殺」を「ほったらかして聞かないふりをし、部下に勝手なことをやらせた」からこそ、谷寿夫は「大虐殺」の主犯として南京雨花台で銃殺され、このことによって「大虐殺」もまた成立したのである。
昨年起こった「教科書問題」あるいは今年話題になった映画「東京裁判」などで、「南京大虐殺」は、再び世の注視を浴びることになった。ここは「教科書問題」を論ずる場ではないが、この時の中国側の主張として特徴づけられたことは、「侵略」と「大虐殺」とがワン・セットになっていることである。「侵略」という覆うべからざる事実を認める以上、「大虐殺」を認めることも、また同様であるという無言の押しつけが、この論旨の中には汲み取れる。
中国の教科書では、こう書いている。「日本侵略軍は至る所で焼き、殺し、奪い、残虐の限りを尽くしたため、無数の都市と農村が廃墟と化し、何千万、何百万の中国人民が殺された。日本軍は南京を占領した後、気違いじみた大虐殺を展開した。南京で平和に暮らしていた住民は射撃練習の的にされ、刃で切られ、石油で焼き殺され、生き埋めにされ、果ては心臓をえぐり取られるものもあった。一ヶ月余りの間に殺されたものは三十万を下らず、焼かれたり壊されたりした家屋は全市の三分の一に達した」このような教科書の表記の前で、多分、映画「東京裁判」の作者は、唯一箇所だけ、とても実写とは思えない「南京大虐殺」の場面を「中国側のフィルムである」という異例なクレジットを付けてまで挿入しなければならなかったのであろう。
今回、十一年前に書いた拙著が文庫本になるというので、あらためて口絵の写真を撮影した佐藤振寿氏にお会いし、ネガから新しく引き伸ばしをして頂いた。第一章の扉に掲載した写真は、南京陥落直後の十二月十三日から入城式の間、つまり「南京大虐殺」が行われたとされる最中に「難民区」で撮られたもので、大きく引き伸ばすと、少なくとも五十人の南京市民と六人の日本軍人がフレームの中に入っていることがわかる。
この中で、顔の表情が撮されている中国人は約二十五人、更に明らかに笑顔を浮かべているのは六人である。日本兵が、南京でどのような蛮行を行ったかの全貌は、今なお明らかではないが、この時、南京全市民を恐怖でひきつらせるような日本軍の暴行が、間断なく、随所で、恣意的に行われなかったことだけは間違いない。
十一年前、僕は全く、何気なく、偶然、「南京大虐殺」に飛び込んでいった。今思えば、それは「日中国交回復」という大きな政治的な動きの中に、突如舞い込んだとんでもない厄介者であったかも知れない。しかし、僕は政治の世界に全く無色であり、他に考慮する何者も無かったからこの仕事を続けたのである。
この仕事は、未完のままに終わっている。僕は歴史の専門家でもなく、法律家でもないから、これ以上「南京事件」を検証する力もないし義務もないが、「南京事件」は、昭和十二年十二月の事件であると同時に、昭和四十七年の、そして昭和五十七年、五十八年の事件であったこともまた事実であった。そしてなお、これは日本民族が生き続け、その歴史が残る限り問題となる試験である。
処女作というものは、読み返してみると誰もがある種の面映ゆいものを感じるであろう。
特にこの本は、テーマがテーマであるだけに各方面からの厳しい批判にさらされた。例えば、洞富雄氏は改めて「南京大虐殺―『まぼろし』化工作批判」という本を出版され、さまざまな点を指摘された。話は細かいが127ページにある小西さんの手紙を取り上げ、原文と不一致な点などもその例にあげた。確かに小西さんの手紙は原文と完全に同じではない。表現を読者に読み易いように部分的に書き直している。僕は学者ではないので、当時「原文」をどの程度に忠実に書かなければならないか、またニュース・ソースをどのように明示しなければならないか、というような配慮に欠けていた。しかし、原文の主旨を歪めるようなことは無論していない。
マギー神父の証言にしても、その曖昧性をもっと斬り込んでも良かったような気がするが、「神父」という肩書きの善意を考慮し、それもしなかった。
取材した人の証言、例えば元朝日新聞今井記者の言葉(228ページ)にしても、彼の話――その録音テープは、今も保存している――は実際には「手記」を書いた本人とはとうてい考えられないほど自分の書いた「手記」とは違う内容のものであった。氏自身、自分の書いた「手記」も所持していない、というのが事実であった。しかし、現に取材をさせて頂いた当人に対して、当時の心境としてはそのような露骨な表現は出来なかった。それが取材する側の心情としてやむを得ないものだと思っていた。その意味では、書くべきであるにもかかわらず、遠慮してしまった証言ないし資料は、今もなお僕の部屋に眠っている。
この際、出来れば、当時のテープを全部聴き直し、更に書き加えたい沢山の資料があったが、やはり、考えた末、それは行わなかった。これは昭和四十七年の書かれた一つのドキュメントとして読まれるべきだと考えたからである。だがそれにしても、「南京大虐殺」は僕の心の中で、誰に、ということではなく、歴史の重い流れに対して、今も割り切れないものを残していることを最後に付け加えさせて頂きたい。
-
解 説
草 柳 大 蔵
本書は、第四回大宅壮一ノンフィクション賞(昭和四十八年度)の受賞作品である。同時に受賞したのは山崎朋子氏の「サンダカン八番娼館」であった。この賞の場合、最終審査に八篇から九篇の作品が残り、選考委員の間で活発な議論が交わされるのだが、この年の両受賞作品については、ほとんど異論らしいものが出ずに、満票で受賞ときまったように、委員の一人である私は記憶している。
その日、私は全く個人的な事情から、鈴木明氏の受賞とそれに続くであろう同氏の文筆活動に、ある種の感慨にとらわれていた。いま、この「解説」を書くにあたって、はじめて告白するのだが、鈴木明氏と私は昭和二十年代の半ばに知りあい、一緒に仕事をした仲なのである。当時、私は新聞記者をしていたが、独立の日にそなえて方々の新聞や雑誌にペンネームで原稿を書いていた。鈴木氏は、その頃発足した民間放送に勤めていて、ラジオ番組のPRをする旬刊紙の編集に携わっていて、特集記事やコラムの原稿をほとんど毎月発注してくれた。二人の間には吉村保三画伯という共通の友人がおり、鈴木氏は吉村氏の家のすぐ裏手に住んでいて、私は彼の家で徹夜をして原稿を書きあげたことを覚えている。
受賞がきまったあと、私は主催者の文藝春秋の担当者に、鈴木明氏の本名と勤務先をそれとなく尋ねた。担当者の答えを聞いたとき、私はすぐに二十年まえの、背が高く、眉目秀麗で、やや外股に歩くのが癖の《彼》を思いうかべた。
旬刊紙の編集者として屡々喫茶店でおちあい、新聞記者の映画批評が印象批評を出ないこと、綜合雑誌の巻頭論文が難解であればあるほど有り難がられていること等を、上体を曲げ頭をすこし振りながら語り続ける《彼》が記憶によみがえってきた。いまでもそうだろうが、いわゆる《大マスコミ》の記事をクソミソにやっつけるのは、昭和二十年代の後半の青年に共通の客気であった。モダンで、シャープで、クールな斬り方や表現方法を、鈴木氏と私は喫茶店でえんえんと喋り続けていたものである。
いま、この解説を書くにあたって、十年ぶりに鈴木氏の作品を読みかえしてみると、あの喫茶店での饒舌が鋭い形で結晶し、鈴木氏に一流の「作法」となってあらわれた思いがしてならない。
劇作家の山崎正和氏は、「同時代史を書くことの意味」をテーマとした論文の中で、マックス・ウェーバーが十七世紀に起こった世界史的変化を「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で纏めたのは二十世紀前半であり、またデイヴィッド・リースマンが二十世紀のアメリカ社会を展望し、その重大な変質を「孤独な群衆」の中で捉えたのは一九七〇年に入ってからであるとして、同時代史に取り組むためには少なくとも半世紀の長さで見渡さなければならないのかもしれない、と述懐している。
この指摘は、「昭和史」と私達の関係についても、極めて有効なのではないかと思う。問題は「見渡す」ための《眼》、あるいは《距離》が醸成されるために時間がかかるということであろう。
ある事件が起こったときに、その事件を直接的・間接的に経験する人たちは、その事件が起きた社会や時代の価値観のパラダイム(枠組み)からなかなか抜け切れないからである。
鈴木氏が扱った「百人斬り」や「南京事件」なども、その典型的なひとつの例であろう。本文を読んで頂ければわかるように、「百人斬り」の新聞報道は両将校を英雄扱いにして疑うところがなかったし、「南京事件」についても、たとえば大宅壮一氏の耳にも入っていて、後年、陸軍報道班員としてジャワに派遣された大宅氏は現地で居合わせた辻政信参謀に「南京では、ずいぶん、派手にやったそうですね」と質問している。
戦後、それまでの価値観が転倒し一掃されてしまうと、こんどは「一億総ザンゲ」というパラダイムが確立し、歴史上の事件に対する「見渡し」の《眼》や《距離》がまたも失われてしまうのである。たとえば、戦艦大和の「片道特攻」という捉え方である。多くの《戦記》ものは戦艦大和が沖縄に出撃するときに燃料をタンクの五〇%しか積まなかったところから、生還を期さぬ「片道特攻」と捉え、この概念を起点として、終戦間際の海軍の異常心理や日本人の常軌を逸した精神主義を論じ続けていたのである。しかし、昭和五十七年一月、雑誌「水交」に寄稿された小林儀作氏の一文を読んで、私は《時代精神》のおそろしさを痛感した。小林氏は「老齢の見ゆえ、このまま黙って死んでゆこうと思ったが」とことわったうえで、はじめて燃料を半分しか積まなかった理由を書いている。
それによると、大和の燃料タンクの大きさからいって、タンクに半分の重油でも、広島県柱島の基地から沖縄海域を往復するのに十分であったという。いってみれば、単純至極、しかももっともな計算である。このような、子供にもわかる計算にあたらないで、燃料半分→片道特攻→ウルトラ精神主義というパラダイムを組み上げてしまう戦後の《精神》とは、いったい、いかなるものであろうか。私は、この一件に代表されるような、急ごしらえの「枠組み」に苛立ちを感じるよりも、空恐ろしさを感じるのである。
鈴木明氏のこの作品を読みかえしてみて、「同時代を見渡す」ための《眼》の卒直さと《作業》の的確さに、今更ながら共感し、賞讃せずには居られない。
――「南京大虐殺」の真相追求が大々的に取り上げられたことが、戦後二回あった。一回は日本戦犯を血祭りにあげるための「極東国際軍事裁判」であり、もう一回が「日中友好」のために、日本の罪悪を総懺悔しようという運動に乗っての「告発」であった。そして、その告発は、幸か不幸か僕の持っていた「南京大虐殺」のイメージを「幻」にかえてしまった。このぼんやりとしたスクリーンを少しでも実像にかえてゆく作業は、やはり誰かがしなくてはならない。そして、いまの僕にいえることは、その「誰か」が「裁判」にも「告発」にも関係しない、ただ「人間」を信ずる「誰か」でなければならない(本文五十五〜五十六頁)
鈴木氏は、出発点にあたって、昭和四十八年当時の日本人が「南京事件」について抱いていたイメージとそれほど変わらない理解の程度だったと書いている。私などもその一人である。鈴木氏が参考文献としてあたった本の何冊かも読んではいたが、「ずいぶんひどいことをしたのだな」という感慨から一歩も出なかった。ただ、日本軍が殺した中国人の数があまりにも多く、「南京陥落で日支事変は終わりだ」という当時の庶民の感想(私の父などもそのように公言して憚らなかった)からすると、戦争終結のまえに何十万人という人間を殺すだろうかという疑問が漠然と残ったに過ぎない。しかし、その疑問も多くの日本人と同じように「戦場心理」というキイ・ワードで帳消しにしてしまった。
しかし、鈴木氏の「平凡な常識」は本多勝一氏の記事によって強勢される。それから洞富雄氏の「南京事件」の読みかえしが始まり、生き証人や遺族の取材が始まる。
じつに実直な《作業》の積み重ねが行われる。読者は鈴木氏の取材に同行しているうちに、「いつ」「どこで」「誰が」「なぜ」の四つの疑問が、取材すれば取材するほどわからなくなることに、苛立ちを覚えるであろう。そのように「南京事件」が《藪の中》に入ってゆくにつれて、《藪の中》に引き込んでしまうエネルギーがあることに気がつく。その状況を鈴木氏は次のように書いている。
――今考えると、これも全く錯覚だったわけだが、僕はこの時、当時の大新聞の従軍記者は、皆事件の真相を知っているのに、その勇気のなさから、真実をひた隠しにして、今日まで来たのだと考えていた。
そして、その怒りは同時に、今日陸続と中国に出かける記者が、当時の従軍記者と同じように何の真実も報道していないのではないかという《疑い》にもつながっていった。この種の《疑問》は、あるいは余りにも素人臭い書生論なのかも知れないが、僕はこと更に《素人だけが当然感ずる疑問》だけをとりあげ、「『南京大虐殺』のまぼろし」なる一文を「諸君!」昭和四十七年四月号に書いた。僕の書きたかったことは「南京大虐殺はまぼろし」ではなく「南京大虐殺」を《まぼろし》にしたのは、真実を語る勇気のなさであり、それは「昭和四十七年にも、また同じようなことが繰り返されているのではないか」という恐怖であった(著者・あとがき)
つまり、鈴木氏は「南京事件」の実像に迫ろうとする道程で、もう一つの実像が浮かび上がってくるという経験をするのである。それは、例えば、洞富雄氏の著作ばかりか、真面目な研究所にまで引用されている「回想録」の著者秦賢助氏がきわめて作話性のつよい人物であったこと、「百人斬り」の記事を書いた浅海記者が、この記事などをもとに銃殺刑に処せられた向井少尉のために、ついに、「あの記事は創作であった」と弁明しなかったことなど、日本人の社会的体質が露出するような事例に突き当たる。
鈴木氏は取材先のことをためらわずに書き込んでいる。近頃流行のニュージャーナリズムとやらは、情景描写や記者の《気分》まで書きつらねるのが普通になっているが、鈴木氏は証言者の「発言」の裏を流れる感情も微妙に酌みとろうとしている。この作業が成功しているか否かは、読者の判断に委せたい。
再読を終わって、私にもう一つの感慨があった。テレビ時代である。映像を媒介として構成される情報は、ペンによるそれよりも、強烈な価値のパラダイムを作りやすいのではないか、という思いである。いや、それはすでに始まっているのかもしれない。
(評論家)
る還へ料資件事京南