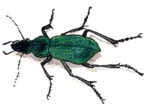
![]()
2005年11月
テントウムシたち 11/27
団地の階段の隅っこで見つけました。今の季節、そこらじゅうにテントウムシがいます。階段を上り下りしていて、危うく踏みつぶしちゃうんじゃないかと心配になります。
テントウムシたちは、寒くなるとこんなふうに建物の隅などで身を寄せ合っています。写真はナミテントウですが、よく見ると1匹だけ(上から3つめ)模様がちょっと違うのがわかります。ナミテントウは結構いろんな模様のバリエーションがあるらしいのです。
ヘナの復活 11/17
これはヘナというバラなのですが、最近こうして花が咲きました。今頃の季節に咲くのは、決して珍しくはないようです。団地の下に植えられているバラにも、いくつか咲いている花やつぼみがあります。
今年の春に買って、一度絵に描いたことがあります。ところがそのあと枯れてしまったのです。うどん粉病とかいう病気だったようで。バラは育てるのが意外に難しい。でも、あきらめずに水や肥料をやり続けていたら、こんなふうに復活しました。まだ一輪ですが。
おしゃれなカメムシ 11/11
カメムシ第2弾。エサキモンキツノカメムシといいます。長い名前ですね。体長約14mm。背中の白いハートが何ともおしゃれ。素敵な模様でしょう。いや、どことなくお侍の紋付きにも似ているような。
団地の4階で見かけました。前にも言いましたが、今の時期はカマキリとテントウムシとカメムシがそこら中を出歩いているのです。死骸もごろごろですよ。
このカメムシ、もう少ししっかり撮影しようと思って家に持って帰ったのですが、いつの間にか姿を消しました。死んでなきゃいいのだけど。
クモの芸術 11/7
今朝家の近くで、たまたま見つけました。朝日を浴びてきらきら光っていたんです。朝8時頃のこの時間帯だけ、太陽があたって、こんなふうに輝くのです。ただのクモの巣なんだけど、こーんなに丸いきれいな形のものは、なかなかお目にかかれません。わざわざ家までカメラを取りに帰って、撮影しました。
家主はどんなクモなのだろう。真ん中にクモのようなそうでないようなものがいたけれど、よくわかりませんでした。もしかすると留守だったのかも知れません。
昨日の夕方から降っていた雨が朝早く上がったのですが、雨粒が糸に残っていたらもっときれいだったろうなあ。
ナナフシ 11/6
これも青梅市の御獄山で見つけたもの。ナナフシは昔、多摩動物園の昆虫館で見たことはありますが、自然の中で見たのはこれが初めてです。光が丘ではまだ一度も見かけてません。
写真のはまだ幼虫。羽が完全に延びきっていないのでわかるでしょう。体長は5cmほどでした。カマキリの仲間ですが、動きが実にスローで、人が手を出しても、逃げるでもなく威嚇するでもなく、ゆっくりと動きます。幼虫だからかなあ。カマキリとはまた違った印象を受けました。
何とかヘリカメムシ 11/5
青梅市の御獄山(みたけさん)で、3日に見つけた虫です。今の季節によく見かける虫は、カマキリ、カメムシ、テントウムシ、といったところでしょうか。でもそれぞれにいろんな形や大きさや色があるので、見ていて飽きません。
このカメムシ、図鑑で調べましたが、ホソヘリカメムシかクモヘリカメムシのどちらかだと思います。図鑑の写真と細部が微妙に違っていて、今ひとつ断定できません。ホソヘリだったら、毒虫、危険!……でも頭の形がひょうきんですね。ちょっと踊ってるでしょう。体長約16mm。





