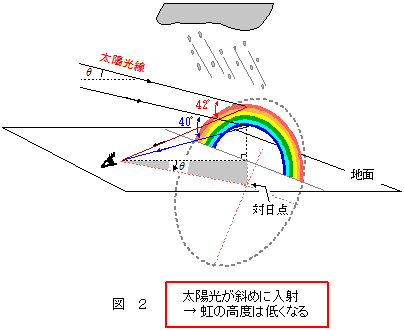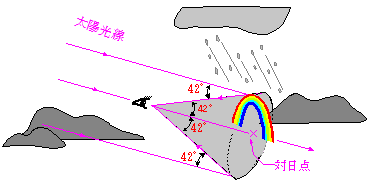
図1のように太陽光線が水平に差し込む場合,対日点は地上すれすれの位置にあって虹の高度は最も高く,大きな虹になって見えます。
太陽光線が水平に差し込むのは夕方か朝方なので,この時間帯に見える虹が最も大きな虹…ということになります。
虹の大きさは虹を見上げたときの仰角の大きさで感じますが,虹の実半径は観測者から降雨地までの距離に比例します。観測者と降雨地との水平距離を $x$ とすれば,例えば主虹「赤」の散乱角を $42^\circ$ として,主虹「赤」の半径は, $x \times \tan 42^\circ$ となります。 したがって $x = 1 \mathrm{km}$ とすると,その半径は約 $900$ mほどになります。
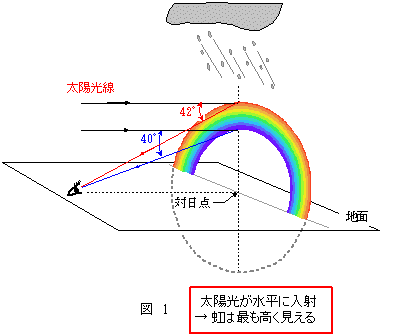
一方図2のように,太陽光線が斜め上方から差し込む場合,虹のできる円錐面は下方に傾くことになります。その結果対日点は地面の下に位置し,円弧の一部のみが地上に顔を出します。ここに虹ができるわけですから,虹の高度は低くなります。容易に分かるように,太陽の高度が高いほど,したがって太陽光線の入射角度 $\theta$ が大きいほど,虹の高度は低くなります。そして, $\theta$ が虹のできる角度 $40^\circ \sim 42^\circ$ より大きくなると主虹の円錐面全体が地面の下に没してしまうことになり,主虹はできないことになります。副虹についても同様のことが言えます。