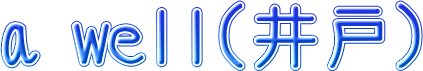
いま、庭に井戸掘りをしています。その様子を少しづつ書いていこうかなと思っています。
と、記述して早3年がたちました・・・・。
このGWの連休を利用して一応足掛け3年(うち2年半はほったらかし状態)の井戸を完成させました。
完成編はこちらです
| <何で井戸?> | |||||
| ある日、庭の水やりの最中に、「この水が井戸水だったら水道代が浮くよなあ?」と思いつきました。 そこで、もし業者に井戸掘りを頼んだらいくらかかるかネットで調べたところ、井戸掘りの業者についてはうまく検索できませんでした。その代わり、簡単な道具で自分で井戸を掘った人のページをいくつか見つけました。 で、僕も掘ってみようと思い立ったのです。 井戸掘りの詳しい原理や、掘り方はここ(自分で出来る打ち抜き井戸の掘り方)を参考にしました。 |
|||||
| <1>準備 | |||||
| まず、井戸掘り器の準備です。 ホームセンターで井戸掘り器の先端部の部品のみを購入し試作品を製作。 柄は壊れた竹馬のシャフトをネジで止めて試し掘り。ちゃんと砂を吸い込むほれることを確認。 そこで、パイプを買いにいつもお世話になってる水道工事店に行きパイプや継ぎ手を購入。事情を説明すると、最適な材質の部品を教えてくれました・・・。(ホームセンターで自分で悩んで選ぶより安心) 値段は・・・、まだ請求書が来てないのでなんともいえないけどホームセンターより安いはず。 早速買ってきた部品を試作機に取り付け井戸掘り開始。
|
|||||
| <2>井戸掘り開始 | |||||
 |
井戸掘り初日の結果です。 1.5メートルぐらい掘ったかな? なんと、ヘドロの層があり、くさいしどろどろしているので結構苦労しました。 中に水が溜まるので、作業しにくいときにはお風呂ポンプで水をくみ出してします。(古いお風呂ポンプが家にあってよかった。) |
||||
| <3>難関 〜小石の大群〜 | |||||
| 井戸掘り二日目のことです。石が多いうちの庭ですが、やっぱり石に直面しました。 握りこぶし大の石が出てきます。根切りぐわという鍬で石をホジクリ出したりしました。 ←「根切りぐわ」です。本来の用途は木の根を切るのかな? ヘドロ層も通過して、うまくいくと思いきや、今度は前出の石とは異質の石がごろごろ出てきます。よく見ると、浜辺に落ちている石ではないですか!角のない丸っこい石しかも握りこぶし大のものがたくさん出てきます。 石をはさむツールを準備し、それで石をつついてつかんでは外に出す。つついて、つかんで、外に出す、の繰り返しです。  ← ←このような、小さい火箸を棒にくくりつけた道具を用意しました。紐を引っ張ると先を閉じるようにしています。 小さな小石は、溝掃除の道具の柄を延長したものを併用します。この道具を中に入れ、中で、先ほどの火箸で小さ目の石を集め入れてまとめて引き上げます。  ← こんな感じの道具で、本来は溝のヘドロをすくう道具のようです。  ← こんな感じで、お風呂ポンプで水をくみ上げながら、底の石を拾っていきます。 <↓作ったけどいまいちだった道具たち↓>   ← ←三目ぐわ?の小型の物の柄を延長しました。 これで小石をかき寄せてすくい取ろうとしましたが、隙間が大きすぎてさっぱり小石が取れません。  ← ←クッキーの缶の底にドリルで穴を開け鉄の棒に針金で縛り付けました。 やはり「すくいにくく」「すくう量も少ない」ので、あまり役に立ちません。  ← ←針金ハンガーの針金を四角い枠にし、オクラの入っていたネットを縫い付けました。 中に入る石が少ないのと、枠がやわらかいので石を拾いにくいです <でてきた小石>  小さいのは、無舗装の駐車場とかにしかれているバラス石ぐらいの大きさの石から、僕の握りこぶしより大きいぐらいの石まで出てきます。まだまだ、たくさんの小石が埋まっていそうな気配です この石、よく見ると。海辺に転がってる石にそっくり。そういえば、「昔この辺は浜辺だった」と年寄りが言ってるので、昔浜辺だったころの石かもしれません。 |
|||||
| <今の状況>三年間ほったらかしてました | |||||
  やっと2mの鞘管(井戸側)が入るぐらいの深さになりました。 連日の雨天のため、水がここまで出てきています。 雨水がたまってるのでなく底から湧いてる感じです。 でも、まだまだ掘り進まにゃいけません。 |
|||||
| この続きはこちらへ | |||||
To Top

