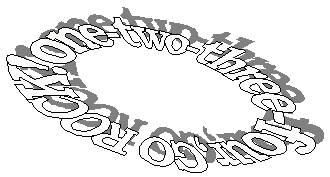
British Rock or Psyche Pop etc...
- K -
選択されたCDにスクロールされるまでしばらくお待ちください。
このページから出る場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを使用してください。
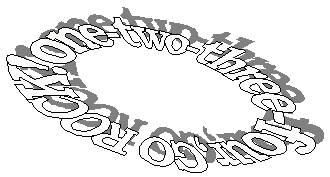
 TANGERINE DREAM/KALEIDOSCOPE
TANGERINE DREAM/KALEIDOSCOPE
B級ブリティッシュロックバンドが1967年に発表した1STアルバムに最初の3枚のシングル曲をプラスしたもの。ねじり曲がったロゴにメンバーのサイケな衣装、それが上半分にある鏡(?)に映ってぐにゃぐにゃになっているというジャケットがそそります。
このグループはよく、初期PINK FLOYD的だといわれています。確かに「DIVE INTO YESTERDAY」など、何曲かではPINK FLOYDの1ST「夜明けの口笛吹き」で聞かれた過剰なエコー感があります。でもトリップ感はありません。「THE SKY CHILDREN」など、後のFAIRFIELD PARLOURを思わせる湿っぽくてなよなよした「泣き」のメロディーが多い。
また、ボーカルが下手なのがB級臭さを強めています。ただしシングル曲も含め全曲をメンバーのオリジナルで勝負したのは偉いと思います。
デビュー曲でもある「FLIGHT FROM ASHIYA」はまさしく1967年のブリティッシュ・サイケデリックの影響をもろかぶった曲。SYD BARRETのスライドギターが今にも聞こえてきそう。B面だった「HOLIDAY MAKER」もなかなかキャッチーな曲
でも2NDシングル「A DREAM FOR JULIE」からはサイケデリック・エラは感じられず、3RDシングル「JENNY ARTICHOKE」に至ってはバブルガム的な曲。「JENNY ARTICHOKE」のB面「JUST HOW MUCH YOU ARE」はもう少しアレンジに凝って上手い女性ボーカルだったらもっと曲が映えただろう佳作。
2NDアルバムはプログレ的だというし、VERTIGOレーベルに残したFAIRFIELD PARLOURの1STはトラッドフォークぽいし、当時は未発表に終わったFAIRFIELD PARLOURの2NDは何とロックオペラだというし、流行りものを追いかけた節操のないグループという印象が残ります。(1998/08/30)
 FAINTLY BLOWING / KALEIDOSCOPE
FAINTLY BLOWING / KALEIDOSCOPE
1969年発表のセカンド。これは2005年に出た日本盤紙ジャケCDです。ジャケットがなんとも魅惑的。霧がかった森に中世風や妖精風に扮した人物を配した、いかにもオリジナルLPは値がはりそうな、ブリティッシュものとしては出来すぎなジャケです。
アルバムの1曲目「FAINTLY BLOWING」はフィードバックが印象的でトリップ感あるスリリングな曲。アルバム最終曲「MUSIC」は長尺でサウンドコラージュ的な曲。プログレ的ともよく評されるが、まだまだサイケの範疇だと思う。
この最初と最後の派手めな曲に挟まれて、その間には穏やかめな、彼らなりのリリシズムや美意識が溢れる曲が詰まっています。歌詞のイメージが伝わらないと魅力半減なのかもしれません。1967年のファーストでは生硬で青臭く、どことなく日本GSのようなセンチメンタリズムもあったが、本作では大分こなれてきた印象。本人が成長したのか、プロデュースやアレンジのためか。後身FAIRFIELD PARLOUR風のフォーキーな曲もあり、美麗なオーケストラを配した2曲「IF YOU SO WISH」「BLACK FJORD」も印象的です。
ボーナストラックではシングルA面曲が2つ。「DO IT AGAIN FOR JEFFREY」はホーン付きの華やかな曲。「BALLOON」は何となく低年齢層向けな穏やかで優しげなシャッフル調。彼らの意匠が感じられるアルバム曲の後で聴くと、致し方ないですが、かなり営業的な印象。
彼らは楽曲の出来だけでなく、ロマン主義的だという歌詞や、ジャケットなどイメージ面にも気をかけた、良い仕事を残したグループと言えるでしょうが、個人的にはボーカリストにもっと魅力があれば、もっと売れたかもとも思います。(2005/09/18)
 TIMELESS AND STRANGE / KEITH CHRISTMAS
TIMELESS AND STRANGE / KEITH CHRISTMAS
後にESPERANTOに加入(1作のみで脱退)し、あのMANTICOREレーベルからも作品を出す。プログレ関係者とも見られがちなフォーク・アーティスト。「FABLE OF WING」(1970年)と「PIGMY」(1971年)からと未発表ライブ1曲からなる編集盤。1969年の「STIMULUS」からは選曲されていないのは残念。ただし、前記の未発表ライブ曲は「STIMULUS」収録曲。
「FABLE OF WING」では1曲が長めで、特にインスト部分が展開されている。しかしアシッドやサイケ的なところはまったく無く、全般的に淡々としてクール、KEITHのやや悲しげな声と相まって、抑制がきいて知的な印象もある。ジャズ・ロック風な「WAITING FOR THE WIND TO RISE」で大活躍するピアノはKEITH TIPPETTのようだし、「THE FAWN」はSHELAGH McDONALDという人の美声が印象的。「LORRI」へと続く構成も良い。「KENT LULLABY」はなんともハモンドが目立つ。
一方「PIGMY」は弾き語りにストリングスを被した曲やよりシンプルな演奏が多く、前作よりもフォーキーな出来。NICK DRAKEとの仕事で知られるROBERT KIRBYがストリング・アレンジを担当したとのこと。特に「TRAVELLING DOWN」「EVENSONG」はストリングスによって端正で美しい佇まい。一方泥臭い「THE WAITING GROUNDS」や前作と同路線の「SONG FOR A SURVIVOR」という曲もある。最後の「FOREST AND THE SHORE」はアルバム最終曲らしいやや荘厳なアレンジ。(2004/02/22)
 HENS' TEETH / BRINSLEY SCHWARZ (FEATURING TRACK BY KIPPINGTON LODGE)
HENS' TEETH / BRINSLEY SCHWARZ (FEATURING TRACK BY KIPPINGTON LODGE)
BRINSLEY SCHWARZ名義ながら、その前身であるKIPPINGTON LODGEが公式に残した全録音であるシングル5枚分のAB面曲を収めたCD。そもそも本盤にBRINSLEY SCHWARZ名義の曲は4曲しかなくて、あとは彼らがBRINSLEY SCHWARZ時代に変名で発表したシングル曲が収められている。さらに交錯することに邦題は「アーリー・ワークス・オブ・ニック・ロウ」となっている。ともかくKIPPINGTON LODGE名義の10曲がまとめて聴けるので便利な一枚。
彼らの5枚のシングルの内、最初の2枚はMARK WIRTZプロデュースによるもの。当時の慣例で、演奏はメンバー達ではなくセッションマンによるもの、コーラスはライナーによるとIVY LEAGUEがゴーストして、そこにメンバーの歌を重ねただけらしい。とはいえ、ポップソングとしてみれば最も完成度の高いのはやはり最初の2枚。デビューシングルで、KINKSを思わせるトラジカル・コメディな「SHY BOY」、2枚目のシングル曲でこれも痛切な「RUMOURS」だけでなく、B面であるオリジナル「LADY ON A BICYCLE」「AND SHE CRIES」も手抜きなしの完成度
3枚目の「TELL ME A STORY」からMARK WIRTZを離れるが、この曲はまだ残滓がある。後にVANITIY FAREに引き抜かれるメンバーBARRY LANDEMANの作品。4枚目の「TOMORROW,TODAY」はソフト・ロック界で著名なCOOK=GREENAWAYによる作品だが、大した出来ではない。
5枚目で最後のシングル曲「IN MY LIFE」はBEATLESの曲のアートロック風カバー。B面にあたる「I CAN SEE HER FACE」はやっと出てきたNICK LOWE作品。後にパワーポップ職人になる彼の、最初にレコード化された作品はまるでVANILLA FUDGEがLOVIN' SPOONFULLの「SUMMER IN THE CITY」を演奏しているような曲。
BRINSLEY SCHWARZ時代の曲はやはり60年代のKIPPINGTON LODGEとは落差があり、同じCDでまとめるには難があると思います。(2001/12/16)
 KOOBAS / THE KOOBAS
KOOBAS / THE KOOBAS
リバプール出身の彼らが1969年に発表(録音は1968年)した唯一のアルバムにシングル曲をプラスしたCD。彼らはこれ以前にPYEから出したシングルがあったり、KUBASという別名義で出した音源も存在する。BEATLESとマネージメントが同じだったという彼ら。BEATLESの最後のUKツアーの前座だったとか。本作でもレコーディング・エンジニアはBEATLESの「SGT. PEPPER'S」での最大の功労者であるGEOFF EMERICKが担当している。
ジャケ写での不敵な笑みが象徴するように、サイケというよりは、R&Bから発展してハードロック直前という印象。陽気さや脳天気さはあまり無い。ジミ・ヘンの影を感じるギターと、うねうねと動くベース。ちょっと粘着質なボーカル。そんなフォーピースの演奏に時折メロトロンが被さる。メロディーも悪くない。コーラスもしっかりしている。前半はイントロにささやき声やフラメンコやら口笛などのSEが入る曲が多い。このあたりはGEOFF EMERICKらしい。
B面に当たる部分の方が出来がよいように思えます。1998年に出たアビーロードスタジオのヒストリーシリーズにも収められた、最もキャッチーな曲である「BARRICADES」に始まり、アルバム中では異色な、ソウルフルな「A LITTLE PIECE OF MY HEART」をはさみ、陰影のあるロッカバラード「GOLD LEAF TREE」からちょっとオリエンタルな「MR.CLAIRE」につなぐ展開が聴きもの。動静の切り替えがあるドラマチックな展開はハードロック/プログレ的。アルバム最終曲「CIRCUS」はタイトル通りサーカスの実況中継といった感じ。SEだらけ。ちょっと意図がわからないですが。
ボーナスとして収められたシングル曲はアルバムと同時期の「FIRST CUT IN THE DEEPEST」(P.P.ARNOLDが歌ったCAT STEVENSの曲)と「WALKING OUT」以外はティニー・ポッパーな曲調で、アルバム曲とは好対照。(2000/10/15)
 HUSH THE DEFINITIVE COLLECTION 1967-1973 / KRIS IFE
HUSH THE DEFINITIVE COLLECTION 1967-1973 / KRIS IFE
MARK WIRTZ関連アーティストとして認知されているアーティスト。2006年に出たこのCDは、1967〜1968年にかけてMGM、MUSIC FACTORYから出たシングル曲、JUDDアルバム全曲とアウトテイク、JUDD名義での1971年のシングル曲、JACKSON&JONESという名義の1971年と1973年のシングル曲からなるもの。
結論から言えば、MARK WIRTZブランドのサイケ・ポップを期待するとかなり落胆します。何よりもPARLOPHONEに残された2枚のシングル曲が未収録というのが痛い。JOHN PANTRYが書いた「THIS WOMAN'S LOVE」も少々期待はずれ、JUDDもアルバム曲のみだが別途CD化済。
だが、サイケ・ポップでなく、ポップ・ソウルや英スワンプとして捉えれば聴きどころの多いCD。KRIS IFEのソウルフルで熱い声も(好みは分かれそうですが)良い。DEEP PURPLEより早くカバーした「HUSH」、JIMMY CLIFFが書いた正統派R&Bな「GIVE AND TAKE」あたりは勢いを感じます。
この流れでJUDDのアルバム曲を聴けば、JUDDというのがKRIS IFE主導のポップなスワンプを目指したプロジェクトだったことも伺えます。MARK WIRTZプロデュースという情報やあのジャケに惑わされていたかと思えます。(そういえば2001年に出た
「THE FANTASTIC STORY OF MARK WIRTZ AND THE TEENAGE OPERA」
でも、KRIS IFEが絡んだ作品のみ、ソウル/R&B色が濃厚なのが印象的でした。)
まあ、そんな中では「UNTIL TOMORROW」「THEE」はMARK WIRTZのアレンジ手腕が効果的なバラード。JUDDのアルバムのアウトテイクだという「STILL STILL STILL」はゴスペル色も感じられる佳作。1971年のシングル曲も同路線。JACKSON&JONESでは、厚めのストリングスがフィル・スペクター風というか、男声デュエットがもろライチャス・ブラザース。(2006/08/15)