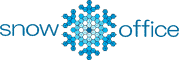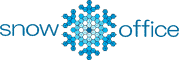| |
|
42:底なし沼
清水小学校裏付近に幾つかの小さい沼があり、その一つを底無し沼と呼んでいた。この沼に踏み込むと足が抜けなくなり、子供たちに恐れられていた。
|
| |
43:オテーネの沼
この沼は金太郎方面にあった裏沼、底なし沼や大沼(緑ヶ丘リンク)の名称ができるまえの名称で、この付近をオテーネと呼ばれ、先の沼が一体となって繋がっていた時の名称で、山線ができたころからオテーネの沼と呼ばれていた。 |
| |
|
44:大沼
現在の市立病院付近に大沼と呼ばれる沼があり、冬になると天然の市営リンク(緑ヶ丘リンク・ガマの穂リンク)があった。大沼は、トンギョ(トゲウオ)やゴザッペ(フクドジョウ)などの小魚がよく釣れ、子供たちの遊び場になっていた。
|
 |
| 昭和36年の天然リンクの緑ヶ丘リンク |
| |
|
|
45:カラス貝の沼
支笏湖道路を挟んで緑リンクの東側に広い沼があり、無数のカラス貝が生息し、浅いことから子供たちの遊び場となり、帰りにはカラス貝を持ち帰っていたりしたことからこのように呼ばれるようになった。この南側や付近には、戦車壕があり、大沼と同じように小魚がよく釣れた。
|
 |
| 昭和33年ころの緑ヶ丘公園から東側(煙突は岩倉ホモゲン工場) |
| |
|
46:へび沼
この沼は、カラス貝の沼より東にあり、今の駒沢高校あたりで、東西に長いこいとからへび沼と呼ばれるようになった。元々湿地帯の連続の場所であり、どこも子供たちの格好の遊び場となっていたが、親に内緒でなければいけない場所だった。緑ヶ丘からこの辺までの山際にはトーチカが点在していた。
|
 |
| 苫小牧地方主要旧地名・名称図の中央部 |
| |
|
47:遠浅沼
遠浅沼は、かなり大きな沼であったが、国土地理院の勇払地区調査報告書(国土地理院技術資料D1-No.419
)で、遠浅沼や安藤沼などは、1965〜1985
年頃の河川改修や用水路の建設等により現在では陸地となり、地形分類図では旧水部(旧版地形図や過去に撮影された空中写真により水部と確認されたもののうち、人工的な改変・水面の低下・海岸線の海側への前進などにより陸化した部分)として記載され、消滅した湖沼に分類されることとなった。 |
| |
48:安藤沼
遠浅沼と同じで、消滅した湖沼に分類されることとなったが、現在の地図上でも静川遺跡の北側にその形を確認でき、グーグルアースでも確認できるが、常時水を湛えていないことから消滅湖沼となっている。 |
| |
 |
| 苫小牧地方主要旧地名・名称図の東部 |
| |
 |
色々と資料を見ていると、気になる名前(下記)が出てくるもので、それをチェックしていると時間が無くなってしまうので、ここで終了するが、ここまで調べるのに図書館職員に随分とお世話になった。
この場を借りて、感謝をしたい。ありがとうございました。またよろしくです。
●沼のマコマイ(ト・マコマイ)川・ヒバリ川飛行場・ヒバリ川
糸井駅から大曲に向かって「沼のマコマイ川」があり、旧苫小牧川に流れていて、有珠川西に長尾の沼、東側に無名の沼、法華寺沼、神社沼があったが、昭和14年からの河川改修により消えていった。この名前が、苫小牧の原語のようである。
|
|
●坊主山・丸山・王子山・坊主山スキー場
坊主山は丸山(マルヤマ所有)と呼ばれていたが、王子製紙が所有すると放牧のために木々を伐採したことから、坊主山といわれるようになった。現在王子山と呼ぶ人がいるが、王子山はもっと広い範囲が王子製紙の山であり、その広い範囲を指して王子山というものである。
●新苫小牧川
糸井地区の土壌改良を目的に昭和27年から28年に有珠川を直接海へ流す工事が行われ、苫小牧川と有珠川(旧名ウシ川)が分離されたが、昭和41年から昭和59年にかけて鉄北湿地帯地区の排水を目的に工事が行われ、再度苫小牧川と有珠川がつながり、合流地点の海側を新苫小牧川とした。
●新川
新川通りに有った川で、明治25年頃に坊主山の手前あたりから防火用水として現新川通り北側(旧苫小牧川の東側)から引かれたもので、新しい川=新川となったもので、旧苫小牧川に流れていた。
|
|
|
|