「教草吉原雀」本文
以下の翻刻の改行は、表紙を除いて、板本の改行に合わせてあります。
( )内は、適宜漢字を当てました。「図版#」参照の後は、ブラウザの「戻る」の機能を用いて下さい。
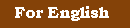
(一丁表)
長唄 冨士田吉治 三弦 杵屋作十郎 杵屋佐次郎
小つづみ 堅田新十郎 たいこ 田中伝左衛門
原板 沢村利兵衛 求板 丸屋鉄次郎
八幡太郎よしいへ 市村羽左衛門 平賀のたかのせい 吾妻藤蔵
教草吉原雀 市村座 酉ノ二月再板 上下
豊久画
(一丁裏)
教草吉原雀
およそいけるをはなすこと人王四十四
代のみかど(帝)くわうせう(光正)天わう(皇)の御宇か
とよ 養老四年のすへ(末)の秋 宇佐八まん(幡)のた
くせん(託宣)にて 諸国に始る放生会 浮寝の
鳥にあらね共 今も恋しき一人住 小夜の枕
よし原
(二丁表)
にかた思ひ かはい(可愛)心とくみもせで何じや何
やらにくらしい 其手でふかみ(深み)へはまちどり(浜千鳥)かよ
い馴たるどて(土手)八丁 口八丁にのせられておき(沖)のかもめ
の二てう(挺)だち 三てう(挺)立 すけん(素見)ぞめきはむく
鳥のむれ(群)つつきつつき(啄木鳥)かうしさき(格子先)たたくゝ
ひな(水鶏)のくちまめ鳥に くじやく(孔雀)ぞめきて
(二丁裏)
めじろ(目白)おし みせすがかき(見世清掻)のてんてつつとん さ
つさおせおせ な(馴)れしくるわ(廓)のそでの
か(袖の香)にみぬやうで見るやうで きやく(客)はあふぎ(扇)
のかきねよりしよ(初)心かはゆくまへわたり
サアきた またきた さはり(障り)ぢやないか 又お
さわりかおこし(腰)のものもがつてん(合点)か 夫(それ)あみ
よし原二
(三丁表)
かさ(編笠)もそこにおけ 二かいざしき(二階座敷)はみぎか
ひだりかおくざしき(奥座敷)でござりやす はや
さかづき(盃)もつてきた とこ(床)へしづかにお出な
さんしたかへといふこへ(言ふ声)にぞつとした しんぞき
様(新造貴様)はねてもさめてもわすられぬ せうしきの
どくまたかけさんす 何かけるもんだへ そふした
(三丁裏)
きぎく(黄菊)としらぎく(白菊)のおなじつとめの其中にほか
のきやくしゆ(客衆)はすて小船 流もあへぬ紅葉ば
のめだつふよう(芙蓉)わけへだて ただなでしこ(撫子)と
神かけて いつかくるわをはなれてしおん(紫苑) そふした
心のおにゆり(鬼百合)と思へば思ふときもせきちく(石竹)になる
はいなア すへはひめゆり(姫百合)おとこめし(男郎花)その楽しみもう
よし原三
(四丁表)
すもみぢ(薄紅葉)さりとはつれないどふよく(胴欲)とかきね
にまとふ朝がほ(朝顔)のはなれがたなきふぜい(風情)な
り しののめ(東雲)か ことがすぎしくぜつ(口舌)の中直り一ト
たきくゆる(燻る)なかうど(仲人)の其つぎき(接木)こそゑん(縁)のは
しそつちのしやう(性)がにく(憎)ひゆへとなりさしき(隣座敷)
のさみせん(三味線)にあはすわるじやれ(悪洒落)まさな
(四丁裏)
ごと(正無事)女郎の誠と玉子の四かく(角)有ばみそかに
月も出る しよんがいな 玉子のよほほいほい
いよほい ほいほいよほほいほ 玉子の四角あれば
みそかに月が出る しよんがいな ひとたき(一炊)はお
きやくかへ きみのねすがた(寝姿)まど(窓)から見れ
ばほたん(牡丹)しやくやく(芍薬)ゆり(百合)のはな しよんがいな
よし原四
(五丁表)
しやくやく よほほいほいいいいよほいほいほいほいよ
ほほいほ しやくやくぼたん ぼたんしやくやくゆり
のはなしよんがいな つけさしはこつちやか
へ エエ はらがたつやらにくひやら どふし
やうこうしやうにく(憎)むとり(鶏)鐘 あかつ
きのめうじやう(明星)が にし(西)へちろりひがし(東)へち
(五丁裏)
ろり ちろりちろりとする時は内のしゆび(首尾)は
ふしゆびと成て おやぢ(親爺)は十めん(渋面)かか(嬶)はごめ
ん(御免)十めんごめんににらみ付られ いな(往)ふよもど(戻)
ろふよといふては小こし(腰)に取ついてならぬぞ
いなしやせぬ 此頃のしな(仕為)しぶり にくい
おさんがあるわいな ふみのたよりになア
よし原五
(六丁表)
こよい(今宵)ごんすとそのうはさ(噂)いつのもんび(紋日)も
ぬしさんのやぼ(野暮)な事じやが ひよくもん(比翼紋)
はなれぬ中じやとしよんがへ こよい
ごんすと其うはさ いつのもん日もぬしさん
のやぼなことじやがひよくもん はなれぬ中
じやとしよんがへ そまるゑにし(染まる縁)のおもしろ
(六丁裏)
や げにはなならばはつざくら(初桜)月な
らば十三夜 いづれおとらぬすいど
し(粋同志)のあなたへいひぬけ こなたのだて(伊達)
いづれ丸かれ候かしく
文久四年
甲子之春再翻
よし原六了