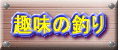● 海上釣り堀についての考察 ●
■はじめに■
私が海上釣り堀の話を切り出すと、熱心に釣りを楽しんでいる友人ほど、「そんなもの、生け簀に魚が入っているのだから、釣れて当たり前」と、あたかも釣りの邪道の様に言われてしまうことがよくあります。
何を隠そう、この私も、初めは全く同じことを言いながら、釣り堀を軽視していました。
ところが、魚が少なくなってしまったのか、海の汚染が原因なのか、はたまた私の腕が落ちたのか、年々釣果が減って行き、やはり釣りというもの、あまりにつれない日が続くといやになってくるものです。(「辛抱が足りない」と言われてしまえば、それまでですが・・・)
■初釣行■
そんなある日、友人と話の種に一度は海上釣り堀にも行っててみよう、ということになり、「釣れて当たり前」の考えのもと、三重県尾鷲の堤防で見かけたことのある釣り堀へ、出向くことになりました。
平日の釣行であることと、三重県でもかなり遠い(名古屋から)場所であったため、友人KU氏と他のお客2人の合計4人でイカダに渡り、釣りを始めました。
たいした情報も得ず出向いたため、ありきたりな装備とエサでの釣りでした。
下図が、当日のタックルです。
| 「海上釣り堀」の仕掛け |
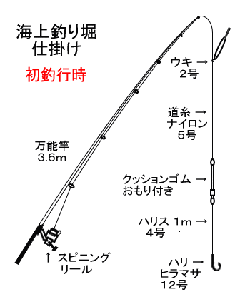 |
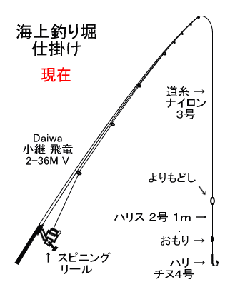 |
| ↑ 画像をクリックすると、拡大します。 ↑ |
が・・・、しかし・・・、1時間、2時間と時間が過ぎていくのですが、全く釣れません。
一緒になったお客2人も、同じレベルなのか釣れていませんでした。
さすがに、営業時間の半分(4時間くらい)が過ぎてしまい、あせり始めました。
こんなはずでは・・・・・? なぜ釣れないのだろう・・・・・?
そうして、ようやく釣り人の魂が燃え始めたのです!
○ エサ− オキアミの大きさを変えてみたり、カラをむいたりと試しました。
○ タナ− 船長に教わったタナ(深さ)を、上層から底まで、変えてみました。
○ ハリ− 大きさを、ワラサ用の大きいハリから、小さいチヌバリ3号に変えました。
○ ハリス− 太さを、ワラサ用4号から2号に落としました。
この様なことは、釣りにとって当たり前のことなのですが、なにせ高をくくっていたので、ついつい基本をおろそかにしてしまっていたのです。
悪戦苦闘の末、ついに、(いや)ようやく、(いやいや)やっとのことで、マダイがヒット!
その後、2匹追加し、釣果はマダイが3匹。
ううう・・・ん、生け簀に入っているとはいえ、自然の海を網で仕切ってあるだけなので、魚にとっても命がけで、さらに、潮の流れや満ち引きなどの条件も、他の釣りと同様に影響があることもわかり始めました。
この釣果では満足できないので、さっそく色々な情報を集め、もう少し上手になるまで研究してみよう、と考えるようになって行きました。
■研究中の事案■
それでは、まだまだ未完成ではありますが、私なりの釣果を上げる基本を書いておきます。
1.ポイント(場所)
イカダの係留の仕方や地形によって、潮の流れ方は様々ですが、潮の満ち引きにあわせて流れることや、魚の居心地がいい場所があると言うことです。
では、どの場所がいいと言うのは、一概に説明がつかない場合が多いので、他の人が連れた場所を記憶し、潮や時間の統計をとっていくことが必要になります。
始めて行く場所や、これが面倒な場合は、船長や店主に状況を聞いてみるのが一番です。
2.タナ(深さ)
マダイ、ワラサ、シマアジなどは、生け簀の中を数匹の群れで、同じ水深を保って回遊していることが多いので、そのタナを早く察知することが大切です。
もちろん、タナは一日のうちでも変化するので、こまめにタナを変えて探ってみることが重要になります。
3.エサ
エサの選択で、一番影響を受けるのは水温です。
15度前後を境に、水温が低いと柔らかいエサしか食わない傾向があるので、特にエビの類は、カラをむいてやることなど、工夫が必要になります。
また、水温が高くなれば、たいていのエサに飛びつくようですが、日によってえり好みが激しいときや、同じエサでは見向きもしなくなることがありますので、船長や店主に状況を聞いて、数種類のエサを用意し、ローテーションするとよいでしょう。
| マダイ |
基本的なエサ |
オキアミ、ウタセエビ、シラサエビ、甘エビ、ボケ、カメジャコ
練りエサ(ダンゴ)、ホタルイカ、ムシエサ(ゴカイ類)
キビナゴ、イワシの切り身
(これらは、たいていのエサ屋で手に入ります) |
過去に釣れた
ことのある
エサ |
ジャガイモ、カボチャ、ミカン、トマト、うどん、鶏のささみ
魚肉ソーセージ、カキ(海の)、ザリガニ
(これらは、基本エサで釣れないときに、昼の弁当のおかずをエサにしたことから始まっていますので、目先が変われば何でも食べるのかもしれません) |
| ワラサ、カンパチ、ヒラマサ |
生きアジ、生きイワシ、冷凍イワシ、アオムシ(ゴカイ)など |
| シマアジ、イサキ |
オキアミ、シラサエビ、甘エビ、練りエサ(ダンゴ) |
| イシダイ |
イシゴカイ、生きエビ、ボケ、カメジャコ |
ワラサなどの青物や、シマアジ、イサキ、イシダイなどは、状況が変わるので、船長や店主に確認する方が良いでしょう。
他、各人様々な工夫があります。 (ヒントは、くさい!、あまい!、派手!)
4.あわせ
腕に自信のある方は、早合わせの方がくちびるに針がかかり、ハリスが歯によって擦れることが少なくなるのでバラしが減りますが、基本的には、早合わせは禁物です。
特にウキ釣りの場合は、ウキが完全に沈むまで待つのが得策です。
また、青物以外をフカセ釣りで釣る場合は、竿の穂先が敏感なタイプのものを使い、魚がエサを食べている様子が竿に伝わってくるので、口に針が入った瞬間を見極めて合わせを入れます。
5.タックル
ウキ釣りではタナをこまめに探るのに手間がかかるため、フカセ釣りの方が便利なのですが、なにせ網の側面や底に根掛かりが頻発しますので、ビギナーの方はウキ釣りをお勧めします。
ハリスは、細ければ細い方が、魚の警戒心も薄れ、潮の流れの影響も受けにくくなるため良いのですが、やはり切れやすくなるため、下記のサイズが目安となります。
マダイなど → フロロカーボン系の4号〜2号
ワラサなどの青物 → ナイロン系の6号〜4号
針は、色々なタイプが販売されているので、魚に合わせて選択します。
大きさは、小さいに超したことはないのですが、小さすぎるとかかりが悪くなり、折れやすくなるので注意して下さい。
6.観察力
どんな釣りにも言えることなのですが、特に釣り堀の場合は、限られた場所に数人の釣り師が集まっているので、釣れた人への観察力が最重要だと考えます。
釣れている人の、エサ、タナ、ポイント(生け簀の縁か中心か)をよく観察しましょう。
聞いてみるのも良いですが、釣り人の習性で、親切に教えてくれる方もおられる反面、話半分のことが当たり前なので、自分の目を信じましょう。
■おわりに■
まだまだ、自信を持って解説するレベルに達しておりませんので、基本的なことばかりだと思われたかもしれませんが、これから海上釣り堀へ行かれる方への参考になれば幸いと思っております。
|