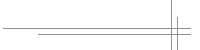|
|
|
|
|
|
11. 旅の意味するもの 12/10(Mon)
迷路のような島の中を歩いた。地図やふもとから見た感触よりも、中はずっと広かった。島には僧院があるだけと思っていたが、これは完全な「町」だ。円形の島を取り囲むように複雑な道路が張り巡らされ、自分がどこにいるのか全くわからなくなる。見上げると、あの特徴的な尖塔がどこからでも見え、それもまた方向感覚を狂わせるに充分だった。
早朝、日が明けぬうちに起き、朝焼けに浮かぶモン・サン・ミッシェルを見た。徐々に色を変えていくその姿に、同じような写真を何枚も何枚も撮った。気が付くと、太陽は高く昇っていた。昨日と同じく、全く雲のない快晴だった。
いったんホテルに朝食をとりに戻ったあと、入り口が開いてから島の中に入り、中を見てまわった。
 ずっと高揚感に浸っていた。日本を離れてからもう随分と日が経つというのに、ここから旅が始まったような気がしていた。そして、惜しみながら何度も振り返り、車を駆って帰路の寂しさを味わっていると、これって人生そのものになんか似てるな、と急に思った。 ずっと高揚感に浸っていた。日本を離れてからもう随分と日が経つというのに、ここから旅が始まったような気がしていた。そして、惜しみながら何度も振り返り、車を駆って帰路の寂しさを味わっていると、これって人生そのものになんか似てるな、と急に思った。
旅を人生に例えるとはまたベタな、と思われるかもしれないが、この時は心底そう思ったのだ。今回のパリは、一カ月近くという、これまでにない長旅である。それほど毎日漁るように観光地を回る必要はないかわり、どうしても緊張感には欠けてしまう。しかしモン・サン・ミッシェルには二日間しかいられない。そしてたぶん、もうここに来ることはないだろう。そう思うからこそ、たどり着いた時の感動があり、この場所に対する強い愛着も湧いたのだと思う。前回、一週間という短い期間でパリを訪れた時のように。
恐らく、パリに一生住むとなれば、この地に対する気持ちは、随分変わってしまうだろう。同じように、この世での生が永遠に続くならもう、何かに感動するとか、何かを愛するようなこともなくなってしまうような気がする。短い時間で終わってしまうと思うからこそ、やれる限りのことをやっておこうと考える。たぶん、帰る日が近づくにつれ、町に対する思い入れは深くなっていくだろう。
「終わり」を意識するというのは、ものすごく大事なことなのではないか。そんなことを思いながら、レンヌへの帰路、車を走らせた。
|
|
|
| |
|
|
12. リヨンにて(一) 12/13(Thu)
パリから遠出をする第二の目的地としてリヨンを選んだのは、作家遠藤周作氏の影響が大きい。氏が若い頃に留学し、そこに題材をとった作品が多数著されている。それらの多くを僕も読み、作品に出てくる風景を、実際に歩いてみたいと思った。
観光案内のあるベルクール広場に降り立ち、その近くでホテルをとる。部屋に入り、遠藤氏の住んでいたプラ通りを地図で探すと、ホテルから歩いてすぐの場所にそれは見つかった。
住所表示は、パリと同じだった。青いプレートに「RUE
DE PLAT(プラ通り)」という名前を見つけた時、何とも言えない感慨が胸に沸いた。
どうということはない道である。少し大通りから入り込み、近くにあるカトリック大学の学生らしき若者が、静かに通り過ぎていく。通りに沿ってしばらく歩くと、急に左手の視界が開けた。大きな赤い橋が見え、その背後にある丘には、中世風のいかめしい寺院が中腹に建っていた。河は、ソーヌ河である。リヨンの町はこのソーヌ河と、もう少し大きなローヌ河とが中心を走り、それらの河に隔たれて旧市街、商業地、新開地とに分かれる。大都会だが、構造は簡単だ。
遠藤氏が下宿したのはどの建物だろうかと考えた。正確な住所などはもちろん、知らない。小説に描かれている周りの風景も、もう50年近くも前の話だから、すっかり変わってしまっているだろう。しかし、この辺りだろうか、どちらにしてもこの辺りを確実に歩いていたんだろうな、などと考えながらうろつくだけでも、すこぶる楽しかった。
 ソーヌ河を渡り、丘のふもとに出た。このあたりが旧市街である。狭い道路が入り組み、まだ日はあるのに、薄暗い。丘沿いなので急な坂道が多いが、意外にたくさんの人がそこを昇り降りして通り過ぎていく。中世のまま、残された街。昔から変わらない場所というだけでほっとするのは、もし次に来る時があっても、同じ風景を見せてくれると思えるからだろうか。 ソーヌ河を渡り、丘のふもとに出た。このあたりが旧市街である。狭い道路が入り組み、まだ日はあるのに、薄暗い。丘沿いなので急な坂道が多いが、意外にたくさんの人がそこを昇り降りして通り過ぎていく。中世のまま、残された街。昔から変わらない場所というだけでほっとするのは、もし次に来る時があっても、同じ風景を見せてくれると思えるからだろうか。
再びソーヌ河に出、河岸の遊歩道を歩く。冬の薄い陽が静かに暮れていくと、ライトアップされた別の顔が浮かび上がってきた。もうかなり寒い。引き返し、夜も賑わうベルクール広場周辺に戻る。
ここでちょっと、嫌な一件があった。fnac(フナック)という、大きな店でのこと。CDや本、電化製品などを売っていて、パリにもいくつか店舗がある。この中を歩いていると、急に呼び止められ、リュックを開けて見せろと言われた。特に不審な行動は何もしていない。リュックは店に入ってから背負ったままだ。なぜ開ける必要があるのか、ただ歩いていただけだと言ったが、黒人の係員はフランス語でまくし立て、何を言っているのかわからない。
おおごとになるのも嫌なので、仕方なくリュックを下ろし、中を見せた。係員はしばらくごそごそとチェックしたあと、何も言わずに元の場所に戻っていった。
突然、腹が立ち、そいつに向かい日本語で怒鳴りつけてしまった。日本でもそんなことはしないのに、気が付いたらキレてしまっていた。係員は平然と立ったまま、聞き流していた。
ホテルに戻っても、気持ちは鎮まらなかった。それでも、リヨンそのものを嫌いになりたくはなかった。明日は、丘の上に登るケーブルカーに乗り、街のどこからも見ることのできた、あの寺院まで行く。そしてそれから、郊外にある公園まで足を延ばす。まだまだこの街でやることはあるのだ。
|
|
| |
|
13. リヨンにて(二) 12/14(Fri)
 その寺院は、ノートルダム・ド・フルヴィエールという。メトロでヴュー・リヨン(旧市街)に移動し、そこからケーブルカーに乗って丘の上に登ると、昨日、街なかから見上げた壮大な建物が、すぐ目の前に出てきた。 その寺院は、ノートルダム・ド・フルヴィエールという。メトロでヴュー・リヨン(旧市街)に移動し、そこからケーブルカーに乗って丘の上に登ると、昨日、街なかから見上げた壮大な建物が、すぐ目の前に出てきた。
中に入ると、他の寺院などと違い、床が細かなタイル張りになっていて美しい。どこかを工事中なのかドリルの音がやかましかったが、その騒音の合間を縫って、小さな音量で賛美歌が流れていた。
中庭に出ると、さすがに高台だけあって、そこから眺める景色は素晴らしかった。上から見ないとわからないが、リヨンの建物の屋根は多くが茶褐色に塗られていて、その統一された色調が街の雰囲気を保っていた。写真でしか見たことのない、フィレンツェの町によく似ている。山側に目を移すと、ソーヌ河が大きく蛇行し、その静かな存在感を示していた。
午後遅く、街の北側にある公園にたどり着いた。ガイドブックには載っていないこの場所に来たのもやはり、遠藤周作氏の関連だった。作品の中に、リヨンの大きな公園を歩き、池のほとりにある音楽堂の裏手に、檻に入れられた猿が置き去りにされている、という描写がある。複数の作品で何度か出てくるシーンなので、よく知っている。今回持ってきた本の中にも、それはあった。公園の名前はわからないが、街の北にある大きな公園は、一つしかなかった。
着いてみると、なかなかに立派な公園だった。周囲に建物がひしめき合っている中にぽつんと出てくる感じは、ロンドンのいくつかの公園に似ていた。
日が沈みそうなので、足を速め、中を見て回った。小さな動物園があり、あまり手入れも行き届かないような場所なのに、ライオンや虎、豹など飼育の面倒そうな動物が多くいたのに驚いた。
さんざん歩き回ったあと、ようやく池が見えた。それ もかなり大きい。このほとりにある音楽堂と、檻を探さねばならない。日のあるうちに、池を一周しよう、そう決めて歩き出す。 もかなり大きい。このほとりにある音楽堂と、檻を探さねばならない。日のあるうちに、池を一周しよう、そう決めて歩き出す。
歩き終えた頃にはもう、辺りは薄暗くなっていた。音楽堂は見つからなかったが、それらしき建物と、檻は見つけた。作品に出てくる記述とは少し違うが、檻のイメージは、作品を読んだ時に抱いたそのままだった。
探し残した所も少しあったが、もう足は動かない。明日の朝、もう一度ここまで来てみることにし、ホテルに戻るメトロに乗る。
|
|
|
| |
|
|
14. リヨンにて(三) 12/15(Sat)
 池には全面に氷が張っていた。日本では見かけない大きな水鳥たちが、その氷の上を歩いていく。時折転びそうになるのが、野生動物にしては情けない。 池には全面に氷が張っていた。日本では見かけない大きな水鳥たちが、その氷の上を歩いていく。時折転びそうになるのが、野生動物にしては情けない。
昨日よりも、確実に寒さは増しているようだった。予定通り、朝のうちにもう一度昨日の公園を訪れ、池の周りを一周した。結局、目当ての音楽堂は見つからなかった。寒風吹きすさぶなかを、ジョギングやローラーブレードの若者が、耳元をかすめるように追い越してゆく。
公園を出てから、メトロの駅付近まで歩き、耐え切れずにカフェに飛び込んだ。ベンチにしばらく座り込んでいたせいで、体が冷え切っていた。ショコラ・ショーで温まるが、悪寒は去らない。風邪をひきかけているようだ。
考えた末、旧市街の丘にあるローマ闘技場に行く予定を覆し、早めにパリに戻ることにした。このリヨンの町で闘技場を見るのは必須事項ではない。また来るときのために残しておく意味もある。
メトロを、ベルクール広場の一つ前の駅で降り、そこから広場に向けて歩いた。まだ見ていないローヌ河を渡るためだ。方向を見失うことはない。フルビエールの丘を目指して行けば、確実にベルクール広場にたどり着く。
ローヌ河はソーヌよりも大きく、質素だった。フランス語だとローヌが男性名詞、ソーヌが女性名詞である理由が、はっきりと判る。丘に沿うように流れるソーヌ河は起伏に富み、見るからに優雅で美しい。橋の上から、河岸ぎわの遊歩道を歩くリヨン市民たちを眺める。みな、川面にもその向こうにある旧市街の丘にも目を向けず、寒さに身をこごめて歩いていく。確かに、寒い街だ。夕方には霧が出ると聞いていたが、今回それを体験することはできなかった。もちろんここで暮らす人々にとってはただ鬱陶しいだけの冬の象徴だろうけれど。
帰りのTGVには、3時前に乗ることができた。二つの河に挟まれたリヨン・ペラーシュ駅から出た列車は、最後の名残にローヌ河を渡り、暗い寒さの中をパリへと進む。
|
|
| |
|
15. 街の中で 12/19(Wed)
この国の人間は優しいだとか冷たいだとか、あの街は綺麗だとか汚いとか、一括りにして語る人がよくいるが、ナンセンスな話だと思う。パリにいても日本にいても、種類は違うが、嫌な思いをすることはいくらでもある。旅行中にそういうことがあると、記憶に深く刻まれやすいだけだ。
統計学的に言っても、全体の特質を述べるには相当数のサンプルが必要だ。実際にそれほどの数の人間と接することは不可能だろう。第一印象が、その人の街に対する評価を、画一的に決めている。
どの国や街に行っても、優しい人と冷たい人がいて、綺麗な場所と汚い場所がある。それだけだ。いや、優しい人と冷たい人、という言い方も実は正しくない。一人の人間の中に、冷たい部分と優しい部分があり、なおかつ同じ人が同じことをされていつも同じ対応をするかというと、そうでもない。日によって、気分によって、冷たい時もあれば優しい時もある。更に、同じことをされても、優しいと感じる人と冷たいと感じる人がいる。とにかく、それだけ混沌としたぐちゃぐちゃしたものが人間の本質だ。
それは、どこの国に行ってもそう変わるものでもない気がする。こちらは同じことをしているのに笑顔を返してくれる人がいれば、怒り出す人もいる。そして、もう一つ。みな、自己中心的だ。
でもこれも、当たり前の話。人に対する優しさは、まず自分の安泰が確保されてからの余裕だと思う。もちろんこれも統計学的に有効なサンプルから述べているのではない。単なる僕の感想だ。
リヨンへの行き帰り、遠藤周作氏の作品をいくつか読んでいた。作品の中には、日本の切支丹弾圧やナチのフランス侵攻などにおいて、人々が拷問され、信仰を捨てたり仲間を裏切ったりする場面が描かれていた。
自分にとって大切な人のことを、自分が拷問されても守れるのか。信仰を捨てずにいられるのか。信仰については元々ないから何とも言えないが、人を裏切らずにいられるかどうか、僕には全然自信がない。そして同時に、どんなに拷問されても自分は人を裏切らないという人がいたら、僕は その人を信用しない。そんな言葉には何の意味もないという場面を、これまで生きてきた中で幾度も見てきたからだ。 その人を信用しない。そんな言葉には何の意味もないという場面を、これまで生きてきた中で幾度も見てきたからだ。
自転車に乗り、緩やかな速度で過ぎ行く風景を眺めていると、そんないろんなことが頭に浮かんでくる。
たくさんの歩行者達。こちらの自転車を見てすぐに脇によける人、全くこちらに気付かない人、気付いても道幅一杯に広がり話をやめない人、…etc.
|
|
|
| |
|
|
16. 次なるトラップ 12/20(Thu)
 こちらでの生活ももう残り僅かとなった頃、次なるトラップに見舞われる。 こちらでの生活ももう残り僅かとなった頃、次なるトラップに見舞われる。
ヒーターが壊れたのだ。リヨンから帰った次の日、ちょうどパリも寒さが厳しくなってきた時だった。
寝る時にもヒーターの灯は消せない。それぐらい部屋は寒かった。コンセントの位置がベッドから遠く、何とか少しでも近づけようと画策したのが仇(あだ)となった。
ヒーターは電気で水を温めるタイプのもので、他の電気機器に比べ大電力となるため、配電盤に直接コンセントがささっているようだ。これが抜けないかと探っていると、実はコンセントではなく、配電盤とヒーターとを繋ぐユニットだった。そしてそれは、少し力を入れると、弾けるように分解した。
「バチン」
部屋の灯りが消えた。ブレーカーが落ちたのだ。これは、ここに住み始めてすぐに経験済みだった。落ち着いて壁を探り、ブレーカーを上げる。
灯りは点いた。配電盤から、コードと金具がぶらさがっていた。配電盤に突き刺すように金具を入れてみる。が、うまくはまらない。
かなり焦ってきた。このまま一晩中ヒーターなしというわけにはいかない。何としても、直さなければ。
遂に配電盤の蓋を開けることにし、四隅についたネジを外す。取り返しのつかないことになる予感はあったが、これより他に手段がなかった。
蓋を開け、ユニットの構造をしばらく調べてから、なんとか組み立ててみる。電源系なので、構造は簡単だ。たぶんこれで大丈夫だろうと思い、もう一度、ヒーターのスイッチを入れる。
点かない。電源ランプの調子が悪い時があるので何度かガシャガシャと入り切りしてみるが、変わらない。
すぐにブレーカーに目をやる。ヒーター個別のブレーカーが落ちているかと探したがそれはなく、代わりにヒーター専用らしき20Aのヒューズを見つけた。
原因がヒューズなら事は単純だが、買いに行くにしても、今日一晩は我慢しなければいけない。再び配電盤のユニットをいじってみる。同じだった。仕方がない。備え付けの箪笥に入っていた毛布を取り出す。ベッドにかけ、厚くなった布団にもぐりこんだ。
翌日の朝、朝食もとらずにメトロでBHVに向かった。ここは、モジュラー分配器の時にも役に立った大型スーパーだ。ここに行けば、家電関連のものは揃う。入ってすぐに目指すヒューズは見つかった。これで直れば、いい。もしこれで直らなければ、自力での対処は行き詰まる。
部屋に取って返し、ヒューズを入れてみる。
点いた!安堵と共にへたり込む。
トラブルへの対応力というのも、たぶん体力勝負なのだろう。疲れてくると、もう何も考えられなくなる。昨日の夜から、直らなかったらどうしようかと気が気でならなかった。ヒューズで直らなければもう、お手上げだ。目の前が暗く沈んでいく気がしたのは、クレジットカードが磁気不良で読めなくなった時と同じだった。
パリの生活に少しは慣れてきたかと自負しかけると、それを嘲笑うように何かが起こる。
|
|
| |
|
17. 手紙 12/21(Fri)
両親に、手紙を書いた。手書きで文字を書くなどという機会はもうほとんどなくなっていたので、書き終わった頃は、一大難作業を終えた気分だった。
長い手紙になった。それは、ここに来る前から考えていたことだった。こちらでの暮らしぶりに加え、去年の三人の旅行のこと、そして、仕事をやめたいきさつ、等々。
仕事のことは、辞める前後でもそれほど詳しい話をしなかったように思う。二度ほど帰省をしたが、通り一遍の話をするだけで、核心に触れるのを、なぜかお互いに避けているような気がした。
手紙で初めて、これからどうしようと考えているか、その辺のことを書いた。まだ誰にも話していない。それがうまくいくのかどうか、自分にも全く自信はない。ただ、そろそろちゃんと足を踏み出さなければいけない、そのためにこちらでの生活を引き上げなければならない、そのあたりの気持ちが、書いている最中に固まってきた。
昨日ベルサイユから戻り、パリの駅に降り立った時、正に「帰ってきた」という実感を味わった。リヨンから帰った時もそうだった。メトロの駅や、街の看板、教会の鐘の響き、そして、人の群れ。まだまだだと思っていた僕も、それなりにこの街の空気を体に包み入れ、自分のものとしていたようだ。
そう、ここには僕が寝起きをし、食事を作ってゴミを出す、いつもの部屋がある。使いにくいシャワーしかなく、ヒーターの行き届かない寒い部屋。キッチンと言っても狭く、まな板もない中、刃のこぼれた包丁で肉を切り、野菜を刻む。窓がうまく閉まらず、必ず鎧戸を閉めてから出掛けなければいけない。不満はたくさんある。
モン・サン・ミッシェルでは、豪華なホテルに泊まった。部屋は広く、ベッドも広かった。暖房完備で、大きな バスタブにたっぷり湯を張ってつかった。快適そのものだった。それでも、その後ここに帰ってきた時、少しも不憫さを感じなかった。自分でも意外なほど、この不便極まる生活を受け入れていた。 バスタブにたっぷり湯を張ってつかった。快適そのものだった。それでも、その後ここに帰ってきた時、少しも不憫さを感じなかった。自分でも意外なほど、この不便極まる生活を受け入れていた。
しかし、だ。去るべき時は近づいている。そう、ここにいることを、「住んでいる」と呼んではいけないのだ。住むために最も重要な要素は、働いてその収入で暮らしていくこと。その決定的な条件が今の僕の生活には欠けている。だから、いつまでたっても、ただの長い旅行にすぎない。
潮時、という言葉が頭に浮かぶ。そして、早く帰らなければいけない、ということも。
|
|
|
| |
|
|
18. 哀しい動物たち 12/22(Sat)
メトロに乗っている犬をじっと見ていると、飼い主の老婆が僕に何か話しかけてきた。何を言っているのかはわからなかったが、駅に着いて降りながら笑顔を向けると、一際大きな声を出して彼女は笑った。
日本だと、犬を連れて歩くのは大抵、犬を散歩させることが目的である。が、こちらでは、人間の外出に犬を連れて行く、というケースが多いように聞く。メトロの構内やレストランにも、犬を連れて入ることができる。詳しくは知らないが、マンションなどで飼うことも、日本ほど難しくないのだろうと思う。
こちらの犬は驚くほど躾が行き届いている。レストランでは主人の椅子の下でじっと待っている。時に楽しげで、時に哀しげなその犬達の瞳を見ていると、彼らにとってこの状態は望むべきものなのだろうか、と思う。
犬を飼う場合、とにかく、人との上下関係をはっきりさせることが大切だとよくいわれる。だが、何の意味での「大切」なのか。本来、動物の間で貴賎や上下はないはずだ。人が上だと考えるのは単なるエゴに過ぎず、バカげた考えだと思う。
ただ、犬にはまだ救いがある。大抵の犬たちは、自分たちの立場を納得し、人とのそういった関係を楽しんでいるように見える。

僕には、動物園や公園などで見かける、子供を乗せて歩くロバの目が、たまらない。彼らはいつも繋がれたまま、じっとうつむいて仕事の時間を待っている。その姿は、いじらしくなるほど従順で、おとなしい。そして伏せた目からは、この世の全てを諦めたような暗い光が発せられている。中世の時代、奴隷たちも同じような目をしていたのだろうかと思うと、あの目が僕にはたまらない。
特に珍しくもなく、頭ばかりが大きくて不恰好なこの動物は、もてはやされるようなこともない。ただその温和しさが買われ、小さな子供を乗せてとぼとぼと歩く立場がようやく与えられた、そんな背景が浮かんできて、いたたまれなくなる。
ブーローニュの動物園でも、リュクサンブール公園でも、そんな彼らの姿を見た。背に乗って子供達が嬌声をあげている。親達は喜んでその姿をビデオや写真に収めている。
しかし、そういう僕もまた、彼らの姿をビデオに撮っているのだ。そして、自分が存在するために犠牲にする多く動物達から、できる限り目をそむけて生きている。
|
|
| |
|
19. 一カ月の同棲生活 12/23(Sun)
ひどく疲れていた。その夜に見たショーは、期待したほどの内容ではなかったうえ、席の割には法外な値段を請求された。
いまだに、パリのキャバレーでの席案内が、よくわからない。普通のショーのように決められた席に応じた値段を支払うのではなく、とりあえず席まで連れて行かれてから、後で料金を請求される。案内される際、係にチップをはずめば、いい席に連れて行ってくれるというが、どのくらい払えばいいのかもわからない。
わざわざショーが始まってから料金を取りに来るのも、謎だ。客席は照明が落とされるため、係員はライトで照らしながら席を回る。ショーの最中にうろうろされるのは、見ていて気が散るものだ。客にも係員側にも、メリットは何もない。これが伝統のスタイルだからなのだろうか。
今回は最初、立ち見の席に連れて行かれてしまった。いろんな人に尋ねた末、ようやく舞台から離れた見づらい席を示される。鼻であしらわれた気がして、なんとも気分が悪かった。
ショーが終わり、いつになく遅い時間にメトロに乗る。駅から地上に上がると、「POLICE」と大きく書かれた車が、行く手を塞ぐように止まっていた。道路には、1台の小型車が無様にひっくり返っていて、その周りで何人かの警官が担架を囲んで作業をしていた。
事故は、起こった直後らしい。少し離れた場所に助手席側が凹んだ車が止まっている。さりげなく中を覗くと、まだ若い女性が、震えるように携帯電話で話しているのが見えた。それらを横目に、早々に立ち去る。駅からアパートまでは近いが、とにかく寒く、早く帰りつきたかった。
薄い霧が出ていた。そのベール越しに、オリオン座が弱い光を放っていた。
いろんなことがあるなあと思った。ここで過ごす時間も、もう残り短い。今思うのは、もしここにずっと住むとなれば、相当の覚悟が必要になるだろう、ということ。嫌なことはきっと、いくらでも出てくる。ガイドブックにある綺麗な綺麗なところばかりではないのだ。旅行で訪れることと、そこに住むこととは、全く違うことだ。僕はたぶん、ここに 「住む」ことはできない。 「住む」ことはできない。
旅行だと、いいとこ取りができるが、住むとなればそうはいかない。何もかもを自分なりに受け入れ、対処していかなければならないのだ。そう考えると、何か恋愛と結婚との関係に似ていると思う。ここで一カ月過ごした時間は、さしずめ短い同棲生活のようなものか。一カ月一緒に暮らしてみて、うーん、この人と一緒にずっと生きていくのは結構大変だなあ、と感じたというところ。だからといって嫌いになった訳では決してない。また旅行として、いいとこ取りをしに、ここに来たいと思う。
|
|
|
| |
|
|
20. 陽水さん 12/25(Tue)
クリスマスイブに賑わうモンパルナスの夜、8時。サイバーカフェの店頭で立ち尽くしていた。あいていると聞いていた店には、シャッターが降りていた。イブの夜なので、今日は早めに店を閉めたようだ。最後のサイトの更新をし、馴染みになった店員に別れの挨拶をするつもりが、果たせずに終わってしまった。
そういえば、と思い直す。この後は、やはり馴染みになったあの店で食事をする予定だった。
アパートから歩いてすぐの場所にある、ベトナム料理店。来た時にすぐ見つけ、入ってみた。フォーという麺と、ナムというソースで食べる春巻がとてもおいしくて、それから幾度も通った。味付けが日本の料理と似ていて、安心して口にすることができた。
 急いで駆けつけると、何とか入り口は開いていた。しかし、中に客は一人もいない。 急いで駆けつけると、何とか入り口は開いていた。しかし、中に客は一人もいない。
「OK?」と尋ねると、うなずいた店員がカウンターに立った。ぎりぎりの所で間に合ったようだ。
店は、ベトナム人の家族で経営されていた。おやじさんは60歳ぐらいだろうか。初めて入った時、僕の顔を見て日本人かと尋ね、そうだと答えると、以後、僕が店に入るたび、
「お〜げん〜きでぇ〜す〜かぁ〜」
と、片言の日本語であいさつをしてくるようになった。一昔前にはやった、井上陽水のコマーシャルと、言い方がよく似ている。僕は心の中で、彼のことを陽水さんと呼んでいた。
自分の日本語が通じるのが嬉しくてしょうがないのか、僕の顔を見るといつも満面の笑みを浮かべながら寄ってきて、何かれと話し掛けてくる。
でも、陽水さんの日本語は、時々おかしい。こちらが何も言わずに食べていると急に、「どいた〜しま〜してぇ〜」などと言ってくる。僕は別に訂正もせずに、笑ってふんふんとうなずく。陽水さんはさらに店の机から何やらごそごそメモみたいなのを引き出し、それを見ながらまたいくつか、日本語らしき言葉を並べる。そして、自分の妻や子供たちに、ベトナム語で何か言っている。顔つきからすると、「俺は日本語だってこんなにしゃべれるんだぞ」と自慢しているようにも見える。
奥さんは、日本語はもちろん、英語やフランス語もあまりしゃべれないようで、ほとんど表に顔を出さない。どこか怯えたような目をしながら、必要な時だけ奥から出てくる。それでも僕が料理をほめると、はにかみながらも嬉しそうな顔をしていた。
陽水さんとも、あいさつ以外は英語でしゃべった。今日が最後なんですと告げると、笑顔で握手を求めてきた。いろいろお礼を言いたかったのに、言葉が上手に出てきてくれなかった。
ようやく、パリの人と知り合いになれた気がする。ベトナム人じゃないかと言われるかもしれないが、違う。異国からやってきて、パリで仕事をし生きている彼らはもうベトナムの人ではなく、確かに「パリの人」だ。
翌日のクリスマス、他の店と同じく、ここも店を閉じていた。パリの慣習に従い、今ごろはあの家族も、揃ってクリスマスディナーを楽しんでいるのだろうか。
|
|
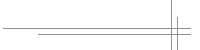 |
|
|
|
|
|
ずっと高揚感に浸っていた。日本を離れてからもう随分と日が経つというのに、ここから旅が始まったような気がしていた。そして、惜しみながら何度も振り返り、車を駆って帰路の寂しさを味わっていると、これって人生そのものになんか似てるな、と急に思った。
ソーヌ河を渡り、丘のふもとに出た。このあたりが旧市街である。狭い道路が入り組み、まだ日はあるのに、薄暗い。丘沿いなので急な坂道が多いが、意外にたくさんの人がそこを昇り降りして通り過ぎていく。中世のまま、残された街。昔から変わらない場所というだけでほっとするのは、もし次に来る時があっても、同じ風景を見せてくれると思えるからだろうか。
その寺院は、ノートルダム・ド・フルヴィエールという。メトロでヴュー・リヨン(旧市街)に移動し、そこからケーブルカーに乗って丘の上に登ると、昨日、街なかから見上げた壮大な建物が、すぐ目の前に出てきた。
もかなり大きい。このほとりにある音楽堂と、檻を探さねばならない。日のあるうちに、池を一周しよう、そう決めて歩き出す。
池には全面に氷が張っていた。日本では見かけない大きな水鳥たちが、その氷の上を歩いていく。時折転びそうになるのが、野生動物にしては情けない。
その人を信用しない。そんな言葉には何の意味もないという場面を、これまで生きてきた中で幾度も見てきたからだ。
こちらでの生活ももう残り僅かとなった頃、次なるトラップに見舞われる。
バスタブにたっぷり湯を張ってつかった。快適そのものだった。それでも、その後ここに帰ってきた時、少しも不憫さを感じなかった。自分でも意外なほど、この不便極まる生活を受け入れていた。
「住む」ことはできない。
急いで駆けつけると、何とか入り口は開いていた。しかし、中に客は一人もいない。