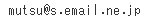HOME -> 城跡データ -> 山形県の城跡一覧(置賜地方) -> 館山城
館山城 たてやまじょう
- 別名
- 舘山要害
- 時代
- 平安時代?~安土桃山時代
- 分類
- 中世連郭式山城
- 規模
- 標高:300m、比高:約20m
- 現状
- 市指定史跡/雑木林・舘山発電所
- 場所
- 山形県米沢市舘山
- 最終訪城日
- 2010年6月19日
藤原経衡が築いたとされる城で、新田氏代々の居城。安土桃山時代には伊達氏の城となる。現在は東端に舘山発電所があり、大部分が雑木林となる。
城史
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 12世紀頃 | 奥州藤原氏一門の藤原経衡(新田冠者)によって城が築かれたと伝わるが定かではない。 |
| 1380年 | 長井庄へと攻め込んできた伊達宗遠に対して、新田遠江守が長井広房の名代として出陣したが、伊達宗遠の謀略によって遠江守は討ち取られ、長井軍は総崩れになって敗北した。 |
| 1390年 | 長井氏の没落後、新田氏は伊達氏の家臣となり田沢の所領を安堵されて舘山城を守ったという。 |
| 1570年 | 新田義直は牧野久仲、中野宗時が起こした伊達氏への謀反に参加し、小松城にて伊達輝宗と戦ったが敗れて滅亡したという。 |
| 1584年 | 伊達政宗に家督を譲った伊達輝宗は米沢城を退去し、舘山城を隠居所に選んで移り住んだ。 |
| 1587年 | 伊達政宗は2月7日に舘山城で地割を開始し、大改修と城下町の整備を始めた。 |
| 1589年 | 伊達政宗は蘆名氏を打ち倒した後に黒川城へと居城を移すが、館山城の工事は伊達鉄斎(梁川宗清)が引き継いで続行された。 |
| 1591年 | 伊達政宗は奥州仕置きによって置賜郡を没収され、新たに旧大崎・葛西領が与えられた。これに伴い舘山城と城下町の整備は未完のまま廃城となった。 |
縄張り
城は鬼面川と大樽川の合流地点付近の丘陵端に築かれており、山の上の端から順に本丸、二の丸、物見曲輪が掘と土塁で隔てられて並ぶ連郭式の縄張りとなっている。なお、武家屋敷は山の北麓の平地にあった。
アクセス
- JR山形新幹線・奥羽本線の米沢駅から「田沢」線のバス(※)に乗り、「舘山発電所前」で下車。山の登り口まで徒歩5分。(※日曜祝日運休)
- JR山形新幹線・奥羽本線の米沢駅から「小野川温泉行き」のバスに乗り、「舘山局前」で下車。山の登り口まで徒歩20分。