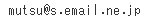HOME -> 城跡データ -> 宮城県の城跡一覧(仙台圏) -> 岩沼城
岩沼城 いわぬまじょう
- 別名
- 岩沼館、岩沼要害、武隈館、鵜ヶ崎城
- 時代
- 平安時代?~江戸時代
- 分類
- 中世平山城
- 規模
- -
- 現状
- 岩沼駅・市街地
- 場所
- 宮城県岩沼市館下
- 最終訪城日
- 2010年8月8日
泉田重光を始めとする伊達家家臣が居城とした場所で、田村宗良の頃に岩沼藩の藩庁にもなった。現在は岩沼駅と市街地化の影響で大半が消滅している。
城史
| 年代 | 出来事 |
|---|---|
| 953年 | 源重之が城を築いたのが始まりで、武隈之館と呼ばれたという。 『岩沼郷風土記書出』 |
| 1582~1585年 | 伊達家臣の泉田重光は武隈の地を与えられ、鵜ヶ崎城を築いて(改築して?)居城とした。この時、重光が沼に囲まれた城を築いたことから「岩沼」の地名が生まれたとしている。 『岩沼の地名の伝承より』 |
| 1585年 | 泉田重光に替わって石田将監が鵜ヶ崎城に配置される。 |
| 1594年 | 石田将監に替わって遠藤兵部が鵜ヶ崎城に配置される。 |
| 1600年 | 遠藤兵部に替わって屋代景頼が鵜ヶ崎城に配置される。 |
| 1602年 | 屋代景頼に替わって奥山兼清が鵜ヶ崎城に配置される。 |
| 1629年 | 奥山氏に替わって伊達宗勝が鵜ヶ崎城に配置される。 |
| 1636年 | 伊達宗勝に替わって古内重広が鵜ヶ崎城に配置される。 |
| 1660年 | 田村宗良は亀千代(後の伊達綱村)の後見人となり、これに伴い岩沼3万石を分与されて岩沼藩が誕生した。鵜ヶ崎城は岩沼要害と称されて藩庁となり、再整備されたという。 |
| 1681年 | 田村建顕が岩沼から一関に移され、岩沼は再び仙台藩領へと戻された。そして岩沼藩誕生以前と同様に古内氏が岩沼に再配置された。 |
| 1869年 | 「戊辰戦争」の結果、仙台藩は新政府軍に降伏し、岩沼城は新政府に召し上げられることになった。 |
| 1874年 | 城は廃城となり、城内の建物は民間へと払い下げられた。 |
縄張り
城は鵜の首のように東へ伸びた丘陵に築かれており、沼に囲まれた要害の地であったが、現在沼は全て埋め立てられて市街地と化しており、近世に本丸のあった丘も岩沼駅の建設に伴って消滅している。今では辛うじて近世の武家屋敷があった場所にその名残を残すのみとなっている。
アクセス
- JR東北本線・常磐線の岩沼駅からすぐ。駅のある場所が本丸跡。武家屋敷跡までは徒歩2分ほど。