■『軍艦島と雜賀雄二』展 呉市立美術館(広島)



↓『1974軍艦島』 (住民がいる頃の軍艦島。無人になる日までを撮影)





↓ 展示室内のモニターで100枚ほどの写真を流した / この写真は、離島する同級生を見送る小学生

↓『軍艦島 - 棄てられた島の風景』 無人になって10年後、再び島を撮りはじめる。







↓左の展示室 『軍艦島 - 棄てられた島の風景』 ↓右の展示室 『月の道 - Borderland』

↓ 『月の道 - Borderland』
月の光だけの長時間露光で撮影。(島の岸壁上を時計回りと反時計回りで、それぞれ一周するというコンセプト)

↓ 展示室中央に斜めの展示壁を設置 / 岸壁上の撮影ではない写真を展示


↓ 中央部、奥の展示室は『軍艦島 - 棄てられた島の風景』


↓左の展示室は『月の道 - Borderland』。時計回りで岸壁上を一周
↓右の展示室は『月の道 - Borderland』。反時計回りで岸壁上を一周

↓ 『月の道 - Borderland』 反時計回りで岸壁上を一周


↓ 撮影場所と撮影方向を地図上で全て示した。最初と最後の写真を同じ地点で撮り、一周したことを示した。

↓ 『GROUND』 軍艦島の地面
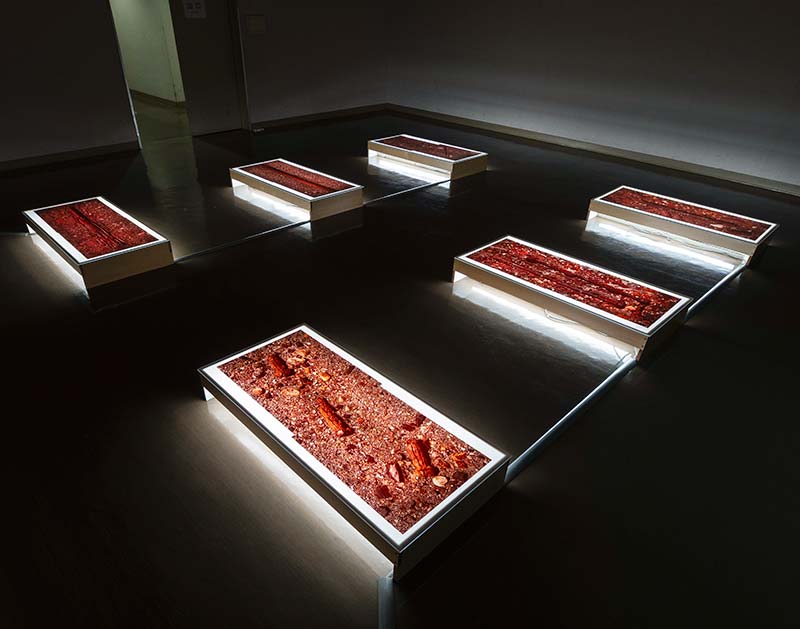


↓ ぼくが問いかけると、「写真の感想をノートに書いている」と答えた小学生の少女と母。



↓ 5月18日の講演の動画がロビーで流されていた。2時間を短縮しても45分。全編を見る人が多かった。

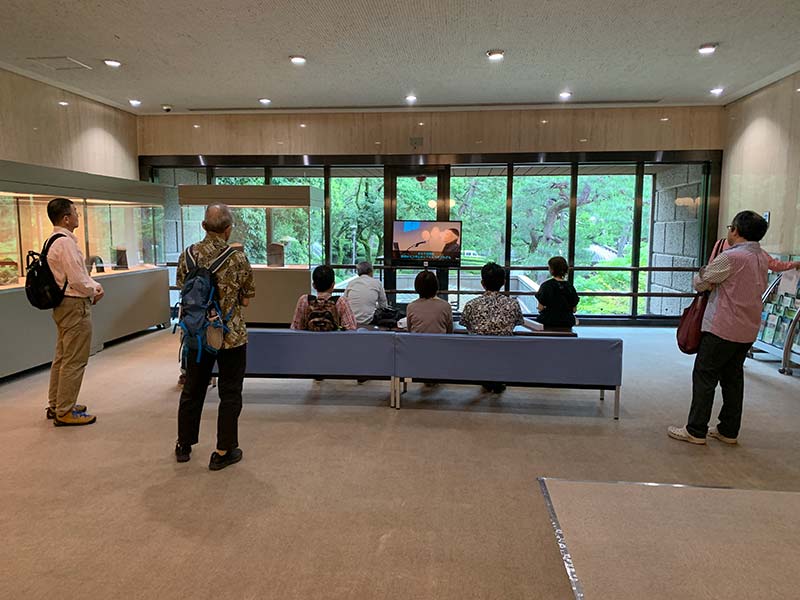

写真の2/3は新潮社写真部、筒口直弘さんの撮影です。 あとは雜賀雄二です。
トーク(講演)には多数のご来場が予測され席を倍増しましたら、すべて埋まりました。
実は定員割れしないかと心配しておりました。
西日本各地や、東京など遠方からも多くご参加くださり、心より感謝します。
美術館の横山館長がぼくに質問される形でトークは始まりました。
「眠たくなったり、途中で抜け出すような講演が多い中で、内容が濃く面白く、最後まで集中して聞きました。こんな講演は珍しいです」
取材に来てくださったある業界紙の記者は、こんな話をされました。
トークでは、皆さんに笑っていただいた箇所もかなりあったと思いますが、以下のメールも届き、雜賀は心打たれました。
「2時間は長いと思っていたが、面白くてあっという間に終わりました」
「話を聞きながら泣いてしまいました」
「軍艦島の撮影に特化した二時間を拝聴し、特に月の道の撮影に関する部分は、撮影の苦労はもちろん、制作の意図、島での体験などを知ることができました。作品を作り上げるまでの壮絶な体験を知ったあと、再度展示室でオリジナルの作品を目にした時、撮影現場と作品の持つ静謐さとの対比に胸を打たれました」
(雜賀註 本人は苦労をしたというよりも、むしろ面白い体験だったと思っています)
それぞれのシリーズのコンセプトは次のページをご覧ください。
『1974軍艦島』
住民の生活。無人に至るまでの1974年の軍艦島
『軍艦島 - 棄てられた島の風景』・『軍艦島 - 眠りのなかの覚醒』
無人となって10年後。棄てられたことで自由を獲得した軍艦島のモノたち
共に同じコンセプトの作品。前者は1984−1986年撮影。後者は1984−2001年撮影。両方に重複する写真があります。
『月の道 - Borderland』
「海、岸壁、軍艦島」に、仏教の死生観「生、中有、死」を重ねた作品。月の光だけで撮影。
『GROUND』
地面に半分埋もれたモノは、自然に還る途上なのか、地面から生まれ出ようとする姿なのか?
展覧会、講演の感想を多くの方からいただきました。許可を得てひとつを掲載します。
++++++++++
雜賀さま
こんにちは。
呉市立美術館「軍艦島と雜賀雄二」に行ってまいりました。
雜賀さんの写真はこれまでも写真集で見ておりましたが、
やっぱりプリントで見ると格別ですね。
展示室でじっと写真を見ていると、自分がいったい今どこにいるのか、
頭がくらくらしてくる感覚でした。
とくに閉山10年後のシリーズの、はがれた天井の写真とぼろぼろになった畳の写真、
どうしてこんなものを美しいと思って見入ってしまうんだろう、目が離せなくなる理由はなんだろう、
と写真の前から動けなくなる感動がありました。
たぶん、その実物を自分が見ても、そこまで感動はしないだろうし、怖いとか汚いとかそういう気持ちになるはずなのに、
雜賀さんの目とカメラを通して、写真の形になって目の前に現れると、どうしてここまで心が動くんだろうか。と、
見終わったあとも、ずっと考えていました。
朽ちていくもの、滅びつつあるものを美しいと思うのは、どうしてでしょう。
大変、おもしろく感じました。
「月の道」も写真集で見たときとはまた違って、空気の感触、風や波の音まできこえてきそうでした。
写真の横に撮影場所が示された地図があるのが良かったです。
遠くに長崎の本土の光が映り込んでいるのを見ると、「こちら」(此岸)と「あちら」(彼岸)の隔たりをより感じられました。
これも写真集で見ていたときには感じなかった点でした。
最後の「GROUND」シリーズは、展示方法がおもしろく、
息子がとても興味をもって時間をかけて見ていみました。
「ここに何かある!」とか言いながら見ていました。
ロビーで、18日のトークの映像がモニターで放映されていました。
トークの中で、雜賀さんがはがれた天井や畳の話をされていましたね。
「かつては誰かが大切にしていたもの」という言葉が印象に残りました。
(雜賀註 : このとき雜賀は次のような話をしていました。
「人の所有物にはヒエラルキーがある。所有物には大切にしているものと、そうでないものという序列があるということ。
しかし島に残されたものは、
人の不在によってヒエラルキーを喪失し、すべてが等価になっていた。
それらを見て、棄てられることは自由になることだと理解した。
棄てられたことで人とモノの主従関係が消滅し、島に残されたものモノは自由を獲得した。
島はそんな状態だった。日常ではありえない状態にショックを受けた。そこからぼくの写真は始まった」)
トークを聞きながら、写真家は本当に命懸けの仕事だと思いました。
体を張って命をかけて、命を削って撮る、雜賀さんのその姿勢にあらためて尊敬の気持ちがわきます。
わたしと同じように、両親も感銘をうけており、
「呉まで来てよかった」と家族で言い合いながら、
呉駅前のお好み焼き屋さんで広島焼きを食べました。
(後略します)
A, Hさん
(デザイナーで、ご本人は東京から、ご両親は長崎から来てくださいました)
115419971