2010年12月4日
サンプラス:ゾーン状態を見る価値のあるベストの1人
文:Tribal Tech
先週、私はここロンドンで、ATP ツアー最終戦を見に行った。ナダル/ベルディヒ戦は、第1セットはタイブレークまでもつれ込む接戦だったが、結果的にはナダルがベルディヒをほぼ型通りに打ち破った。いつものようにナダルは堅実な試合運びで、彼の運動能力は信じがたい見ものである。
私はこの3年間に、フレンチ・オープンでナダルのプレーを2回見てきた。彼はかなり容易にモヤとアルマグロを下していた。だが、こう考えずにはいられなかった。ナダルはゾーン(そう、神話の領域!!)に入り込む選手だとは思わないし、彼のプレーは対戦相手を一方的に叩きのめし、人々がその後何年間も、その事を話題にするようなテニスではないと。
 |
| 1999年ウィンブルドン |
そしてこのテーマに関して範囲を広げると、この25年間でゾーン状態のプレーをした選手は、そう多くなかった。
もちろん、1人の選手がもう一方に対して素晴らしいプレーをした例はあった。2008年フレンチ決勝戦でナダルがフェデラーに対して、1991年USオープン決勝戦でエドバーグがクーリエに対して、あるいは1989年ウィンブルドン決勝戦でベッカーがエドバーグに対して、などである。
だが私は、ピート・サンプラスがゾーン状態に入ると、対戦相手を完全に圧倒する1人の選手であったと思う。現在の世代では、ロジャー・フェデラーが多くの相手に対して、明らかに似通った事をしてきた。
しかしながら、サンプラスは誰もそれを予想していない試合で、そして彼に対抗しうると見なされた相手に対して、それを為したという事実を私は気に入っている。例えば、2007年オーストラリアン準決勝での、ロディックに対するフェデラーの出来ばえは驚くばかりだった。しかしロディックは才能の点で、明らかにフェデラーより下の部類にいたし、今もそうだ。そして私の目には、そもそも生来の才能があるプレーヤーとは見えない。
 |
| サンプラス対アガシ、 1999年シンシナティ準決勝 |
ゾーン状態のサンプラスを見て興味をそそられるのは、彼がプレーするペースである。彼は常に、すぐにでもサーブが打てる用意ができていたのだ! レンドル、ナダル、クーリエ、ベッカー、ジョコビッチについて考えてみれば、これらの男たちは非常に慎重なペースでプレーをした。特にサーブを打とうとする時には。したがって彼らのゲームは、自分が何をしようとしているか / いたか、が重要なだけでなく、対戦相手のリズムと集中をくずす効果も担っているのだ。
サンプラスのサーブは非常にリズミカルだったため、まるで相手をせかしているように見え、それは彼らに無力感を感じさせる事にもつながった。サンプラスが意図的にしていたのかは分からないが、確かにそういう影響が生じていた。
ゾーン状態の選手がもう1人のトップ選手である対戦相手を圧倒した顕著な例には、以下のような試合もある。
2000年 ATP マスターズ決勝戦:グスタボ・クエルテンがストレートセット(3セット)でアンドレ・アガシに勝利。バックハンドが好調な時、クエルテンには驚くべきショットを繰り出す能力があった。さらに、非常に優れたファーストサーブを持っていた。アガシはグスタボのリズムを崩すべく、あらゆる事を試みたにもかかわらず、彼はアガシにチャンスを与えなかった。
2007年オーストラリアン・オープン決勝戦:セレナ・ウィリアムズがマリア・シャラポワに6-1、6-2で勝利。私の意見では、セレナの最も優れたプレーぶりだった。彼女はシャラポワのサーブを事もなげにリターンしていたが、注目に値する出来ばえだった。
2004年USオープン決勝戦:フェデラーがヒューイットに6-0、7-6、6-0で勝利―――何というスコア! フェデラーは第1セットでヒューイットを圧倒し、第2セットでヒューイットはサービング・フォー・ザ・セットを迎えたが、ブレークされる。フェデラーはタイブレークをものにし、第3セットではヒューイットを圧倒した。
以下はサンプラスがゾーン状態に入り、ほぼ完璧なテニスをした試合である。
1999年ウィンブルドン決勝戦:サンプラスがアガシに6-3、6-4、7-5で勝利。アガシはこの試合に、ブックメーカーと解説者(私ではない!)によれば、少しだけ優勢な立場として臨んだ。恐らく彼らは新しいチャンピオンを期待しており、そしてサンプラスはその年の前半、好調ではなかったからだろう。
 |
| サンプラス対ヘンマン、 1998年ウィーン準々決勝 |
そしてアガシの出足は非常に好調で、最初の7ゲームでは、サーブを含めてすべての面でサンプラスと対等だった。しかし3オール、サンプラスのサーブで0-40から、あとは知ってのとおり、サンプラスは別の次元に行ってしまった。第1セット後半から第2セット前半にかけて、サンプラスが続けざまに勝ち取った5ゲームは、1人のプレーヤーが、実際にとても良いプレーをしているもう1人のトップの対戦相手に上回るプレーをした、歴史上でも最高のテニスだと考える。
1999年 ATP ファイナル決勝戦:サンプラスがアガシに6-1、7-5、6-4で勝利。スコアからも明らかで、サンプラスは非常に良いプレーをし、アンドレはしょげ返っていた。彼は試合後の観客へのスピーチも辞退したほどだった。アンドレはラウンドロビンでピートを負かしたが、決勝戦では散々に打ちのめされた。アナウンサーがピートにこう尋ねた時、彼は試合を要約していたのだった。「あなたはこの試合を、来シーズンへのテストにしたいと言いました。これはあなたのテスト法ですか!?」と。
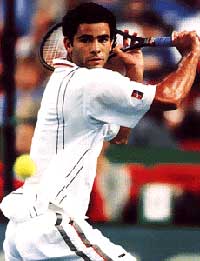 |
| サンプラス対ラフター、 1997年デビスカップ準決勝 |
しかし、サンプラスがプレーする様は信じがたいものだった。その時点では、彼はチャンに対して1勝6敗だったが、巨匠のレッスンのごとく右に左にとウィナーを連発したのだった。それはサンプラスのキャリアにおいて、ハードコートではそれほどサーブ&ボレーをしていない時期だった。
サンプラスが披露した他の顕著なマスタークラス:
1990年USオープン決勝戦:アンドレ・アガシを6-4、6-3、6-2で破る。
1997年デビスカップ準決勝:パトリック・ラフターを6-7、6-1、6-1、6-4で破る。
1997年オーストラリアン・オープン決勝戦:カルロス・モヤを6-2、6-3、6-3で破る。
2000年USオープン準々決勝:リチャード・クライチェクを6-7、7-6、6-4、6-2で破る。
1995年ウィンブルドン決勝戦:ボリス・ベッカーを6-7、6-2、6-4、6-2で破る。
「ゾーン状態の」サンプラスのビデオ3本
http://www.youtube.com/watch?v=oAsmtp1nSqE
http://www.youtube.com/watch?v=5Q84AZ1Qsys
http://www.youtube.com/watch?v=ozxjmfIuvEo