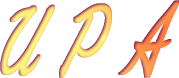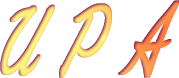| <エリトリアの現状> |
★30年にもおよぶ内戦の末、ようやく1993年にエチオピアから独立しました。その後何度か紛争があり、エチオピアとの国境付近には避難民キャンプが存在し、また、その周辺には未だに兵士の遺体がそのまま残っている所があるそうです。今後にわたって民族間の問題が起こらないとは言い切れませんが、現在のところは一応平穏であると言えます。首都アスマラや今回私が訪問したマッサワでは、さまざまな国の支援をあいまって、近代化が進んでいます。 |
|
|
| <届けた物資> |
★しかしながら、エリトリアという国は、「他国の支援に頼りすぎず、自立した国づくり」を目指しています。私たちは今回、そんなエリトリアに支援物資として「カーブミラー」を2セット届けました。 |
|
|
| <カーブミラー?> |
★ある日、日本のエリトリア大使館でエリトリアを知る日本人の集まりがありました。そこで「自分たちがエリトリアに何かできることはないか」と言う話になり、「カーブミラーを届けてはどうか」との意見が出ました。そこでPeace
Boatがエリトリアに寄港するということで、そのカーブミラーをUPAチームが届けるということになりました。
★エリトリアでは近代化と共に、自動車の普及が進んでいます。しかし、道路の状態が悪い上、首都アスマラ〜マッサワ間はカーブの多い山道がたくさん。なのにカーブミラーがなく、事故が多くて危険だということです。そこで、日本から届けるカーブミラーの利便性を知ってもらい、さらにはその2つを見本に自分たちの手でどんどんカーブミラーを作っていって、それがエリトリアの産業となればまさに「自立」できるんじゃないだろうかということです。また、アフリカ全体で見ても、カーブミラーがそれほど浸透しておらず、エリトリアを中心に他国にも広がれば、さらにエリトリアにとっても素晴らしい経済効果が生まれるでしょう。 |
|
|
| <問 題 点> |
★しかし、すべてが完璧に私たちの希望通りになるでしょうか?それはあくまでも私たち「日本人」の考え。実際にミラーを受け取ったエリトリア側から「使い方がわからない」と言われ、説明書を後日送付したそうです。技術者を送ったわけではないのでどうなるか心配です。
★また私個人の考えとしては、アフリカ全体でのカーブミラー産業は限界があるのではないかと思います。まず、自動車の普及が進んでいるとはいえ、アフリカ全体が車社会になるとは思えませんし、一部の国だけかもしれません。
★カーブミラーが自然界に与える影響はないでしょうか?今までなかったところにいきなりカーブミラーが出現。人間は適応できても、動物たちはどうでしょう?考え出したらキリがないことですが、やはりその辺も頭の隅に置いておかないといけないと思います。 |
|
|
| ★UPAのお手伝いをしながら、私は「支援」について今までにないくらい考えました。「支援」って、どこまでやればいいの?エリトリアには何回も行っているPB。現地の人たちは歓迎してくれましたが、一方で「PB=日本人=物がもらえる」という考えが彼らの頭にあることは否定できないでしょう。実際に交流相手に「お金をくれ」と言われたり、「カメラちょうだい」とか物を一瞬の隙をついてスラれた人もいます。私たちが行くことによって、現地の人たちがそのような考え・行動をするようになってしまったのだったらどこが「支援」なのでしょう。これではエリトリアのかかげる「自立した国づくり」をも脅かすことになるかもしれません。どうすることが一番いいんでしょうか。このことは、これからの「課題」と言えると思います。ここまで読んでくださった方は、一度ご自身で「支援」について考えてみていただけますか?そしてそれを教えてください。ぜひ貴重なご意見をお待ちしております! |
|