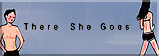
乽働儖儀儘僗戞屲偺庱乿僕乕儞丒僂儖僼乛桍壓婤堦榊栿丂崙彂姧峴夛
嶰晹峔惉偺挿曇SF丅戞堦晹偼僑僔僢僋丅戞擇晹偼柉榖丅戞嶰晹偼僇僼僇晽晄忦棟丅偱傕偭偰捠偟偰撉傓偲杮奿儈僗僥儕乮偨偩偟扵掋偵傛傞撲偺夝柧偼側偟乯丅僥乕儅偼乽傾僀僨儞僥傿僥傿乿偲乽恀幚偼側偄乿丅僱僞僶儗側偟偵偙傟埲忋摜傒崬傓偺偼擄偟偄側偁丅
傾僀僨儞僥傿僥傿偺僥乕儅傪孈傝壓偘傞堊偵孞傝曉偟弌尰偡傞偝傑偞傑側乽懠恖偱偁傞帺暘乿偺僀儊乕僕偑僌儘僥僗僋偱丄偡丒偰丒偒乮偼乕偲乯丅
乽恀幚偼側偄乿僥乕儅傪孈傝壓偘傞偨傔偵嶌幰偑嵦梡偟偨昤幨偺傒偱乮偡側傢偪愢柧側偟偱乯丄乽尒偐偗乿偲乽恀憡乿偲乽偝傜偵傂偭偔傝偐偊偭偨恀憡乿偲丄偝傜偵偦傟傜傪摨楍偵昞尰偡傞偲偄偆棧傟嬈丅偟偐偟丄偱傕幚嵺偵偼偦傟傜偺偆偪偳傟偐偑婲偙偭偨偺偱偟傚丠 偲尵傢傟偰偟傑偆偲崲傞傛偆側婥偑偟傑偡丅偳傟傕偑惉傝棫偨側偄偲偄偆曽偑傛偐偭偨偺偱偼側偄偐偲姶偠傑偡丅
巆擮側偑傜巹偺摢偼慹嶨偵弌棃偰偄傞偺偱丄慹嶨側岆偭偨撉傒曽側偺偐傕偟傟傑偣傫丅
偦偆偄偊偽戞堦晹偼彮擭偺栚偱僑僔僢僋悽奅傪昤幨偡傞偍榖偱丄偙偺傛偆側庤朄偼堎悽奅傪撉幰偵彮偟偢偮愢柧偡傞榖偱傛偔嵦梡偝傟傞偺偱偡偑丄捠忢偼偙偺庤偺庤朄傪嵦梡偡傞偲偒偵偼丄偟偽偟偽嶌幰偼偦偺枺椡揑側堎悽奅偵杤擖偟偰丒悓偭偰丒偄傞偙偲偑傎偲傫偳側偺偱偡偑丄壗屘偐撉傫偱偄傞娫拞乽嶌幰偑傛偦傪岦偄偰偄傞帇慄乿偑姶偠傜傟傑偟偨丅偙偺姶妎偼偳偙偐偱妎偊偑偁傞側偁偲偟偽傜偔峫偊偰偍傝傑偟偨偑傗偭偲巚偄摉偨傝傑偟偨丅庩擻彨擵偺嶌昳偵忢偵偮偒傑偲偭偰偄傞姶妎偱偟偨丅
乽働儖儀儘僗戞屲偺庱乿撉椆丅擇廃栚偵撍擖丅
乽働儖儀儘僗戞屲偺庱乿撉傒巒傔傞丅
僼僕僥儗價偺俀俈帪娫僥儗價偱栭拞偵傗偭偰偄偨乽僇儅憶偓乿偼丄偝傫傑偑偄傜傫巇愗傝傪嫮惂偟偨偨傔偝傫傑屼揳偵側偭偰偟傑偆丅栴晹偼嶦堄傪書偄偰偄偨偵堘偄側偄丅偦偺偁偲偺乽憗挬寍恖偺偳帺枬乿偼丄儀僗僩僥儞曽幃偱壧偺偆傑偄寍恖偑恀柺栚偵壧偆偲偄偆僐儞僙僾僩偱丄傑偁弌偰偔傞寍恖偝傫偺壧偑偆傑偄偙偲偆傑偄偙偲丅摿偵怷嶰拞偺戝搰偲偐儁僫儖僥傿偺徏杮偲偐丅嵟屻偵戞堦埵偺撪懞偑僐儞僩乮奒抜僆僠傑偱両乯傪傗偭偰偟傑偄戝崿棎偵側偭偨偲偙傠偱撪懞僾儘僨儏乕僗両偲嫨傫偱婰擮幨恀傪偲偭偰廔傢傝偲偄偆巹岲傒偺僌僟僌僟姶偑婐偟偄僐乕僫乕偱偟偨丅
崱擔傕乽働儖儀儘僗戞屲偺庱乿偼彂揦偱尒摉偨傜偢丅敪攧擔偵抲偄偰偄側偄偲偄偆偺偼僠僩傑偢偔側偄偐丅
俀俈帪娫僥儗價偺僄儞僨傿儞僌偼壀懞VS.嬶巙寴偺儃僋僔儞僌偱丄壀懞偑僲僢僋傾僂僩偝傟扴壦偱塣偽傟偰偄偭偰堛幰偺怺崗偦偆側僐儊儞僩偑偁偭偰丄奆偑怱攝偟偰偄傞偲偙傠偵恄梎偵偐偮偑傟僞僀僈乕儅僗僋偺柺傪偐傇偭偨壀懞偑応撪偵棎擖偟戝憶偓丅傛偐偭偨傛偐偭偨偲戝僼傿僫乕儗傪寎偊偰偄傞偲偙傠偵朰傟嫀傜傟偰偄偨侾侽侽倠倣儅儔僜儞傪憱偭偰偄偨壛摗偑壗屘偐娫偵崌偭偰僑乕儖偡傞傕扤偵傕憡庤偝傟偢偵儅僕僊儗偱戝朶傟丅偲偄偆揥奐傪婜懸偟偰偄偨偺偱偡偑丄偦偙傑偱傔偪傖偄偗僗僞僀儖偵偡傞傢偗偵偼偄偐側偐偭偨傜偟偔巆擮丅
乽抴鍋偺旝徫乿丂僥傿僄儕乕丒僕儑儞働乛暯壀撝丂栿丂垽恖傪媠懸偡傞奜壢堛偲摝朣拞偺嬧峴嫮搻偲壗幰偐偵娔嬛偝傟偨抝偺3偮偺榖偑岎嶖偟偨帪偵壗偑婲偙傞偐丅僼儔儞僗嶻傜偟偔愢摼椡偵寚偗傞偒傜偄偑偁傞偑丄擺摼椡偑偁傞彫愢丅嬧峴嫮搻偺抝偲惛恄昦堾偵擖堾偟偰偄傞彈惈偑丄僾儘僢僩偺搒崌偺偨傔偵弌偰偔傞恖宍偲姶偠傞偐丄偦傟偲傕嫋梕斖埻偱偁傞偺偐偱昡壙偑暘偐傟傞偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅
彮偟椓偟偔側偭偨偍偐偘偐丄偡偙偟尦婥偵側偭偨丅偙偺婡夛傪摝偡偲傑偨偄偮恖娫偵栠傟傞偐暘偐傜側偄丅乽働儖儀儘僗戞屲偺庱乿傪扵偟偵丄偲傝偁偊偢崙彂姧峴夛偺杮傪抲偄偰偄偦偆側彂揦傪嶰尙夞偭偰傒傞偑巆擮側偙偲偵偲偄偆偐傗偼傝偲偄偆偐尒摉偨傜側偄丅戙傢傝偵壗嶜偐峸擖丅
僕儉丒僋儗僀僗乽巰傫偱偄傞乿敀悈u僽僢僋僗丂
僴乕僪僇僶乕偑弌偨偲偒丄挌搙巰傫偱偄傞榖傪彂偙偆偲峫偊偰偄偨偲偙傠偩偭偨偺偱僔儑僢僋傪庴偗偨婰壇偑傛傒偑偊傞丅(枹撉乯
怷攷巏乽楒楒楡曕偺墘廗乿丂島択幮暥屔丂偙偺僔儕乕僘偱偄偮傕旲偵偮偄偰偄偨僉儍儔朑偊偑杮嶌偱偼偦傟傎偳婥偵側傝傑偣傫偱偟偨丅悇棟彫愢偲偟偰偺僈僠僈僠偺榑棟偺烞傪媮傔偰偄傞恖偵偼岦偐側偄傛偆側婥偑偟傑偡偑丄嵟弶偵弌偰偔傞撲偺楒恖偺惓懱偺堷偭挘傝曽偑柺敀偐偭偨偱偡丅
僄僀僩儅儞乗怴嶌2004擭搙斉 愨懳撉傔側偄尪偺撉傒愗傝寙嶌慖丂僩儔僂儅儅儞僈僽僢僋僗孠揷 擇榊 塸抦弌斉丂梒抰墍偺偙傠孠揷師榊偺乽僄儕乕僩乿傗乽僨僗僴儞僞乕乿傗乽挻將儕乕僾乿傪撉傒傆偗偭偨傕偺偱偟偨丅偦偺崰婛偵対廵晄朄強帩帠審偱姳偝傟偰偄偨偨傔丄傕偆怴嶌偑撉傔側偄偺偩側偁偲掹傔偰偍傝傑偟偨丅偦偺屻廆嫵揑枱夋傪昤偔傛偆偵側偭偨傛偆偱偡偑丄慄偑堘偆恖偵側偭偨傛偆偱偡丅僄僀僩儅儞偺怴嶌偲偄偆偙偲偱偮偄攦偭偰偟傑偄傑偟偨丅僼僅儘乕儚乕傪嫋偝側偄桞堦柍擇偺僔儍乕僾側慄偼寬嵼偱側傫偲傕偆傟偟偄尷傝丅僄僀僩儅儞偼堦嶌偺傒偱丄偁偲偼媽嶌偺撉傒偒傝偺嵞榐丅偱傕傗偭傁傝愄偺慄偺傎偆偑僔儍乕僾偩側偁丅
悇應偩偑丄僄儗儀乕僞乕偺塣峴偼偄偔偮偐偺僾儘僌儔儉偑偁偭偰丄偦偙偐傜椺偊偽恖傪岠棪傛偔塣傇僐乕僗丄徚旓揹椡愡栺僐乕僗丄拞梖僐乕僗側偳偐傜慖戰偱偒傞傛偆偵側偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲巚偆丅偦偟偰偙偺僄儗儀乕僞乕偼側傞傋偔恖傪嵹偣側偄僐乕僗偺愝掕偵側偭偰偄傞偵堘偄側偄丅偦偆偱側偗傟偽偙偺僄儗儀乕僞乕偺堎忢側塣峴偼愢柧弌棃側偄丅儃僞儞傪墴偡偲嶰婡暲傫偱偄傞僄儗儀乕僞乕偱堦斣墦偄偲偟偐巚傢傟側偄僄儗儀乕僞乕偑屇傃弌偝傟傞丅偦偆偱側偗傟偽丄椺偊偽俉奒偐傜侾侽奒傊堏摦偟傛偆偲忋儃僞儞傪墴偡偲9奒偺僄儗儀乕僞乕偑堦扷俉奒傪捠傝夁偓侾奒傑偱偨偳傝拝偄偰傗偭偲俉奒偵傗偭偰偔傞丅 堦偮偩偗媬偄偑偁傞偲偡傟偽丄偙偺僄儗儀乕僞乕偑嶰旽惢偱偁偭偰丄峴偔愭奒儃僞儞傪娫堘偊偰傕僟僽儖僋儕僢僋偱僉儍儞僙儖偱偒傞偙偲偔傜偄偐丅 僄儗儀乕僞乕偵忔傝崬傓偲僪傾偑暵傑傞丅峴偔愭儃僞儞傪墴偝偢偵偄傞偲乽峴偔愭儃僞儞傪墴偟偰偔偩偝偄乿偲傾僫僂儞僗偝傟傞丅 摿偵峴偒偨偄奒傕側偄偺偱偦偺傑傑曻抲偟偰偍偔丅愡揹偺堊偐僄儗儀乕僞乕偺拞偺徠柧偑徚偝傟傞丅椬偺僄儗儀乕僞乕偑摦偄偰偄傞偺偐丄儌乕僞乕偺壒偲儚僀儎乕偑傇偮偐傞傛偆側壒偑暦偙偊傞丅敔偑摦偒弌偡丅徠柧偲奒悢昞帵偼徚偊偨傑傑側偺偱壗奒傊岦偐偭偰偄傞偺偐傛偔傢偐傜側偄丅恖偑忔傝崬傫偱棃偨帪偵儃僞儞偑墴偝傟偰偄側偗傟偽婏堎偵巚傢傟傞偩傠偆偲丄儃僞儞偺偁傞曽岦傊庤傪怢偽偟偰懱偺僶儔儞僗傪曵偡丅傛傠偗偰擇嶰曕慜偵恑傓丅暻偑側偄丅埫埮偺拞偍偦傞偍偦傞曕偄偰傒傞偑暻偵摓払偟側偄丅僄儗儀乕僞乕偑摦偔壒偑側偍嬁偔丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
乽儁儁儘儞僠乕僲乮棯乯乿傪丄偁偪偙偪偱尒偐偗傞忬嫷偑挿偔懕偄偨偣偄偱丄側傫偐帺暘偺僥僉僗僩偱偼側偄傛偆側婥偝偊偟偰偒傑偟偨丅
抧柺偵嶶傜偽偭偰偄傞僫僀僼偲悺摲偲僼儔僀僷儞傪廍偭偰僇僑偵擖傟傞丅嶮偼暡乆偵側偭偰旘傃嶶偭偰偄傞偺偱獯偱廤傔偰恛庢傝偵偲傝億儕戃偵擖傟偰擱偊側偄僑儈偲偡傞丅嶵偒嶶傜偝傟偨僗僷僎僢僥傿偼偔傑偱偱偐偒廤傔僑儈僶僒儈偱廍偄忋偘丄愭傎偳偲偼暿偺億儕戃偵擖傟擱偊傞偛傒偲偡傞丅抧柺偵峀偑偭偰偄傞愒崟偄愼傒偼儂乕僗偱悈傪嶵偄偰愻偄棳偡丅抧柺偵墶偨傢傞戝偒側夠偼婥偑偮偐側偐偭偨偙偲偵偟偰偦偺傑傑偵偟偰偍偄偰峔傢側偄丅偳偙偐傜偐帇慄傪姶偠偰巇曽偑側偄応崌偼丄擔偑曢傟傞慜偵嶌嬈傪廔椆偡傞偙偲丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
偁傑傝偺弸偝偵壗傕巚偄晜偐偽側偄偺偱偟偽傜偔偍媥傒偟傛偆偐偲巚偭偨偺偩偑戝惣壢妛偺乽壨尨偵偰乿偑偡偛偔嫲偄榖側偺偱偛徯夘丅堜屗偺榖偺帪傕巚偭偨偺偱偡偑丄忋庤偔愢柧偱偒側偄嫲偝丅扨偵婋側偐偭偨榖偵側傝偦偆側偲偙傠傪丄弌偰偔傞暔帠暔帠偡傋偰壭乆偟偄怓崌偄傪懷傃偰偄偰乧乧偭偰丄幚榖偩偭偨傜側傫偐嵎偟偝傢傝偑偁傞傛偆側偙偲傪丄崱彂偄偨傛偆側婥偑偡傞偺偱榖戣傪曄偊傑偡丅偄傑傑偱尒暦偒偟偰堦斣嫲偄偲巚偭偨榖偼丄暵偞偝傟偨晹壆偺暻偵僋儗儓儞偱傃偭偟傝偲彂偐傟偨乧乧偲偄偆榖丅擇斣栚偵嫲偄偲巚偭偨榖偼
------------偙偙偐傜堷梡--------
煭棊偵側傜側偄偔傜偄嫲偄榖傪廤傔偰傒側偄丠Part23(俀偪傖傫偹傞)
http://hobby2.2ch.net/occult/kako/1038/10382/1038209969.html
852 柤慜丗 1/4 搳峞擔丗 03/01/10 00:05
彫妛榋擭惗偺崰偺榖偩丅
恊愂晇晈偑墦曽偱媫梡偑偱偒偨偲偐偱丄巕嫙傪梐偗偵棃偨丅
偪傚偆偳搚梛擔偱丄椉恊傕梉曽傑偱弌妡偗傞梊掕偑偁傝丄
杔偑偄偲偙払偺偍庣傝仌棷庣斣傪偡傞偙偲偵側偭偨丅
偄偲偙偼幍嵨抝偺巕偲枀屲嵨丅偟偒傝偵梀傏偆偲偹偩偭偰偔傞丅
巇曽側偄偺偱枀偺梫朷傪暦偄偰丄偐偔傟傫傏傪偡傞偙偲偵偟偨丅
偄偲偙払偼塀傟傞懁偱丄杔偑屲廫悢偊偰扵偡偙偲偵側偭偨丅
抝偺巕偼墴擖傟偵塀傟偰偄偨偺傪偡偖偵尒偮偗弌偟偨偺偩偑丄
枀偺曽偼偳偙偵塀傟偰偄傞偺偐丄側偐側偐尒偮偐傜側偄丅
偦傫偱丄杔偼乽傕偆偄偄偐乕偄乿偲惡傪偐偗側偑傜扵偡偙偲偵偟偨丅
傗偭傁傝巕嫙偩丅乽傕偆偄乕傛乿偲曉帠偟偰偔傞丅
偳偆傕儀僢僩偺壓偵恎傪愽傔偰偄傞傜偟偄丅
杔偼壒傪棫偰偢偵偦偙傪擿偒崬傓偺偩偑丄巔偼側偄丅
853 柤慜丗 2/4 搳峞擔丗 03/01/10 00:06
傑偨惡傪偐偗傞偲丄徫偄傪墴偟嶦偟偨惡偱曉偟偰偔傞丅
傗偭傁傝墴擖傟偐丠
偟偐偟偦偙偵傕偄側偄丅
偄偲偙傕堦弿偵扵偟偨偺偩偑丄尒偮偗弌偣偢偵偄偨丅
杔偼彮偟晄埨偵側偭偰~嶲丅傕偆弌偰偍偄偱傛茞簜饛銈皞絹B
枀偼晽楥応偺僪傾傪奐偗偰丄偵偙偵偙偟側偑傜尰傟偨丅
乮偝偭偒扵偟偨偗偳側乯
偳偙偵塀傟偰偨偺偐暦偔偑丄旈枾偩偲尵偭偰嫵偊偰偔傟側偄丅
偦偺屻偼僎乕儉傪偟偰夁偛偟偨偑丄傗偭傁傝偢偭偲摢偵傂偭偐偐偭偰偨丅
栭偵側偭偰偄偲偙偺晝恊偑寎偊偵棃偰丄擇恖偼婣偭偰偄偭偨丅
杔傕怮傞帪娫偵側傝晍抍偵擖偭偨丅
854 柤慜丗 3/4 搳峞擔丗 03/01/10 00:07
偳偆偟偰傕拫娫偺僇僋儗儞儃偺偙偲傪峫偊偰偟傑偆丅
偦偺偆偪偆偲偆偲偟巒傔偨崰丄埫偔偟偨晹壆偺拞偐傜惡偑偟偨丅
乽丂傕丂偆丂偄丂偄丂偐丂亅丂偄丂乿
偼偭丠嬃偄偰栚傪妎傑偡偲嵞傃惡偑丅
乽丂傕丂偆丂偄丂偄丂偐丂亅丂偄丂乿
旝偐偵丄偦傟偱傕妋幚偵丄偦偺惡偼暦偙偊偨丅
杔偼巚傢偢晍抍偺拞偵傕偖傝偙傫偩丅
偦傟偼偁偺屲嵨偵側傞彈偺巕偺惡偠傖側偄丅
傕偭偲擭攝偺丄偍偦傜偔戝恖偺彈惈偺惡偩丅
乽丂傕丂偆丂偄丂偄丂偐丂亅丂偄丂乿
偩傫偩傫嬤偯偄偰偒偰偄傞丅
懱偼恔偊丄姰慡偵僷僯僢僋忬懺偩偭偨丅
855 柤慜丗 4/4 搳峞擔丗 03/01/10 00:08
偦傟偱傕丄曉帠偼擇偮偟偐側偄偙偲偼暘偐偭偰偄傞丅
愨懳偵乽傕偆偄乕傛乿丄偲偼尵偊側偄丅
乽傑乕偩偩傛乕乿杔偼夅偺柭偔傛偆側惡偱欔偄偨丅
乽丂傕丂偄丂偄丂偐丂亅丂偄丂乿
偍偦傜偔惡偺庡偼晍抍偺偡偖嬤偔傑偱棃偰偄偨丅
乮偁偁丄傕偆尒偮偐傞乯偦偆姶偠偨弖娫偩偭偨丅
杔偑摢偐傜旐偭偰偄偨晍抍偑丄惃偄椙偔尀傝忋偘傜傟偨丅
栚傪尒奐偄偰斶柭傪忋偘傞偲丄偦偙偵偼扤傕偄側偐偭偨丅
憶偓傪暦偄偰晝恊偑晹壆偵嬱偗偮偗偰偒偨丅
乽偳偆偟偨両壗偑偁偭偨丠乿
杔偼恔偊側偑傜尵偭偨丅
乽晍抍偑傆偭偲傫偩乿
------------堷梡廔傢傝--------
媥傒偺娫偵撉傫偩杮丅姶憐傪彂偔偲偒偵偼側傞傋偔億僕僥傿僽側傕偺傪彂偔偙偲傪怱偑偗偰偄傞偺偱偡偑丄柺敀偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢僱僈僥傿僽側暥復偟偐偐偗側偄偺偱僞僀僩儖偺傒丅
僀儞丒僓丒僾乕儖丂墱揷塸榊丂暥寍弔廐幮
嬻拞僽儔儞僐丂墱揷塸榊丂暥寍弔廐幮
僒僞乕儞丒僨僢僪僸乕僩丂僌儔儞僩丒僉儍儕儞丂憗愳暥屔
愭偺撉傔側偄暔岅(PJ寙嶌廤乮俈乯)丂億乕儖僕僃僯儞僌僗丂僩僷乕僘僾儗僗幮
杺寱揤隳丂怷攷巏丂島択幮暥屔丂
偄偮傕偼揹幵偵嵹偭偰堏摦偟側偑傜CD偱壒妝傪挳偄偰偄傞丅
偠傖偁丄揹幵傪妝婍偵偟偰偟傑偍偆丅
斷偑奐偔壒
僄傾乕偑僞儞僋偵媗傔傜傟傞壒
斷偑暵傑傞壒
幵椫偑夞揮傪巒傔傞壒
儌乕僞乕偑壛懍偟側偑傜夞揮偡傞壒
僷儞僞僌儔僼偑壦慄偲怗傟傞壒
慄楬偺宲偓栚傪傑偨偖壒
晽偑僈儔僗傪恔傢偣傞壒
楢寢婍偑傇偮偐傞壒
嵗惾偵恖偑嵗傞壒
偮傝妚偑偒偟傓壒
僄傾僐儞偑晽傪憲傞壒
幵撪曻憲偺儅僀僋偺僗僀僢僠偑墴偝傟偨壒
崱搙偼CD偱堏摦偟偰傒傛偆
僔儀儕傾傊
僴儚僀傊
杒崙傊
撿崙傊
堦塉崀偭偨屻偺栭傊
孨偺榬偺拞傊
傂偲傝傏偭偪偺栭傊
崅峑帪戙偺壆忋傊
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
偁傞偐偳偆偐傛偔傢偐傜側偄愇嫶傪搉傞丅柖偑怺偔偰壨偺岦偙偆娸傑偱偑尒搉偣側偄丅曕偄偰偄偔偲嫶偺壓偵棳傟偰偄傞偼偢偺悈偺壒偑暦偙偊偰偔傞丅岦偙偆偺嫶偺偨傕偲偺曽偵偼摦偐側偄擇恖偺恖塭偑尒偊傞丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
枽偺摂戜傪弌偰丄悈暯慄偵攚傪岦偗媢偵岦偐偆丅娚傗偐側嶁摴傪搊傝揥朷戜偵偨偳傝拝偔丅寶暔偺廃傝偵偼壗傪偐偨偳偭偰偄傞偺偐尒摉偑偮偐側偄愇憿偑偁偪偙偪偵曻抲偝傟偨傛偆偵抲偐傟偰偄傞丅梿慁奒抜傪傓傗傒偵偖傞偖傞偲夞偭偰偄傞偲壆忋偺揥朷強偵弌傞丅壆忋偺拞怱偵抲偐傟偨傗偖傜偵搊傞偲愭傎偳偺摂戜偲偦偺偼傞偐愭偵悈暯慄偑尒偊傞丅偖傞傝偲尒夞偡偲愭傎偳尒偊偨摂戜偲偙偙傑偱曕偄偰偒偨摴偑徚偊偰偄傞丅晄巚媍側偙偲偵偙偺揥朷戜偼360搙慡偰悈暯慄偵埻傑傟偰偄傞丅偙偙偼偄偮傕嫮偄晽偑悂偄偰偄傞丅晽偼帹尦偱偛偆偛偆偲儂儚僀僩僲僀僘傪惗傒弌偡丅偙偺揥朷戜偼悽奅偺壥偰偱偁傞悈暯慄偐傜摍偟偔嫍棧偑偍偐傟丄偡側傢偪偙偙偑悽奅偺拞怱丅偦偆側傜偽偙偺偛偆偛偆偲柭傞壒偼偙偺応強傪幉偵抧媴偑夞揮偡傞壒丅揥朷戜偑幉偲偟偰抧媴傪巟偊偰偄傞廳傒偑攚拞偵偺偟偐偐傞丅巹偼巚傢偢嫨傇丅偦偺惡偼娵偄揥朷戜傪娵偔埻傓暬偵斀幩偟丄奼嶶偟偰嶶偭偰偄偔傋偒偦偺惡偼丄慡偰偺曽岦偐傜巹偵栠偭偰偔傞丅壗傕挳偒偨偔側偄巹偼椉庤偱帹傪傆偝偓丄偟傖偑傒偙傓丅庤偱梷偊傜傟偨帹偺墱偵棳傟傞寣塼偑棳傟傞壒偑偛偆偛偆偲嬁偄偰偔傞丅帹傪傆偝偄偩傑傑栚傪偮傓傝丄崱偼尒偊側偄摂戜偵巚偄傪抷偣傞丅摂戜偵巆偭偰偙偪傜傪尒偰偄傞偼偢偺孨偺摰傪巚偆丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
擔杤偼抶偔側偭偨偲偼尵偊丄柧傞偄偆偪偵戅幮偡傞側傫偰柌偺傑偨柌丅恖偵偼偆偐偑偄抦傟側偄棟桼偱墂偺峔撪偵怮偦傋傞恖偨偪傪屪偓墇偟側偑傜夵嶥傪弌傞丅偍搾偺拞偵擖偭偨傛偆側惗偸傞偄嬻婥傪偐偒暘偗側偑傜壠楬偵媫偖丅恖捠傝偑懡偄偔偣偵奨摂偑彮側偄摴偺偣偄偱廃傝偑埫偄丅摨偠曽岦偵曕偔恖偨偪偼壗屘偐懚嵼姶偵朢偟偄丅偙偺偆偪堦恖擇恖偑桯楈偱偁偭偰傕扤傕婥偵偟側偄丅巹偑桯楈偱偁偭偰傕扤傕崲傜側偄丅墶抐曕摴偱棫偪巭傑傞偲廃傝偺恖偑傒側敀偄僔乕僣偺傛偆側傕偺傪摢偐傜旐偭偰偄偨丅偦偆偄偆偙偲偐丄偲峇偰偰摢偵旐傞僔乕僣傪扵偟偰姄傪偁偝傞丅尒偮偐傜側偄偺偱嫲弅偟側偑傜僴儞僇僠傪摢偵嵹偣傞丅怣崋偑惵偵側傞慜偵堦惸偵敀偄僔乕僣偺孮傟偺恖偑曕偒弌偡丅屻傠偐傜墴偟弌偝傟偰巹傕幵摴偵憲傝弌偝傟傞丅僗僺乕僪傪弌偟偰墶抐曕摴偵撍偭崬傫偱偔傞僩儔僢僋偺塣揮惾傪尒傞偲塣揮庤偼敀偄僔乕僣傪旐偭偰偄傞丅婥偑偮偔偲堦恖偱墶抐曕摴偺庤慜偵棫偭偰偄傞丅怣崋偑惵偵側偭偨偑丄搉傜偢偵堷偒曉偡丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
揹幵傪崀傝偰夛幮偵岦偐偭偰曕偄偰偄傞帪偵RC僒僋僙僔儑儞偺僩儔儞僕僗僞儔僕僆傪挳偄偰偄偨傜椳偑弌偰偒偨丅壗屘媰偔偺偐峫偊巒傔傞偲夛幮偵峴偐偢偳偙偐墦偄扤傕抦傜側偄搚抧傊峴偭偰偟傑側偗傟偽偄偗側偔側傞傛偆側婥偑偟偨偺偱偙偺椳偼柍偐偭偨偙偲偲偄偆埖偄偵偡傞偙偲偵偟偨丅彫偝偄彜揦偵旘傃崬傓丅斀幩揑偵岥偐傜弌傞埆堄偺柍偄偙偲偩偗傪堄枴偡傞尵梩偩偗傪岥偵偟側偑傜儁僢僩儃僩儖偺偍拑偲儅僀儖僪僙僽儞儔僀僩傪攦偆丅偍偼傛偆偭偡偄傗偁弸偄偱偡偹偐側偄傑偣傫偹傎傜傕偆偙傫側偵娋偑挬偭傁傜偐傜偹偊枅擔戝曄偩傢偝係侾侽墌偹偁侾侽墌偁傝傑偡偐傜偼偄偳偆傕偠傖偁丅揦偐傜弌傞偲傾僗僼傽儖僩偐傜弌偰偔傞梲墛偵懌尦傪闳傔側偑傜壗傕峫偊側偄峫偊側偄偲孞傝曉偟欔偒側偑傜夛幮傊偺摴傪媫偖丅棤惡偺儘僢僇乕偼傑偩壧偄懕偗偰偄傞丅孨偺抦傜側偄儊儘僨傿乕丅墶抐曕摴偺岦偙偆偵偼價儖偑丅尒忋偘傞偲塤傂偲偮側偄惵嬻傪攚偵棫偭偰偄傞價儖丅挳偄偨偙偲偺側偄僸僢僩嬋丅價儖偺憢僈儔僗偵偼惵嬻偲儃僂儕儞僌応偺娕斅偺僺儞偩偗偑塮偭偰偄傞丅挳偄偨偙偲側傫偐側偄丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
摿偵彂偒偨偄偙偲傕側偄偺偱丄偟偽傜偔乽娫愙揑側寁夋(Oblique Strategies)乿偱梀傫偱傒傞丅
墂偺峔撪偵擖傞偲擔嵎偟偑幷傜傟偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢晄巚媍側偔傜偄椓偟偝傪姶偠側偄丅挬偺弌嬑偺偨傔偵嶦摓偡傞恖乆偼搶惣偵怢傃偰偄傞慄楬偺撿懁偲杒懁偐傜廤傑偭偰偔傞丅慄楬偺椉懁偵姴慄摴楬偑憱偭偰偄傞偨傔丄撿杒偺慄懳徧偺埵抲偵偁傞墶抐曕摴偺怣崋偼摨帪偵惵偲側傝丄寢壥偲偟偰堦搙偣偒巭傔傜傟偨恖偺棳傟偼堦惸偵撿杒偐傜嶦摓偡傞丅夵嶥偵帄傞峀偄愇偺奒抜傪桳岠偵巊梡偱偒傟偽椙偄偺偩偑丄墂偺愝寁幰偼忋傝揹幵偵忔幵偡傞忔媞偑僗儉乕僘偵棳傟傞傛偆偵愝寁偟偰偍傝丄奒抜偺塃偵愝抲偝傟偰偄傞僄僗僇儗乕僞乕偐傜塃懁偺擖応梡夵嶥塃懁偺忋傝曽柺儂乕儉偵棳傟崬傓埲奜偺棳傟傪嶌傝弌偡偵偼忈奞暔嫞憱偵嶲壛偡傞妎屽偑昁梫偲側傞丅偁偄偵偔偙偺墂偺嬤偔偵岺応偑偁傞偨傔乮偦傟傕塃懁偵乯夵嶥偺嵍懁偐傜弌偰偒偨棳傟偑夵嶥偺庤慜傪墶愗偭偰塃懁偵棳傟偰備偔丅偦偺棳傟傪撍偭愗偭偰偝傜偵塃懁偵棳傟傞慜屻偺恖偺棳傟偵忔傜偢壓傝揹幵偵忔傞偨傔偵偼棨忋慖庤偺慺梴偑昁梫偲偝傟傞丅奒抜偐傜戝検偵棳傟弌偡恖偵棳傟傪墶愗偭偰僄僗僇儗乕僞乕偵忔傞丅娭搶偱偼塃懁偼媫偖恖偺偨傔偵偁偗傞偙偲偵側偭偰偄傞偑丄挬偺弌嬑帪偵媫偄偱偄側偄恖偼偄側偄偙偲偐傜峫偊傞偲椉懁傪嬻偗傞傋偒偱偁傠偆丅偡傞偲僄僗僇儗乕僞乕偵儀儖僩偵忔傞偙偲偑悇彠偝傟傞丅僄僗僇儗乕僞乕偑廔椆偟夵嶥偵帄傞傑偱偺抁偄帪娫偵屻傠億働僢僩偐傜掕婜寯傪庢傝弌偡丅帴婥幃掕婜寯側傜偽峏偵掕婜擖偐傜掕婜傪庢傝弌偡丅僗僀僇偱偁傟偽偦偺傑傑掕婜擖傪曐帩偡傞丅掕婜擖傕偟偔偼掕婜寯傪塃庤偵宖偘偨僗僞僀儖偱嵍尐偵妡偗偨姄偑偢傝棊偪側偄傛偆偵拲堄偟側偑傜峏偵姄偑懠恖偵傇偮偐傜側偄傛偆偵攝椂偟偮偮丄慜傪墶愗傞岺応偵岦偐偆恖偺棳傟偺塓偵姫偒崬傑傟側偄傛偆偵僗僥僢僾傪摜傓丅帴婥幃掕婜寯側傜偽僗僀偲夵嶥偵媧偄崬傑傟夵嶥婡偺拞偺崅懍偵夞揮偡傞僑儉儘乕儔乕偵摫偐傟偮偮帴婥僿僢僪偵偰撉傒庢傜傟恖偺曕傓懍偝傪偼傞偐偵挻偊偰夵嶥婡偺弌岥偵弌尰偡傞丅僗僀僇偺応崌偼強掕偺応強偵墴偟晅偗傞丅墴偟晅偗傞応崌偵侾昩埲忋墴偟晅偗側偄応崌偼夵嶥偑寈崘壒傪敪偟丄斷偑暵傑傞丅屻傠偵懕偄偰偄偨恖偺棳傟偑巭傑傝偙偺娫敳偗傔丄偖偢偱偺傠傑傔丄懯攏偑丄閱攏偑偲攍惡傪梺傃偣傜傟傞丅愗晞傪巊梡偡傞応崌偼奒抜傪忋偭偰夵嶥偺慜傪堦扷墶抐偟愗晞斕攧婡偵偨偳傝拝偄偨屻丄峏偵夵嶥偺慜傪墶愗傞昁梫偑偁傞丅柍帠偵夵嶥傪捠夁偡傞偲偦偙偵偼儂乕儉傊偲懕偔奒抜偑懸偭偰偄傞丅夛幮偵帄傞椃偼傑偩巒傑偭偨偽偐傝偱偁傞丅
Oblique Strategies Copyright(c). 1975, 1978, and 1979 Brian Eno/Peter Schmidt
偦偟偰斷偑暵偞偝傟偨丂壀搱擇恖丂島択幮暥屔
妀僔僃儖僞乕偺拞偵暵偠崬傔傜傟偨抝彈巐恖丅悢儢寧慜偵巰傫偩桭恖傪嶦偟偨偺偼偦偺拞偺扤偐丅暵嵔忬嫷傪晳戜偵偟偨杮奿儈僗僥儕偺寙嶌偲偄偆偙偲偱撉傫偱傒傞丅偙偺僩儕僢僋偩偲丄傕偭偲暔岅揑偵怺偔弌棃偦偆側婥偑偟傑偡偑丄偁偊偰僩儕僢僋傪惗偐偡堊偩偗偵暔岅偑曺偘傜傟偰偄傞丅偳偆偟偰偙傫側偙偲偵側偭偰偟傑偭偨偐丄偲偄偆僩儕僢僋偼慺惏傜偟偄偺偵丄側傫偩偐傕偭偨偄側偄傛偆側婥偑偟傑偡丅
怴丒搚梛儚僀僪嶦恖帠審丂乣嫗搒榤恖宍嶦恖帠審乣丂偲傝丒傒偒亊備偆偒傑偝傒丂僪儔僑儞僐儈僢僋僗
備偆偒傑偝傒偼擔忢傪昤偔枱夋壠偱丄偲傝丒傒偒偼旕擔忢傪昤偔枱夋壠偩偲偄偆偙偲偑擛幚偵傢偐傞崌嶌偱偟偨丅
僩僯乕偨偗偞偒偺僈儞僟儉枱夋丂僩僯乕偨偗偞偒丂妏愳僄乕僗僐儈僢僋僗
弶戙僈儞僟儉偺TV斉偲塮夋斉偲彫愢斉傪撉傫偱偄側偄偲椙偔棟夝偱偒側偄枱夋丅偟偐偟柾幨偑偆傑偄側偁丅
嵟埆偩偤両 栭拞偵峏怴偡傞壣傕偹偉丅偮偄RC僒僋僙僔儑儞偺儀僗僩斉側偳攦偭偰偟傑偭偰丄巭傑傜側偔側偭偰庤帩偪偺CD偁傝偭偨偗挳偒側偍偟偰偨傜摢偑惔巙榊偵側偭偪傑偭偨丅偁偁丄偙傫側婥帩偪偆傑偔彂偗偨偙偲偑側偄丅偆乕偅巇帠傪僒儃偭偰偔偩傜側偄嶨暥傪彂偄偰偨偺偝丅孨偺抦傜側偄僐僺儁丅暦偄偨偙偲偺側偄傾儊儕僇儞僕儑乕僋丅庤岰偺偮偄偨懯煭棊偱丄攋抅偟偨榖傪彂偔偺偝丅堄枴傕側偔僆僠傪偮偗傞偤丅傊傊偄両 儀僀儀乕摝偘傞傫偩丅嶨暥偼傕偆懖嬈偩偲丄偁偄偮偼僒僀僩傪忯傓偺偝丅偍帡崌偄偩偤丅偄偄暵嵔暥偩側丅懯栚恖娫偩偭偨偺偵丄側傫偩偐傑偲傕偵側偭偨側丅懯煭棊僆僠偑姦偡偓偨傫偩傠偅丅偍偍丄塤偺愗傟娫偵婸偔僆乕儖僗僞乕愴丅埫埮偐傜暦偙偊偰偔傞慖嫇懍曬丅偙傫側栭偵懯煭棊傪彂偗側偄側傫偰丅偙傫側栭偵岆夝庍偱偒側偄側傫偰丅
嶰偮曇傒僸儘僀儞丂KAYO丂億儕僔僢僋僗偺僉乕儃乕僪偺拞偺恖偺僜儘乮儈僯乯傾儖僶儉丅側傫偲僞僀僩儖嬋偺乽嶰偮曇傒僸儘僀儞乿偼徏杮棽嶌帉丄嵶栰惏恇嶌嬋丅戝屼強偺嬋偵嬞挘偟偰偄傞偺偐儃乕僇儖偵椡偑擖傝偡偓側偺偑巆擮丅擇嬋栚偼偼偭傄偄偊傫偳偺柤嬋乽壞側傫偱偡乿丅彈惈帇揰偲側偭偨壞偺晽宨偑怴慛丅嶰嬋栚乽杔偨偪偺帪娫乿KAYO帺恎偺嶌帉嶌嬋丅壚嶌丅巐嬋栚乽儈僪儕億僢僾偱乿億儕僔僢僋僗偺僊僞乕偺拞偺恖嶌帉嶌嬋丅尦婥偑偄偄億僢僾僗丅儔僗僩偑乽偝傜偽僔儀儕傾揝摴乿徏杮棽亅戝戧塺堦僐儞價偺柤嬋丅側傫偐億儕僔僢僋僗偺HAYASIHI巵偺婅朷廩懌傾儖僶儉偺傛偆側婥偑偟偰側傝傑偣傫丅偄傗撪梕揑偵偼埆偔偼側偄傫偱偡偗偳偹丅惿偟傓傜偔偼丄偳偆偟偰傕偙偙偼KAYO偱側偗傟偽偄偗側偄偲偄偆惪媮椡偵寚偗傞傛偆側婥偑偟偰側傜側偄偺偱偡丅偄傗丄傎傫偲偵埆偔偼側偄傫偱偡偗偳丅
昐婍搆慠戃丂晽丂嫗嬌壞旻丂柺敀偄偐媗傑傜側偄偐偲尵傢傟傞偲柺敀偄偺偱偼偁傞偑丄僉儍儔朑偊傊偺孹岦偑恟偩偟偔丄偳偆傕姶怱偱偒側偄丅
偛巜揈偺捠傝丄僸儘僔偱偡丅偱偡丅偲偄偆傆偆偵丄彂偄偰偟傑偆偲丆儌乕僯儞僌柡丅偺傛偆偵乬偳偙偱丄暥偺嬫愗傟乭丅偐傛丗偔丄傢偐傜丏側偔丄乽側傝傑乿偡偹乮丏乯偱傕僸儘僔偱偡丅傛傝併傕憗偄亂曣偝傫亃偲偄偆亙愭椺亜傕偁傞嚈偟丄丩壌僇僱僑儞丩偲尵偊侓側偔亊傕側偄亊偐傕丠偹
扥壓嵍慥偲偄偊偽丄偙偺慜榐夋偟偰偍偄偨拞懞巶摱偺扥壓嵍慥傪憗憲傝偱僠儍儞僶儔偺応柺偩偗尒偰傒傑偟偨丅惽庤偺棫偪夞傝偑晛捠偺帪戙寑偺嶦恮偲堘偄丄懱傛傝愭偵搧傪傗偨傜怳傝夞偟偨傝丄偲巚偊偽恎懱偛偲撍偭崬傫偱峴偭偨傝偡傞嶦恮偱柺敀偐偭偨偺偱偡偑丄揋曽偑奆偑奆丄嵍慥偺尒偊傞傎偆傊尒偊傞傎偆傊夞傝崬傫偱傗偭偰偁偘偰偄傞偺偑晄帺慠偺傛偆側婥偑偟傑偟偨丅愗傜傟偰尒偊側偄栚偺曽傊夞傝崬傓傋偒偱偁傠偆偵丅暥屔偱弌偰偄傞偙偲偩偟丄尨嶌撉傫偱傒傛偆偐側丅偁丄惵嬻暥屔偵傕偁傞偧丅偟偐偟丄朙愳墄巌偱塮夋壔偱偡偐丅柊嫸巐榊傪愭偵傗偭偨傎偆偑傛偔側偄偐丅
僞僶僐偼儅僀儖僪僙僽儞儔僀僩傪堦擔堦敔丅僞僶僐傪媧偆偺偼娚枬側帺嶦丅偩偐傜丄懱偵埆偄偐傜傗傔側偝偄偲偄偆拤崘偵偼嬯徫偟偐晜偐偽側偄丅SIESTA偲偄偆僞僶僐偑恄撧愳導尷掕偲偄偆偙偲偱攧偭偰偄偨丅儗儌儞僌儔僗偺崄傝偑偡傞僞僶僐偲偄偆愰揱暥嬪偱偁偭偨丅妋偐偵壩傪偮偗偰傒傞偲儗儌儞僌儔僗偭傐偄崄傝偑偡傞丅偨偩偟僞僶僐偺崄傝傕枴傕偟側偄丅晻傪奐偗偰嶰廡娫曻抲偟偨僞僶僐偵崄椏傪怳傝偐偗偨姶偠丅
Alphabet H偲偄偆僞僶僐偑攧偭偰偄偨偺偱攦偭偰傒傞丅恀偭愒側僷僢働乕僕偵戝偒側H偲偄偆暥帤偑僨僓僀儞偝傟偰偄傞丅敔偺奐偗曽傕撪敔傪僗儔僀僪偝偣傞偲偙傠偑栚怴偟偄丅娞怱偺僞僶僐偼偙傟傑偨枴傕崄傝傕敄偄丅怴暦巻傪娵傔偰媧偭偨曽偑傑偟偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞丅
僴儕乕億僢僞乕偺怴嶌偺僞僀僩儖偼"Harry Potter and the Half Blood Prince"
僴儕乕億僢僞乕偲敿働僣墹巕乧乧偱偡偐丅
敾寛傪壓偡乧乧丅
悈懞旤昪偺乽巹彫愢乿乮怴挭暥屔乯傪撉傒巒傔傞丅僂僄僽偵僥僉僗僩傪忋偘偰偄傞恎偱偙偆偄偆偙偲傪尵偆偺偼側傫偱偁傞偑丄墶彂偒偺彫愢偲偄偆傕偺偵嫮楏側堘榓姶偑偁偭偰変側偑傜傃偭偔傝丅晳戜偑傾儊儕僇偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢巹彫愢僗僞僀儖偱偁傞偲偄偆暥壔揑側陹陾姶傪憹暆偝偣傞憰抲偲偟偰桳岠偵嶌梡偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟傞側偳偲傕偭偲傕傜偟偄偙偲傪尵偭偰傒傞丅偟偐偟丄墶彂偒偵偙傟傎偳堘榓姶傪姶偠傞偲偄偆偺偼壗側傫偩傠偆側偁丅巹偺擭楊揑側傕偺側偺偐側偁丅庒偄崰偼偦偆偱傕側偐偭偨傛偆側婥偑偡傞側偁丅婥偺偣偄偐側偁丅
偲偄偆偙偲偱丄墶彂偒偮側偑傝偱愇崟払徆偺乽怴壔乿乮僴儖僉暥屔乯傪撉傫偱傒傞丅奌愳徿岓曗丄栰娫暥寍怴恖徿岓曗丄愹嬀壴徿岓曗偺乽暯惉俁擭俆寧俀擔乧乿乮惓幃偵偼柍戣乯偲偦偺懕曇偺乽怴壔乿傪傑偲傔偨暥屔丅暥屔廂嵹偵偁偨偭偰廲彂偒偵曄峏偝傟偰偄傞偺偑巆擮丅撪梕偼儗億乕僩宍幃偺僴僱僱僘儈愨柵偺曬崘丅SF偲偟偰撉傓偲傾僀僨傿傾枾搙偑掅偄偟丄傾僀僨傿傾帺懱傕惗偐偝傟偰偄側偄傛偆偵巚傢傟傞偑丄暥寍帍偵墶彂偒偱敪昞偝傟偨偙偲傪峫偊傞偲丄偦偺懚嵼帺懱偑嫮楏側堘榓姶傪敪惗偟偰偄偨偲悇應偝傟傞丅巆擮側偙偲偵偦偺堘榓姶偼偙偺嶌昳偱姰寢偟偰偍傝丄奜傊偺峀偑傝偑姶偠傜傟側偄丅偦傟偼偦傟偱堦偮偺塅拡傪宍惉偟偰偄傞偲偄偆堄枴偱偼偄偄偺偱偡偑丄慡偔巆擮丅
敿拑偱偡丅
乽偁側偨丄僔儏儗僢僋偵偦偭偔傝偹丅乿
偲壠撪偐傜尵傢傟傑偟偨丅
敿拑偱偡丅
摽揷偝傫偲偙偱偍巕條偑屼惗抋側偝傟偰傔偱偨偄尷傝偱偁傞偑丄偙傟傪嶨暥偵偲偄偆惡傕偪傜傎傜偲堦審偩偗乮忕択偱乯暦偙偊偰偒傑偟偨偑丄煭棊偵側傜側偄偙偲偵側傞傛偆側婥偑偄偨偟傑偡偺偱帺弆偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅側偵偟傠抋惗偱嶨暥偲偄偆偲嵟弶偵摢偵晜偐傫偩僱僞偑審乮偔偩傫乯偩偭偨傝偟傑偡偐傜丅
敿拑偱偡丅
側偵傗傜乽屍妉捁偺壞乮偆傇傔偺側偮乯乿偑塮夋壔偩偦偆偱丄幚憡帥徍梇娔撀偲偄偆偙偲偱婜懸丅僸儘僀儞偵尨揷抦悽偲偄偆偺偼丄僨價儏乕埲棃偺僼傽儞偱偁傞巹偱傕偪傚偭偲堘偆偺偱偼側偄偐側偳偲巚傢偞傞傪摼側偄偺偑斶偟偄丅偱傕儊僀儞僩儕僢僋偑傾儗偩偐傜塮夋偺応崌丄僩儕僢僋偑曄峏偝傟傞偐傕丅偱傕傾儗傪曄偊偪傖偆偲慡慠堘偆榖偵丄側偳偲峫偊偰偄傞偆偪偵丄嶨暥彂偒偱攝栶偑壜擻偩側側偳偲撪椫僂働側帠傪巚偄偮偄偨偺偱偡偑丄偳偆傕偙傟傕嵎偟偝傢傝偑偁傝偡偓傞傛偆側婥偑偟偰偒傑偟偨偺偱杤丅
敿拑偱偡丅
枩擻偹偓偺乽傇偝偄偔乿偑偄偄偍榖偩側偁丅偡偛偔傛偐偭偨偱偡丅堦偮慜偺乽媫峴揹幵偺峴曽乿傒偨偄側偺傕岲偒偩偗偳丅
敿拑偱偡丅
側傫偐慡慠柊傟傑偣傫丅壓忦偝傫偺乽抶寱乿偑惁偄丅巆擮側偙偲偵巹偼帪戙彫愢偵慳偄偺偱丄乽抶寱乿傪惓摉偵昡壙偡傞偙偲偑弌棃側偄偺偑巆擮偱偡偑丄偲偵偐偔乽抶寱乿偲偄偆傾僀僨傿傾偑惁偄丅偦偟偰偦偺乽抶寱乿偲偄偆傕偺偑偙偺偍榖偺拞偱愯傔傞埵抲偺僶儔儞僗偑愨柇丅乽抶寱乿偑嫊峔偱偁傞偙偲偺徾挜側偺偐嫵孭偺嵽椏偱偁傞偺偐敾慠偲偟側偄偲偄偆偺偑偄偄丅
敿拑偱偡丅
側傫偐慡慠柊傟傑偣傫丅
敿拑偱偡丅
敿拑偱偡丅
側傫偐僥僉僗僩彂偔婥偵側傟側偄偺偱崿棎偟偨悈偺棳傟偺忋偵壦偐傞嫶傪憐憸偟偰傒偨傝偡傞丅
偝偪偲偹偙偝傑俀丂搨戲側傪偒丂僄儞僞乕僽儗僀儞僐儈僢僋丂偳偆傕慜姫偐傜僺儞偲偙側偄偺偱偁傞偑偙傟偼偄偭偨偄偳偆偟偨偙偲偱偁傠偆丅偹偙偝傑偺僉儍儔偑偄傑傂偲偮棫偭偰偄側偄偲偙傠偑暔懌傝側偄偺偱偁傠偆偐丅偆偆傓丅偆偆傓丅
僱僈僥傿僽僴僢僺乕丒僠僃儞僜乕僄僢僡丂戧杮棾旻丂妏愳暥屔丂塉偺拞儊儕乕僑乕儔僂儞僪偑夞傜側偄乽儔僀敒敤偱偮偐傑偊偰乿丅壗屘夞傜側偄偐偲偄偆偲丄夞傞偙偲偼堦偮偺媬偄偱偁傝摨帪偵夝寛偱偁傞偐傜丅嶌幰偼杮擻揑偵偦傟傪夞旔偟丄偁偐傜偝傑偵敄偭傌傜側儀僯儎斅偵儁儞僉偱昤偐傟偨條側夝寛傪偁偊偰栚偺慜偵抲偔丅偦偟偰嶌幰傕搊応恖暔傕撉幰傕惓偟偄夝寛偑懚嵼偟側偄偙偲傪抦偭偰偄傞偑屘偵丄偙偺夝寛偲偦偺棤偵偁傞傕偺偵偮偄偰抦傜側偄傆傝傪偡傞丅偦偺堄枴偱偼嶌幰偲搊応恖暔偲撉幰偼嫟斊幰偱偁傞丅
側傫偐僥僉僗僩彂偔婥偵側傟側偄偺偱悈偺忋偺墝傪憐憸偟偰傒偨傝偡傞丅
愗晞傪攦偭偰偲傝偁偊偢儂乕儉偵擖偭偰偒偨WISH偲偄偆柤慜偺楍幵偵忔偭偰傒傞丅帺桼惾偺憢嵺傪妋曐偱偒偨偺偱僇僶儞偺拞偵曻傝崬傫偩傑傑曻抲偝傟偰偄偨暥屔杮傪揔摉偵慖傫偱撉傒偼偠傔傞丅傢偨偟傪尒偐偗傑偣傫偱偟偨偐丠丂僐乕儕傿丒僼僅乕僪憗愳epi暥屔丂撉幰傪徫傢偣傞偙偲傪栚揑偲偟偨抁暥丅嶨暥偲偄偆偙偲偱偊偊傗傫丅栿幰偁偲偑偒偱惙戝側僱僞偽傜偟偑偁偭偨丅愺憅媣巙偑奜弌偟傛偆偲偡傞偲斷偺慜傪昐旵偺崟擫偑廤抍偱墶愗偭偰側傫偐偄傗側姶偠傪偆偗傑偡傛偆偵偲庺偄傪偐偗傞丅嶰敿婯娗偑斶柭傪偁偘巒傔偨偺偱柊傞丅
栚傪妎傑偡偲憢偐傜尒偊傞傾僗僼傽儖僩偑崟偔岝偭偰偄傞丅偳偆傗傜嬻偐傜悈偑棊偪偰偒偰偄傞傛偆偩丅巹偑嵗偭偰偄傞堉巕偼壗屘偐崅懍偱堏摦偟偰偄傞傜偟偔丄廃傝偺宨怓偑傕偺偡偛偄惃偄偱屻傠偵壓偑偭偰偄偔丅抧媴偑抋惗偟偰偐傜壗壄夞傕壗挍夞傕嬻偐傜悈偼崀偭偰偼巭傒崀偭偰偼巭傒丄偦偺搙偵搚偼嶍傜傟丄娾偼梟偐偝傟丄愇偼嵱偐傟丄偦偟偰壗廫壄夞傕壗昐挍夞傕悈偼棊偪丄抧昞偺弌偭挘傝偼嶍傜傟丄傊偙傒偼杽傔傜傟抧媴偼姰慡偵側傔傜偐側媴懱偲壔偟偰偄傞偼偢偱偁傞偺偵丄偁偺憢偐傜尒偊傞嫄戝側搚偺夠偼壗偱偁傠偆丅僼儖僿僢僿儞僪偟偰偄傞搚偺嫄戝側夠偼丄偝偡傟偽怴偨偵嬻拞傛傝弌尰偟偨傕偺偵堘偄偼側偔丄恖偲偦偺暥柧偵偦偺傛偆側嫄戝側搚夠傪柍悢偵弌尰偝偣傞椡偑側偄偙偲偐傜丄偦偼堎惎偺抦揑惗柦懱偺巇嬈偵懠側傜側偄偱偁傠偆丅
巹偑嵗偭偰偄傞堉巕傕傠偲傕崅懍偱堏摦偟偰偄傞嵶挿偄嬥懏偺敔偼丄偦偺堎惎偺抦揑惗柦懱偑嶌惉偟偨搚偺嫄戝側夠偱墌宍偵埻傑傟偨搒巗傊偲妸傝崬傫偱偄偔丅堎惎偺抦揑惗柦懱偑堄恾揑偵埻傫偩搒巗側傟偽丄偦偺廧柉偼堎惎恖偱偁傞偑昁掕丅僯儏乕僩儞偺姷惈偺朄懃傪柍帇偟偨枹抦側傞椡偵傛傝丄嵗惾偺塣摦偼掆巭偟偦偺堎惎恖偑廧傓搒巗傊崀傝偰偄偔巹丅摴峴偔恖恖偼巹偺棟夝偱偒側偄壒惡傪敪偟僐儈儏僯働乕僔儑儞傪偲偭偰偄傞傛偆偩丅
堄枴傕側偔巜掕偝傟偨応強偱堄枴傕側偔巜掕偝傟偨嶌嬈傪廔偊丄堎惎恖偵漟抳偝傟傞偙偲傪嫲傟丄偡偖偵WISH偲偄偆柤偺敔偵旘傃忔傞丅嵗惾偵嵗偭偰偐傜丄H.A.巵偵楢棈偲傟偽傛偐偭偨偐側偲巚偆娫傕側偔堄幆傪幐偆丅
側傫偐僥僉僗僩彂偔婥偵側傟側偄偺偱揤崙偑柍偄偙偲傪憐憸偟偰傒偨傝偡傞丅
擔杮暥妛惙悐巎丂崅嫶尮堦榊丂島択幮暥屔丂晽楥偵擖傞慜偵偪傚偭偲撉傫偱傒傛偆偲偟偨傜巭傑傜側偔側偭偰寢嬊挬偺屲帪丅柧帯帪戙偺暥崑偑偳偺傛偆偵暥妛偺壜擻惈傪奼偘傛偆偲偟偰偄偨偐丅偦偟偰偳偺傛偆偵偝偝偄側惉壥傪摼偰丄柍巆側幐攕傪悑偘偨偐偵偮偄偰丅朻摢偐傜嵟屻傑偱巰偺垼偟傒偩偐姶彎偩偐偑偮偒傑偲偭偰棧傟側偄丅戫栘偑僽儖僙儔僔儑僢僾偺揦挿傪偟偰偄偨傝壴戃偑AV娔撀傪傗偭偨傝偲丄偁偄偐傢傜偢偺尮堦榊愡丅摉慠偦傟偵偼昁慠惈偑偁傞傢偗偱丅
崅嫶尮堦榊偺彂偔傕偺偼戝岲偒偱丄偱傕偁傑傝恖偵徯夘偟偨偔側偄偲偄偆婥帩偪傕偁傞丅壗屘側傫偩傠偆丅斵偺彂偔傕偺偵偼姶彎偵堨傟偰偄偰丄巹偺怱偺庛偄晹暘傪巋寖偡傞偐傜偩傠偆偐丅
擔杮暥妛惙悐巎偼垼偟傒偵堨傟偰偄偰丄偦傟偼暥妛偑壗帠偐惉偟摼傞偼偢偲偄偆妝娤庡媊偵婎偯偄偰偄傞偐傜偱丄寢嬊偺偲偙傠惉偟悑偘傜傟側偄乮偐偭偨乯偲偄偆尰幚偵捈柺偡傞偐傜丅偦偆偄偆堄枴偱偼丄壗帠傕惉偟悑偘傜傟側偄偲偄偆梊姶偵枮偪堨傟偰偄偨僑乕僗僩丒僶僗僞乕僘偑丄寢嬊偼偝偝傗偐側岾暉姶偲嫟偵姫傪暵偠傞偲偄偆揰偱杮彂偲昞棤傪側偟偰偄傞偲傕尵偊傞丅
僑乕僗僩丒僶僗僞乕僘偵偮偄偰偼傕偭偲岅傝偨偄婥帩偪傕偁傞偺偩偑丄椺偊偽戝岲偒側応柺乧乽彮擭偑捛愓拞偵寕偨傟偰巰偸偲偙傠偺昤幨乿偲偐乽攎徳偑墛忋偡傞僩儔僢僋偵撍偭崬傓応柺偱昤偐傟偨揤嵥偺斶偟傒乿偲偐丅偁丄側傫偩偐恖偑巰偸偲偙傠偽偐傝偩丅
岲偒側傕偺偵乮柍堄幆偺偆偪偵乯嫟捠揰偑偁傞偺偼偡偛偔晄巚媍丅壗屘恖偑巰傫偱偟傑偆偍榖偽偐傝側偺偩傠偆丅偦偆偄偊偽丄崅峑偺帪偵岲偒側儅儞僈傪嫇偘偰偄偭偨傜壗屘偐摨惈垽幰偑弌偰偔傞偍榖偽偐傝偩偭偨偙偲偵婥偑偮偄偰烼偵側偭偨偙偲偑偁偭偨丅偁傟傕晄巚媍偩偭偨側偁丅乮擮偺堊偵怽偟忋偘傑偡偑丄巹偼摨惈偵偼惈揑側嫽枴偼側偄偟丄偡偖偵巰偸梊掕傕偁傝傑偣傫丅乯
側傫偐僥僉僗僩彂偔婥偵側傟側偄偺偱晽偵悂偐傟偰傒偨傝偡傞丅
朑偊傞僔僠儏僄乕僔儑儞丅
庡恖岞偲揋懳偟偰偄傞埆偑偄偰丄挿擭偵搉偭偰懳棫偟偰偄傞忬嫷丅偦偙傊怴偨偵嫮椡側椡傪帩偭偨戞嶰惃椡偑弌尰偟丄椺偊偽恖椶柵朣側偳傪峴偍偆偲偡傞丅偳偆傗傜偦傟傪峴偆偩偗偺幚椡偑偁傝偦偆偱偁傞丅庡恖岞乮払乯偼戞嶰惃椡偺栰朷傪杊偑偹偽側傜側偄偲寛堄偡傞偑丄偦偺椡偑偁傑傝偵傕嫮偔偰偳偆嶌愴傪楙傠偆偐擸傫偱偄傞偲偙傠偵丄埲慜偐傜揋懳偟偰偄偨埆偐傜價僕僱僗暥彂偑晳偄崬傓丅
攓孾
帪壓傑偡傑偡偛惔徦偺抜丄偍宑傃怽偟忋偘傑偡丅暯慺偼奿暿偺偛崅攝傪帓傝丄岤偔偍楃怽偟忋偘傑偡丅憗懍偱偼偛偞偄傑偡偑丄嶐崱掗搒偵墬偒傑偟偰偼掗搒攋氂抍偲柤忔傞柍朄幰偺廤抍偑挼椑骐缁偟偰偄傞偙偲偼恓堜條偵偍偐傟傑偟偰傕偍暦偒媦傃偺偲偙傠偲懚偠忋偘傑偡丅
偐偹偰傛傝暰幮偵偍偒傑偟偰偼掗搒偺巟攝傪傕偔傠傒崙柉傪巟攝壓偵偍偔傋偔塻堄搘椡偟偰偄傞偲偙傠偱偼偛偞偄傑偡偑丄枩偑堦偵傕掗搒攋氂抍偺栚揑偲偡傞掗搒偺夡柵偍傛傃崙柉偺枙嶦偑払惉偝傟傑偡偲丄暰幮偺栚揑偱偁傝傑偡偲偙傠偺掗搒偺巟攝偵巟忈傪惗偠傞傗偺寽擮偑暐怈偝傟偸偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅捠忢側傜偽暰幮偼朤娤偡傞偲偙傠偱偛偞偄傑偡偑丄愭擔偺儐儕僆儞寑応偵偰帵偝傟傑偟偨掗搒攋氂抍偺攋夡峴堊偺寢壥偺恟戝偝傪娪傒丄偙傟偼曻抲偱偒偸偲偺寢榑偵帄偭偨師戞偱偁傝傑偡丅
偮偒傑偟偰偼丄恓堜條偵偍偐傟傑偟偰偼暰幮偲偺娫偵挿婜娫偵搉傝傑偟偰揋懳娭學傪抸偄偨偲偄偆宱堒偼偛偞偄傑偡偑丄忋婰偺帠忣傪娪傒丄堦帪揑偵揋懳娭學傪搥寢偄偨偟傑偟偰嫟捠偺揋偱偁傝傑偡偲偙傠掗搒攋氂抍偺栚揑偺慾巭偵娭偟傑偟偰嫟摤偟偰偼偄偐偑偐偲偛採埬偝偣偰偄偨偩偒傑偡丅暿巻偵婰嵹偟偰偍傝傑偡忦審偑婱堄偵偐側偄傑偟偨傜丄側偵偲偧暰幮偲怴婯偍庢傝堷偒帓傢傝傑偡傛偆丄傛傠偟偔偛崅攝偺傎偳偍婅偄怽偟偁偘傑偡丅
側偍丄偛嶲峫傑偱偵偙偺嫟摤偼塱懕揑側傕偺偱偼側偔丄掗搒攋氂抍偺攋夡峴堊偑慾巭偝傟傑偟偨嬇偵偼丄暰幮偼掗搒偺巟攝偵岦偗偨妶摦傪嵞奐偡傞強懚偵偛偞偄傑偡丅
偛懡朲拞嫲傟擖傝傑偡偑丄媂偟偔偛専摙偺忋壗懖偛崅攝傪帓傝傑偡傛偆偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅側偍丄徻偟偔偼偍揹榖偱偍栤偄崌傢偣壓偝偄丅
彂拞偵偰傑偢偼偍婅偄怽偟忋偘傑偡丅
枛昅側偑傜偛堦摨條偵偔傟偖傟傕傛傠偟偔怽偟忋偘偰偔偩偝偄丅
宧嬶
庡恖岞乮払乯偼丄妱傝愗傟側偄傕偺傪姶偠側偑傜偙偺採埬傪庴戻偡傞丅偟偐偟峴摦傪嫟偵偡傞偙偲偼庡媊偵斀偡傞偺偱丄暿乆偵戞嶰惃椡偵棫偪岦偐偆丅庡恖岞偑愨懱愨柦偺婋婡偵娮偭偨偲偒偵丄媽棃偺揋偑傂偦偐偵彆偗傞丅庡恖岞偼偦傟偵婥偑偮偐側偄丅庡恖岞偼抦宐偲桬婥偱戞嶰惃椡傪晻偠崬傔丄崀嶲偡傞偙偲傪姪崘偡傞丅戞嶰惃椡偺庱椞偑嵟屻偺斀寕傪峴偍偆偲偡傞丅庡恖岞偼偦偺峌寕偵旛偊偰峔偊傞偑壗傕婲偙傜側偄丅戞嶰惃椡偺嵟屻偺旈枾婎抧偵傕偖傝偙傓偲丄庱椞偼柍巆側巰懱偲側偭偰偄傞丅庡恖岞払偑斀寕偟偰偄傞寗偵媽揋偑戞嶰惃椡偺慻怐偵愽擖偟丄庱椞傪嶴嶦偟偨傜偟偄丅媽揋偼栚揑傪払偡傞偲垾嶢傕側偟偵偦偺巔傪徚偟偨丅
偲偄偆僔僠儏僄乕僔儑儞偑岲偒偱偨傑傜側偄偺偱偡偑丄
愮棦娽傪帩偮抝/儅僀働儖丒僋乕儔儞僪/島択幮暥屔偼儂乕儉僘塱墦偺廻揋儌儕傾乕僥傿偑戝妶桇両偲偄偆偙偲偱偰偭偒傝偦偆偄偆偍榖偐偲巚偭偰撉傫偱傒偨偺偱偡偑丄偳偆傗傜偦偆偱傕側偄傒偨偄偱乮彑庤偵乯偑偭偐傝丅儂乕儉僘偲儌儕傾乕僥傿偑嬞挘姶傕柍偟偵暯婥偱摨偠応強偵嫃傞傫偩傕偺丅柍偄暔偹偩傝偲暘偐偭偰偄偰傕側偁丅偄傗丄傕偪傠傫埆偄偺偼巹側偺偱偡偑丅
屗揷惤巌偺乽There She Goes乿傪扵偟偰栭偺奨傪渇渞偄曕偄偨偺偩偑尒偮偐傜側偄丅[amazone偱峸擖]丅僒僀僩偵抲偄偰偁傞mp3傪挳偄偰傒傞偲僯僇晽枴偺僥僋僲億僢僾偱側偐側偐偄偄姶偠丅
RC僒僋僙僔儑儞偺僗儘乕僶儔乕僪偼巹偵偲偭偰摿暿側嬋偱丄偲偄偆偺偼乽挀幵応偱乿偲偄偆側傫偲偄偆偙偲傕側偄尵梩偱傕恖傪媰偐偣傞偙偲偑弌棃傞偲偄偆偙偲傪嫵偊偰偔傟偨嬋偩偐傜丄偲偄偆偺偼抲偄偲偄偰屗揷巵偺僗儘乕僶儔乕僪偺夝庍傕偄偄側偁丅傑偁婥偵擖偭偨傜攦偭偰傒偰傛丅
嬤揝僶僼傽儘乕僘傪僆儕僢僋僗偵攧媝偡傞榖偑恑傫偱偄傞傜偟偄丅偙偺傑傑恑傓偲僷儕乕僌偑堦媴抍尭傞偙偲偵側傞偱偼側偄偐丅偦偆側傞偲丄埲慜偐傜鄮偭偰偄偨侾儕乕僌惂傊偺堏峴傊抏傒偑偮偄偨傝偡傞偺偱偼側偄偐偲怱攝偱偁傞丅偙偺傑傑媴抍偺搼懣偑偳傫偳傫恑傓偲丄媶嬌揑偵偼僾儘栰媴侾儕乕僌偳偙傠偐丄僾儘栰媴侾僠乕儉惂偲側偭偰偟傑傢側偄偐偲怱攝偱偁傞丅帋崌偟側偔偰傕柤幚嫟偵僾儘栰媴嵟嫮僠乕儉偲柤忔傞偙偲偑弌棃傞偲偄偆棙揰偼偁傞偑丅
偍尵梩偱偡偑乧乮俆乯丂僉儔僀側偙偲偽惃懙偄丂崅搰弐抝丂暥弔暥屔丂埲慜偐傜壗屘擔杮偺偙偲傪僕儍僷儞偲尵偆偺偐晄巚媍偱偟偨丅側傞傎偳杮擔乮儂儞僕僣乯偲摨條偵丄擔傪僕僣偲撉傫偩偺偐丅偙傟偩偗偱傕掕壙暘偺壙抣偑偁傞偲偄偆傕偺偱偁傞丅
廟傝偨偄揷拞丂揷拞孾暥丂懷偵戝偒偔乽拑愳徿庴徿嶌乿偲彂偄偰偁傞丅拑愳徿庴徿捈屻偵幐鏗偟偨揷拞孾暥偺堚峞廤偲偄偆懱乮偰偄乯偱曇嶽偝傟偨抁曇廤丅偁偄偐傢傜偢懯煭棊SF偱撪梕偼婼抺丅懠恖偺懯煭棊傪暦偔偲晄桖夣偵側傞巹偑巚傢偢徫偭偰偟傑偆丅枩恖偵偼偍姪傔偱偒側偄偑丄偔偩傜側偄偙偲偑岲偒側傂偲側傜偳偆偧丅
娙扨偵抐傟側偄丂搚壆尗擇丂怴姧側偺偵抲偄偰側偄杮壆偑懡偔偰扵偟夞傝傑偟偨丅攧傟偰側偄偺偐側丅撪梕偼憡曄傢傜偢丅
億儕僔僢僋僗偑僸僇僔儏乕偺僷僀僋乮儔僀僽僶乕僕儑儞乯傪僇僶乕偟偰偄傞偺偱丄偮偄偱偵僇僶乕尦傪挳偒曉偟偨傝偡傞丅寢嬊丄僷僀僋偭偰壗幰側傫偩傠偆側偁丅傑偝偐僫儉丒僕儏儞丒僷僀僋偺偙偲偱偼偁傞傑偄側丅
億儕僔僢僋僗偑僾儔僗僠僢僋僗偺good両傪僇僶乕偟偰偄傞偺偱丄偮偄偱偵僇僶乕尦傪挳偒曉偡丅挻偄偄偐偘傫側壧帉乮夛榖嫵幒偺椺暥偦偺傑傑乯偲丄僠僇偺敋敪偟偨儃乕僇儖偑偁偄偐傢傜偢奿岲偄偄丅
抍挿偺堦枩傪摜傒傑偟偨丅
僐僯乕丒僂傿儕僗偺乽將偼姩掕偵擖傟傑偣傫乿偺昡敾偼椙偄傛偆偱偡偑丄偁傞僒僀僩偱乽僪僁乕儉僘僨僀丒僽僢僋乿偲乽峲楬乿傪撉傫偱偐傜撉傓偙偲丄偲彂偄偰偁偭偰傔偘傞丅偳偪傜傕忋壓姫偺戝嶌偱偼側偄偐丅嵟嬤杮壆偱傕尒偐偗側偄偟丄杮壆偱扵偡強偐傜巒傔側偄偲偄偗側偄偱偼側偄偐丅
挬擔怴暦偱乽將偼姩掕偵擖傟傑偣傫乿偺彂昡傪尒偐偗傞丅乽儃乕僩偺嶰恖抝乿傊丄偳偆偄偆晽偵僆儅乕僕儏偑曺偘傜傟偰偄傞偐彂偄偰偁傞偱偼側偄偐丅偦偆偄偆傕偺偼撉傫偩恖偑僯儎儕偲偡傟偽偄偄偲偙傠偱偁偭偰丄撉幰偺枾偐側妝偟傒傪扗偭偰暯慠偲偟偰偄傞偙偺懺搙傛丅彂昡傪彂偄偨孖揷榡偲偄偆恖偼丄挷傋偰傒傞偲揤惡恖岅偺拞偺恖傜偟偄丅側傞傎偳暥復偵垽忣傪書偐側偄恖偑彂偒偦偆側偙偲偱偁傞丅傑偁偙偆偄偆偙偲傪彂偄偰偟傑偆恖偵偼丄偄傑偝傜壗傪尵偭偰傕柍懯偩傠偆丅將偵姎傑傟偨偲巚偭偰掹傔傞偟偐側偄丅將偼姩掕偵擖傟傑偣傫丅
巰幰偺懱壏丂戝愇孿丂妏愳儂儔乕暥屔丂尦棨忋偺擔杮戙昞慖庤偱嶰廫嵨偺埨揷偼僄儕乕僩僒儔儕乕儅儞丅僴儞僒儉偱壏岤偱楢懕嶦恖斊丅偦偺恖偵僗儁傾偑側偄丄偐偗偑偊偑側偄恖偩偐傜嶦偡丅偲丄擔忢偺峴堊偺傛偆偵斀暅偝傟傞嶦恖偺忣宨傪昤偔丅偙偺榖丄嫲偄偐嫲偔側偄偐偲尵傢傟傞偲丄巹偼嫲偔側偐偭偨偑丄庡恖岞偺偁傝傛偆偑柺敀偐偭偨丅乽嶦恖偵帄傜偢惗偒偰偄傞埨揷乿偲偄偆僥乕儅偺嶌昳傕撉傫偱傒偨偄丅偦偆偄偆偺偼傕偆偁傞偺偐側偀丅
僜僼僩儅僔乕儞丂僶儘僂僘丂壨弌暥屔丂僇僢僩傾僢僾偺偲偙傠偑偲偰傕柺敀偄丅偲偄偆偙偲偼帊偲偟偰撉傫偱偄傞偺偐側丅
壓嵢暔岅丂浽杮栰偽傜丂彫妛娰暥屔丂偳偆傗傜塮夋偑昡敾傜偟偄偐傜偲偄偆偙偲偱撉傒巒傔傞丅偁傑傝偵傕彫愢揑偱側偄岅傝岥偱嬃偔丅抝惈偑丄堦尒彈惈揑側傕偺傪栚巜偟偰彂偄偰偄傞傛偆偵姶偠傜傟傞丅側偵偟傠梊旛抦幆偑慡偔側偄偺偱側傫偲傕偄偊側偄偺偩偑丅寁嶼偱傗偭偰偄傞偺偐揤慠側偺偐丅
僥僉僗僩偺嶍彍偺棟桼偑丄巹偺堦嶐擔偺擔婰偺偣偄側傜偽戝曄怽偟栿側偄丅偁傟偼帺暘偵岦偗偰彂偄偨傕偺偱丄恖條偺暥復偑偳偆偺偙偆偺偲偄偆偮傕傝偱偼側偐偭偨偺偱偡偑丄偦偺傛偆偵庴偗巭傔傜傟偨偲偄偆偱偟偨傜巹偑埆偄偺偱偡丅偛傔傫側偝偄丅
polisix / National P
崱偛傠挳偄偰偄傞傢偗偱偡偑丄僊僞乕僥僋僲僷儞僋僶儞僪偺杮椞敪婗偲偄偆偐懠恖偵偼棟夝偱偒側偄偼偠偗偭傉傝偑婥帩偪偄偄偱偡丅側偵偟傠僐乕儔僗偑乽僺僢僺僉僺僢僺乕僺乕両乿壧帉傕傎偲傫偳堄枴偑傢偐傝傑偣傫丅傛偔傢偐傝傑偣傫偑丄側偤偐巹偼巹偵偼棟夝偱偒側偄傕偺偑岲偒側傛偆偱偡丅乽僇僕儍僇僕儍僌乕両乿偲偵偐偔堄枴偑傢偐傝傑偣傫丅
僟儞僙僀僯偺乽悽奅偺奤偺暔岅乿傪撉傫偱偄傞搑拞丅嵟弶偺曽偼変枬偲偄偆忣曬傪摼偰丄妎屽偟偰撉傒巒傔偨偺偱偡偑丄嵟弶偐傜側傫偲偄偆偐偡偛偔柺敀偄丅恄榖揑悽奅偺昤幨偱偁傞抁偄偍榖偑偨傑傜側偔枺椡揑偱丄偦偙偼変乆偺悽奅偲堎側傞朄懃側偺偱偁傞偑丄偦偺棟夝偱偒側偝偑柺敀偄丅
傗偭傁傝丄堄枴側傫偰扅偺忺傝偱偡傛丅
乽嫲晐偼儚僯偺擼偐傜傗偭偰偔傞乿偲偄偆偙偲偱壗偐彂偗側偄偐偲峫偊偰偄傞偺偱偡偑堦岦偵傑偲傑傜側偄撪偵傕偆6寧丅愢柧偡傞偺傕柺搢偔偝偄偺偱丄傛偔暘偐傜側偄恖偼儚僯偺擼偲偐僂儅偺擼偱専嶕偟偰偔偩偝偄丅
偙偙偐傜榖偼曄傢傞偺偱偡偑丄嫲晐偺姶忣偲摨條偵夣丒晄夣偺姶忣傕儚僯偺擼乮擼姴乯偐傜傗偭偰偔傞偺偱偡丅偱偡偐傜棟惈揑側巚峫傪偮偐偝偳傞怴旂幙乮恖偺擼乯偱晄夣側帠崁偵偮偄偰偄偔傜愢柧傪偮偗傛偆偲偟偰傕偆傑偔偄偒傑偣傫丅棟孅偑偁偭偰晄夣偵側傞偺偱偼側偔丄晄夣偩偐傜偁偲偱棟桼傪扵偟弌偡偺偱偡丅偱偡偐傜偦偆偄偆椶偺榖偵偮偄偰偼丄懠幰偼嫟姶偡傞偐斲掕偡傞偐擇幰戰堦偵側傝傑偡丅晄夣偵嫟姶偡傟偽偦傟偼晄夣偱偁傝傑偡偟丄晄夣傪斲掕偡傟偽丄偦傟偼嫟姶偺斲掕偱偡偐傜晄夣偲側傝傑偡丅偙偙偐傜摫偒弌偣傞偺偼晄夣側傕偺乮亖垽忣傪書偗側偄傕偺乯偵懳偡傞扨弮側尵媦偼晄夣偟偐彽偐側偄偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅扨弮側晄夣偺昞柧偼丄儚僯偑妉暔傪欨偊偰悈拞偱偖傞偖傞偲夞偭偰偄傞偺偲戝嵎偁傝傑偣傫丅岥偵偣偞傞傪摼側偄偺偱偟偨傜丄偱偒傟偽寶愝揑側採尵傪丄偦傟傕柍棟側傜偽側偵偐寍傪尒偣傛丅偲帺暘偵尵偄暦偐偣傞枅擔偱偡丅儚僯偑僌儖僌儖丅
側傫偐摢偺拞傪嶳梤柡偺榖偑偖傞偖傞夞偭偰偄偰懠偺帠傪彂偗側偔側偭偨偺偱丄峓奣偺傒彂偄偰偍偔丅彂偄偰傒傞偲傗偭傁傝嫻暢偑埆偄榖側偺偱塀偟偰傒傞丅
傎傫偱傕偭偰幚偼嶳梤柡偙偺崙偺墹彈偱丄偍忛偵栠傞偙偲偵側傞丅徔偼偦偺夁掱偱塹暫偵嶴嶦偝傟傞丅嶳梤柡偼偦偺慺杙側弮恀偝偱偍忛偺恖乆偺怱傪桙偟偰備偔丅嶳梤柡偺悽榖傪偟偰偄偨彈姱偺巰懱偑敪尒偝傟傞丅師偵彈墹偑嶦偝傟傞丅斊恖偼嶳梤柡偱偁傞偺偩偑丄媨掛撪偺暋嶨側棙奞娭學偵暣傟偰嶳梤柡偺懚嵼傪棙梡偡傞恖偺巚榝偲丄傗傫偛偲側偄恖乆摿桳偺僄僉僙儞僩儕僢僋側怳傞晳偄偺偨傔丄恀憡偼側偐側偐柧傜偐偲側傜側偄丅偮偄偵嶳梤柡偑巰懱偱敪尒偝傟傞丅巰懱偺椬偵棫偪偡偔傫偱偄偨墹巕偼丄巹偑嶦偟偨偺偩偲欔偔丅
嶳梤柡偼怷偱曢傜偟偰偄偨偙傠嶳梤偑曣恊丄徔偑晝恊偲偟偰堢偭偰偄偨丅傕偪傠傫徔偼嶳梤擕傪庢傞偨傔偲怘擏梡偵嶳梤傪帞堢偟偰偄偨丅擕偑弌側偔側偭偨嶳梤傪怘梡偲偟偰搄嶦偡傞慜偵丄徔偼嶳梤偲惈岎偟偰偄偨丅偦傟傪抦偭偰偄偨嶳梤柡偼偦偆偄偆傕偺偱偁傞偲巚偄崬傓丅偡側傢偪丄惈岎屻偑側偝傟偨屻偵曅曽偼嶦偝傟傞傋偒偱偁傞丅偍忛偵栠偭偨嶳梤柡偼丄彈姱偑埀堷偟偰偄偨偺傪栚寕偟丄偦偟偰惈岎偑峴傢傟偨偺偵傕偐偐傢傜偢彈姱偑嶦偝傟側偄偺傪垽忣偑懌傝側偄晄溹側偙偲偱偁傞偲斶偟傒丄憡庤偵惉傝戙傢傝彈姱傪嶦奞偟偨丅彈墹偵娭偟偰傕摨條偱偁偭偨丅嶳梤柡偲墹巕偼憡巚憡垽偱偁偭偨偑丄偲偆偲偆堦偮偵側傞帪偑偒偨丅偦偺偁偲丄嶳梤柡偼帺暘傪嶦偡偙偲傪梫媮偡傞偑嫅傑傟偨堊丄垽傪姰惉偝偣傞堊偵偦偺応偱帺巰偟偰偟傑偆丅側偤側傜偽嶳梤柡偵偲偭偰抝彈偺垽偲偄偆傕偺偼乽偦偆偄偆傕偺偱偁偭偨乿偐傜偩丅
彂偄偰偐傜婥偑偮偄偨偑丄嫗嬌壞旻偺僷僋儕偺傛偆側婥偑偟偰偒傑偟偨丅
懕偒傪彂偄偰傒偨偺偱偡偑丄偳偆偵傕偙偆偵傕僄儘僌儘偱僫儞僙儞僗側榖偵側偭偰偟傑偄傑偟偨偺偱杤丅偲偄偆偙偲偱僒僀僩柤傕敿拑偵栠偟傑偟偨丅
 丂偲傝偁偊偢丄僗僥僼傽僯乕巓枀偺徰憸
丂偲傝偁偊偢丄僗僥僼傽僯乕巓枀偺徰憸
愄乆丄偁傞怺偄怷偺峏偵怺偄栁傒偺拞偵昻偟偄徔偑廧傫偱偄傑偟偨丅偁傞擔巇帠傪廔偊偨徔偑壠楬傪媫偄偱偄傞偲戝偒側栘偺崻杮偵饽傪尒偮偗傑偟偨丅偦偺饽偺拞偵偼壜垽偄愒傫朧偑偡傗偡傗偲柊偭偰偄傑偟偨丅徔偼偙傟偼揤偺宐傒偩丄憗懍崱斢偺梉斞偵偟傛偆丄偲偦偺愒傫朧傪楢傟偰婣傝傑偟偨丅
偦偺愒傫朧偺壜垽偝偵傎偩偝傟偰丄徔偼愒傫朧傪帺暘偺巕嫙偲偟偰堢偰傞偙偲偵偟傑偟偨丅嶳梤偺擕傪堸傫偱偡偔偡偔偲堢偭偨愒傫朧偼丄嶳梤廘偄彈偺巕偵堢偪傑偟偨丅
偁傞擔丄嶳梤柡偑怷傪嶶曕偟偰偄傞偲丄偦偙偵乧乧