|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お正月はアッという間に終わってしまいました
(2010年1月3日 日曜日)
明けましておめでとうございます。新年早々3が日の間、日記の更新を怠けておりました。初めての“滋賀暮らし”で、あちらこちらへの初詣に興味津々だったのと、相変わらずおいしい物には目がない私は食べ歩き三昧で、パソコンのキーを叩くことをすっかり忘れてしまっていました。本当に申し訳ありませんでした。まあ訪問くださる方もいつもの2分の1(20〜30人)くらいでしたから、お互い様ということで、お許し頂けるかも・・・。
さて皆さんの新しき年のスタートはいかがでしたか?忙しいお仕事や活動も暫しの間ホッと一息つかれ、きっと元気で楽しいお正月を過ごされたことでしょう。存分にリフレッシュされたところで、さっ!2010年もどうぞ思う存分にご活躍くださいね。毎日が殆ど“お正月”(?)状態の私からも応援しています。
そこで自分の日記はほって置いても、島本町議会の市民派3議員(平野・澤嶋・戸田議員)と伊集院議員および川口町長、大津市議会では会派「清正会・杣」の4議員(宮尾・小松・谷・山本議員)については毎日朝晩の訪問を欠かしませんでした。皆さん、意欲溢れる新年の抱負を語ってくれていて、とてもうれしく頼もしく思いました。
一方貴重な正月休みを体調の回復に当てている澤嶋議員には、残念ながらブログでお目にかかることはできませんでした。今、最も応援が必要な澤嶋さんに「私ができることは何だろう?」と、ずっと答えを捜しているものの、先の経験からも差し出がましいことは自重しなければなりません(当選後十分な情報発信が叶わない澤嶋議員に、私から緊急避難的な“応援ニュース”の発行を提案しましたが、見事断られた経緯があります)。
しかし、そうこうしている内に1月25日には、澤嶋議員が所管する建設水道常任委員会での請願審査が行われます。審査の準備等調査にも体力を割かねばなりません。また仕事始めの明日4日からは、他の用件も容赦なく入ってきます。委員会までは何とか乗り切って、根本的な治療に備える体力アップを図られるよう願って止みません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
初詣の“はしご”です
(2010年1月4日 月曜日)
今日から新しい年の仕事が始まりました。人も車も一斉に動きだしました。大津市役所も島本町役場も業務開始、今年も(こそは?)より良い住民サービスに全力を尽くしてくださいね。一方仕事を持たない私たち夫婦にとっては、鏡餅を前にお節料理の残り物(ヤッパリ作りすぎました)を食べていると、ダラダラと正月休みが続いているようなものです。まあ、帰省していた次男を昨日送り出したことくらいが、お正月の終了を意識させた出来事です。
「もう時間に追いかけられるような生活にはサヨナラしたい」と望んだ結果、時間のメリハリを細かくつける必要性が薄れ、緊張感を欠く状況が生まれています。これはよろしくありません。そこで今年の課題の一つは「ノンビリ感とピリピリ感が程よくミックスした生活のリズムを、日常的につくり出すことへの努力をする」と決めました。
「そんなの簡単でしょ。趣味のサークルやボランティア活動は、いつでもメンバーを大歓迎じゃないの?」との親切なアドバイスがありそうです。う〜ん、確かにそうかもしれませんが、私が望んでいることとはちょっと違っているような・・・そんな気がしています。そこで、初詣をした何ヶ所かの寺社では「どうぞ、人びととの良き出会いをいただけますように」とお願いをしました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
滋賀の“美味しんぼ”は、まず近江牛から
(2010年1月5日 火曜日)
お正月のお節料理ばかりでは帰省中の次男がかわいそうな気がして、え〜いっ!と近江牛のステーキを奮発しちゃいました。唐橋にある松喜屋本店で至福のお味を堪能しましたが、2時間足らずで普段の食費1か月分がお財布から飛んでいきました。松喜屋は明治初期に牛を連れ、東海道を半月かけて歩き、東京の需要に応えた最初の家畜商人です。ちなみに「松喜屋」の屋号は、元々は牛を納めていた東京の牛なべ屋の名称で、後にその屋号を貰ったようです。
松喜屋が始めた牛と同行の東海道五十三次は、明治18年には神戸から横浜への海上輸送に切り替わりました。そして近江牛を含め近畿周辺から運ばれた牛は、積出港の「神戸」の名を付けた「神戸ビーフ」として高い評価を得るようになります。近年はそれぞれの和牛ブランドが認証制度による厳しいチェックを掛けています。従って、肉屋さんが勝手に「近江牛」と称して販売できないことになっています。
近江牛の定義は「黒毛和牛で、最も長く飼育されたのが滋賀県内であること」とされ、近江牛を置く指定店も決まっています。指定店は滋賀と京都を合わせ107店舗しかありません。さらに今後は、公募の市民モニターが表示の是非を確認するシステムも検討されているようです。
勿論肉の味を向上させる研究も重ねられています。滋賀県畜産技術振興センターでは「えさを外国産のトウモロコシから国産・県産の米や糠を使用する“昔型”に変えること」を指導しています。“昔型”のえさには、風味を増す「モノ不飽和脂肪酸」が多く含まれていることが分かっています。一頭約3百万円の近江牛ブランドを守るのは、随分大変なんだと知りました。
前段の内容は、朝日新聞滋賀版の記事から引用した所もあります。当記事の冒頭にはアンケートを行ったことが紹介されています。滋賀県以外の千人に尋ねた「滋賀県と言えば何?」の答えは、当然ながら1位は�「琵琶湖�」でした。そして堂々の2位に入ったのが「近江牛」だったのです。ミディアム・レアの近江牛は、深くとろけるようなお味で大満足しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
島本町の体育館自販機に、やっと電気メーターが付きます
(2010年1月6日 水曜日)
これまでの日記で何度か、役場本庁舎とその他の公的施設に設置された自動販売機のことについて書きました。本庁売店・ふれあいセンターについては、公的スペースの使用手続きも自販機に係る電気代徴収も正常に行われていました。しかし消防庁舎については、使用許可・電気代共に正しくない事務が行われていました。ただし、このことが発覚後の消防は、割合早い(約20日間での)改善を図りました。まっ、これが当り前なのです。
ところが体育館に設置された自販機については、設置の申請・許可手続はされていたものの、自販機を稼動させる電気代の徴収は行われていませんでした。教育委員会は当然収入されるべき電気使用料を見逃していたのですから、これは金額の大小に係らず“不正”な行為です。少なくとも昨年の9月28日に、私が情報公開請求を行った時点から、もう有耶無耶にしておけることではないと分かっていたはずです。
にも拘らず約3ヶ月もの間、教育委員会生涯学習課はノラリクラリと“不正”を続けてきました。自販機のみの電気料金を明らかにするためには別メーターの取り付けが必要ですが、自販機を設置している母子寡婦福祉会に説明し納得してもらうことが、何故そんなに困難だったのでしょう?全く理解に苦しみます。メーター設置を渋るような団体なら、教育委員会は公共スペースの使用許可を取り消せばよいだけの話です。
教育委員会は何でこんな簡単な事が是正できないのか?と、私は3ヶ月間ずっと思っていました。例え担当課長が判断できなくとも、上司の事務局次長・教育次長・教育長は、当事案が正常でないことくらいは分かっていたはずです。離れた町とはいえ、この間の教育委員会の姿勢が正しくないと認識せざるを得ないのは、悲しくて残念でした。
12月議会最終日(17日)の傍聴時に生涯学習課を訪れて、事態が変わっていないことを確認し「もうええやん、知ったこっちゃない」と呆れ果てました。しかし私もしつこい性格、というより「こんなん許せんわ」との気持がヤッパリ消えませんでした。年が明けて「もうこれがホンマに最後の確認」と、本日電話をしてみました。すると、なんとなんと「今月中ごろには別メーターを設置することになっています」と、シャラ〜ッとした答えが返ってきました。
「よかった、よかった」なんて言いたくありません。「ったく!今まで何しとったん!」と言いたいのを、私はこらえていました。担当職員の次の言葉を待ちましたが、当然ながらありませんでした。私ならこう続けます。「ご指摘いただきながら、是正まで時間を要しました。申し訳ありませんでした。少なくとも私どもがモタモタしていた間(3ヶ月間)の電気料金は、住民の皆さんの税金を当てるわけにはいきません。現在どのような補填の方法があるのか検討しております」・・・私にこれくらいのことは返しても当然ではないでしょうかねぇ〜。
写真は「滋賀の“美味しんぼ”スイーツ編」です。1月2日は「クラブ・ハリエ」のバームクーヘンを求めに、近江八幡市の「日牟禮ビレッジ」を訪れました。ビレッジには「ハリエ」(洋菓子)と「たねや」(和菓子)が向かい合って趣のあるお店を構えています。バームクーヘンは“大人買い”で数箱を、「たねや」ではお正月の干菓子を求めました。ヴォーリズの住居であった洋館が、「ハリエ」のカフェとして開放されています。美味しいケーキでティータイムを楽しみました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お正月は食べてばかりじゃなかったですよ
(2010年1月7日 木曜日)
お正月最終の3日は、守山市にある佐川美術館に行きました。本日勤務先の千葉へ帰る次男の運転で夫と3人、対岸の湖東へ湖岸道路をドライブしました。湖西とは趣が違う琵琶湖の風景を見ることができ楽しかったです。大津に越してきて4ヶ月余りになりますが、こうして外出する度に、まだまだ琵琶湖周辺のホンの一地域しか訪れていないことを実感します。これからの“お楽しみ”がドッサリ残っていると思うことにして、せいぜい足腰を鍛えておくことにしましょう。
佐川美術館には、以前から行ってみたいと思っていました。美術館は広大な水面に浮かんでいるような平屋の建物です。一切の色彩を排した建材(石・ガラス・アルミ・ステンレス等)が用いられていますが、冷ややかな印象は受けませんでした。それは館を巡る水面が雲の流れや木々の梢を映し、また風が起こす波紋のさまを見せてくれるからだと思います。シンプルな建物に多様な表情を与える水の力は、大したものだと改めて気付きました(ただし設計者からみれば、私の印象は全く的外れなものかもしれませんが)。
展示室は「平和の祈り・平山郁夫館」、「ブロンズの詩・佐藤忠良」、「守破離の彼方(しゅはりのかなた)・楽吉左衛門館」の3室からなっています。巨匠たちの作品を前に、絵画や彫刻や陶芸のイロハも解らない私が発する言葉は何もありません。ひとことだけ言えば、まるで小学生の感想ですが「平山郁夫館」や「佐藤忠良館」では、温かく平安に満ちた気持になれたような気持がします。ブロンズ像の一部は触れることができ、とてもよいことだと思いました。
一方「楽吉左衛門館」の作品からは、暗い闇の中で激しく闘っているような孤独さと強さを受けました(実際展示の照明は極端に暗く、まるで穴倉にいるような感じです)。楽焼の15代当主である吉左衛門氏は館の設計・展示のみならず、併設の茶室の設計・プロデュースも全て手掛けています。吉左衛門館は2年余前に完成したのですが(美術館は12年前に開館しています)、数々の賞を得る高い評価を受けています。
また館では、毎月2日間だけお茶席が開かれます。楽氏の自作の茶碗が使われることもあって、大変な人気です。当然、美術館の入館者も当初より飛躍的に伸びたらしいです。次男は日本の歴史に割合興味を持っていて、私も夫も知らないことを一杯知っています。茶道の心得があるわけではないのですが(厳密に言うと、少しの間習っていましたが挫折したみたい)、歴史の中で茶わんが果してきた役割等も何故かスラスラと説明してくれます。
以前、東京の三井記念美術館で国宝の志野茶わん「卯花墻」を見た次男は、もう一つの国宝(和物茶わんで国宝は2つだけ)白楽茶わん「不二山」を見るためだけに、諏訪市のサンリツ服部美術館まで車を飛ばしたそうです。一昨年夏に帰省した時は、次男の案内で京都の楽美術館にも行きました。次男はその折には甚く感動していましたが、今回は余りうれしそうではありませんでした。次男曰く「ちょっと奇をてらい過ぎやなぁ」、オットット・・・15代目になんてことを!でも実は、私も内心チョッピリそう思っていたのです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
「広報おおつ」1月15日号の休刊理由が分かりません
(2010年1月8日 金曜日)
ここ大津市も島本町と同様に、月2回の広報紙が発行されています。ただし広報紙の形態は島本の新聞型(タブロイド版)と違い、A4版冊子型です。表紙には毎号、素敵な写真が(勿論カラーで)掲載されています。実際表紙を見るだけで、「読んでみようかな」という気になります。年末に届いた1月1日号も、勿論隅から隅まで目を通しました。
島本町の広報紙はもう手に入れる機会はありませんから、町のホームページで見ています。新年号の第1面は、例年通り町長と議長の挨拶が掲載されていました。どちらも殆ど実のないありきたりの文章で、住民が受ける印象は極めて薄い内容です。挨拶なんて「そんなもんだ」と言ってしまえばそれまでなのですが・・・。
せめて川口町長なら「まちづくり基本条例」の近々実現を目指すとか、菅議長なら「議会基本条例」策定に向けて努力するとか、何か一つでも具体の中身を示すべきでしょう。大津市広報の1日号は市長への新春インタビュー形式で、今年度主要事業の検証と来年度の抱負を掲載していました。まあ、これとて市長の「アレもしました、コレもしました」のPRですが、市民には身近な事業が出てくるので、島本町よりは分かりやすい内容だと思いました。
ところで、大津市の1日号広報に「1月15日号は休刊します」と書いてあったことが、ずっと気になっていました。何故発行しないのか理由を知りたいと思い、市役所に電話してみました。秘書広報課広報係の女性職員が応対してくれました(ちなみに大津市役所では、名前を名乗らない職員が多いです)。「何でこんなこと訊いてくるんやろ?」との彼女の疑問が、そのまま受話器を通して伝わってきました。
私は「実は引越してきたばかりなので大津のことは良くわからないのですが、広報紙は楽しみに又頼りにして読んでいます。前に住んでいた町では1日号も15日号も発行していましたので、休刊の理由を知りたいと思って電話しました」と尋ねました。職員は「さあ〜?1月と8月の15日号は例年発行していませんので・・・。特に新年は印刷(紙面のレイアウトも含めて)を委託している会社の休みも有りますし・・・。ほかの市でも、そんなところもありますし・・・」と答えました。
ア〜ァ、これでは説明になっていません。印刷会社のせいではなくて、市役所が休刊を決めたのでしょ。だったら市の側に理由が存在するのです。例えば職員態勢の問題だとか、経費の削減を図るためとか、素人が考えてもいろいろあるじゃないですか?それと「ほかの市」ってどこですか?たとえ滋賀県内の殆どの自治体が1月15日号は発行しないとしても、県内唯一の中核市である大津市が右へ倣えと言うのも理屈に合わないですね。
とまあ、あんなこんなの反論もしたかったですが、どうやらムダなようなので止めました。彼女は途中で何度も電話を中断して、同僚或いは上司と相談しているようでした。しかし、それでも前述のような答えしか返せないのですから仕方ありません。電話を切ってから、職員の言う「ほかの市」を調べてみました。
滋賀県内には13の市と7つの町があります。大津市と同様の1月15日・8月15日号を休刊にしている自治体は3市(草津・近江八幡・彦根市)です。守山・甲賀・高島・長浜・米原市の5市は1月も8月も2回の発行を行っています。あとの4市(東近江・栗東・湖南・野洲市は月1回の発行です。ちなみに町では、殆どが月1回となっています。
以上の状況はネットで各市町のホームページを一つひとつ検索してみて判りました。大津市と同様の「ほかの市」は、確かに存在しますが少数です。広報課の職員としてこのような事実を踏まえていたなら、私に対して無造作に「ほかの市でもありますし」というような根拠は示さない方が良かったでしたね。
いずれにしても市民からの問合せに苦労しているような職員には、同僚や上司がしっかりサポートしてほしいものです。しかし殆どの上司の本音は「適当にあしらっとき」と指示しているのではないかと、疑わざるを得ない今回の大津市の対応でした。間違いではないかもしれないけれど、的を得ず誠意のない回答は、市民に対して随分失礼なことだと感じました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
砂浜の掘り起しが始まりました
(2010年1月9日 土曜日)
我マンションの目前に広がる湖岸で、いよいよ本格的に砂浜の再生工事が始まりました。過日の日記でも書いた「柳が崎湖畔公園整備工事」のうち、今年度事業として行なわれる“はだしで歩ける砂浜”復活への第一歩です。先ずは浜を覆い尽くしている草を刈り取り、台風で倒木寸前のまま放置されていた柳の大木も先日切り倒されました(残念ながら、回復は困難だったとか)。
柳の枝には、春になれば芽吹いたであろう小さな芽が一杯ついていました。このまま枯れてしまうのは間違いないのですが、なんだか可愛そうで私は一枝貰って帰りました。紅白の和紙を小さく切って“もち花もどき”に仕立て、お正月の鉢植えにあしらいました。柳は公園整備に係る検討委員会でも、「柳が崎公園」のシンボルツリーとして「残しましょう」と合意がされていただけに残念です。
正月休みが明け工事が始まってからは、毎日様子を見に行っています。最初は「なんや?このおばちゃん」というような顔をしていた工事請負業者の人たちも、「寒い中の工事で大変ですね。きれいな砂浜にしてもらえるようで、完成がとても楽しみ」などと話しているうちに、彼らも私の質問に気軽に答えてくれるようになりました。
今工事は、巨大なパワーショベルで硬くなった砂地を15センチほど掘り起こしています。掘り返した砂の山が、いくつも湖岸にできています。次の工程はこの砂山の砂をふるいにかけて、きめ細かな砂に再生するストーンピッカーの使用となります。浜は2ヘクタール以上の広さがありますし、湖に注ぐ柳川の親水整備工事も遊歩道の工事も控えていますから、3月末までの工期に間に合うのかしらと少し心配です。
工事の進捗状況を見届けてから、その足で日課のウオーキングに出かけます。近江神宮への往復が散歩の定番コースです。最近は県道である神宮道の“おもて道”を通らずに、土手に沿って柳川を遡って行く“うら道”を歩きます。土の感触が心地よく、せせらぎの水音や土手で震える小さな草々にも癒されます。ウオーキングの帰りも再び湖岸に出て、暮れいく琵琶湖を眺めて終了です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大津の歴史を少しは知っておかなくちゃ
(2010年1月10日 日曜日)
良い方に考えてあと20年くらいを生きるとすれば、大津市のことをもう少し知っておかなくてはならないと、引越し後ずっと思っていました。そこで先ずは「大津市史」を求めなくてはと、歴史博物館に行ってみました。市史の存在は確認したのですが、なんと全部で10巻!(島本町史は2巻)もありました。ちなみに1巻2,500円です。
金額が嵩むという問題もありますが、市史を求めなかったのは発行後30年以上を経て色あせ古びた装丁を目にしたからです。さらには過去30年間の大津市の姿が記載されていないなら、急激に変化を遂げた大切な時代がスッポリと抜け落ちてしまうことになります。それでは、大津の歴史の中身が薄いものになるのではないかと考えたからです。
迷っていると、博物館の学芸員さんが進めてくれたのが「図説 大津の歴史」(上・下巻で5千円)でした。パラパラ見てみて、とても読み易いと感じました。「図説」と銘打つだけあって、絵図や写真が多く使用されています。例えば文化財や市域の航空写真などは、何百字を費やしても1枚の写真に勝る説明はない、といった場合は多いです。また記載の固有の名詞には、すべて振り仮名が打ってあるのも助かります。
「専門的に使われるのでなければ、こちらをお勧めします」と言う学芸員さんに従い、購入しました。「図説 大津の歴史」は、市政100周年(1998年=平成10年)を記念して取り組まれた事業で、翌年に発行されました。帰宅して早速本を開いてみましたが、とても面白くて次々とページを繰っていました。
例えば1ページ目には「原始・古代」の章として、琵琶湖の形成について記されています。現在の琵琶湖の原形は今から200万年前に誕生しましたが、実はそれ以前に「古琵琶湖」が存在していたと書いてあります。最古の琵琶湖はなんと!600万年前に、今よりずっと南の三重県上野盆地にできた小さな湖でした。その後鈴鹿山脈等の隆起による影響を受けながら、現在の琵琶湖の原形が現れたのが120万年前とされています。
次のページには「シガ象の発見」と題した小見出しがあります。70万年〜50万年前に、伊香立・真野・志賀で象が生息していたことが、発見された化石で分かりました。以前に甲西町(合併前)の博物館で、象の足跡の化石を見たような記憶があります。琵琶湖の周辺に、象がいたなんて凄いです。その後氷河期が到来し、象は絶滅してしまったのでしょう。以降数十万年後に(今から3万5千年くらい前)旧石器時代が到来しますが、真野・田上山・瀬田川・南志賀等で石器が発見されています。旧石器時代の後に、やっと縄文時代が到来します。
たった数ページを繰っただけですが、興味は尽きません。「古琵琶湖」も「象」も私が知らなかっただけかもしれませんが、これからも「大津の歴史」を折に触れて手に取る楽しみが増しました。2巻読み終えたら、ちょっとは“大津通“になっているでしょうか?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
延暦寺・日吉社の門前町として栄えた坂本
(2010年1月11日 月曜日)
週末パラサイトの長男がこの連休、久しぶりに名張から帰ってきています。年末年始を恒例の海外で過ごしていたので、そのお土産を持ってきてくれました。「今日のお昼は何を食べようか」と言うことになって、「じゃ坂本の鶴喜そばを」と早速のリピーターに(晦日そばがとても美味しかったのです)。前回はざるそばでしたが、今回は旬の鴨肉がたっぷり入った鴨なんばにしました。1,380円は少々高いかしらと思いましたが、期待を裏切らない美味しさでした。
体も暖たまったので、坂本の街をぶらぶらと散策をしました。散策と言ってもお蕎麦屋さんから少し足を延ばした程度ですが、それでも延暦寺・日吉社の門前町であった坂本の当時を少し偲ぶことができました。先ず訪れたのは「公人屋敷」(旧岡本邸)です。公人(くにん)とは、延暦寺の僧侶でありながら妻帯と名字帯刀を認められた人々のことで、延暦寺の僧坊等に所属し治安維持や年貢・諸役を収納する仕事をしていました。
公人屋敷では「漆喰鏝絵展」(しっくいこてえてん)が開催されていました。鏝絵は昨年の春に、次男と山形を旅行した時に興味を持ちました。ちなみに鏝絵とは、左官が壁を塗るコテで絵を描いたところから由来しています。作者は70歳半ばの男性ですが、「坂本城」や「近江八景」など郷土の題材が多く選ばれていました。屋敷では鏝絵展のほかに「新年の祝い膳展」も開かれ、立派な漆塗りの膳が座敷に再現されていました。
公人屋敷のあとは、数ある「里坊」の中でも最高位・最大級の「滋賀院門跡」を訪れました。「里坊」とは、延暦寺の僧侶が高齢になって山を下り、里で暮らすための住まいのことです。坂本には多い時で90ヶ所、今でも54ヶ所の里坊が残っています。「滋賀院門跡」は代々の天台座主の御座所であり、地元では「滋賀院御殿」とも呼ばれています。1655年に天海大僧正が、後陽成天皇から御所の高閣を賜って建立しました(明治時代に焼失し、再現されました)。
院内は大変立派で見ごたえがありました。ありがたい説法も頂けて、450円の拝観料は“お値打ち”です。また池泉築山式の庭園は、三代将軍家光の命による小堀遠州の作庭とされています。さらには、院を囲む白土塀は「穴太衆積」(あのうしゅうづみ)の石垣上に築かれています。穴太の石垣はこのあたり一帯で多く見られ、その景観には歴史の流れを溯る感があります。
「穴太衆」とは、延暦寺のお堂に係る基礎石組みの担当をした石工集団のことです。彼らが穴太村の出身であることから、「穴太衆」と名づけられました。彼等の工法は、自然石の組み合わせのみで石を積み上げ、小石を詰め石として用いているのが特徴です。城造りが盛んになると、彼らは九州・関東・北陸等の各地で仕事をするようになりました。現在の坂本では、一軒のみが「穴太衆積」の技術を継承しているらしいです(素晴しい!)。
今日は「坂本」の奥の深さにほんの一部ですが、触れることができてうれしかったです。「鶴喜そば」は美味しかったし、もう言うことなし!です。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sさん、資料を送ってくださってありがとう
(2010年1月12日 火曜日)
12月に、島本町の情報で入手したい資料がありました。しかし、町外に転出した私は情報の請求ができません。そこでSさんの名前で手続をしてもらいました。当然、情報公開の決定通知書はSさんに届きます。Sさんは閲覧し、コピーをとった文書を私に送ってくれました。本日宅配便が届き、早速目を通しました。Sさんの多忙な仕事も気軽に動けない状況をも分かりながら依頼をしているのですから、本当に申し訳なく有難く思っています。
私も人付き合いは良い方ではありませんが、島本町で行っていた仕事からすれば(ちなみに議員でした)、Sさん以外にも頼めない人がいないわけではありません。でもなんと言うか、阿吽の呼吸で私が知りたいことの本質をわかってもらえるのは、Sさんかなぁ〜と思うのです。まあ、これからはどんどん島本町のことは遠くなっていきますから、Sさんの手を煩わせることもなくなってくるはずです。
さて送ってもらった文書ですが、1つは12月議会における一般質問の通告書と答弁書です。通告書は議員が質問内容を議長に提出したものです。答弁書は理事者が通告書に従って回答したものです。一問一答方式で行われる一般質問ですから、いずれの内容も冒頭に行われる発言を文書化したものです。従って簡略な記述もあれば、細目を設けた詳細な内容もあり様々です。
通告内容が簡単なのは、清水・高山・岡田・川嶋議員でしょうか。詳しく一問目を書いているのは、伊集院・冨永・河野・外村・藤原・澤嶋・東田・平野・戸田議員です。いずれが良いとか言うものではありませんが、短い質問に長く盛りだくさんの答弁が出てくる不思議さは感じないでもありません。いずれにしても一問一答方式は質疑答弁の分かりやすさと共に、理事者に対してどれだけ切り込めるかといった、いわば議員の力量をも露呈してしまう側面を持っています。
もうボチボチ、一般質問の全部を記録した会議録の反訳原稿が上がってくる頃だと思いますが、とりあえずは入手の答弁書より結論部分のみ(尚且つ私が勝手に選択した答弁を)お知らせしようと思います。まあ、本来なら1回目の質疑答弁が終わってから丁々発止のやり取りが行われた後、稀には議員の力量が勝って最初の答弁を覆させることが無きにしも非ずですが、今議会では多分なかったように思います(全て傍聴していませんが)。
ということで各議員の質問に対する理事者の答弁を、答弁書に記載された範囲で書くつもりでしたが、本日の日記が長くなりそうなので次の機会にまわします。また請求した2つ目の情報「12月6日の町内一斉清掃に係る住民の参加・職員の出勤状況がわかるもの」も同様に日を改めてお伝えしたいと思います。本日は困難な状況下で情報を入手してくれたSさんへの感謝を表すのみに止めて、日記を終わりたいと思います。写真はお正月に訪れた近江八幡市の風景です。
|
|
|
|
|
宮尾大津市議のブログ「償ったあとは、教訓を活かすことが重要です」への感想
(2010年1月13日 水曜日)
13日付朝日新聞朝刊の滋賀版に、「大津市立中学校教諭逮捕」の記事が載りました(各紙でも同様の記事が掲載されたはずです)。朝日新聞では、1段見出しの小さな記事の扱いでした。逮捕の理由は滋賀県青少年健全育成条例違反です。29歳の男性教諭が、15歳の女子高生(元教え子)に複数回の猥褻行為を行った事件です。
女子高生への思いを馳せると共に、あとを絶たないこの種の事件に苦々しさと怒りを覚えずにはいられません。新聞掲載後、直ぐに宮尾孝三郎大津市議のブログに事件のことが触れられていました。「さすが宮尾議員!いつもながら迅速な情報提供」と感謝したいところでしたが、ブログの内容が私には今ひとつよく理解できなかったのです。
宮尾議員は新聞記事を転載したうえで自身の意見を書いているのですが、「適正に導いていくことを期待します」とか「人は過ちを繰り返し生きています」、また「責めることは容易ですが、教訓を生かすことが重要です」などと語っています。これらの文言は全て、加害の教諭にも被害の女子高生にも共に当てはまることだとは思います。事件が起こって騒ぎ立てて、それで終りでは決してありません。宮尾議員の主張する通りだと思います。
でも・・・多分私の読み取りが不十分なのでしょうが、宮尾議員の文章には女生徒に対するいたわりや共感が希薄なように思えてなりません。当然報道されない事情が双方共に存在する可能性もあります。しかしながら今回の事件では、子ども(未成年)であり女性である一人の人間の人権が損なわれたことを、先ず第一番に認識することが何よりも大切ではないでしょうか。このことなしには、深い反省も今後の導きも生きたものにはならないと思います。
宮尾議員のブログは毎日更新され、充実した内容でいつも楽しみに読んでいます。今事件について報告されているのも、今のところは多分宮尾議員だけだったと思います。口はばったいことを言ってしまいましたが、私にも譲れない思いがあるのです。お気を悪くされずに、一市民の感想と受け止めていただければ幸いです。
本日の日記は昨日に引き続き、島本町議会12月議会における各議員の一般質問について書くはずでした。しかし飛び入りで“事件発生”についての感想を優先させてしまいました。まあ、いずれにしても私の日記で書いていることなんて、大したことではありませんが・・・。
|
|
|
|
|
逮捕教諭が在籍の校長先生は、とても丁寧な応対でした
(2010年1月14日 木曜日)
昨日の日記で、女子高生への猥褻容疑で大津市の中学校教諭が逮捕された事件について書きました。新聞記事には当然ながら、教育長の謝罪の弁が載っていました。そこで私は、大津市と大津市教育委員会、およびI(頭文字です)中学校のホームページを見てみました。いずれの機関も、事件に係る報告や謝罪の言葉は一切掲載されていませんでした。
島本町でも先日、女子高生への痴漢行為で消防職員が逮捕される事件が報道されています。市民派議員たちの要求もあって、町長は事件の概要と被害者および町民への謝罪、再発防止への誓い等を町ホームページに掲載しています。従って大津市においても今回は当然、ホームページを媒体として「お詫び」を行っているはずだと思ったのです。しかしながら、どこを捜しても事件のことには全く触れられていません。
「新聞で報道されたから、それでいいだろう」というものではないと思います。そこで私は、教育委員会に電話をしてみました。閉庁時間を過ぎていましたが、F課長補佐が丁寧に応対してくれました。しかしF氏は、肝心の市民への説明責任と謝罪は新聞報道で済んでいるとの主張を崩しませんでした。
私は島本町と同様に「せめてホームページへの掲載を」と求めましたが、「インターネットをしない人たちもおられますので」とF氏は答えました。私は「いえいえ例えそうだとしても、ホームページに掲載しないよりした方が、少なくとも今より多くの人に伝えられますよ。検討をお願いいたします」とだけ伝えて電話を切りました。F氏は「ご意見は感謝します」と返してくれましたが、まあ検討はしないだろうなと思いました。
次に、当該教諭が勤務しているI中学校に問い合せました。ちなみに中学校のホームページにも、事件のことは何も載っていません。「事件のことで」と伝えると、直ぐにN校長に電話が繋がりました。校長先生は先ず謝罪の言葉を述べてから、この2日間で学校が行った対応を詳しく述べてくれました。
校長は事件を知らされて直ぐにPTA本部に報告、続いて学校協力者会議を開き説明と謝罪、今後の対応策を協議しました。全生徒・保護者への説明を行い、常駐のスクール・カウンセラー配置も予定しています。まあ、ここまでは常套ながら出来うる限りのことを、学校長としては行っているように思いました。
校長先生は最後に「お問い合せくださってありがとうございます。今回の事件は本当に申し訳ないことだと思っています。またいつでもどのようなことでも、ご意見をいただきたいとお願いいたします」と言いました。何の肩書もなく保護者でもない、さらには学区の地域住民でもない私に対して、校長先生は大変真摯な姿勢で対応してくれました。この学校長の下なら、心配ないかも・・・と私は少し安堵しました。
|
|
|
|
|
平野議員が議会リポートを送ってくれました
(2010年1月15日 金曜日)
このところ平野議員のブログ更新が少々停滞し心配していましたが、12月議会の「議会リポートNo.34」に係る作成に多忙だったのだと分かりました。年が明けて次々入ってくる公務に加えて、ニュース発行の作業が重なると大変です。さぞ忙しい毎日だったでしょう。
議員の活動報告については発行・配布に至る苦労が分かるだけに、送ってもらったリポートは有難く隅から隅まで読みました。いつものことながら平野さんの地道で誠実な議員活動が良く分かる紙面で、頼もしくうれしく思いました。
さて話は変わりますが、本日(1月15日朝刊)の朝日新聞「ひととき」欄に掲載された文章に引き付けられました。大津市在住の60歳、主婦の方の投稿です。「いつか流鏑馬のように」と題したその内容から、投稿主が弓道を始めたきっかけが近江神宮で見た流鏑馬であったことが分かります。
11年間の弓道修行の中で会得してきた技量も精神の高みに触れる喜びも、まだまだ道半ばと書かれていますが、「今年こそ心、身、弓の三位一体となって勢いよく的を射抜きたい」との抱負で締め括られています。清々しくて、とても良い文章です。
日記にも書きましたが、私も昨年11月に近江神宮の流鏑馬を初めて見て感動しました。でも、とてもとても彼女のように弓を引きたいという気持ちにまでは至りませんでした。年齢は私と5歳しか違わないのに彼女の感受性の豊かさ、いえそれ以上に道場通いの行動力に脱帽です。
現在は「錬士」という称号を取るために5年間も審査を受けているものの、なかなか突破することができず、基本を一つ一つ地道に積み上げて続けていると書かれています。同じ60代でも同じ流鏑馬を見ても、こんなに素敵な女性がいるのだと思うとうれしくもあり羨ましくもありで、・・・チョッピリ自己嫌悪に陥ります。
15日の日記はこれで終わりますが、14日の日記もアップしていますので読んでみてくださいね。写真は本文の内容とは直接関係ありませんが、「近江神宮」をキーワードにすれば少し係わりがあるように思い選びました。
|
|
|
長田の「鉄人28号」像は、大きくてビックリ!
(2010年1月16日 土曜日)
明日1月17日は、阪神淡路大震災が起こってから15年目にあたります。震災後初めて神戸の街に入ったのは、確か2週間後くらいでした。その後1年くらいは数回訪れていましたが、年を経るごとに出かけることはなくなっていきました。「1・17のつどい」には参加をしたいとずっと思っていましたが、地震発生の5時46分までに現地に到着することが困難で諦めていました。
昨年は前日に神戸に入り、宿泊をすることで初めての参加ができました。5時46分の黙祷時には、犠牲になられた方々への鎮魂の想いと「忘れてはならない」との決意で心が震えました。今年は15年目の節目の年であり、私は仕事を退いた自由の身でもありますから、是非参加をしたいと思っていました。しかし週末パラサイトの長男が帰ってくるので、ちょっと迷っていたのです。
「そうや、一緒に行けばええやんか」と、長男に「一度は集いに参加をした方がええよ、いや参加すべきや」と半ば強引に誘ったところ、意外にも「そうやな」と言いました。ネットでビジネスホテルの「東横イン」を予約して、午後から長男の車で出かけました。三宮まで1時間半くらいかかりました。ホテルにチェックインした後、暗くなる前に新長田へ出かけることにしました。
去年の夏に建てられた「鉄人28号」の像を見るためです。長田は最も酷い被害を受けた地域です。駅周辺は区画整理で新しく美しく再建されましたが、新店舗の賑いもいまひとつで街の活気に繋がる再生には至っていませんでした。そこで地元の商店主たちがプロジェクトを作り、話し合いの中から生まれたのが原寸大の「鉄人28号」像を建てる計画でした。
なぜ「鉄人28号」なのか?それは作者の漫画家「横山光輝さん」が、ここ長田の出身者であったことと、「鉄人」のパワーを再生の力にしたいと願う地域の人びとの思いが繋がったからだと言われています。像の高さは18メートルもあり、凄くでかい!迫力満点です。総工費1億3,500万円(うち神戸市の補助が4,500万円)の大部分は寄付金らしいですが、全額賄えているのかは分かりません。
1億円を超えるお金を費やしたけれど、機能的には何の役にも立たない巨大モニュメントです。どう評価するかは難しいところでしょう。批判も多くあると言われています。でも像を目にしたとたんに、なんか力湧いてきますよねぇ〜。「わぁ〜おっきい」と見上げる人びとの顔は、皆笑っています。
「震災を忘れない、震災前に生きていた人々を忘れない、震災前の暮らしや神戸の街を忘れない・・・そして未来に向かって進んでいこう」と、長田の人びとは決心したのです。震災を乗り越える中で生まれた「鉄人28号」です。震災モニュメントとして、後世に残していく価値は十分にあるのではないかしらと思います。そのためにも多くの人たちが長田を訪れ、地域の活性化に力を貸すことが求められています。
夕食事には異人館通り(坂)をぶらっとしましたが、明日の朝に備えて早めにベッドに入りました。モーニングコールは4時にセットです。
 |
 |
 |
「1・17のつどい」で祈る
(2010年1月17日 日曜日)
朝5時、私と長男は「1・17のつどい」が開かれる東遊園地(公園)に向って、フラワーロードを歩みました。街角のあちこちから人影が現れ、たくさんの人びとが帯状になり共に通りを進んでいきます。神戸の街に、15回目の祈りの一日が始まろうとしています。
 |
|
阪神淡路大震災で亡くなった6,434人の方々をはじめ、被災した人びとと被災した街の全てに思いを馳せ祈ること、そしてこれからも決して忘れないこと、それが私の出来るせめてもの“1・17の誓い”です。会場では「1995 1・17」の形に並べられた6,434基の竹灯篭に灯が入り、広場は祈る人たちで埋め尽くされました。

「1・17」の「・」(点)にあたるところには、各地から寄せられた竹灯篭の灯が丸く輝いていました。竹筒には提供者の団体名が書かれています。私は「島本竹工房」の竹筒を探しました。2007年より毎年100基の竹筒を寄贈されていると聞いているので、今年もきっとあるはずと必死に探しました。ありました!2本もありました。ありがとう!私がお礼を言うのも変ですが、元島本町民としては、やはりうれしく誇らしく感激しました。
|
|
|
暫くして会場にアナウンスが流れました。5時46分の地震発生時刻が近づいています。
1995年1月17日午前5時46分
阪神淡路大震災
震災が奪ったもの
命 仕事 団欒 街並み 思い出
・・・たった1秒先が予知できない人間の限界・・・
震災が残してくれたもの
やさしさ 思いやり 絆 仲間
この灯は
奪われた
すべての命と
生き残った
わたしたちの思い
むすびつなぐ
「1・17 希望の灯」の碑文に刻まれた言葉が読み上げられ、みんなの胸に染み入りました。そして5時46分を知らせるチャイムと共に、深い祈りをささげる黙祷が続きました。隣に立つ人もそのまた隣の人にも涙が頬を伝っていました。何千人もの人たちが集っているにも拘らず、広場には静寂の時が流れました。
続いて追悼式典が行われます。神戸市長の挨拶とご遺族の言葉のあと、ゴスペル歌手の森祐理さんが「しあわせ運べるように」を歌いました。森さんは当時大学生の弟さんを失っています。美しく優しい歌声が未だ明けやらぬ空に吸い込まれていきました。作詞作曲は小学校の音楽の先生、臼井真さんです。2千人の被災者が暮らす学校の避難所で地震直後に生まれた歌は、子どもたちに歌い継がれて国内はもとより国外にも広がっています。

式典後、遺族の方々はメモリアルホールの水面に菊の花を浮かべる献花を行い、ホール地下の碑(亡くなった人びとの名前が刻まれています)にお参りをします。とても混雑しているので、私たちは遠慮しました(昨年は混雑が落ち着いた昼間に、もう一度訪れ献花等を行いました)。
今年の集いは厳しい寒さが丁度緩んだ日に行われましたが、さすがに明け方は冷え込みます。ボランティア団体が用意された暖かい飲み物等が、体を温めてくれて本当に有難かったです。「紀州梅の郷・救助隊」の茶粥(大きな梅干付き)と「スターバックス」のコーヒーは昨年に頂いた同じメニューですが、今年はさらに「ヒューマン・ファースト」のカレーとチャイも頂いてしまいました。ささやかですが、それぞれにカンパをしました。
ちょっとタプンタプンになった温かいおなかを抱えてホテルに戻りました。会場の外では、鳥取県江府町から運ばれた雪を使って作られた(神戸の中学生が作ったそうです)雪地蔵が、参加者たちを見送ってくれました。「つどい」に係られた全ての皆さん、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

つい数日前にもハイチで大地震が発生しました。桁違いの死者数と壊滅的な被害の様子が報道されていますが、本当に胸が痛みます。本日の「1・17のつどい」でもハイチ支援の訴えが行われていました。阪神淡路大震災の復興の知恵と力が、ハイチの人びとに役立つことを信じて神戸をあとにしました。
町の体育館に設置された自販機電気料支払が、やっと正常な形になりました
(2010年1月18日 月曜日)
島本町教育委員会生涯学習課の体育館を担当する職員に電話をしました。体育館に設置されている飲料水等の自動販売機に、やっと電気メータが設置されたことを確認できました。これでやっと1月15日分の電気代からは、自販機の設置団体である「島本町母子寡婦福祉会」から町に収めてもらうことになりました(ただし町は1年間分をまとめて徴収します)。
担当職員は私がこれまで何度も催促してきたため、是正が遅れたことを一応謝りました。間違いを正すのに、何故こんなに月日を費やしたのか?ホンマに呆れた仕事振りです。教育委員会は「細かいこと言うな」とか「団体への配慮も必要やし」とか、内心ではいろいろ言い訳しつつ渋々私の指摘に従ったのでしょう。いなくなってせいせいした筈の「南部」に、しつこく追求されることの不愉快さは多分大きかったと思います。
自販機に係る便宜供応は、島本町だけではないかもしれません。自販機は余りにも身近すぎて、住民もよく利用する割には関心を示さない存在です。それ幸いに、マズイと分かりつつ正さない“お役所”はあるかもしれないと思いました。そうそう、大津市役所にもかなりの自販機が設置されているけれど・・・心配になり電話してみました。管財課と人事課が丁寧に答えてくれました。
結論から言うと市役所庁舎に係っては(多数ある施設等へは確認していません)、正しい事務執行がされています。自販機を設置するスペースについては「財産の目的外使用許可」がおろされ、使用料も電気料金も設置者から収納されています。ややれ安心しました。この点は、島本町より大津市のほうが正しいといえます。
ただし5階フロアーの職員食堂・売店に設置されている自販機は、電気代のみが市に納められていますが、設置スペースの使用料は全額減免されています。市は職員互助会を通して、母子福祉会(「のぞみ会」)に無償で場所を提供しています。しかし、それでも電気代は徴収できています(この点についても島本町より正しいです)。
自販機についてはクドクドと何度か日記に書いてきましたが、これで一件落着です。あと残っている問題点は体育館と消防庁舎の自販機に関して、遡及して電気料金を徴収できるかどうかという点です。まあもう、部外者の私が出る幕ではありません。
|
|
|
「大津の歴史」近代編には嘉田由紀子学芸員(現知事)も執筆
(2010年1月19日 火曜日)
この前の日記にも書きましたが、「図説 大津市の歴史」を読み始めています。まあ、読むと言っても「図説」の名の通り絵図や写真が多く掲載されているので、気軽にパラパラとページを繰って見ている状況です。先ずは興味のありそうなところをと開いてみると、ホ〜ッ!現滋賀県知事の嘉田さんが2項目の執筆をしていることを発見しました。
原稿を書いた10年前の嘉田さんは、「滋賀県立琵琶湖博物館総括学芸員」であったことが記されています。時を経て、まさか知事になるとは当人を初め誰も思っていなかったことでしょう。本の中で嘉田さんが執筆したのは、「琵琶湖総合開発」と「琵琶湖の水質保全運動」の項です。特に後者の項については、嘉田さん自身の活動の歴史とも重なる内容で興味深く読みました。
ところで、私は未だ“生”嘉田知事を見たことがないのです。県議会の傍聴も行っていませんし、大津市議会の小松明美議員(無所属の市民派)が何度か誘ってくれた「嘉田知事と語る会」(正式名称は失念)にも参加できていません。嘉田知事が誕生した時、琵琶湖を守りダムや新幹線の駅を拒否した滋賀県の人たちは偉いなぁ〜と感心しました。ちなみに大阪府橋下知事誕生の時には、特段感じることはありませんでしたが・・・。
今、尊敬する知事がいるこの地に移り住んで、よかったなぁとうれしく思っています。
写真は東京のブリジストン美術館で求めた、ドガの踊り子のフィギュアです。小さい像ですが、美しく仕上がっています。スカートだけが本物のチュール布でできているのもステキです。どこか嘉田知事の雰囲気と似通っているような気がしませんか?知事がいつまでも美しくキリリと、「山椒は小粒でも・・・」の心意気を失われないように祈っています。

歩道のない国道、何とかして欲しいです
(2010年1月20日 水曜日)
2月になれば、大津での暮らしも半年を迎えます。新しいマンションもすっかり体に馴染みました。欲を言えばキリがありませんが、近隣の既存建物等については少々の不満がないわけではありません(競輪場など)。しかし身の丈にあった分相応の暮らしが大事だと思い、お財布事情も考慮してここを選びました。間違いではなかったと思っています。なによりも毎日湖畔に立てる爽快さは、代え難い喜びです。
そして湖畔は今、周辺の整備と合わせて美しい砂浜を取り戻すための公園化工事が進んでいます。これはマンション住民にとって大きな朗報です。しかし一方、喜んでばかりはいられない困った事態があります。しかも、事態改善への方向性は容易に見出せそうにもありません。困った事態というのは、我がマンションに接している国道161号線の片側に歩道がないことです。
マンションに一番近い交差点から北に向う道路には、歩道が片側しか設置されていません。つまり我がマンション側には歩道がなく、アクセスには危険が伴うといっても過言ではありません。特に車イス、乳母車、自転車、障がい者やお年寄りや小さな子どもたちは、より一層の危険を感じているはずです。ただ白線を引いただけの狭隘なスペースを、真横を走る車に怯えながら歩行しているのが実態です。
大津京駅へ行く(つまり南に向う)時は、マンションの多くの人たちが危険を避けて整備が予定されている公園用地の中を通ります(勿論私もそうしています)。ただ北へ向う場合は湖面を渡っていくことはできませんから、よろけないように白線“上”を歩いていきます(白線内というには余りにも幅員が狭い)。国土交通省の辻元副大臣は「国道のバリアフリー化」に力を入れてくれるそうでうれしく思いますが、いやはや此処はそれ以前の問題です。
昨年公園整備についての工事説明会が行われた折にも、質問や要望の多くに歩道の設置を求める声がありました。歩道のない国道側に公園のメインエントランスが設けられる計画ですが、誰もが抱いている歩行への危険をどのように回避、或いは緩和できるのかが求められます。国道ですから市が単独で改善できるものではありませんが、いつ事故が起きても不思議ではない現状を放置していて良いわけはありません。
メインエントランスの公園部分は平成23年度に完成予定と言われています。国道沿いに公園を訪れた人がエントランスにたどり着く前に車と接触したり、エントランスを出た途端に事故にあう可能性がないとは言えません。みんな「良い公園にしてもらえる」と喜んでいるのです。公園への安全なアクセスのためにも、国と市はこの機会を逃さず、安全な歩行の確保に向けて知恵と力を絞って欲しいと切に願っています。
|
|
|
いよいよストーンピッカーのお出まし
(2010年1月21日 木曜日)
我がマンションの湖岸東側砂浜は、広範囲にわたり見事に一皮剥けてしまいました。硬くなっていた元の砂浜全域の表層部分を、一皮めくったように削り取る作業が終了したようです。削り取った砂(というより土っぽい)は積み上げられて、湖畔にいくつもの小山が出現しました。これからの作業には、いよいよストーンピッカーがお出ましです。小山の砂をストーンピッカーにかけて小石等の異物を取り除き、きめ細かいサラサラ砂にして湖岸に戻します。
私は毎日作業を見ていますが、暫く前から湖岸には自由に出入りができなくなりました。重機が何台も入っているため、危険だからというのは分かります。けれど今日は、いつもと違う重機が動いています。大きなショベルカーの先にカゴ状の物が付いていて、それがクルクル回りながら砂を吐き出しています。
顔見知りになった工事の人に「あれがストーンピッカーですか?もう少し近寄って見たいのですが」とお願いをしてみました。ここまでならオッケーという所を示してもらって、浜に入れてもらいました。犬の散歩に水辺近くまで行っている人もいましたから、そう不都合なことではなかったと思います。砂を篩いにかけるカゴは簡単な仕組みですが、見ていておもしろかったです。
今年度末までの工事は砂浜の回復と琵琶湖に注ぐ柳川の整備、そしてマンションに沿って設置される遊歩道の新設です。今日私が驚いたのは、細い柳川の川幅が何倍にも広がっていたことです。両岸の土手を削り川底を浚ったわけですから、元の柳川は見る影もありません。「エ〜ッ!こんなに変えてしまうのですか」と問うと、「土砂の堆積で変わってしまった川幅を元に戻すだけ。元々の柳川にするだけのことです」と返されてしまいました。
まあ、そう言われれば黙るしかありません。私は草の土手の間をサラサラ流れる“春の小川”(思わずこの歌を口ずさみたくなるような)状態の柳川が好きだったのですが・・・。「時間はかかるでしょうが、ちゃんとビオトープが形成されるような柳川に再生してくださいね」と、(工事の人に伝えても仕方がないかもしれませんが)お願いをしました。
寒さがまたぶり返してきました。一日中湖畔の寒風にさらされて工事をしている人たちは、仕事とはいえ体には大変厳しいと思います。お礼と激励の言葉を伝えて、本日のウォッチングは終了です。日記の末尾で恐縮ですが、一言感謝を。先日宮尾大津市議のブログで、ここの工事が紹介されていました。航空写真に赤ペンで工事範囲等が示してあり、とてもわかりやすい説明がされていました。現地をちゃんと見てくださっていることをうれしく思いました。
 |
 |
|
我家のマンションと削り取った砂の山
|
ショベルカーの先に付けたストーンピッカー
|
 |
|
|
浚渫で川床が広がった柳川(今は見るも無残な状態)
|
|
アウシュビッツを訪れてから、15年の時が流れました
(2010年1月22日 金曜日)
昨年末に「アウシュビッツ収容所入口の看板盗難」との新聞記事が出ました。その後早期に発見されましたが、今日の新聞では看板が国立博物館に返却されたことが報じられています。一連の報道を目にして、改めて15年前を思い出しました。
1995年の晩秋、私と長男はハンブルグ市に住むドイツ人の友人を訪ねました。その折にアウシュビッツ収容所(現在は国立博物館)とビルケナウ収容所を訪れたのです。東西ドイツのベルリンの壁が崩壊して5年後、ポーランド大使館はまだ旧東ドイツのベルリンにありました。
大使館で観光ビザを申請し寝台列車でポーランドに入り、途中の国境で税関の検閲を受けました。ワルシャワからクラコフへは再び列車で、クラコフからはバスでアウシュビッツ収容所に到着しました。既に雪が降っている寒さで、荒涼とした収容所跡を黙々と歩いたことを思い出します。体に感じる寒さよりも、人間の犯した罪の大きさ深さに心が凍りました。
ところで、ドイツ人の友人は島本町で長い間同じマンションに暮らし、共にささやかな活動をしてきた仲間です。彼女は私の議員活動も積極的に応援してくれていました。阪神淡路大震災が起きた2ヵ月後に、彼女は生まれ故郷のハンブルグへ帰りました。私たちが訪れたのは、その年の10月後半から11月にかけてです。20日間の滞在でした。
私は10月議会を終えて12月議会が始まるまでの間を利用して、長男は翌年就職までの自由時間を使っての旅でした。あれからもう15年も経ったのですね。彼女にはこの間何度か日本に来た折に会っていますから、そんなに時を経たようには思わなかったのです。小さな新聞記事が、一挙にあの頃を引き寄せてくれました。
初めての海外旅行が13時間(当時は長時間のフライトでした)もかかりフラフラで、フランクフルト空港でコートを忘れたこと・ワルシャワで切符を買った長男が、窓口のおばさんと言い合って取られすぎのお金を戻させたこと・ハンブルグの電車内では誰も漫画週刊誌を読んでいないこと・若い男性も布製の買い物袋を持っていること・街中のごみ用ドラムが分別仕様で設置されていたこと(今では日本も当り前ですが)・・・なんかどうでもよいことがやたら懐かしく思い出されます。
「10年後には絶対再訪するわね」「議員を辞めたら、直ぐ飛んで来るね」と、15年前ハンブルグ駅で別れる時に彼女と約束しているのですが、未だ果せていません。写真は旅行から帰って発行した「なんぶニュース No.47号」です。表紙にはアウシュビッツ収容所を訪れた感想を書いています。
わかりにくいのですが、左端の写真上部に今回盗難にあったプレートが写っています。「働けば自由になる」との文字で、「ARBEIT(働く)」の「B」が上下逆さまになっています。これはプレートを作らされた収容者のレジスタンスとも言われています。ちなみにポーランドではアウシュビッツとは言わず、オシフィエンチムと称していました。アウシュビッツは1939年、ナチスによって変更させられた名称だからです。
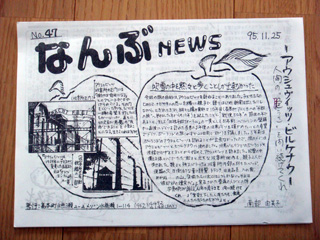
我家の目の前に、平和堂が出店計画?
(2010年1月23日 土曜日)
我がマンションは、国道161号線を挟んで大津競輪場の真向かいに建っています。競技施設に隣接した北側には、2万7千平方メートルの屋外駐車場もあります。スーパーマーケットの平和堂が、その駐車場の3分の1(9千平方メートル)を買収して出店を計画しているようです。この話は噂話として、私もマンションの住民からも聞いたことがあります。先日はマンション管理組合の理事会でも、正式議題ではありませんが話題に上ったそうです。
平和堂は滋賀県内ですでに63店舗、大津市内だけでも13店舗を出店しています。アルプラザのような大型店とフレンドマートのような小型店を、「ドミナント戦略」でアメーバー状に店舗網を広げていっています。ちなみに「ドミナント戦略」とは「一定地域に多店舗を集中して出店し、“点”ではなく“面”で優位を占める店舗戦略」だそうです。また国内のみならず、先日テレビでも放映され話題になりましたが、中国の長沙・東塘・株州市への平和堂進出に注目が集まっています。
今回当地に計画している店舗は、立地条件や面積からして大型ショッピングセンターではなく、生活便利店の小型スーパーマーケットだと考えられます。まあ消費者の立場からすれば、至近距離で日常の買い物に不自由しない状況が生まれるのですから、歓迎すべきことなのかもしれません。
しかし現在でも5、6分で業務用スーパーが2店舗あり、大型の薬局スーパーも2店舗あります。また徒歩13分くらいで大津京駅前の大型スーパー・ジャスコがあります。散歩がてらの買い物には丁度良い距離だと思っているので、私は日常生活に特段の不自由は感じていません。またマンションから北には唐崎のフレンドマート(平和堂小型スーパー)があり、唐崎・坂本・堅田と平和堂のドミナント戦略が展開されています。
ただし、スーパーマーケットは平和堂ばかりではありません。生協のコープ滋賀もあり、唐崎にはその名も「ハッピーテラダ」というスーパーもあります。実は我家の“御用達”は、このハッピーテラダなのです。同じ食品が他店よりも安いし、入っている魚屋さんはピチピチ鮮魚を扱っています。さぁ〜て、このような状況下で平和堂の戦略に勝算はあるのかしらとも思いますが、素人の私が心配しても仕方がありません。
心配すべきは小売商店への影響ですが、浜大津の中心部のように昔から存在している商店街が、大型スーパーによって“シャッター街”に衰退したというような状況には至らないと思います。つまり元々この近辺には、小売の商店は無きに等しいからです。あとはスーパーの出店によって、交通事情がどのように変化するかということでしょう。先日の日記でも述べましたが、国道の片側に歩道がない状況もあわせ考えると、店舗へのアクセスと近隣住民の安全性は整合性のあるものでなければなりません。
|
|
|
|
|
出店計画を平和堂は認め、市役所はノーコメント
(2010年1月24日 日曜日)
昨日の日記では「?」マーク付きの平和堂出店計画でしたが、その後平和堂の本社に問合せてみました。単刀直入「競輪場の近くに住んでいる者ですが、競輪場の駐車場に平和堂さんがスーパーを造ると聞きました。それは本当でしょうか?」と訊ねました。開発部の職員は、最初のうち言葉を濁していました。
私は続けて「もし本当ならとってもうれしいです。期待しています。実は駅前のジャスコまで行くのが大変なんです」(実際は全然大変じゃないですが)と、ライバル(?)スーパーの名前を出しました。すると「それはありがとうございます。出店の計画を進めています」と、あっさり認めました。
次に市役所の開発調整課へ電話をしました。平和堂で確認したことは伏せて、「開発にかかわる事前相談や協議、或いは既に許可の申請は出ていますか」と訊いてみました。職員は「そのような計画があるのかないのかも答えることは出来ません」と返しました。私は「分かりました。それでは一般論として、スーパー等の出店に係る事務の流れを説明してください」と再度訊ねました。
お役所という所は計画を知っていても、形ある手続が終了していないと「そうだ」とは絶対に認めませんから仕方がありません。職員は「1,000平方メートル以上の開発なら、都市計画における区画ケースの変更に当たるため、必ず開発の許可申請が必要です。しかし申請が出ても、市民の問合せには応じられません。確認は情報公開請求を行って下さい」と言いました。私は「はい、おっしゃる通りです」と、心の中で呟きました。まぁ、いずれ地元住民への説明があるでしょう(ただし、その時には何かあってももう遅いと言うのが常ですが・・・)。
さて、お次は競輪場を所管している公営競技事務所へ電話です。ここでは冒頭に平和堂が計画を認めていることを出しました。その上でスーパーマーケット用地になる駐車場の賃貸契約について訊ねました。ここで私が勘違いをしていたことが明らかになりました。それは駐車場が競技場と同じく、大津市が滋賀県から借りていると思っていたことです。
駐車場の地権者は複数の民間人で、市は2万7千平方メートルのうち9千平方メートルについては昨年末で賃借契約料の解消を折り込んだ予算を立てています。平和堂は12月以降に、民間地権者から土地を購入したのでしょう。「へ〜っ」と思ったのは、賃貸契約の解消が既に4月の当初予算で行われていた点です。当り前のことながら、計画は随分前から進んでいたわけです。
ところでスーパーの規模や開店時期等、消費者が知りたいことは誰も教えてくれませんでした。また本件については、私が日頃チェックしている市議さんたちのブログでも見たことがありません。言い忘れていましたが、市が支払っていた2万7千平方メートルの借地料は6,336万円で、随分大きな金額でした。今後は少なくとも、その3分の1が経費削減されることになります。しかし年間2億とも3億とも言われる競輪事業の歳入不足解消には、程遠い削減額です。
|
|
|
会派「人びとの新しい歩み」の三議員、請願審査お疲れ様でした
(2010年1月25日 月曜日)
請願審査が行われた建設水道常任委員会を傍聴しました。請願の件名は「食料の自給力と、食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正について国への意見書提出を求める請願書」という長い名称です。請願者は山崎1丁目の備酒 有子さん外36人です。請願の主旨等は、既に紹介議員の平野議員・戸田議員がブログで詳細な説明を行っていますので、ここでは省略いたします。
請願は誰でも行うことができる憲法で認められている権利ですから、議会は必ず請願を受理し議案として上げ、結論を出さなければなりません。先ずは所管の常任委員会で審査・採決され、(今回の請願なら)本会議の3月議会で最終の討論・採決を行います。同時に請願者への結果報告と、請願項目を明記した意見書が国へ提出されることで一件落着です(意見書の成文化については、改めて議会内で調整されることでしょう)。
当請願は正面切って賛否が分かれるような中身ではありません。食料の自給“力”向上と、食の安全・安心を求めることは誰しもが頷かざるを得ない内容であり、それらを担保するためには国の食品表示制度改正は求められて当然です。従って誰も反対出来ないと思われる請願で、委員会の採決結果は「採択すべきもの」と決しました。
島本町議会の一定の“良識”が確認できて、良かったと私もホッとしました(この請願を反対されたら、町議会の評価はガタ落ちです)。また全委員が採決に当たり、その理由を述べる討論を行ったことも良き現象です。ただし、自由民主党クラブのS議員が行った質疑・討論は、私には単なる嫌味としか受取れませんでした。
S議員は請願の主旨に対する質疑は全くすっ飛ばして、「何で意見書として上げなかったのか」とか「意見書を議題として上げるための、賛成議員4分の3の定義をこそ提起すべきではないか」等、私から見れば“的外れ”な意見を繰り返していました(なんか、カッコわるぅ〜)。
まあ、いずれにしても請願を提出された住民の皆さんの決意と、その決意を忠実に答弁に反映した紹介議員と、答弁を引き出す質疑を展開した委員(市民派S議員や共産党T議員)のご苦労を称えたいと思います。そうそう、今までなら自由民主クラブと“鉄のアングル”を組んでいた公明党(О議員)、山吹民主クラブ(H議員)の賛成表決も評価しておきましょう。
最後に紹介議員の戸田議員が発言した言葉を書いておきたいと思います。戸田さんは今回の請願審査に当たり、従来にも増して多方面にわたる“勉強”をされたことが良く分かりました。“知識の豊かさ”に加えて、説明力の過不足のなさは先輩の平野議員と肩を並べるほどの力量を発揮していました。大したものだと私もうれしく思いました。
T議員が「農業が農業として成り立つ仕組を町として追及することが大事だと思うが、見解を示されたい」と質疑したことに対して、戸田議員は次のような答弁を返しました。「T議員と同様の認識を持っている。足元の地産地消が果されなければ、声高に叫んでも仕方がない。しかし今回の請願は小さいけれど、政治に係ろうとする住民の発芽であると考えている」。大事な観点をよどみなく示して、戸田さん“決め”ましたね!
そう、今後はあらゆる事態に対して住民の“発芽”が望まれますが、いつも今回のような大義名分が生きる請願が出されてくるとは限りません。過去の請願のように住民の利害が相反するがゆえに出された、つまり町の施策や議会の姿勢が問われるような請願も突きつけられることでしょう。島本町に特化した課題で切れば血が出るような“生々しい”問題に、戸田議員のみならず先輩の平野・澤嶋議員も含めた市民派議員がどう対峙していくか、本当に楽しみです。
本日25日は、午前中の傍聴後夕方近くまで澤嶋さんとご一緒しました。近々体調不良の根本的な治療のため、暫くの間公務を休まざるを得ない澤嶋さんの話を、ただ黙って聞かせてもらいました。私にできることといえば、それくらいしかありません。澤嶋さん!食べて笑って、そして泣いて、新しい体験に立ち向かう元気は出ましたか?あなたの一歩に限りない応援を送ります。今までも苛酷なほど頑張っているけれど、もうひと踏んばり頑張って・・・待ってます。
写真は、「後鳥羽上皇離宮跡か?」とクローズアップされ、全国に発信された遺跡発掘現場です。昨日(24日)の説明会には千人を越える見学者があったとか。私も本日資料だけでも頂こうかと思いましたが、無理なようでした。現場には今日も遠方からの見学者が来ていました。教育委員会の職員も2人いて、遺跡発掘の担当者から少し話を聞けたのは幸いでした。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
島本で、温かいお声をたくさんかけていただきました
(2010年1月29日 金曜日)
25日の議会(委員会)傍聴に続き、4日目後には再び島本町へ。先ずは○○さんのジュエリー展にお邪魔をして、“目のお正月”を楽しみました。○○店主Nさんの“美”に対する揺ぎない言葉は、いつ聴いても清々しく胸に響きます。Nさんはお店をしているにも拘らず、議員の私をずっと応援してくれていました。Nさんの町政に対する鋭い視点に、ハッと気づいたことも反省したことも多々ありました。私が町外に転居した今も変わりなく、うれしいお誘いを下さっています。
○○を出て、お昼ごはんを近くのお店で取りました。「オ〜ッ!久しぶりですね。元気でしたか」と△△店主の温かい声が飛んできました。私が大津市へ引越したことを聞いたご主人は、琵琶湖で釣りを楽しんでいることを話してくれました。鮎釣り大漁の成果を、携帯電話の画像で見せてくれました。ここでも「寄ってくれてうれしかったですわ。元気でね」とのうれしい言葉を背に店を出ました。
阪急水無瀬駅のバリアフリー工事の進み具合を見てから、楠公道路をJR島本駅に向って歩きました。生協の向かいには、完成した健康モールビルが建っています。近隣住民に多大の日照被害等をもたらす当ビル建設に対し、私は何度も議会において質してきました。結局、隣接する大美自治会との協定書を結ばずに工事を進め、住民の願いは無視されたままビルは完成しました。
町行政の斡旋も功を奏さないまま事業主の“横暴”を許したことは、今後の開発行政・まちづくりに大きな禍根を残したと残念でなりません。また私と私の後を受け継いでくれた市民派議員の力が及ばなかったことは、本当に申し訳なく胸が痛みます。自治会の掲示板には、今も建設に対する抗議のポスターが貼られ、ノボリも立てられています。
交差点でビルの写真を撮っていると、大美自治会の方が通りかかり声をかけてくださいました。私が「建ってしまいましたね。お役に立てず、済みませんでした」と伝えると、「いえいえ、よく頑張ってもらいました。南部さんが退職してから後も、事業主の強硬姿勢には変わりがありませんでした」と返されました。そして「大津でもご活躍くださいね」と、反対に私を励ましてくださいました。
電車に乗る前に、よく野菜を買っていた八百屋さんに寄りました。八百屋の主人は「大津でも用が足りるのに、わざわざ寄ってもらってありがたいです」と喜んでくれました。帰路少々重たいですが、オレンジとイチゴと花菜を買いました。すると「うれしかったから、オマケです」と、葉付きの上等ミカン数個を私の両手に乗せました(このミカン、すご〜く!おいしかったです)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歴史文化資料館でカルタの原画展と陶芸展を楽しみました
(2010年1月30日 土曜日)
島本町の歴史文化資料館を訪れたのは昨日ですから、29日の日記の続きを書いていることになります。JR島本駅から帰路に着く前に、駅に隣接している資料館を久しぶりに訪れました。「しまもと郷土かるた」の原画展は毎年見てきたので、今回も機会があればと願っていました。切り絵作家の藤田さんが作成された絵札は、本当に素晴しいです。写真撮影は不可で、ご紹介できないのが残念です。
今回は
- 「千鳥とぶ淀の川瀬の三十石船」
- 「離宮八幡油の座」
- 「ぬくもりを今に伝える楠公焼」
- 「瑠璃光山洞の薬師の勝幡寺」
- 「大沢の千年杉は記念物」
- 「若狭より年季奉公幼き子」
- 「鎌倉の仏ひっそり極楽寺」
- の原画が展示されています(1月末日まで)。
受付で、「水無瀬駒」と題した小冊子が販売(200円)されていたので購入しました。水無瀬駒については以前の日記でも詳しく書きましたが、町文化財保護条例施行に伴い指定文化財の第一号とされたのが「水無瀬駒 関連資料」です。また、先日行われ大盛況だった広瀬遺跡の発掘現地説明会の資料も頂くことができました。
館内では、陶芸クラブ「炎」の作品展も開かれていました。資料館が自主グループの活動に対して、やっと作品発表の場を提供し始めたようですね。良いことだと思います。「炎」のメンバーによる作品の説明もあって、じっくりと楽しむことができました。ここでも転居したことを初め、温かいご挨拶を複数の人たちから頂きました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
早春の花々を愛でました
(2010年1月31日 日曜日)
新しい年が始まって、早一ヶ月が過ぎました。1月の日記は虫食い状態を脱することができて、訪問してくださった皆さんへの申し訳が少しは立ったかなと思っています。とはいうものの記事の中身は平々凡々、特にお知らせしなくてはならないような“特ダネ”もありませんでした。それでも毎日、仕事をしていた頃と同じくらいのアクセスを頂いています。うれしく有難く・・・未だ続けてもよいのかなぁ?と、勝手な判断をしています。
さて標題の「早春の花」は、菜の花と梅の花を指しています。菜の花は守山のなぎさ公園、梅の花は坂本の旧竹林院で観賞しました。比良の山々と琵琶湖を背景にした一面の菜の花畑は(時節柄多くのブログでも紹介されており)、行ってみたい憧れの風景でした。昨日(30日)は良い天気でしたから、いざ現地へと勇んで出かけました。このところの暖かさで比良山が雪化粧していなかったのは少々残念でしたが、菜の花はとても見事でした。
梅を観賞した竹林院は旧の里坊(比叡山の僧侶が隠居後暮らした宿坊)で、最初に訪れたのは去年の11月末でした。今年で4回目の盆梅展が開かれているので、守山の帰りに寄ってみました。山本哲平大津市議のブログで、盆梅展のことが紹介されていたので興味を持っていたのです。50鉢の梅は未だ蕾のものが多く、見頃はもう少し先でしょうか。まあ、近くにはおいしい「鶴喜そば」もあるので、次回は満開を見計らって再訪しようと思います。
しかし花は少なくとも、樹齢百年を超える幹や枝振りを鑑賞するだけでも値打ちがありました。盆のように浅い鉢で、何故太い梅の木が長年生き続けられるのか?盆梅の面白いところです。ところで、盆梅といえば長浜が有名ですね。でも、盆梅の発祥地は大津市だそうです。大正時代の初めに、膳所中庄の生駒晴彦氏が「梅仙窟」と称し公開したのが始まりだと言われています。
そして平成19年、75年ぶりに開催されたのが「坂本盆梅展」です。坂本在住の河村庄太郎さんから、丹精込めて育てた盆梅を出展してもらっています。もうすっかり“坂本の風物詩”として定着しているようです。盆梅は趣のある竹林院の座敷と庭園にとてもよく似合って、清々しく堂々とその存在を主張していました。尚、盆梅展は3月7日まで開かれています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|