ルワンダ共和国 発行
| その6 コペルニクス | |
|
|
コペルニクス生誕500年記念 ルワンダ共和国 発行 |
| その5 コペルニクス | |
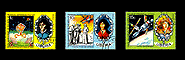
|
コペルニクス生誕500年記念 リベリア共和国 発行 |
| その4 コペルニクス | |
|
|
コペルニクス生誕500年記念 キューバ共和国 発行 |
|
Update ! その3 ケプラー | |

|
ケプラー生誕400年記念 アラブ首長国連邦フジエラ 発行 |
| その2 コペルニクス | |

|
コペルニクス生誕500年記念 ブルンジ共和国 発行 |
| その1 コペルニクス | |
|
|
コペルニクス生誕500年記念 モルディブ共和国 発行 |
| コペルニクス (Nicolas Copernicus) | ポーランド (天文学者) | 1473生 - 1543没 |
|
地動説 それまでの天文学では、プトレマイオスの宇宙体系である天動説が正しいものと考えられていましたが、計算が複雑な上、水星や金星の限られた運動や、火星や木星、土星の逆行を上手く説明することができませんでした。 コペルニクスは、1510年頃、「コメンタリオルス」(天の運動を説明する仮説の概要)という論文を、教会の非難を恐れて、無記名で友人の天文学者たちに送りました。そこには「太陽はほぼ宇宙の中心にあり、地球は1日に1度地軸の周りを自転しながら、太陽の周りを1年周期で回転している」という、いわゆる地動説が書かれてました。これは、惑星の運動を簡単に説明できると共に、歳差運動まで説明することができました。そして晩年に、仲間の天文学者の薦めでその内容をまとめた「天体の回転について」が出版されました。 なお、惑星の軌道を真円としたために、正確な計算には天動説と同じ周転円を使わなければなりませんでした。 | ||
| ケプラー (Johann Kepler) | ドイツ (天文学者) | 1571生 - 1630没 |
|
ケプラーの法則 ケプラーは、ティコの膨大な観測データを元に、惑星の運動法則を見つけだしました。火星の軌道を楕円とすると観測データと一致することを見つけ、1609年の「新天文学」にまとめました。これが、ケプラーの第1法則、第2法則です。さらに研究を進め、1919年に「世界の調和」で第3法則を発表しました。 ケプラーの法則を元に算出される惑星運動は非常に正確で、天動説を確かなものにしました。また、のちのニュートンによる万有引力の法則の発見にも貢献しました。 第1法則……惑星は太陽をその1つの焦点に持つ楕円軌道の上を運動する。 第2法則……惑星と太陽を結ぶ線分が、等しい時間に描く面積は等しい。 第3法則……惑星の太陽からの距離の3乗と惑星の公転周期の2乗の比は一定である。 | ||