
CHANDOS
CHAN 8545
ヴァーノン・ハンドレイ/アルスター管弦楽団
国内外で高い評価を得たスタンフォードの出世作。
最初の2つの交響曲は、自分の作風を模索しているというような感じで、あまりスタンフォードらしさが前面に出てこない作品であったが、この交響曲第3番は彼の作曲家としてのアイデンティティが感じられる優れた作品である。しかも、この作品はドイツ、オランダ、アメリカなど数カ国で演奏され、いずれも好評を博しており、スタンフォードがグローバルな名声を獲得することになった代表作ということができる。ドイツ的な堂々としたスケールの大きさのなかに繊細さが垣間見られ、各所で使われているアイルランド民謡の旋律も曲をいっそう親しみやすいものにしている。ところで、第3楽章はブラームスの交響曲第4番第2楽章冒頭のモチーフを引用(盗作?)したという疑惑があるそうだが、そんなことは曲の本質とはあまり関係ない。そんなことを言っていたら、世の作曲家は全て盗作していることになってしまう(ちなみに盗作される度合いのNo.1はグレゴリオ聖歌)。それに、このモチーフはブラームスとは違ったかたちで曲に生かされているところを楽しむのもまた一興というものだろう。さて、この作品の中で私が最も気に入っているのが第4楽章である。全曲中でアイルランド民謡が最も効果的に使われており、輝かしい管の響きと歯切れのよい弦の絶妙なマッチングがすばらしい。これを聴けば、あなたもスタンフォードのとりこになること間違いなし。

CHANDOS
CHAN 8884
ヴァーノン・ハンドレイ/アルスター管弦楽団
曲のモットーは、"Thro' Youth to Strife, Thro' Death to Life."
交響曲第4番は、スタンフォード自身によって曲にモットーが付与されている。それは「若さゆえの闘争、死があるからこその人生」(Thro'はThroughの略)というものだが、この曲はあまり「闘争」というイメージで捉えられるような激しい部分は皆無といって良い(ライナーノーツによれば、スタンフォード自身がこのモットーは曲の性格を表したものではないと言っているそうな)。冒頭から唐突に主題が始まる第1楽章は、「若さ」を表現したというだけあって、流れるようなロマンティックな調べから若々しい息吹を感じることができる。寂しげに鳴くクラリネットの音色に誘われて始まる第2楽章は、人生における悲劇をあらわしたということである。この楽章は主に劇音楽「オイディプス王」のフレーズを基調につくられたらしい。ちょうど、この「オイディプス王」の前奏曲がカップリングされているので聴き比べてみるとよいかもしれない。雰囲気は似ているのではないかと思う。全体として静かに微妙な感情の機微が表現されており、続く第3楽章とともに非常に美しい楽章である。第3楽章は第2楽章よりももっと悲劇性が増した暗めの旋律によって始まる。この楽章は「死」をイメージしているそうだが、中間部は非常に穏やかな旋律美が支配し、静かな感動が呼び起こされる。この楽章は全曲の中でも特に美しい。第4楽章は活気に満ち溢れており、第2〜第3楽章にかけての暗さが吹っ切れたかのような陽気な雰囲気に包まれて終結部へ至る、まさにドイツ・ロマン派十八番の展開である。
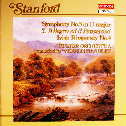
CHANDOS
CHAN 8581
ヴァーノン・ハンドレイ/アルスター管弦楽団、ロナルド・ダヴィソン(オルガン)
穏やかな流れの中で静かに響くオルガンの音色。
交響曲第5番は、スタンフォードがピューリタン革命、王政復古、名誉革命へと続く17世紀の動乱期に生きた詩人ジョン・ミルトン(「失楽園」が有名)の「陽気な人と悲しげな人」という抒情詩に触発されて作曲した作品である。曲自体はおとなしめな造りである。第1楽章は荘重でありながらも陽気で活動的な印象を持たせた曲調で、第2楽章も第1楽章の雰囲気を引き継いで陽気さが感じられるメヌエットとなっている。第3楽章はうって変わって、内に沈むような静かで宗教的な色彩が濃い叙情的な楽章となっている。まさしく「ふさぎの人」を彷彿とさせる。しかし、暗く沈鬱なイメージとは違い、旋律は美しく、はかなげな印象の強い楽章である。最後の第4楽章は、遠くからかすかに響く晩鐘によって始まり、静かな中にも内に秘めた情熱が見え隠れするような荘厳さが感じられる。やがて、オルガンの響きによる恍惚としたひとときが演じられ、クライマックスへ向けて静かな盛り上がりをみせて曲が終わりを迎える。アイリッシュ狂詩曲第4番は、朝靄の中にひっそりと静まり返った山間部の湖を連想させる序奏部から一転して、陽気で流れるようなアイルランド民謡の旋律が登場し、やがてアルスターの行進曲の勇壮で激しい旋律から、チェロによる吟唱を唄うような渋い旋律へと移り変わり、だんだんとクライマックスへとゆっくりと盛り上がっていく、非常に起伏に富んだすばらしい作品である。

CHANDOS
CHAN 8627
ヴァーノン・ハンドレイ/アルスター管弦楽団
2人の芸術家のために書かれた知られざる2つの名曲。
アイリッシュ狂詩曲第1番は、19世紀ドイツを代表する名指揮者ハンス・リヒターに捧げられた曲である。ティンパニとブラスによる勇ましい戦いの動機の後に、ハープによる優美なグリッサンドに続いて有名なアイルランド民謡「ロンドンデリー・エア」の旋律が穏やかに流れるように演奏される。この時のオーボエの音色はなかなか味があって良い。この後を受けて、ティンパニとブラスによる戦いの動機と「ロンドンデリー・エア」がミックスされた快活で美しい旋律が奏でられ、力強いブラスとパーカッションで曲を閉じる。「勇」と「美」が渾然一体となってすばらしいハーモニーを形作っている作品である。交響曲第6番は、スタンフォードによって"偉大な芸術家ジョージ・フレデリック・ワッツのライフワークに敬意を表して"という副題が付けられている。このワッツは、「イギリスのミケランジェロ」と呼ばれている人物だそうで、数々の傑作を世に残している彫刻家であり画家である(ロンドンのケンジントン・ガーデンにある「肉体のエネルギー(Physical Energy)」という騎馬像は彼の作品)。スタンフォードは、このワッツの死に際して、その偉大なる功績をたたえる意味から、彼の作品から得られるインスピレーションに基づいてこの曲を作曲したと言われている。この交響曲第6番はスタンフォード畢生の名曲といっても良い出来であるのにもかかわらず、これまでほとんど演奏される機会がなかった。これまで長いこと埋もれていたこの作品に光を当てたハンドレイの功績は非常に大きいといえる。「愛」と「死」をテーマとするこの曲は、スタンフォードの叙情性を余すところなく表現している。特に第2楽章のコールアングレによる「愛」の主題の美しいことこの上もない。他の楽章もスタンフォードの旋律美とオーケストレーションの妙を充分に堪能できる。まずは一度聴いてみるべし。

CHANDOS
CHAN 8861
ヴァーノン・ハンドレイ/アルスター管弦楽団、ラファエル・ウォールフィッシュ(チェロ)、ジリアン・ウェイアー(オルガン)
オルガンが大活躍をするスタンフォードの隠れた名作。
まず、この1枚に収められた曲の中でイチ押しなのが、オルガンと管弦楽のための演奏会用作品である。オーケストラに負けじと活躍するオルガンの力強い響きと起伏の激しい迫りくるエキサイティングさが魅力の作品である。彼の交響曲を聴きなれた人には「これがスタンフォード?」というぐらい、インパクトが強い。出だしからオルガンが活躍しまくり、途中展開部で穏やかな雰囲気にホッとするのもつかの間、怒涛のごとくオルガンとオーケストラがしのぎを削る終結部へまっしぐら。これほどオルガンが自己主張をして、オーケストラと張り合っている作品はなかなかお目にかかることは少ない。是非、聴いてみることをお勧めする。他の2曲は、スタンダードなスタンフォードを楽しむことができる作品。交響曲第7番は、第3番や第4番などに比べると少々影が薄いが、ロマン派的な旋律美を充分堪能できる曲である。アイリッシュ狂詩曲第3番は、オーケストラの軽やかな伴奏に乗って演奏されるチェロの陽気な調べが魅力的である。

CHANDOS
CHAN 8736
マーガレット・フィンガーハート(ピアノ)、ヴァーノン・ハンドレイ/アルスター管弦楽団
ドイツ・ロマン派のエッセンスたっぷりのピアノ協奏曲。
ドラマティックな出だしで始まるピアノ協奏曲第2番は、ブラームスとシューマン、ラフマニノフ、チャイコフスキーを足して4で割ったようなロマンティックな作品。ロマン派好きにはこたえられない逸品である。初めて聴いた人でも「これ、どっかで聴いたことあるな」と思える親しみやすさが売りの曲だ。第1楽章は、甘美でありながら力強いピアノ・ソロとオーケストラのかけあいが見事。全体を支配する勇壮かつドラマティックな主題は聴くものをいやがおうにも惹きつけて離さない。第2楽章は終始おだやかで、もろブラームスといった感じ。第3楽章は、3拍子の活発な出だしで始まる。中間部はブラームスのピアノ協奏曲第2番第3楽章を思わせるピアノ・ソロのうねりを聴くことができる。この曲は、本当に徹頭徹尾、ロマン派で押し通したような作品である。イギリス風主題による演奏会用変奏曲は、"Down Among the Dead Men"(死者たちの下へ)というイギリスの古くからある有名な曲を主題として使っているそうな。曲は非常に変化に富んでいて面白い。メリハリの利いた歌うような旋律があるかと思えば、宗教的で沈思な旋律が流れ、勇壮で明るいテーマが現われるかと思えば、柔和なタッチのフレーズがそこかしこと現われる。この曲もピアノ協奏曲第2番と同様に徹頭徹尾ロマン派で、このCDをはじめて聴いた人は、ドイツの有名な作曲家の知られざる協奏曲だと思ってしまうかもしれない。