![]()
(04/1/30作成)
(04/3/6掲載)
今回の定期演奏会の曲目「ドン・ファン」は、ニューフィルとしては初めてのR・シュトラウスへの挑戦となります。創立20周年を経て、初めて可能となったこの挑戦、実際に直面してみるとその音符の多さには圧倒されてしまいます。この試練を乗り越えて、私たちは確実に成長していくことになるのでしょう。
R・シュトラウスといえば、「有名さ」という点では「ドン・ファン」をはるかにしのぐ曲があるのは、ご存じのことでしょう。それは、彼の7つの交響詩のうちの5番目の作品、「ツァラトゥストラはこう語った Also sprach Zarathustra」。ただ、実際に聴かれているのは、この、ニーチェの著作をタイトルに持つ深遠な内容の、演奏には30分以上を要する交響詩の全曲ではなく、その、ほんの冒頭の部分のみであることは、注意しておく必要があります。種を明かせば、この冒頭のファンファーレの部分が、1968年に公開されたスタンリー・キューブリックの映画「2001年宇宙の旅 2001:A Space Odyssey」で非常に印象的な使われ方をしたために、一夜にして有名になってしまったということなのです。例えばエルヴィス・プレスリーが彼のショーのオープニングにスウィング・モードでアレンジしたり、デオダートが16ビートに乗せてフュージョン(当時は「クロスオーバー」と言っていましたが)シーンでヒットを放ったりという、クラシック以外のカテゴリーでの格好のテーマとなるにいたって、この曲は作曲者や曲名が分からなくても大衆に認知されるという、いわば匿名性すら持ち得た「名曲」となったのです。
キューブリックがこの映画の音楽として最初に構想していたものは、実は、「ツァラ」などのクラシックの既存の曲をそのまま使うという、今のような形ではありませんでした。彼は、かつて一緒に仕事をしたことがあったアレックス・ノースという作曲家に、きちんとした「映画音楽」を作ってもらおうと思っていたのです。そのために、これは映画音楽を発注する際の常套手段ではあるのですが、「こんなイメージの曲」というサンプルを収録したテープ(「テンプ・トラック temporary music tracks」)をノースに渡します。しかし、出来上がったノースの音楽はキューブリックの満足するものではなく、サウンドトラックとして採用されることはありませんでした。結果的には、そのテンプ・トラックがそのまま使われることとなり、そこに入っていた「ツァラ」が、シネラマのスクリーン上で鳴り響くことになるのです。ちなみに、この時にノースが作った音楽は、1993年にジェリー・ゴールドスミスの手によって録音され、我々は初めて、もしかしたらこの映画を彩っていたかもしれない曲たちを聴くことが出来るようになりました。確かに、その「メイン・タイトル」は、「ツァラ」を下敷きにしたことがありありと分かる曲調となっています。
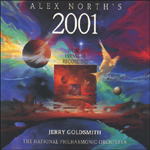 |
| VARÈSE SARABANDE/VSD-5400 |
元はテンプ・トラックとは言っても、映画の中で使われれば、きちんと演奏者などはクレジットされますし、もちろん、サントラ盤のレコード(当時はLPですね)も発売になりました。1968年の公開時に、SIE-13 STという品番でMGMよりリリースされたLPをCD化したものが、このPOLYDOR盤です。なぜか、リゲティの「ルクス・エテルナ」が、「音質上の問題」ということで、LPでのゴットヴァルト盤(WERGO/WER 60162-50)からフランツ盤(DG/423 244-2)に差し替えられていますが、他のタイトルは、もちろんLPと同じものです。そして、ここでの「ツァラ」の演奏は、「カール・ベーム指揮/ベルリン・フィル」と表記されています。
 |
| POLYDOR/831 068-2 |
不思議なことに、映画のエンドタイトルでは、他の曲では全て演奏者が明記されているにもかかわらず、「ツァラ」だけは何の表記もありませんでした。
これがエンドタイトルの画像です。例えば、上の「青きドナウ」の場合は、曲名「THE BLUE DANUBE」の下に「performed by 〜」と、演奏家とレーベルが明記されていますが、下の「ツァラ」では、この曲の英語表記「THUS SPOKE ZARATHUSTRA」の下には、何も書かれていないのです。
ですから、サントラ盤で「ベーム指揮」と書いてあれば、皆それを信用するのは当然のことです。この曲が世界中でヒットするきっかけとなったそもそもの音源は、ベームの演奏のもの、というのは、長い間の「常識」になっていたのです。
ところが、1996年になって、TURNERというレーベルから、もう1種類のサントラ盤がリリースされると、その「常識」は見事に覆されることになるのです。ここでは、収録曲が「映画の中に現れる音楽」と、「補助音源」という2つのカテゴリーに分かれているのですが、それによると、映画に使われた「ツァラ」は「ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮/ウィーン・フィル」だというのです。そして、「補助音源」の方に、「オリジナルのMGMサウンドトラック盤に入っていたもので、映画では使われていない」というコメント付きで、MGM盤に収録されていた「ツァラ」が入っていたのです。ここからが、ちょっと複雑な話になるのですが、普通はそれがベーム盤だと思うのが当たり前ですね。ところが、そこにあるクレジットは「エルネスト・ブール指揮/南西ドイツ放送響」、つまり、同じ映画のサントラでリゲティの「アトモスフェール」を演奏しているのと同じ演奏家のものだったのです。しかし、この「ブール指揮」による演奏は、どう聴いてもMGM盤サントラで「ベーム指揮」とクレジットされている音源と同じものです。大体、ブールが「ツァラ」を録音したなんて、聞いたこともありません。そこで、これを厳密に検証してみようと思い、それぞれの元になった音源を入手して、比べてみました。その結果分かったのは、映画に使われていたのは、確かにカラヤン/ウィーン・フィル、1959年録音のジョン・カルショーのプロデュースによるDECCA盤だったということです。冒頭レガート気味のトランペットや、いかにもカルショーらしいティンパニの響きなど、間違いありません。一方の「未使用音源」は、やはりMGM盤の表記通り、1958年録音のベームによるDG盤でした。トランペットが出る前のオルガンの一瞬の途切れや、3回目のトランペットの低めの音程などが、明白な特徴です。ですから、この表記は、TURNER盤の痛恨のミスプリントだったのです。
TURNER/R2 72562
これは推測に過ぎませんが、カラヤン盤を映画で使用したものの、サントラ盤を発売する際には権利の問題などでDECCAの音源は使えず、やむなく同系列のDGにあったベーム盤を使ったのではないでしょうか(このようなケースは、現在でもコンピレーション・アルバムを作る時には日常的に発生しています)。制作者は、その時はライバル同士だった2つのレーベルが、後に同じグループになってしまうなど、夢にも思わなかったことでしょう。
 |
 |
| DECCA/SXL 2154(LP) | DG/463 190-2 |
さらにもう一つの大胆な推測を披露させてもらっても構わないでしょうか。今回映画のDVDと元の音源を聴き比べて分かったのですが、映画の冒頭「ド−ソ−ド」というトランペットの上向音型の時に最初からはっきり聴くことが出来る、バックでゴーゴーと鳴り響いているまるでSE(音響効果)で作ったような低音は、後で付け加えられたものではなく、最初から録音されていたものだったのです。これは、録音にあたったDECCAの天才エンジニア、ゴードン・パリーの渾身の仕事、オルガンの32フィート管のペダル音Cとバスドラムとコントラバスのトレモロを、ギリギリのレベルで収録したものなのですね。この、まるで地響きのような低音は、この冒頭のシーンの壮大なイメージをどれほど強烈にサポートしていたことでしょう。実は、これは必ずしも楽譜に忠実な演奏ではなく、本来は3度目のファンファーレのあたりでやっとトレモロが聴こえてくるというのが「正しい」演奏なのです。それにあえて逆らったカラヤンと録音スタッフ、これがあったからこそ、キューブリックはこの録音を選んだのでしょう。もちろん、ベームによるDG盤のような「正しい」演奏では、そんなインパクトなどさらさら感じることの出来ない平凡なペダルの音しか聴くことは出来ません。ですから、もしキューブリックが、カラヤン盤を聴かずにベーム盤をサントラに採用していたとしたら、この曲はもしかしたら今のような人気曲にはなってはいなかったのではないか、というのが、私のちょっとした推測です。
ところで、このTURNER盤のサントラ、ミスプリントはこれだけではありません。映画のエンドクレジットにも、そしてMGM盤にも登場しなかったリゲティの「アヴァンチュール」を「映画の中に現れる音楽」としてきちんと取り上げたのまでは良いのですが、その表記が「リゲティ指揮」となっています。これも手持ちの「ブルーノ・マデルナ指揮」のWERGO盤(WER 60045-50)と聴き比べてみましたが、全く同一の録音でした。せっかく良い仕事をしているのに、こんなにミスが重なっては何にもなりません。
(2013年1月20日追記)
TURNERのサントラ盤は、2010年頃にSONYからリイシューされました。しかし、ジャケットには同じ版下が使われており、ここまでに述べたミスプリントは一切訂正されてはいませんでした。
余談ですが、このように、映画で使われた音源はそれまでにLPとして市場に出ていて、現在はCDとして入手出来るものなのですが、唯一、「モノリスのテーマ」として使われているリゲティの「レクイエム」だけは、放送音源が使われているのです。これは、いくら調べてもこの「フランシス・トラヴィス指揮/バイエルン放送響」という音源がリリースされた形跡がないので、直接指揮者のトラヴィスにメールを出して明らかになったこと。しかも、トラヴィス自身から、その音源をCD−Rにしたものをプレゼントされてしまいましたよ。
ただ、この演奏の録音データが、「1968年」というのが、新たな謎を産みます。キューブリックがノースにテンプ・トラックを渡したのは、1967年の12月、ということは、その中にはこの「レクイエム」は入っていなかったことになります。その段階ではモノリスのテーマにこの曲を使うという構想はなかったのか、あるいはキューブリックは、1965年3月14日のこの曲の世界初演(ミヒャエル・ギーレン指揮スウェーデン放送管弦楽団・合唱団、合唱指揮はエリック・エリクソン)をストックホルムで聴いていたほどのマニアだったのか、それを確かめるすべは、私にはありません。(この件はほぼ解決しました。「追記」をご覧ください。)
(2005/5/2追記)
最近、カラヤン/ウィーン・フィルの「ツァラ」をプロデュースしたDECCAの伝説的なプロデューサー、ジョン・カルショーの自伝「Putting the Record Straight」(1981)の日本語版が出版されました(タイトルは「レコードはまっすぐに」)。その中(282ページ)でカルショーはしっかり「キューブリックがカラヤンの録音を採用した」と述べています。しかも「デッカがキューブリックにテープの使用許可を与えるにあたり、デッカやカラヤンの名前を画面に出さないのを条件にした」とまで。
当事者の言葉はなんと重みがあることでしょう。これで、この件に関する疑問は氷解しました。「レクイエム」についても、どこかにこのような証言がないものでしょうか。
(元の本はこのように価値の高いものなのですが、この日本語版には問題がないとは言えません。この部分でも、ベーム盤に関する余計な「注釈」は、顰蹙を買うだけのものでしかありません。)
(2006/6/19追記)
「デッカが名を伏せたため、ベーム指揮ドレスデン・シュターツカペレのDGG盤が使用されたと思っている人も多い。」という初版に於ける痛恨の誤記は、最近の増刷ではきちんと「ベルリン・フィル」に訂正されている事が、確認できました。
(2011/10/27追記)
ひょんなことから、トラヴィスが「レクイエム」を演奏した日が分かりました。コンサートが行われたのは1967年12月15日、それがラジオで生中継されたとすれば、キューブリックがテンプ・トラックに加えた可能性も出てきます。原文はこちら。
"Francis Travis tells me that the recordings Kubrick used were from a live performance of the Requiem given on 15 December 1967 in Munich and broadcast on German radio (presumably WDR?). They were never commercially released."