

 |
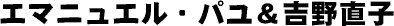 |
| 吉田ヒレカツ |
2004年11月17日・仙台電力ホール
(2004/11/18記)
 |
| これは当初のチラシです。 |
まだ師走には間があるというのに、街中にクリスマス・ツリーのようなものを飾り、このイエス・キリストの生誕を祝う行事へ向けての準備を早々と行うというのが、最近のこの国の習わしなのであろうか。なにやら今年は青い色をした電飾が流行りのようで、その、いかにも冷ややかな光には、この行事で祝うべき対象には全く興味のない輩が、ただ商魂を丸出しにしているという心根の卑しさが反映されているのでは、と感じるのは、私だけかしらん。そんな人工的な演出に満ちた繁華街の喧噪から通り1本隔てたところにあるのが、今夜の演奏会の会場の電力ホールである。以前、パユが弦楽器とのアンサンブルを披露してくれたのもこの会場であるし、同じ世代の日本のフルーティスト、瀬尾和紀がギターとの二重奏を聴かせてくれたのも、やはり、仙台ではおそらく最も長い歴史を誇っているこのホールであった。
この演奏会、当初予定されていたハープの安楽真理子が、突然来日(メトロポリタン歌劇場の奏者である彼女はアメリカ在住)出来なくなってしまい、吉野直子に変更になるという旨が、主催者から告げられていた。なんでも東京での演奏会はそのために中止になってしまったということである。この日の会場がほぼ満席という状態であったのは、もしかしたらそのような事情から、わざわざ東京あたりからやってきた客がいたせいなのかもしれない。なにしろ、前回モーツァルトの四重奏曲などが演奏された時などは、同じ会場が半分ほどしか埋まってはいなかったのだから。なにはともあれ、満員の聴衆の中でのフルートの演奏会などは、この仙台では異例とも言えるもの、やはり、この青年フルーティストの人気というものは、飛び抜けて高いことが実感されたものだ。
しかし、その、会場を埋め尽くした聴衆の中には、いささかこの場には相応しくない向きも混じっていたのではないかという印象は、ぬぐい去ることは出来ない。まず、開演前に後の方の席で立ち上がって大声でがなり立てる人がいたのには驚かされた。どうやら携帯電話の使用をたしなめる意図であったようなのだが、その、あまりに傍若無人な態度には、怒りさえおぼえたものだ。さらに、今回主催者が用意した曲目紹介の冊子が、なんと普通の薄っぺらな紙の表裏にただ複写しただけのものだったのにも、情けなさは募る。そのような安価な造りであるから、手にとって読んでいるだけでもかなりの音を発するし、それを会場の全員が行えば、とてつもなく盛大な音響がわきおこることになるのである。そのことに気付いた私は、もちろん演奏曲目は周知のものばかりであったから一切見る必要もないこともあって、早々に持参していた袋の中にしまっておいたのだが、演奏会を解説とともに味わう勉強の場だと信じ切っている無知な聴衆には、そのような配慮など望むべくもないのは明白なことであろう。彼らは曲の合間合間にこのお粗末な冊子に印刷された文章を読もうと試みた結果、あたかも会場の中で大雨が降っているかのようななんとも耐え難い雑音を発し続けていたのである。ある時などは、いざ、演奏を始めようと一旦楽器を構えた演奏家たちが、あまりの無神経な騒音に耐えかねて、曲を始めることを放棄するといった屈辱的な場面すらも見られたのである。そして、これはあるいは致し方ないことなのかもしれないが、演奏中に咳払いが多く聞かれたのも、著しく感興をそぐものであった。たとえ我慢が出来ないほどの咳であっても、万策を講じて出さないようにするのが、演奏会における一つのマナーであると私は信じてきたのであるが、遠慮のかけらもみせず、堂々と何度も何度も精一杯の力を以て咳払いを発している人間を見ると、どうもこの会場にはパユと吉野のファンばかりが集まっているのではないことが、如実に分かってしまう。
さあ、パユの登場である。吉野の桃色の衣装に合わせたのだろうか、蜜柑色のネクタイが非常に印象的である。せり上がった額を隠そうともしない潔さも、遠目にもはっきり分かる腹部の突出ぶりを見ると、納得できるというものだ。声楽家同様、管楽器奏者は体も楽器の一部なのだから、太鼓腹を恥じる理由など何もないのである。その代わり、彼には余人には代え難い流し目の魅力がある。時折客席を眺め回すその視線のなんとも色っぽいこと。これでは、若い女子が惹きつけられてしまうのも納得だ。
前半の曲目はバッハと武満徹という、ユニークなものだった。最初に演奏された、本来はリュートのためのハ短調のパルティータが、今まで抱いてきたパユの印象を裏切らない、いかにも洗練された軽やかな音と、柔らかなアタックで始まった時、このフルーティストは、以前のモーツァルトの時に見せていた自己の主張、あるいは「思想」と言い換えても構わないものを、さらに推し進めていることが確信された。殆どビブラートのかかっていない、それでいて華やかさが失われていない不思議な響きは、まるでバッハが生きていたバロック時代の楽器がそこで奏でられているかのような錯覚に陥らせてくれるものであった。もちろんパユが使っているのは金製の現代の楽器なのであるが、凡庸なフルート奏者が力一杯鳴らすような部分でも、彼はいともさりげなくふんわりとした音で対処しているのである。ただ、そのような音と、彼が作り上げようとしている表現の間に、何か違和感のようなものが感じられるのは、どうしたことだろう。それに対して、ハープの吉野は、本来は普通の鍵盤楽器のためのパートを、まるで最初からハープのためのものであったかのような恐るべき演奏を見せてくれていた。
次のやはりバッハの無伴奏パルティータとの間には、エリック・サティの曲を武満徹が編曲した「星たちの息子」が演奏された。ここでは、パユの何人にも代え難い弱音の魅力が、遺憾なく発揮されることになる。と同時に、バッハの曲の間にこの曲を置いた意味も、痛いほど伝わってきたものだ。このサティで見せた蒸留水のような淡泊な音で、次のパルティータが始まったのだから。この組曲も、まさにパユの意図が隅々まで徹底した演奏であった。中でもサラバンドで見せた自由自在な装飾には、光るものがあった。
そして、前半の最後はアルトフルートに持ち替えての武満の「海へⅢ」であった。パユが吹くアルトフルートは生では初めて聞いたが、もちろん普通のフルートと同じ「思想」で貫かれていることはいうまでもない。特に、聴き取れるか聴き取れないかというほどの超絶的な弱音といったらどうだろう。この曲は、今回キャンセルを余儀なくされた安楽と、エミリー・バイノンとの共演を実際に聴いたことがあるが、それとは全く異なった趣、あちらの色彩的な魅力に対して、こちらは何か「禅」あたりにも通じようかという極めて深刻な側面を引き出していたのが印象的だった。
後半は、この組み合わせでの名曲集といった趣である。まず、ある程度予想されたことではあるが、フォーレの「ファンタジー」が、とてつもない弱音で始まったのには、いささか驚かされたものだ。しかし、それよりも驚嘆したのは、ハープが主導権をとっている部分での徹底した引き方である。とてつもなく難しいパッセージを、あくまでさりげなく、殆ど聞こえないように吹ききる技量は、まさに驚嘆に値するだろう。次のドビュッシーの「小舟にて」が、やはり今まで他の演奏家では聴いたことのないような徹底した弱音で始まっても、もはや驚くことはない。これが、パユの「思想」なのであろうから。ラヴェルの「ハバネラ」では、オクターブ間の実に滑らかな音の移動が、殆どこの楽器の特性を無視しているほど滑らかに行われ、更なる驚嘆の念に駆られるのであった。
ここで、次は各々の独奏となるため、一旦二人とも退場となる。そして、パユ一人が舞台に登場するとともに、照明が落とされるという演出で、ドビュッシーの「シランクス」が始まった。このアイディアは、実は以前のこのホールでの瀬尾和紀の演奏会の時にも取り入れられていたものである。ただ、瀬尾の場合は客席の非常灯もすべて消してしまって、文字通り完全な闇を作っていたので、その効果は絶大なものがあったが、今回はなぜか非常灯は点いたままであったため、ぼんやりと演奏者が見えてしまうという、かなり間の抜けたものになってしまっていたのは残念だ。高音の「ミ」の音を出し損なうという、およそパユらしからぬ失態を演じていたのも、その間抜けさを増強させることになっていたのではないだろうか。その後、ハープ独奏による「月の光」そして再び二重奏で「アラベスク第1番」、「美しき夕暮れ」といったドビュッシーの名曲が続いていくのだが、いささか緊張感に乏しいものに感じられたのは、この痛恨のミスのせいだというのは、少しうがった見方かしらん。
ところが、このあとにハープ独奏でフォーレの「即興曲」が始まった時、
会場の空気はガラリと変わってしまった。そこには、この演奏会が始まってからこれまでついぞ聴くことの出来なかった、真の意味での「生きた」音楽があったのである。揺るぎないテクニックと、湧き出る情熱で訴えかけようとする心情の吐露、この1時間ほど、もしかしたらこの演奏会では求めてはいけなかったのではないかと思っていた「音楽の喜び」が、この曲の中には確かに存在していたのである。先ほどまで絶え間なく続いていた無神経な咳払いも、この曲の間は1度も聴くことがなかったという事実が、いかに、この演奏に何もかも忘れて没頭できるだけの魅力があったかを、如実に物語っているのではないだろうか。
最後のドップラーとザマラとの共作になる「カジルダ幻想曲」も、この名演のあとではいささか精彩を欠くことになってしまった。あまりにも淡泊すぎる音、それでいて自然な流れに背くような音楽の運びというパユのフルートがほぼ2時間にわたって鳴り響く場というのは、実はそれほど居心地の良いものではないという事実に、そろそろ私の方が気付いてきたのだろうか。しかし、最後の煌めくような音階の応酬では、ようやくフルート本来の魅力に触れられたような気持ちにもなった。
熱狂的な拍手に応えて演奏されたアンコールは、当初の曲目として入っていたイベールの「間奏曲」であった。なんでも、この演奏会のテレビコマーシャルでこの曲が使われていたということで、これを期待して訪れた聴衆は、やっとここに来て溜飲を降ろしたことだろう。
パユのフルートというものは、もしかしたら今までのフルーティストが作り上げてきた概念とは全く次元の異なるものなのかもしれない。そしてそれは、おそらく現在よりさらに進化した未来のフルーティストのあるべき姿なのかもしれない。しかし、私にとってはそんな未来など願い下げである。いかに時代が進もうが人間の情感のありようなどはそうそう変わりようがないはずなのである。いかに古いといわれようが、私の中には心の琴線に触れる音楽をなによりも大切にしたいという思いが厳然として存在している。2時間以上に及ぶこの演奏会の中で、パユの演奏は、一度として私の心の深い部分に届くことはなかったのである。そう、まるで演奏会の前に見た、あの青く冷たい光を放つクリスマス・ツリーのように。







