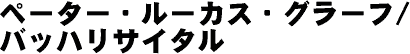|
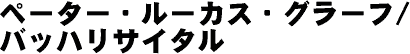 |
| 吉田ヒレカツ |
2001/9/3記
今年も、「仙台バッハ・アカデミー」の季節がやってきた。昨年の今ごろも、このアカデミーの講師として来日したペーター・ルーカス・グラーフのモーツァルトを聴いて、とても豊かな音楽を体験できたのだが、今年のプログラムのメインはバッハ、また違った楽しみが味わえることを期待して、会場に足を運んだ(9月2日・名取市文化会館中ホール)。交通の事情から、ホールにたどり着いたのは開演の直前であったのだが、ロビーでは私の若い友人である瀬尾和紀君が待っていてくれた。以前彼のリサイタルの批評を書いたことがきっかけで知己となったのだが、なんでも山形の蕎麦を食べるためにわざわざ休暇を取って、パリからやってきたということであった。
さて、今回のグラーフのリサイタルであるが、まず、プログラム・ビルディングからして特異なものである。休憩をはさんだ前半、後半とも、バッハのソナタが2曲ずつ演奏されるのだが、それぞれの間に、前半はドビュッシーの「シランクス」、後半は福島和夫の「冥」という、無伴奏の曲が入っているのである。バッハとは全く異なる語法によって語られるこれらの小品が、リサイタルの中でどのような存在価値を主張するのか、そのあたりも聴き所といえよう。
最初に演奏されたのは、ト短調の、ほとんど間違いなく偽作と確定されているソナタ。昨年のモーツァルトの場合もそうであったが、グラーフという演奏家は、コンサートの最初の曲の一番最初の音から、強烈な自己主張を持って聴衆にある種の挑戦を仕掛けることを生き甲斐としているのではないか。ついそんな考えを抱かずにはおかないような、独特なフレージングで開始された第1楽章は、思いがけないダイナミクスや煌くような装飾で、まさにグラーフの手の中で踊りまわらされているような錯覚に陥ってしまう。続く第2楽章も、譜面づらは起伏の少ない穏やかなものだが、グラーフの手にかかると、いたるところに斬新なアイディアを発見しないわけには行かないような豊かな音楽に変貌する。1例は、幾度となく繰り返されるロングトーン、伸ばしている音のどこを切ってみても違う表情が現れるという、まさに金太郎飴とは正反対に位置する様相を味わえたものだ。
2曲目の「シランクス」は、幾分ゴツゴツした、ということは、バッハの中に置かれても全く違和感のないドビュッシーであった。感覚に訴えることを潔しとしない、あくまでドビュッシーの持つ構成感を重視した解釈、演奏であった。
そして、前半の最後は、大曲のロ短調ソナタ。紹介するのが遅れてしまったが、この演奏会での伴奏楽器はチェンバロではなくピアノ、もちろんコンサートグランドであった。音量的なバランスは保つために、蓋は完全に閉じられていて、ピアニストは左のペダル(ウナ・コルダ)を踏みっぱなしという状態であったから、この曲のようにピアノとフルートが対等の立場で主張し合わなければならないものでは、どうしてもピアノの音楽が控え目になってしまう。グラーフの変幻自在の音楽について行こうというピアニストの努力はかなり見られたが、やはりフルートだけが目立ってしまったという印象はぬぐえない。
このソナタも、一瞬たりとも気を抜けない、他の演奏者では聴くことのできないようなアイディアがびっしりと詰まった濃厚なものであった。もちろんメカニックは完璧だし、ブレスコントロールは見事としか言いようがない。そう、確かに見事な演奏であるし、音楽を通して訴えかけようとしているものには、とても大きなものがあるということは痛いほど伝わってくることはまちがいのない事実なのである。しかし、音楽を享受する際には、その先に聴き手の主観というものが関与してくるのは避けることはできない。ここで敢えて私の主観を引き合いに出させてもらえるのならば、もっと流れに逆らわない心地よさを味わわせて欲しかったという不満は残る。
後半に移ろう。最初はハ長調のソナタ、やはり偽作とされているものである。これも、先ほどのト短調に通じるような自由な発想にあふれており、退屈する暇などさらさらない、興味深いものであった。
そして、「冥」である。かのガッツェローニのために作られたフルートソロのための曲、もはや現代音楽の古典として、様々なフルーティストがこの曲からそれぞれの魅力を引き出していることはご存知であろう。ポルタメントや微分音を多用した、極めて演奏の難しい曲で、一歩間違えば、単なるテクニックのひけらかしに過ぎなくなってしまうやっかいな作品ではあるのだが、グラーフはここから見事に共感のできるものに具現化してくれていた。四分音の必然性であるとか、ホィッスル・トーン(文字通り「口笛」で代用)がそこに置かれている意味であるとかが、これほど明確に伝わってきた演奏を、私は知らない。フルートの最低音であるCの最後の音が、音色の変化とともに減衰していってついには静寂が訪れた瞬間の美しかったことといったら。
この演奏を聴いたあとでは、最後のホ短調のソナタの世界に入り込むには、いささかの躊躇が伴われたことは、告白しなければならないだろう。しかし、第3楽章になった頃には、大胆なルバートが生み出す緊張の一瞬を楽しむ余裕も出てきたというものである。
ここで、この完全無欠とも見える音楽家にもやはり人間としての弱さがあるのだということを知らしめてくれたハプニングをご紹介しよう。この曲も最後に差し掛かったあたりで、グラーフはおそらく汗のせいで楽器と口元との具合が悪くなったとみえて、休みのない箇所で強引に楽器を口から離して汗を拭ってしまったのである。もちろん、次の音を出すタイミングには間に合わず、ついに音が抜けてしまったという訳であるが、なぜかほほえましくも感じられてしまったものである。
アンコールでは、一晩のコンサートを終わっても、まだ余力があるのだと誇示しているかのように、先ほどのハ長調ソナタの第3楽章が、2割程度速いテンポで演奏された。今年72歳を迎える演奏家には、「老い」などという概念は通用しないのではないか。それどころか、作り上げられた音楽は、「老成」とか、「円熟」といったような言ってみれば温和なイメージとは程遠い、攻撃的で力みなぎるものである。彼の音楽からは、同世代の指揮者、ニコラウス・アーノンクールのように、いつまでも前進する姿勢を忘れない強靭なものを感じないわけにはいかないのである。