|
【2003/09/08】
「党や政府幹部の子どもには、男の子が多い」
SARS騒動が一段落したこの夏、子どもを授かった母親が検診で通う上海の病院でこんな噂を耳にした。農村では男の子どもが多いとは聞いていたが、党や政府の幹部にも男の子どもが多いという話は初めて聞いたと、その女性は言う。
しかし、10年ほど前、アメリカのプリンストンに本部を置く中国の民主化団体がすでにこの情報を取りあげていた。指導部の詳細な家族構成はめったに公表されることがないため、確固たるデータは示されていなかったが、民主化団体のメンバーには党や政府中枢でブレーンとして働いた人物も少なくなく、直接見聞した内部情報を根拠としてあげていた。
だが、中国の人口構成で男の子どもが多いというのは、党や政府の幹部に限ったことではない。成人男子を含め、全ての省、直轄市、自治区において男の人口が女を上回っていることが国勢調査で明らかになっている。
2000年に行われた第5次「全国人口普査公」(国勢調査)によると、中国の総人口は12億6,583万人(香港、澳門は含まず)。このうち男が6億5355万人 、女が6億1228万人。男女比では男52%、女48%。女を100人とする性比では男106.7人になる。
地域別性比で最も男の比率が高いのは広西壮族自治区で112.7人、ついで雲南省と貴州省が110.1人、海南省が109.8人、北京市が109人と続く。逆に男の比率がもっとも低いのは山東省で102.5人。
日本の法務省統計局発表の資料(2001年)によれば、性比で男の人口比が高いのはインドの106.4人、バングラデシュの106.3人に続いて、中国は3番目の105.8人。人口3000万以上の国で男の人口が女を上回っているのはいずれもアジアとアフリカ地域の国となる。
一方、日本の人口性比は95.7人。日本と同じように男の人口が女より少ないのは、アメリカの97.30人、イギリスの97人、ドイツの96.10人、フランスの95人など、欧米に集中する。世界の性比の平均は、女100人に対して男105人ほどとされる。これを規準とすれば、平均値を示しているのは上海市、浙江省、吉林省など10省市程度に過ぎない。
革命や戦争、政治運動、海外流出などで男女別構成に変化が生じながらも、1949年の新中国建国以来、中国は一貫して男の人口が女を上回り、性比は105人前後で推移している。
なぜ中国では、男の人口が多いのか。その回答として中国政府の動きが指摘される。今年、政府は国務院機構を改革し、国家計画生育委員会を国家人口・計画生育委員会に名称変更した。
この理由として、独生子女(一人っ子)政策を継続し人口増加を引き続き抑え込むとともに、新生児の男女比率の偏りを抑制するためだとする。つまり、中国政府も男女比で、とりわけ新生児や若年層に不自然な傾向強いと認めていることになる。
日本も年齢別性比で見ると、48歳までは男の人口の方が多く、特に0歳から23歳までは常に105人代にのぼる。最大値は21歳の106.3人(2001年10月1日現在)。 しかし、地域の総人口の平均値とはいえ、広西壮族自治区のように性比が112.7人というような極端な比率になるのは、専門家からは人工流産などが恣意的な動きが日常的に行われてきたためだと指摘されている。
伝統的な男尊女卑の価値観とともに、一人子政策で子どもが1人しか産めないために、なんとしても男の子どもをと望む傾向が強い。このため地域によっては、出生前の性別検査禁止通達を出しているところもある。
先に上海の主婦の友人の中にも、出生前の性別検査で女児だと判明し、産むべきかどうか迷ったと告白する主婦もいた。一人子政策の結果、今世紀半ばには日本をしのぐ高齢化社会が到来すると言われる中国。このまま突き進めば、高齢化とともに自然な性比とはほど遠いアンバランスな社会にもなりつつある。
|
| |
|
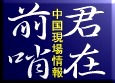
※
君在前哨/中国現場情報
 トップ・ページへ 返回首頁 トップ・ページへ 返回首頁
※
|
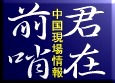
 トップ・ページへ 返回首頁
トップ・ページへ 返回首頁 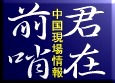
 トップ・ページへ 返回首頁
トップ・ページへ 返回首頁