|
〔023〕 自転車から車へと急速に変わる都市部の移動手段
|
|
【2003/02/16】
朝夕のラッシュ時、自転車通勤の人波で道路があふれる光景は、すでに過去のものになりつつある。現在、中国の都市部では、自転車から車、それも自家用車へと個人の移動手段が大きく変わろうとしている。
しかし、自動車の生産や販売台数、あるいは保有率の急上昇ぶりは日本へもさかんに伝えられているが、モータリゼーション化の大きなうねりに連動するもので見過ごされがちなのが免許取得の動きだ。
10年ほど前まで、中国で車の免許を持っているのは運転手など、限られた専門職の人たちだった。そのため、車の購入もさることながら、現在、免許取得に人々は大きな関心を寄せている。
中国語で自動車教習所は「駕校」という。都市部周辺にはこの駕校が次々と開校され、24時間電話対応サービスや送迎バスを用意するなど生徒集めの競争が激化。さらに各校とも自社のホームページを製作し、サービス内容をアピールし始めている。
普通車の免許取得の教習料は平均3000元から4000元(1元=約15円で、約4万5000円から6万円)、約60時間程度の講習を受けて免許を取得するのが一般的だ。
自家用車の購入に中国人が感心を寄せ始めたのにはさまざまな理由がある。昨年(2002年)秋に、中国は世界貿易機関(WTO)に加盟。これにともない排気量3リットル未満の輸入車の関税が70%から40代に引き下げられた。さらに、2005年には輸入枠が撤廃される予定だ。
このため、中国国産メーカーは輸入車に対抗するため相次いで値下げを断行、価格競争が激化し購買意欲を刺激している。
北京、上海には地下鉄があるとはいえ、公共交通機関の主体はまだバスに頼らざるを得ないのが実情だ。東京の感覚では地下鉄やJRを利用すれば30分ほど行ける距離感のところを、バスを乗り継ぎ1時間半近くをかけて通勤する人も珍しくない。
こうした実情からも、自家用車購入へと人々は動き始めている。地方都市にある外国語大学を卒業し、北京大学大学院へと進み、日本に留学してきた中国人が、数年前、北京に戻って友人たちと再会したときのこと。
外国語大学を卒業した級友の多くは外資系企業に就職し、約束の場に自家用車で駆けつけ、全員がスーツ姿だった。一方、北京大学大学院時代の同級生のほとんどは大学に残り研究者への道を進んだ。彼らはかつての姿のまま自転車でやって来た。このあまりにも対照的違いに、生活格差の開きを思い知らされたと述べたことがある。
ところが、最近の「人民日報」の報道では、自動車の新規登記に占める自家用車の割合は60%を占め始めているという。
最近では、「経済型較車」、いわゆる大衆向け乗用車が多数発売され、1万元(約15万円)から1万5000元(約22万5000円)という大幅値下げを行うメーカーも表れ、標準タイプの車体価格が8万元(約120万円)程度の車種も販売されるようになった。
通常、この価格帯の車種を購入する場合、頭金が3万元程度、残りを5年ローンで組むのが一般的だとされる。しかも、車の買い換えも頻繁に行われるようになり、中古車も出回るようになってきた。
都市部の住民が中心とはいえ、自転車組だった人々が車組へと変わる速度は、ここ数年の間にますます加速されそうだ。
|
| |
|
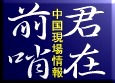
※
君在前哨/中国現場情報
 トップ・ページへ 返回首頁 トップ・ページへ 返回首頁
※
|
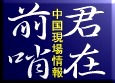
 トップ・ページへ 返回首頁
トップ・ページへ 返回首頁 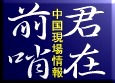
 トップ・ページへ 返回首頁
トップ・ページへ 返回首頁