|
〔022〕 胡錦涛新政権でもゆるまない言論への締めつけ
|
|
【2003/02/09】
昨年(2002年)11月の第16回中国共産党全国代表大会で、党総書記が江沢民から胡錦涛へ引き継がれ、2100人を超える代表の中に私営企業の経営者6人が初めて参加するなどして、国民政党へと変化する中国共産党を印象づける報道が日本では一部でなされた。
だが、大会から3ヶ月が過ぎ、北京の夕刊紙記者は「予想通りのこと、変化の兆しは皆無」と伝えてきた。彼は大会閉幕直後に、改革・開放による市場経済化の浸透を受け、変わりつつあるのは経済政策に限られ、表現の自由に関してはまったく期待できないと分析した。
「大会開催前の時点で、我々を取り巻く環境は決まっていただけに、中国のメディア関係者は醒めた目で大会の成り行きを見続けていたんだよ」
というのも、新聞を始めとして各メディアを監督する機関の人事は、大会以前に決定済みだったためだ。
大会一ヶ月前の10月に、党中央は1992年から中央宣伝部部長を務めてきた丁関根に代え、新たに劉雲山(55)を任命した。
中央宣伝部の正式名称は、中国共産党中央宣伝部という。党の思想や路線などを伝え教育する組織として、建国以来、党中央の重要な一機構と位置づけられてきた。このため、中央宣伝部長は党の公式イデオロギーの代表者であり、歴代部長には保守派幹部がおくられてきた。前部長の丁関根も鄧小平や江沢民からは信任が厚かった、だがメディア関係者からはもっとも嫌われていた。
新たに中央宣伝部部長となった劉雲山は漢族だが、内モンゴル自治区で師範学校を卒業して以来、同自治区で党員として経験を重ね自治区の党委常任委員や副書記などを歴任、1993年から中央宣伝部副部長を務めてきた。
内モンゴル自治区での劉雲山の手腕を知る記者は、党官僚としての活動経験しかなく、上層部の通達のままに動き、政治姿勢は前任者にひけをとらない保守派だという。丁関根が中央宣伝部部長に就任した翌年に劉雲山は副部長になった間柄だけに、この人事は世襲と同じ意味合いしかないと、その記者は見ている。
この中央宣伝部トップの人事異動の前には、国務院直属機関の国家広播電影電視総局(放送・映画・テレビ総局。以下、広電局)局長も、田聡明から徐光春に代わった。
広電局は文字通りラジオ、映画、テレビを管理する中央官庁で、1998年3月の国務院機構改革で日本の国会にあたる国務院の直属機関となった。だが、実質的には中央宣伝部、つまり党の指揮下にあるとされている。
徐光春も丁関根の下で中央宣伝部副部長を務めた人物であり、共産党中央の直属で主に知識層向けの全国紙「光明日報」の元編集長でもあった。
劉雲山と徐光春は、第16回党全国代表大会で中央委員に選出された。さらに、中央委員会による第1回全体会議で新しい24人の中央政治局委員らが決定され、劉雲山は中央政治局委員とともに中央書記処書記にも選ばれた。
先の北京の夕刊紙記者は、「この人選こそがメディアに対する姿勢を雄弁に語っている」という。
北京のテレビ局で報道企画番組にたずさわる記者は、毎週初めに開かれる会議を苦痛に感じている。というのも、会議とは名ばかりで、一方的に報道に関する禁止事項が命令のように伝えられるためだ。
しかも正当な理由として社の上層部が認めない限り欠席は許されず、欠席すれば勤務評定に記すとして、出席を強いられているという。
「不正や汚職を取材しても、番組で伝えられるのはあらましだけ。その背景まで踏み込んでも放送されない。社の上層部が握りつぶしてしまうからだが、実はもっと上の機関、広電局や中央宣伝部からの指示が働いているとしか考えられない」
不正や汚職報道は、一般市民のガス抜きにしかなっていない、突っ込んだ取材をすれば共産党の体質に行き着くだけに、党や政府は従来の報道規制をゆるめることはないだろうという。
パリに本部を置く国際ジャーナリスト団体「国境なき記者団(Reporters Without Borders)」は昨年10月に、世界139ヵ国・地域の報道の自由度を示すランキングを発表した。
この調査結果では、中国は最下位から2番目の138番目。番組や記事、作品の検閲のほか、メディア関係者の拘束、逮捕も中国では珍しくない。
ちなみに、最下位の139位は北朝鮮。日本は、フィンランドや南アフリカとともに26位。アジアで報道の自由度がもっとも高いとされたのは香港で18位だった。
|
| |
|
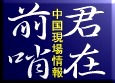
※
君在前哨/中国現場情報
 トップ・ページへ 返回首頁 トップ・ページへ 返回首頁
※
|
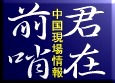
 トップ・ページへ 返回首頁
トップ・ページへ 返回首頁 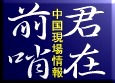
 トップ・ページへ 返回首頁
トップ・ページへ 返回首頁