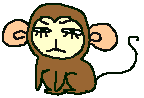
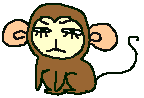
まずは、ある最近の体験から。
そのアイスクリームが運ばれてきた瞬間、こともあろうか私の心はその場になかった。通路を隔てた隣のテーブルでは、スペイン語では鳩のことを何と呼ぶのか、などということを家族連れが話していた。聞くともなしに聞こえてきた隣席の会話をバネにさらに跳躍した私の心は、モロッコはアトラス山脈の麓か、あるいはコーカサス山脈の麓か、どこか遠いところを浮遊していたようである。「心そこにあらず」のまま、自動人形のように動いた私の右手が匙で口に運んだヴァニラ・アイスクリームは、珍妙な味がした。山羊の乳でも、羊の乳でもない、これといった特徴のない獣の乳の味。チーズあるいはヨーグルト独特の匂いもしない。発酵させ忘れたのであろうか。数秒経ってようやく気づいた。ああ、ここは遊牧民の土地ではない。私が口に運んだのは、牛の乳から作られた氷菓子なのだ。そしてここは、西洋料理店の中なのだと。
我に返ってからも、最初に感じたアイスクリームの珍妙な味は口の中にまとわりついていた。本来楽しめたであろうはずのアイスクリームの味覚は、食事が終わるまで戻ってくることがなかった。
いったい、私の内部で何事が起きていたのであろうか。いまから思えば、心が異国の山脈の麓を漂流するあいだ、私の味覚は、埃っぽい戸外の明るい光線から遮蔽された静謐な屋内で新鮮な発酵乳に蜂蜜を振りかけて食べるときのそれに、知らず知らずのうちに波長を合わせてしまっていたとしか考えられない。
味覚の領域ではないが、これと似たようなことを別に経験したことがある。かつて外国で暮らしていたとき、ふと気がつくと一週間以上日本語を使っていないというようなことがあった。そんなとき、偶然入った料理店の隅のテーブルで食事をしている東洋人とおぼしき客同士の交わす会話が耳に聞こえてきた。それは、ペシャペシャ、クシャクシャとした音で構成されていて、当方には一言も理解できないことからも、アフリカのどこかの言葉に似ているようでもあった。
どのくらいの時間が経過してからであろうか、五秒だったかも知れぬし一分であったかも知れないが、突然、ある瞬間から、彼らの会話が分かるようになった。話されていたのは他ならぬ日本語であった。
インド料理ではなくタイ料理を食べに行こうという場合、タイ料理ファンならば、おそらく「タイ料理の構え」を独立して持っているに違いない。しかし、タイ料理に対する造詣がそれほど深くなく、スパイスが多いカレー料理の延長、ぐらいにしか思っていない人は、たぶん、「インド料理の構え」でタイ料理を味わうのではないだろうか。
例えば、こういう風に言えないだろうか。「遊牧民料理の構え」を持ったままフランス料理店に入ってしまうと、「西洋料理の構え」をもってすれば旨いと感じたはずの料理が、なぜか旨いと感じない。タイのカレーを何度も食べ続けるうちに、「インドカレーにしては変な味がするカレー」が次第に「美味しいタイカレー」に変化するのと並行して、その人の内部に「インド料理の構え」に加えて「タイ料理の構え」が形成されてくる。「関西料理の構え」をもって東北料理を食しても、珍妙な味がするだけであろう。つまり、ある料理を食してそれが美味しいか不味いかを決定づけるのは、料理が口に運ばれる瞬間に当の食事者がどのような「構え」をもっていたかに大いに依存するのではないか。
生まれて初めてフォアグラを食する経験をした人は、その味と食感を形容するのに困難を覚えるだろうが、そこに「和食の構え」を持ち込むことによって、「こってりした鮟肝のような食べ物」という言い方でフォアグラにとにかくも一定の座標を与えることができる。同じ伝で、ポルチニ茸は「肉厚の椎茸」として存在を確認される。
「構え」の果たした役割は集団社会の中でも確認できる。日本にはかつてフランス料理ブームなるものがあった。1970年から90年頃までであろうか。日本人は「西洋料理の構え」を身につけ、そのうちの多くの人は、日本的という制約の中でこそあれ「フランス料理の構え」をも獲得したと思われる。やがてイタリア料理が本格的に日本上陸を果たしたとき、これを熱狂的に迎えたのは、「フランス料理の構え」および「和食の構え」をもってイタリア料理を食し、これに「ソースがくどくなくさっぱりしている」、「素材の持ち味が生かされている」、「麺に腰があって美味しい」という評価を与えた人々であった。すなわち現在の日本のイタリア料理ブームを支えているのは、現代でいえば30?40歳以上の、イタリア料理に出会う前にフランス料理に感作された人々であったのだといえる。読者の皆さん、もしあなたがこの世代に属するなら、あなたはイタリア料理を楽しむときに、ひょっとして「フランス料理の構え」のまま食卓に向かい、フランス料理からのズレの感覚を楽しんでいるだけのかも知れない。かくいう私もこの世代に属するので、自分のなかの「イタリア料理の構え」が本物かどうか、甚だ自信がない。
もうひとつ別の例を示すなら、外国における和食の有りようが、やはり「構え」の集団的働きを示している。それは米国における和食と欧州の和食の違いに端的に現れている。米国における和食は、何はさておき低脂肪食であり、健康食であるのであって、実際に供される料理が日本に実在するのかどうかは問題にされない。米国における大衆和食は「米国料理の構え」のままで食してもそれなりに賞味できるようなものが人気を博す。一方、欧州における和食は、日本独自のスパイスや発酵製品を躊躇せずに用いる。また、消費者はある料理屋が日本の味そのままを出しているかどうか(オーセンティックであるかどうか)を常に気にしている。この違いはとりもなおさず、「米国料理の構え」を持っている人々と「西欧料理の構え」を持っている人々という、嗜好の違う消費者集団が異なる和食文化を誘導した結果と言えるだろう。
今回で「西洋料理店の楽しみ」は最終回を迎えたが、西洋料理の楽しみの根源は、いかに「型にはまって、型から出るか」に帰されると思う。型にはまる、とは、自分の中で「フランス料理の構え」、「プロヴァンス料理の構え」あるいは「トスカーナ料理の構え」を如何に育て、輪郭を磨くか、ということである。型にはまりきることによって、その中で、例えば、秀逸なアイスクリーム、ぎりぎり合格点のアイスクリーム、まずいアイスクリームという評価体系ができあがっていく。型から出る、とは、古典的な価値体系からのズレや跳躍を愛でる態度であり、それには食事者の方で故意に「構え」をずらしても良いし、あるいは料理の方において古典的な枠から飛び出すような冒険がなされてもよい。
そして、いつ、型に入り、いつ、型から出るのかを決めるのは、他でもない食事者自身の判断である。料理店では同席者とか、料理人とか、相手がいることであるから、自分勝手に妄想をたくましくすることは必ずしも勧められない。しかし、他者に説明可能な範囲内で、自らの欲望を開放し、一層の快楽を追求することこそ、生きている証なのではないだろうか。そこ息づくのは、我が儘ではない。楽しむぞ、という精神である。そのなかから、作る人と食べる人の交歓が生まれるであろう。
終
(1999年3月31日)
「第3回:食卓の脇役達」へのアッペンディクス
連載第3回を執筆後、目から鱗、舌から舌苔の落ちるような経験をしたので、追記しておきたい。高松市郊外にある饂飩専門店でのこと、いわゆる笊(ざる)饂飩を注文したところ、薬味の一つとしてレモンの櫛切りが添えられてきた。そもそも生臭みなどのないはずの饂飩にレモンとは異な物を出すものだと思い、騙されたつもりでレモンを数滴搾って見たところ、意外や意外、レモン汁が饂飩の中から無理矢理に小麦粉の生臭みを引き出し、それでいて、一旦引き出した生臭さをレモン汁が完璧なまでに成敗しているのであった。脱帽。