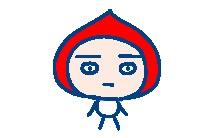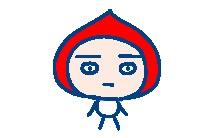連載:西洋料理店の楽しみ
第4回:ソースの話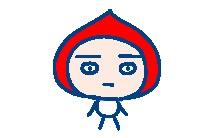
西洋料理といえば、ソースを語ることを避けて通るのは難しい。事実、肉、魚あるいは野菜といった主材料の下ごしらえよりもソースの調製の方に手間と時間がかかる料理が少なくない。なかには、主材料よりもソースの方に重きが置かれる料理すらある。たかが、ソース、されどソースである。
フランス料理の調理人が数日間かけてソース作りをする、あるいはソースの素になるソースを作り、あるいは出汁を取ることが稀ではない、ということはよく知られている。従って、食事をいただく方、すなわち客の側としても、ソースにこそ料理人の技量と思い入れが現れていると考えて、じっくりと味わうことになる。また、何をおいても、ソースと主材料の相性をとくと検分しないわけにはいかない。
ソース:その第三の楽しみ
さて、注文した料理がテーブルに運ばれてきたとしよう。客にとって、まず第一の楽しみは、皿の上の素材の配列や盛り方の工夫あるいは色合いを見ることである。第二の楽しみは、皿から立ち上る香気を鼻から吸い込み、それぞれの素材から立ち上る匂いの溶け合い混ざり合いを楽しむことである。ここまでは誰でもすることであろうと思う。いよいよ次の段階、それは行儀の悪い私ならではの行動であるが、右手の小指の先で軽くソースを掬い、その指先を舐めることである。これは、どのマナーブックにも出ていない。だから、他人には決しておすすめできないわけだが、では私がなぜそうするのかを説明しよう。
料理を味わう楽しみは、絵を見る楽しみに似ている。前に触れたように、料理が出てくる前からその先触れを楽しまない手はない。魚や甲殻類の料理を注文すると、捌く前の生き物を丸ごと見せに来る店がある。これには公正な取引履行の目的もあるが、客の期待感を高めるという大切な役割がある。そして料理が出来上がるや、テーブルのすぐ横で皿に取り分けてくれたりもする。こうして料理は目の前に立ち現れる。この一連の過程は、美術館での絵画鑑賞にたとえれば、長いギャラリーを歩きながら、遠くに小さくお目当ての絵が目に入ったときの感覚、そして一歩一歩歩みを進めて近づくうちに次第に絵画の構図や主題の輪郭、要素が少しずつ見え始めるときの様子に似ている。
一旦絵画に対面するや、しばらく全体を見、それから近づいて細部を見、そしてまた離れて全体を見、また近づいて先ほどとは別の細部に目を凝らす、これが絵を味わおうとするときに我々がとる自然な行動である。これと同じことが料理にも言える。皿の上で嗅ぐ香りはあくまでも料理の全体(の一側面)でしかない。また、料理の主材料とソースを絡めて食べるときの味覚、これも料理全体(の別の一側面)でしかない。物事を知るには、全体は全体で重要なのだが、部分も部分で重要なのである。長い話になったが、こういう理由で私は、思わず、ソースを舐めてしまうのである。
指に勝るものなし
ではなぜ、指でなければいけないのか。誰でも指を舐めるときには上下両唇の接合面に塗りつけ、次にそれを舌先で反復して擦るようにするが、これが一番よく味がわかる方法だからである。さもなければ、フォークの先端部分に若干ソースを付着させて運ぶとか、あるいはパンに染み込ませて口に運ぶという方法もあるが、なぜか前者では味が微弱だし、後者では、ソースの味がするにはするが、それはパンの塩味とか油だとかに被さったソースの味である。料理の構成要素としてのソースの味だけを確認するには、やはり指に勝るものはないようだ。
余談であるが、ご飯つきのカレーを食べるときも、やはり手で食べると美味しい。というより、ひと味違う。それはなぜかと考えたが、口に運ぶ前に飯の固まりをカレーと混ぜ合わせる行為の間に、カレーの成分が飯粒の全周にまとわりつき、そのために口に入れたとたんに味が炸裂するように舌に伝わる、それに、飯を噛めば噛むほどに味が引き立つせいではないかと思う。匙を使ってお行儀よく食べる場合には、あらかじめカレーと飯を念入りに掻き混ぜておかない限り、本当の味が出現するころには既に食べ物は喉を通り過ぎてしまっている。と口で言うのは易しいが、どうして、これも普通のカレー店で実践するには相当の勇気が必要で、万人には勧められない。
ドレッシングなるもの
全てのソースが手間と時間をかけて作るもの、あるいは暖かいものばかりではない。日本でドレッシングと呼ばれるサラダに味をつけて喉ごしをよくするための液体あるいはかなり固体に近い流動体、あれもフランス語ではソースという。いずれにせよ、ソースとはAとBという素材を組み合わせることによって、個々の元々の素材にはない、第三の味を追求する行為が凝縮させたものである。それ自体が料理の主材料と組み合わされることで、さらにまた一次元上の味を醸し出すことを狙っているのだから、ソースとは、まさに止揚法の魔術師のような存在であると言っても過言では無かろう。
さて、ソースの暖かいか冷たいかには関係なく、食事をするときに時に戸惑うのが、食べ終わったときに皿の上にソースを残してもよいのか、それとも、パンに付けて掬って食べてもよいのか、という問題である。
過ぎ去った感覚を求めて、、、
結論から言えば、これは三つの場合に分けられると思われる。第一に高級料理店の場合。気取った店では、たいていソースの分量は主材料の量に対して計算されてでてくる、というよりソースはどちらかというと常に少な目なので、そもそも問題が生じない。第二に庶民のための料理店の場合であるが、ここではソースは、これでもか、とばかりに皿の上に洪水を起こしていることが多い。質より量と言うわけか。このような店では他の客の目を気にすることも体面を憚ることもないので、滋味豊かなソースであれば、パンに染み込ませるなり何なり、好きなだけ食べることができる。不味いソースなら残せばよい。最後に、中間の料理店、これが難物である。私個人は、美味なソースであればパンに付けてなるべく残さずに食べることが多い。ただし、これは我ながら卑しい食べ方だと思う。なぜなら、その料理人が意図した本当の味、あるいは濃い密度の味というものは、主材料が皿から消えた時点でなくなっており、ソース付きのパンを食べるのというのは、本当の味の残像を追いかける行為だという気がするからである。そんなことをすれば、本当の味の記憶の輪郭を曖昧なものにしてしまう危険すらある。しかしながら、この世の中は綺麗事ばかりではないのも事実である。過ぎ去った感覚を未練がましく追いかけるというのも何とも人間臭い行為だという気がする。単なる言い訳か。
英国:出来合いソースの本場
ソースは調理人が主材料にあわせて特別に調製するものばかりとは限らない。ウスターソースに代表されるような出来合いのソースも多く存在する。調理人としての英国人にはソース作りの才覚がないので、非常に不味いソースを手間暇かけて作るより、美味とは言えないまでも市販のソースを買って済ませる方が理に叶っているのである、などという暴論を展開するつもりは毛頭ない。とはいえ、出来合いソースの故郷とでもいえるのは、やはり英国であろう。
甘美な揺り椅子:出来合いソース
出来合いのソースを侮ってはいけない。私個人の経験だが、英国系の航空会社の機内食で「ハニーマスタード・ソース」なるものが供され、その旨さに仰天したことがある。もちろん、塩や酢なども入っているが、文字通り蜂蜜と粒マスタードを主原料とするソースで、少し歯ごたえと苦みのある葉野菜と共に食して美味であった。その驚きがあまりに強烈であったため、後日、舌の記憶を頼りに似たようなソースを自作し、子羊のリブを漬け焼きにして食したほどであった。英国では、業者ごとに、一般的なソースから多少の独創性を凝らしたソースまで、各種販売されているようである。既成のソースは、一旦味に慣れてしまえば、もはや食べる人に嬉しい驚きを与える力はないが、新奇なものが与える刺激を有害なものとして遠ざけようとする精神、つまり、”Home
Sweet Home” の精神の持ち主には、無くてはならぬ揺り椅子であろう。
ソースは人を幸せにする。人生の幸福は、サラダボールの底にあるといったのは、たしかエミール・ゾラだったか。
(1999年2月11日)
次回最終回は「欲望の開放」。お楽しみに。