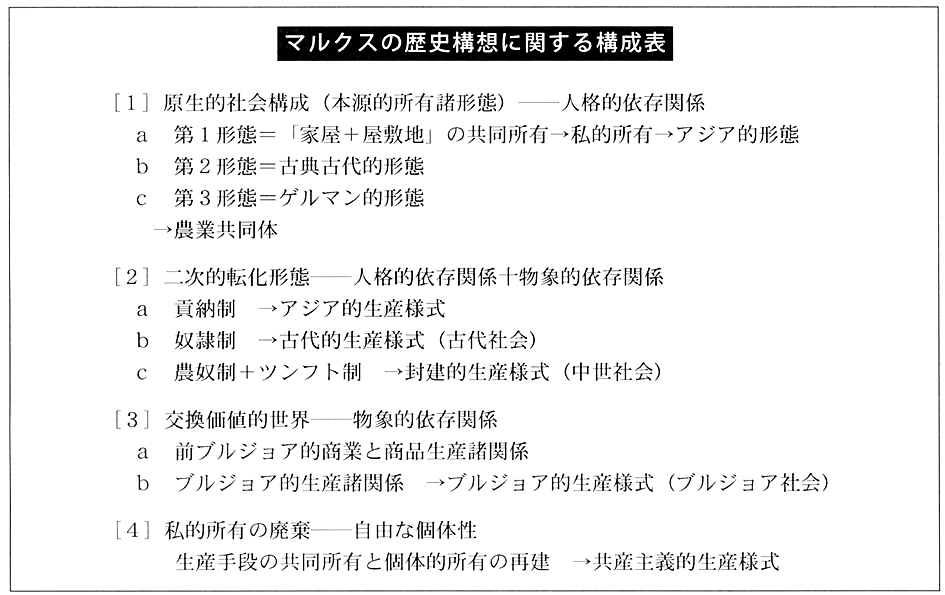HOME亜夁嫀崋亜92崋
尋媶夛曬崘丗嫟摨懱丒巗柉幮夛丒傾僜僔僄乕僔儑儞
丂儅儖僋僗偺嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑
丂偙傟傑偱丄恖娫偑桳巎埲棃偵宍惉偟偰偒偨懡條側幮夛傪偄偔偮偐偺儌僨儖偲偟偰奣妵偟丄乽尨巒嫟摨懱仺搝楆惂仺晻寶惂仺帒杮庡媊仺幮夛庡媊乿偺傛偆偵丄幮夛敪揥偺楌巎偲偟偰攃埇偡傞帋傒偑峴傢傟偰偒偨丅偩偑丄偦傟偼乽恑傫偩儓乕儘僢僷偺巗柉幮夛偲抶傟偨擔杮偺擾懞嫟摨懱乿偲偄偭偨傛偆偵丄儌僨儖偵夁偓側偄傕偺傪慡悽奅嫟捠偺婎弨偲懆偊丄奺抧堟偺幮夛偑傕偮嬶懱揑側撪梕傪柍帇偟偰丄堦曽揑偵彉楍壔偡傞寢壥偵傕偮側偑偭偨丅悽奅偑戝偒偔曄壔偟偮偮偁傞崱擔丄傢傟傢傟偼偙偆偟偨宱尡傪斀徣偟偮偮丄夵傔偰夁嫀乮嫟摨懱乯偐傜尰嵼乮巗柉幮夛乯偵帄傞幮夛儌僨儖偺楌巎揑側揥奐傪摜傑偊丄枹棃乮傾儕僔僄乕僔儑儞乯傊岦偗偰丄師偺幮夛峔憐傪揥朷偟偰偄偔抜奒偵偁傞丅偦傫側娤揰偐傜丄摉尋媶強偱偼崱擭搙偺抁婜廤拞尋媶島嵗偲偟偰乽嫟摨懱丒巗柉幮夛丒傾僜僔僄乕僔儑儞乿偲戣偟偰丄嶰夞偺尋媶夛傪幚巤偟偨丅崱夞偼偦偺戞堦夞丅嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑傪傔偖偭偰丄娭搶妛堾戝妛偺搉曈寷惓偝傫乮幮夛巚憐巎乯偵偍榖傪巉偭偨丅埲壓偼丄偦偺奣梫偱偁傞丅
偼偠傔偵
丂巹偼丄戝妛擖妛偺堦擭屻偵戝妛暣憟偑婲偒偨丄偄傢備傞抍嵃偺悽戙偱偡丅傕偲傕偲棟壢宯偱丄暔棟妛傪曌嫮偟傛偆偲戝妛偵擖傝傑偟偨偑丄帪戙晽挭偺拞偱丄偙傟傑偱偁傑傝偵幮夛偵偮偄偰抦傜側夁偓偨偲婥偯偒丄偦偙偐傜妛惗塣摦側偳偵傕娭傢傝傑偟偨丅妛惗帪戙偵偼儗乕僯儞偵擖傟崬傫偩偙偲傕偁傝傑偡偑丄懖嬈偡傞崰偵偼媈栤傪姶偠傞傛偆偵側傝丄偦傟偐傜儅儖僋僗側偳偺曌嫮傪巒傔傑偟偨丅
丂儅儖僋僗庡媊偼丄僄儞僎儖僗丄儗乕僯儞丄僗僞乕儕儞偲偄偆嬝傪捠傜側偗傟偽丄傕偭偲暿偺壜擻惈偑偁偭偨偼偢偱丄偦偺揰偼杮摉偵傗傝捈偟偑昁梫偩偲巚偄傑偡丅巹偺巇帠偼儅儖僋僗庡媊斸敾偺傛偆偵尒偊傑偡偑丄儅儖僋僗庡媊偐傜棧傟傞偲偄偆堄枴偱偼側偔丄傕偭偲傑偲傕側儅儖僋僗庡媊偱側偗傟偽側傜側偄偲峫偊偰尋媶偟偰偄傑偡丅
丂杮擔偺僥乕儅偱偁傞嫟摨懱乛嫟摨幮夛偵偮偄偰峫偊傞傛偆偵側偭偨偒偭偐偗偼丄2002擭崰偵強桳榑偵娭偡傞榑暥傪彂偔拞偱丄夵傔偰儅儖僋僗偺強桳榑偵惓柺偐傜庢傝慻傓昁梫惈傪姶偠丄亀宱嵪妛斸敾梫峧亁乮1857擭乣58擭幏昅丅埲壓亀梫峧亁偲棯乯傪撉傫偩偙偲偱偡丅撉傒恑傔傞偲丄彮側偔偲傕愴屻50擭偵傢偨傞擔杮偺嫟摨懱榑尋媶偺傎偲傫偳偵崻杮揑側寚娮偑偁傞偲暘偐偭偰偒傑偟偨丅
丂愴屻擔杮偺幮夛壢妛偺拞偱丄擾懞偺嫟摨懱揑側婯惂傪揚攑偟偰巗柉幮夛傪幚尰偡傞偲偄偆柆棈偱嫟摨懱偐傜巗柉幮夛傊偺堏峴傪榑偠丄嫟摨懱傪抶傟偨傕偺偲尒側偡嫟摨懱榑尋媶偑偁偭偨偙偲偼丄偛懚抦偩偲巚偄傑偡丅偲偙傠偑丄屻偱弎傋傑偡傛偆偵丄偦偺婎杮揑側挊嶌偱偁傞戝捤媣梇偺亀嫟摨懱偺婎慴棟榑亁傪偼偠傔偲偟偰丄偦傟傜偺亀梫峧亁嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑攃埇偼偙偲偛偲偔娫堘偭偰偄偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂懠曽丄嫟摨懱榑偵庢傝慻傓偙偲偼丄扨偵巚憐巎揑側堄媊偑偁傞偩偗偱側偔丄尰嵼幮夛偺徟揰偵側偭偰偄傞栤戣傪峫偊傞忋偱傕廳梫偩偲巚偄傑偡丅偲偄偆偺傕丄偙偺娫丄僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉乮嫟摨懱庡媊乯傗僫僔儑僫儕僘儉丄偁傞偄偼岞嫟寳榑傗巗柉幮夛榑側偳丄偝傑偞傑側宍偱嫟摨懱庡媊傪傔偖傞媍榑偑峴傢傟偰偄傞偐傜偱偡丅巹偼丄偙傟傜偺嫟摨懱庡媊偵懳偟偰斸敾傪傕偭偰偄傑偡偑丄嫟摨懱庡媊傪斸敾偡傞嵺偵偼丄儅儖僋僗偺媍榑傪摜傑偊傞昁梫偑偁傝傑偡丅偦偙偱崱夞偼丄儅儖僋僗偺嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑偵偮偄偰徯夘偟偨忋偱丄尰戙偺嫟摨懱庡媊傪偳偆昡壙偡傞偐偲偄偆弴彉偱恑傔偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅
侾丏亀宱嵪妛斸敾梫峧亁偺嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑
丂傑偢偼亀梫峧亁偺嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑傪尒偰偄偒傑偡丅偙偙偱巹偼乽嫟摨懱乿偱偼側偔丄乽嫟摨懱乛嫟摨幮夛乿偲偄偆尵梩傪巊偭偰偄傑偡偑丄偙傟偼丄堦斒偵乽嫟摨懱乿偲屇偽傟傞慻怐偺拞偵偼幙揑偵堎側傞撪梕偑娷傑傟偰偍傝丄偦傟傪嬫暿偟偨偄偐傜偱偡丅
丂幚偼丄儅儖僋僗偑亀梫峧亁偺拞偱嫟摨懱偵娭楢偟偰巊偭偰偄傞尵梩偵偼丄嘆Gemeinde丄嘇Gemeinwesen丄嘊Gemeindewesen丄嘋Gemeinschaft偺巐庬揯偑偁傝傑偡丅偦偺拞偱傕婎杮揑側嬫暿傪昁梫偲偡傞偺偼Gemeinde丄Gemeinwesen偱偡丅懡偔偺尋媶幰偼堦墳丄偦傟偧傟傪栿岅忋偱嬫暿偟偰偄傑偡丅Gemeinde偼偩偄偨偄乽嫟摨懱乿偲栿偝傟偰偍傝丄掕栿偲尵偊傑偡丅堦曽丄Gemeinwesen偼掕栿偑側偔丄乽嫟摨廤抍乿偲偐乽嫟摨抍懱乿丄偁傞偄偼乽嫟摨慻怐乿偲偄偭偨栿岅偑偁偰傜傟偰偄傑偡丅偟偐偟丄偙偺嬫暿偼晄揙掙偱偡丅
丂傑偢丄偨偲偊偽亀帒杮榑亁偺東栿偱偼Gemeinde偲Gemeinwesen傪嬫暿偣偢丄偡傋偰乽嫟摨懱乿偲栿偝傟偰偄傑偡丅偁傞偄偼亀僪僀僣丒僀僨僆儘僊乕亁偺応崌丄暈晹暥抝栿傕廰扟惓栿傕淎徏徛栿傕丄偄偢傟傕Gemeinde偲Gemeinwesen傪乽嫟摨懱乿偲栿偟偰偄傑偡丅偩偐傜丄擔杮岅偱撉傓尷傝丄擇偮傪嬫暿偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅
丂東栿偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅懡偔偺尋媶幰偨偪偼丄偣偭偐偔Gemeinde偲Gemeinwesen偵暿乆偺栿岅傪梌偊偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄撪梕揑偵偼嬫暿偣偢偵丄偡傋偰摨偠傕偺偲偟偰媍榑偡傞孹岦偑偁傝傑偡丅幙揑偵嬫暿偡傞昁梫惈偑暘偐傜側偄偐傜偱偡丅
丂偨偲偊偽戝捤媣梇偼丄Gemeinde傪乽嫟摨懱乿偲栿偟丄撪梕揑偵偼擾嬈嫟摨懱偲棟夝偟偰偄傑偡丅堦曽丄Gemeinwesen偼乽嫟摨慻怐乿偲栿偟偰偄傑偡丅偦偺忋偱丄偙偆尵偭偰偄傑偡丅乽Gemeinde偙偦丄Gemeinwesen傪崻掙偵傕偪丄帺屓傪嵞惗嶻偟偰偄偔庡懱偨傞傋偒幮夛娭學偱偁傞乿丅偮傑傝丄Gemeinde偼嵞惗嶻慻怐丄嵞惗嶻偟偰偄偔庡懱偱偁傝丄偦傟偵懳偟偰Gemeinwesen偼丄嵞惗嶻偟偰偄偔庡懱偱偁傞Gemeinde偺崻掙偵偁傞廤抍揑丒嫟摨揑側慻怐偩偲偄偆偙偲偱偡偹丅偦偟偰丄偙傟偲娭楢偟偰丄戝捤偼儅儖僋僗偐傜2売強堷梡偟偰偄傑偡丅傑偢亀梫峧亁偐傜乽恖乆偼嫟摨懱偺強桳偲偟偰偺偦偆偟偨戝抧偵慺杙偵娭學偡傞乿偲偄偆売強丅偦傟偐傜丄亀帒杮榑亁偺旕忢偵廳梫偱桳柤側売強偱偡偑丄傾僕傾揑側宍懺偵偮偄偰丄乽帺懌揑側嫟摨懱偑偨偊偢摨偠宍懺偱嵞惗嶻偝傟乿偲偄偆売強丅偙傟傪偦偺傑傑撉傓偲丄嫟摨懱偼嵞惗嶻偵娭學偁傞傛偆偵棟夝偱偒傑偡丅偲偙傠偑丄偙偙偱戝捤偑乽嫟摨懱乿偲栿偟偨2売強偲傕丄儅儖僋僗偺尨暥偱偼Gemeinwesen側傫偱偡丅偮傑傝丄傕偲傕偲Gemeinwesen偱偁傞晹暘傪丄戝捤偼Gemeinde偱偁傞偐偺傛偆偵乽嫟摨懱乿偲栿偟丄Gemeinde偼嵞惗嶻偵娭傢傞偲偄偆榖傪偟偰偄傞傢偗偱偡丅
丂寢榑傪尵偊偽丄幚偼Gemeinwesen偙偦嵞惗嶻偵娭傢傞傫偱偡丅偙偺嬫暿偼旕忢偵廳梫偱偡丅偵傕偐偐傢傜偢丄偦傟傪慺捠傝偟偰偄偨傢偗偱偡丅偁偺戝捤媣梇偱偡傜丄弌敪揰偵側傞婎慴奣擮偱廳戝側岆夝傪偟偰偄偨偺偱偡偐傜丄戝曄側偙偲偱偡丅
仭Gemeinde偲Gemeinwesen偺奣擮揑嬫暿
丂偱偼丄Gemeinde偲Gemeinwesen偼丄撪梕偲偟偰偳偆堘偆偺偐丅儅儖僋僗偼偳傫側応崌偵Gemeinde傪巊偭偰偄傞偐偲偄偆偲丄堦偮偼僊儕僔傾偺億儕僗嫟摨懱丄傕偆堦偮偼僎儖儅儞偺柉夛偱偡丅偙偺擇偮偺嫟捠揰偼丄傑偢抝惈偩偗偺慻怐偱偁傞偙偲丄彈惈偼偄側偄偲偄偆偙偲偱偡丅傑偲傔傞偲丄Gemeinde偼抝惈拞怱偺惌帯揑慻怐偲尵偊傑偡丅偦傟偵懳偟偰丄Gemeinwesen偼抝彈椉惈偐傜側傞宱嵪揑嵞惗嶻慻怐偱偡丅偙傟傎偳堘偆傫偱偡丅
丂変乆偑堦斒偵嫟摨懱偲尵偆応崌丄偍偍傓偹抝惈偲彈惈偑偄傞僀儊乕僕傪巚偄晜偐傋傞偼偢偱偡丅偲偙傠偑丄僊儕僔傾偺億儕僗傕僎儖儅儞偺柉夛傕丄抝偑巇愗偭偰偡傋偰傪寛掕偟丄彈惈偼娭梌偱偒側偄丅偙偆偟偨慻怐偑懚嵼偟偨偙偲偼楌巎揑帠幚偱偡丅偲偙傠偑丄偦傟偙偦偑乽嫟摨懱乿偩偲偟偰丄偙偺僀儊乕僕偱嫟摨懱榑傪峔惉偟偰偟傑偊偽丄彈惈傕宱嵪傕敳偗棊偪偨傕偺偵側傜偞傞傪摼傑偣傫丅
丂偙偙偱丄儅儖僋僗偺桳柤側尵梩傪擇偮嫇偘傑偟傚偆丅偨偲偊偽丄乽彜昳岎姺偼嫟摨懱偲嫟摨懱偺娫偱惗偢傞乿偲偄偆僥乕僛丅偙偙偱乽嫟摨懱乿偲栿偝傟偰偄傞偺偼偳偪傜偐丅傕偪傠傫Gemeinwesen偱偡丅彜昳傪惗嶻偡傞慻怐偼丄Gemeinwesen偱偡丅偦傟偐傜乽尵岅乮尵岅懱宯乯偼嫟摨懱偺強嶻偱偁傞乿丅偙偺応崌偺嫟摨懱傕丄傗偼傝Gemeinwesen偱偡丅偨偟偐偵丄惌帯尵岅側偳偼Gemeinde丄抝惈偩偗偱嶌傞偙偲傕壜擻偱偟傚偆丅偟偐偟丄擔杮岅偲偄偆尵岅懱宯偼抝惈偩偗偱偼晄壜擻偱偡丅
丂変乆偼堦斒偵乽嫟摨懱乿偲偄偆尵梩傪巊偄傑偡偑丄幚偼偦偺拞偵抝惈偩偗偑巇愗偭偰偄傞傕偺偲偦偆偱側偄傕偺偑偁傞偲棟夝偟偰弶傔偰丄彈惈傪娷傓慡懱偲偟偰偺嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑偑妉摼偱偒傞偺偱偡丅偟偐偟丄偙偺嬫暿偼崱傑偱曁傠偵偝傟偰偒傑偟偨丅偦偺寢壥丄彈惈傪娷傓宱嵪揑嵞惗嶻慻怐乮Gemeinwesen乯偺堄枴偱偺嫟摨懱傪僀儊乕僕偟側偑傜抝惈偺傒偺惌帯揑慻怐乮Gemeinde乯偵娭傢傞晹暘偺榑媍傪偟偰偄偨傝丄偁傞偄偼媡偵丄彈惈傪娷傓宱嵪揑嵞惗嶻慻怐乮Gemeinwesen乯傪榑偠側偑傜丄専摙懳徾偼抝惈偺傒偺惌帯揑慻怐乮Gemeinde乯偵娭偡傞婰弎偩偭偨傝丅偦偆偟偨崿摨偑墶峴偟偰偄偨偺偑丄偙傟傑偱偺嫟摨懱傪弰傞媍榑偱偡丅偙傟偼夵傔傞昁梫偑偁傞偲巚偄傑偡丅
丂幚嵺丄偙偺娤揰偐傜儅儖僋僗傪撉傔偽丄Gemeinwesen偺晹暘偵偼丄傢偢偐偲偼偄偊丄偒偪傫偲彈惈偑弌偰偒傑偡丅傑偨丄乽嫟摨懱偺夝懱乿偲偄偆帪偵丄儅儖僋僗偑憐掕偟偰偄傞偺偑Gemeinde偱偼側偔Gemeinwesen偱偁傞偙偲傕傛偔暘偐傝傑偡丅傑偢偼丄偙偆偟偨揰傪擮摢偵抲偄偰偄偨偩偒偨偄丅偦偺堄枴偱丄巹偼Gemeinde傪乽嫟摨懱乿丄Gemeinwesen傪乽嫟摨幮夛乿偲嬫暿偟偰屇傫偱偄傞偺偱偡丅偮偄偱側偑傜丄Gemeinwesen偼乽嫟摨懱惂搙乿丄Gemeinschaft偼乽嫟摨廤抍乿側偄偟乽嫟摨惂乿偲栿偟傑偡丅乮埲壓丄偦偺堄枴偱擔杮岅偺傒巊梡乯
仭亀宱嵪妛斸敾梫峧亁偺杮尮揑強桳宍懺榑
丂埲忋傪摜傑偊偨忋偱丄偱偼亀梫峧亁偺杮尮揑強桳乮仸乯宍懺榑偼偳偆棟夝偱偒傞偐丅
丂偙傟傑偱偺尋媶巎偺拞偱丄杮尮揑強桳偺戞堦宍懺偼丄偍偍傓偹乽傾僕傾揑宍懺乿偲栿偝傟丄棟夝偝傟偰偒傑偟偨丅偦偟偰丄偙偺傾僕傾揑宍懺偐傜戞擇宍懺乽屆揟屆戙揑宍懺乿傊丄偝傜偵戞嶰宍懺乽僎儖儅儞揑宍懺乿傊丄偲偄偆傛偆偵懆偊傜傟偰偒傑偟偨丅偟偐偟幚偼丄偙傟偼傑偭偨偔偺岆撉偩偭偨傫偱偡丅偲偄偆偺傕丄戞堦宍懺偼恖娫偑掕廧偡傞埲慜偺嫟摨幮夛傪娷傫偱偄傞偐傜偱偡丅偦偙偱偼丄乽傑偢傕偭偰堦庬偺帺慠惗揑側嫟摨幮夛偑嵟弶偺慜採偲偟偰尰傟傞乿偲尵傢傟偰偄傑偡丅
丂傕偪傠傫丄嫟摨懱偼懚嵼偟傑偣傫丅偦傕偦傕崙壠偑偁傝傑偣傫偐傜丅壠晝挿揑側娭學偑偁偭偨偲偟偰傕丄傑偩傾僕傾揑宍懺偵偼払偟偰偄側偄抜奒偱偡丅傾僕傾揑宍懺偼掕廧擾峩偑巒傑偭偰偐傜偺偙偲偱丄戞堦宍懺偼偦傟埲慜偺抜奒傪娷傫偱偄傞丅崙壠傪憐掕偟側偄傛偆側抜奒偱帺慠敪惗揑偵尰傟傞嫟摨幮夛偱偁傝丄抝惈偩偗偑巟攝偡傞惌帯揑慻怐偲偟偰偺嫟摨懱偼懚嵼偟側偄傢偗偱偡丅
丂偲偙傠偑丄恖娫偑掕廧偡傞傛偆偵側傞偲丄戞堦宍懺偺偁傝曽傕曄壔偟傑偡丅掕廧偑巒傑傞偺偼丄昘壨婜偺廔傢傝偑1枩擭慜偱丄杚抺偲擾峩偺奐巒偑6000乣7000擭慜偱偡偐傜丄偩偄偨偄偦偺曈傝偱偡丅柉懓偑宍惉偝傟傞偺偼偦偺屻偱偡丅掕廧偺巒傑偭偨忬懺偱偼丄傑偩崙壠偼懚嵼偟偰偄傑偣傫丅柉懓偲偄偆旕忢偵嬅廤惈偺崅偄廤抍偑宍惉偝傟傞偺偼丄4000乣5000擭慜偺偙偲偩偲尵傢傟偰偄傑偡丅偦偺崰偵旕忢側姳偽偮偵廝傢傟丄廤抍壔傪枾偵偟側偄偲恖娫偑惗偒巆傟側偄偙偲偐傜丄柉懓偲偄偆廤抍偑宍惉偝傟偨偲尵傢傟傑偡丅偩偐傜丄偦傟偲嫟偵崙壠傗巟攝奒媺偑惗傑傟偰偔傞偲偄偆弴彉偩偲巚偄傑偡丅
丂偦偺抜奒偱弶傔偰丄僗儔僽揑宍懺偲偐屆戙働儖僩偲偐丄偄偔偮偐偁傞宍懺偺堦偮偲偟偰傾僕傾揑宍懺偑栤戣偵側傝傑偡丅傾僕傾揑宍懺傪娙扨偵僀儊乕僕偡傞偲丄偄偔偮偐懚嵼偡傞彫婯柾側嫟摨幮夛偺忋偵丄偦傟傜傪摑妵偡傞傛偆側宍偱孨庡傗姱椈廤抍乮忋埵偺嫟摨廤抍乯偑懚嵼偟丄嫟摨幮夛偑偙偺尃椡偺枛抂慻怐偲偟偰偺嫟摨懱偵乮抝惈拞怱偵乯曇惉偝傟傞偲偄偆姶偠偵側傝傑偡丅奺抧堟偺搚抧傪愯桳偡傞偝傑偞傑側嫟摨幮夛偑偁傝丄偦偺忋偵嵟崅偺摑堦懱偲偝傟傞孨庡傗惌帯慻怐偑懚嵼偟偰巟攝偟偰偄傞丅
丂偩偐傜丄傾僕傾揑宍懺偱偼丄嫟摨幮夛偵傛偭偰側偝傟傞強桳偲丄偦傟傜傪巟攝偡傞憤妵揑側摑堦懱偵傛傞崅師偺強桳偲偄偆宍偱丄強桳偑擇廳偵側偭偰偄傞傢偗偱偡丅偙偙偱偼丄嫟摨幮夛偑忚梋惗嶻暔傪嵟崅偺摑堦懱偱偁傞孨庡側偄偟忋埵偺嫟摨廤抍偵峷擺偲偄偆宍偱嵎偟弌偡娭學偑惉棫偟傑偡丅儅儖僋僗偼丄戞堦宍懺偺婎杮偼傾僕傾揑宍懺偺拞偵傕娧偐傟傞偲尵偭偰偄傑偡偑丄偦傟偼丄忋埵偺強桳娭學傪奜偟偰傒傟偽丄嫟摨幮夛偑憡曄傢傜偢幚幙揑偵搚抧傪愯桳偟偰偄傞偐傜偱偡丅
丂師偵丄戞擇宍懺乽屆揟屆戙揑宍懺乿偍傛傃戞嶰宍懺乽僎儖儅儞揑宍懺乿偺榖偵堏傝傑偡丅偙傟傜偵偍偄偰嫟摨懱偼丄屆揟屆戙乮僊儕僔傾乛儘乕儅乯揑宍懺偺応崌偵偼億儕僗嫟摨懱偮傑傝崙壠偲偟偰丄僎儖儅儞揑宍帨偱偼柉夛乮愴憟傗嵳釰偺偨傔偵嵜偝傟傞廤夛乯偲偟偰丄偦傟偧傟棟夝偝傟偰偄傑偡丅
丂偱偼丄嫟摨幮夛偼偳偙偵偁傞偐丅偙傟偵偮偄偰偼丄僊儕僔傾側傜偽億儕僗嫟摨懱偲嬫暿偝傟傞僆僀僐僗偺椞堟丄偮傑傝搝楆傗彈惈偑幚嵺偵惗嶻妶摦傪峴偆椞堟偵偁傞偲傒傜傟傑偡丅偩偐傜丄儅儖僋僗偼戞擇宍懺偵偮偄偰傕丄乽晹懓慻怐偐傜攈惗偡傞嫟摨幮夛傪嵟弶偺慜採偲偡傞強桳宍懺乿偱偁傞偲弎傋偰偄傑偡丅嫟摨幮夛偑側偄偲嫟摨懱偑堐帩偱偒側偄偐傜偱偡丅摉慠偲尵偊偽摉慠偱偡偑丅
丂堦曽丄僎儖儅儞揑宍懺偱偼丄嫟摨懱偼峆忢揑側慻怐偱偼偁傝傑偣傫丅傓偟傠丄乽帺桼側搚抧強桳幰偱偁傞壠挿偑愴憟傗嵳釰偺偨傔偵愜乆偵嵜偡亀廤夛亁偲偟偰尰懚偡傞偩偗偱偁傞乿偲尵傢傟傑偡丅偮傑傝丄僊儕僔傾偺億儕僗嫟摨懱偺傛偆偵乽崙壠丄崙壠惂搙偲偟偰偼懚嵼偟側偄乿偲偄偆偙偲偱偡丅僎儖儅儞偱偺嫟摨幮夛偵偮偄偰偼丄嵞惗嶻偺扨埵偱偁傞奺壠偺宱嵪揑側娭學偲偟偰懆偊傜傟偰偄傑偡丅奺乆偺壠偱偺搚抧強桳傪尦偵嵞惗嶻傪峴偭偰偄傞偙偲偑婎杮偱偁偭偰丄擖夛抧偺傛偆側搚抧偺嫟摨強桳娭學偼曗姰揑側傕偺偩偲尵偆傢偗偱偡丅
丂儅儖僋僗偼偦偺屻丄嵞惗嶻偲擇師揑揮壔宍懺偵偮偄偰媍榑偟偰偄傑偡丅拞怱偲側傞偺偼嫟摨懱乛嫟摨幮夛偺嵞惗嶻偱偡丅儅儖僋僗偼乽惗嶻偦偺傕偺偺栚揑偼丄惗嶻幰傪丄奺恖偑傕偮偙偺乮惗嶻偺乯媞懱揑懚嵼彅忦審偺拞偱丄偙傟傜偺忦審偲偲傕偵丄嵞惗嶻偡傞偙偲偱偁傞乿偲尵偭偰偄傑偡丅乽惗嶻幰偦偺傕偺偺嵞惗嶻乿偙偦偑惗嶻偺栚揑偱偡丅偙傟偼丄柧傜偐偵嫟摨幮夛偺嵞惗嶻傪弎傋偨傕偺偩偲尵偊傑偡丅摨帪偵丄嫟摨幮夛偺嵞惗嶻偼嫟摨懱偺嵞惗嶻傪敽偄傑偡偐傜丄偦偺尷傝偱嫟摨懱偺嵞惗嶻偵偮偄偰傕媍榑偟偰偄傑偡丅偟偐偟丄偙傟偼媡偱偼偁傝傑偣傫丅嫟摨懱偑嵞惗嶻傪扴偆傢偗偱偼側偄丅偙傟偼丄傛偔妎偊偰偍偄偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅
乮仸乯儅儖僋僗偵傛傟偽丄恖娫偼帺慠偺拞偱惗傑傟偨帺慠揑懚嵼偱偁傝丄惗妶婎斦偱偁傞戝抧傕帺慠偐傜梌偊傜傟偰偄傞丅恖娫偼丄強梌偺惗妶彅忦審偱偁傞戝抧偵懳偟丄帺暘偺恎懱偺墑挿偲偟偰摥偒偐偗丄帺屓偵崙桳偺乮eigen乯傕偺偲偟偰娭學偡傞丅偙傟偑杮尮揑側強桳乮Eigentum乯偱偁傝丄偙偙偱偼楯摥偲強桳偲偑摨堦偱偁傞丅
仭擇師揑揮壔宍懺偲嫟摨懱乛嫟摨幮夛偺夝懱
丂栤戣側偺偼丄搝楆惂傗擾搝惂摍偺擇師揑揮壔宍懺偱偡丅偙傟傑偱偼丄椺偊偽屆揟屆戙揑宍懺傗僎儖儅儞揑宍懺偵搝楆惂傗擾搝惂傪廳偹偰峫偊傞懆偊曽偑崻嫮偔偁傝傑偟偨偑丄偦偆偱偼偁傝傑偣傫丅杮尮揑強桳偺宍懺偼婎杮揑偵偼奒媺娭學傪娷傫偱偄傑偣傫丅傓偟傠丄儅儖僋僗偼偦偺擇師揑側揮壔宍懺偲偟偰擾搝惂傗搝楆惂偲偄偆傕偺傪憐掕偟偰偄傞偺偱偡丅椺偊偽丄屆揟屆戙偱尵偆偲丄僊儕僔傾偁傞偄偼儘乕儅偱丄愴憟傪捠偠偰懠偺柉懓傪惇暈偟偨帪偵偦偺柉懓傪搝楆偲偟偰慻傒崬傓丄偦偆偄偆奿岲偱搝楆惂偑恑傓偲偄偆偙偲偱偡偹丅
丂偦偆偟偨擇師揑揮壔宍懺偑搝楆惂傗擾搝惂偲偄偆奿岲偱榑偠傜傟偰偄傞偲偄偆偙偲丄偦偟偰丄偦傟偑嬤戙偵帄偭偰夝懱偟偨棟桼偵偮偄偰偼丄杮尮揑強桳偺彅宍懺偺拞偱偝傑偞傑側宍偱巹揑強桳偑敪惗偟丄偦傟偵敽偭偰嫟摨幮夛偑孈傝曵偝傟偰偄偔夁掱偑傕偆彮偟徻偟偔媍榑偝傟傞傋偒偱偡偑丄巆擮側偑傜偦傟傪榑偠傞梋桾偼偁傝傑偣傫丅
丂偲傕偁傟丄儅儖僋僗偼杮尮揑強桳宍懺偵偮偄偰榑偠偨嵟屻偵丄杮尮揑強桳偍傛傃嫟摨幮夛偺夝懱偵偮偄偰丄巐偮偺懁柺偐傜弎傋偰偄傑偡丅偡側傢偪嘆搚抧偵懳偡傞強桳娭學偺夝懱丅偦偟偰嘇梡嬶偵懳偡傞強桳偺夝懱丅偙傟偼拞悽偺僊儖僪偺傛偆偵梡嬶傪帺壠強桳偡傞偙偲偵傛偭偰帺棫偟偰偄傞偲偄偆強桳娭學偺夝懱偱偡丅偝傜偵丄搚抧偲梡嬶偺強桳娭學傪夝懱偝傟偨寢壥偲偟偰丄嘊惗妶偵昁梫側徚旓庤抜偺強桳偁傞偄偼愯桳偺夝懱丅
丂偪側傒偵丄傕偟嘆偲嘇偺夝懱傪慜採偲偟偰丄側偍嘊偵帄傜側偄偲偡傟偽丄偦傟偼搝楆偺強桳偱偁傞偲儅儖僋僗偼尵偭偰偄傑偡丅搝楆偼強桳娭學傪帩偨偢徚旓庤抜偩偗偑偁偰偑傢傟傞偐傜偱偡丅偩偐傜丄儅儖僋僗偑嬤戙偺捓嬥楯摥幰傪乽捓嬥搝楆乿偲屇傫偩偺偼丄扨側傞椺偊偱偼側偔丄搚抧偲梡嬶偲偄偆惗嶻庤抜偺柍強桳偺拞偱丄恏偆偠偰徚旓庤抜傪愯桳偱偒傞傛偆側娭學偼丄傑偝偟偔堦庬偺搝楆惂偵懠側傜側偄丄偲偄偆堄枴偵側傞偱偟傚偆丅
丂偦偟偰嵟屻偵丄嘋楯摥幰帺恎偑媞娤揑惗嶻彅忦審偵懏偟偰偄傞傛偆側彅娭學偺夝懱丅偙傟偼丄偨偲偊偽儘乕儅偺帪戙偺僋儕僄儞僥乕儔乮曐岇楆懏丄恊暘巕暘乯娭學偺傛偆偵丄惗嶻庤抜偲娭傢傝側偔梴傢傟傞偲偄偆娭學丄偦傟偐傜掚巘偺傛偆偵偁傞庬偺僒乕價僗傪採嫙偟偰廂擖傪摼傞傛偆側娭學偱偡丅
丂埲忋偺傛偆側嫟摨幮夛偺夝懱偲偄偆楌巎揑側夁掱傪捠偠偰丄擇廳偺堄枴偱偺帺桼側楯摥幰偑惗傑傟傞偙偲偵側傝傑偡丅偮傑傝丄僋儕僄儞僥乕儔娭學偺傛偆側恖奿揑側曐岇楆懏偺娭學偐傜偺帺桼偲摨帪偵丄媞娤揑側偁傜備傞強桳偐傜偺帺桼偲偄偆擇廳偺堄枴偱偺帺桼傪妉摼偟偨楯摥幰偺弌尰偱偡丅偦偟偰丄偙偺楯摥幰偼懳徾惈丄偮傑傝帺暘帺恎偺楯摥傪幚尰偡傞媞娤揑側懚嵼忦審傪帩偭偰偄側偄偲偄偆堄枴偱乽柍強桳乿偱偁傞偲尵傢傟傑偡丅
丂幚偼丄偙偺柍強桳偵偮偄偰丄儅儖僋僗偼1857擭偔傜偄偐傜63擭傑偱乽愨懳揑昻崲乿偲昞尰偟偰偄傑偡丅搚抧偲梡嬶偲偄偆楯摥傪幚尰偡傞忦審傪幐偄丄杮尮揑側強桳傪幐偭偰巹揑強桳偵偨偨偒崬傑傟丄柍強桳偲側傞偙偲丄偦傟偙偦偑昻崲偺拞偺昻崲丄愨懳揑昻崲偱偁傞丅儅儖僋僗偼偙偺偙偲傪帵偡偨傔偵丄巹揑強桳偑惉棫偡傞埲慜偺杮尮揑強桳宍懺偵棫偪婣偭偨傢偗偱偡偑丄偙傟傑偱尒偨傛偆偵丄偙傟傑偱変乆偼偦偺撪梕傪廫暘偵棟夝偱偒偰偄側偐偭偨偲巚偄傑偡丅埲忋偑亀梫峧亁偺嫟摨懱乛嫟摨幮夛榑偵娭偡傞戝傑偐側愢柧偱偡丅
俀丏乽僓僗乕儕僠傊偺夞摎憪峞乿偺擾嬈嫟摨懱榑
丂師偵乽僓僗乕儕僠僿偺夞摎憪峞乿偺擾嬈嫟摨懱榑傪峫嶡偟傑偡丅帪戙偼亀梫峧亁偐傜20擭傎偳壓傝傑偡丅儅儖僋僗偼1881擭丄僓僗乕儕僠偲偄偆儘僔傾偺妚柦壠偐傜幙栤偺庤巻傪庴偗庢傝傑偡丅偦偟偰丄儘僔傾偵偍偗傞擾懞嫟摨懱傪妚柦偺棫応偐傜偳偆昡壙偡傞偐傪峫偊丄夞摎偺庤巻傪憲偭偰偄傑偡丅儅儖僋僗偼偙偺庤巻傪彂偔偨傔偵丄憪峞傪巐偮巆偟偰偄傑偡偑丄偦傟傜偼乽夞摎憪峞乿偲憤徧偝傟傑偡丅
丂幚偼丄儅儖僋僗偼夞摎憪峞傪幏昅偡傞夁掱偱丄怴偨偵偝傑偞傑側棟榑揑専摙傪峴偭偨寢壥丄偙偙偱弶傔偰擾嬈嫟摨懱榑傪採婲偡傞傫偱偡偹丅偲偙傠偑丄偙傟傑偱偺擔杮偺嫟摨懱榑偱偼丄偙偺揰偑娕夁偝傟偰偒傑偟偨丅偦偟偰丄戝捤媣梇傕娷傔偰傎偲傫偳偑儅儖僋僗偺杮尮揑強桳宍懺榑傪擾嬈嫟摨懱榑偺嶰宍懺偺傛偆側宍偱丄崿摨偟偰棟夝偟偰偒偨偺偱偡丅偦偺堄枴偱丄崱傑偱偺擾嬈嫟摨懱榑偺棟夝偼丄慡偔堘偆偲尵傢偞傞傪摼傑偣傫丅
丂偝偰丄幚偼儅儖僋僗偼堦楢偺夞摎憪峞偺拞偱傕丄愭偵尒偨嫟摨懱偲嫟摨幮夛偺嬫暿傪寴帩偟偰偄傑偡丅夞摎憪峞偼僼儔儞僗岅偱彂偐傟偰偄傞偺偱丄commune偲communaute偲偄偆嬫暿偵側傝傑偡丅亀梫峧亁偱偺嬫暿偲廳偹偰峫偊傟偽commune偼Gemeinde偮傑傝乽嫟摨懱乿丄communaute偼Gemeinwesen偮傑傝乽嫟摨幮慡乿偵憡摉偡傞偲尵偊傞偱偟傚偆丅偲摨帪偵丄媍榑偺崪奿偼丄傗偼傝communaute乮嫟摨幮夛乯傪婎斦偵偟偰慻傒棫偰傜傟偰偄傑偡丅
丂夞摎憪峞偺戝傑偐側崪奿偼丄嘆幮夛偺戞堦師揑峔惉偁傞偄偼尨巒揑嫟摨幮夛偵娭偡傞晹暘丄嘇擾嬈嫟摨懱榑偺晹暘丄嘊怴偟偄嫟摨懱偮傑傝儘僔傾偺擾懞嫟摨懱乮儈乕儖嫟摨懱乯偵娭偡傞晹暘丄偺嶰偮偵暘偗傜傟傑偡丅
仭尨巒揑側嫟摨幮夛
丂儅儖僋僗偼擾嬈嫟摨懱榑偺慜偵丄偝傑偞傑側尨巒揑側嫟摨幮夛偵偮偄偰怗傟丄師偺傛偆偵巜揈偟偰偄傑偡丅偡側傢偪丄偝傑偞傑側尨巒揑側嫟摨幮夛傪乽慡偰摨楍偵偍偄偰峫偊傛偆偲偟偨傜岆傝傪斊偡偙偲偵側傠偆丅抧幙妛忋偺抧憌偲摨偠傛偆偵丄偙傟傜偺楌巎揑側峔惉偵傕丄堦師揑丄擇師揑丄嶰師揑摍偺宆偺慡宯楍偑懚嵼偡傞乿偲丅
丂偙偆偟偨嫟摨幮夛偼丄偨偲偊偽壠壆偺強桳傗搚抧偺強桳丄峩嶌偺宍懺側偳偵傛偭偰偄偔偮偐偺宆偵嬫暿偝傟丄嬫暿偺偝傟曽傕帪戙偵傛偭偰堎側傞偲尵傢傟傑偡丅偙偆偟偨嬫暿偺墑挿慄偵丄尨巒揑側嫟摨幮夛偼偝傑偞傑側敪揥抜奒傪宱偰丄楌巎揑偵嵟嬤偺嫟摨幮夛偵帄傞傢偗偱偡偑丄儅儖僋僗偼偦偆偟偨嵟嬤偺嫟摨幮夛偲偟偰儘僔傾偺擾嬈嫟摨懱傪埵抲偯偗傑偟偨丅
丂乽偝傑偞傑側尨巒揑嫟摨幮夛偑丄偡傋偰摨偠宆偱巇棫偰傜傟偰偄傞傢偗偱偼側偄偲丅斀懳偵丄偙傟傜嫟摨幮夛偺憤懱偼丄宆傕帪戙傕堎側傝丄廲婲揑側敪揥彅抜奒傪巜偟帵偡幮夛彅廤抍偺堦宯楍傪側偟偰偄傞丅偙傟傜偺宆偺堦偮偑擾嬈嫟摨懱偲屇傇偙偲偵庢傝寛傔傜傟偰偒偨偺偩偑丄儘僔傾偺嫟摨懱偺宆傕偦傟偱偁傞乿丅
丂偱偼丄擾嬈嫟摨懱埲慜偺尨巒揑側嫟摨幮夛偼丄偳傫側摿惈傪帩偭偰偄傞偐丅師偺巐揰偑嫇偘傜傟傑偡丅戞1偵丄奺峔惉堳偑帺慠揑側寣墢娭學傪婎慴偲偟偰偄傞丅戞2偵丄壠壆偑嫟摨強桳偁傞偄偼廤抍嫃廧偱偁傞丅偨偩偟丄偦偙偐傜巒傑偭偰丄壠壆傗晘抧偼擾嬈嫟摨懱埲慜偺抜奒偱偡偱偵屄恖揑愯桳丄偮傑傝嫟摨強桳偩偗傟偳傕奺壠懓偼暿乆偺壠壆偵嫃廧偡傞宍懺偵傑偱恑傓偲傕憐掕偟偰偄傑偡丅戞3偵丄搚抧偼婎杮揑偵嫟摨強桳偱偁傞丅偙傟偼杮尮揑強桳宍懺偺戞堦宍懺偲偟偰棟夝偱偒傑偡丅戞4偵丄峩嶌偼嫟摨惂偱偁傞丅
仭擾嬈嫟摨懱榑
丂擾嬈嫟摨懱偼偙偆偟偨尨巒揑側嫟摨幮夛偺嵟嬤偺宆丄尨惗揑宍懺偺嵟廔搳奒偲偄偆宍偱埵抲偯偗傜傟偰偄傑偡丅
丂乽乻擾嬈嫟摨懱乼偼偳偙偱傕幮夛偺尨惗揑峔惉偵偍偗傞嵟嬤偺宆偲偟偰尰傟傞偺偱偁傝丄屆戙偍傛傃嬤戙偺惣儓乕儘僢僷偺楌巎揑塣摦偵偍偄偰偼丄擾嬈嫟摨懱偺帪婜偼丄嫟摨強桳偐傜巹揑強桳偺夁搉婜偲偟偰丄戞堦師揑峔惉偐傜戞擇師揑峔惉傊偺夁搉婜偲偟偰丄尰傟傞乿丅
丂偙偺傛偆偵丄擾嬈嫟摨懱偼戞堦師揑峔惉偐傜戞擇師揑峔惉傊偺夁搉婜偲埵抲偯偗偱偡偐傜丄偦傟傪柍帇偟偰杮尮揑強桳宍懺榑偺嶰宍懺傪擾嬈嫟摨懱偺嶰椶宆偺傛偆偵棟夝偡傞偺偼丄柧傜偐側岆撉偩偲尵偊傑偡丅
丂偱偼丄偙偺擾嬈嫟摨懱偼丄偄偮尰傟傞偺偐丅儅儖僋僗偼丄惣梞偱儘僔傾偺擾懞嫟摨懱偵懳墳偡傞偺偼乽僎儖儅儞恖偺嫟摨懱偱丄嬌傔偰嵟嬤偺傕偺乿偩偲尵偭偰偄傑偡丅掗惌婜儘乕儅偺惌帯壠丒楌巎壠僞僉僩僁僗偺帪戙乮婭尦1悽婭崰乯偵懚嵼偟偰偄偨僎儖儅儞偺嫟摨懱偱偡偹丅暿偺尵偄曽偱偼丄僇僄僒儖偺帪戙乮婭尦慜1悽婭乯偵偼乽傑偩懚嵼偟偰偄側偐偭偨乿偑丄婭尦4悽婭埲崀偺僎儖儅儞柉懓戝堏摦偺偲偒偵偼乽傕偼傗懚嵼偟偰偄側偐偭偨乿偲傕尵傢傟傑偡丅
丂儅儖僋僗偵傛傟偽丄僇僄僒儖偺帪戙偵偼丄偡偱偵峩抧偑偝傑偞傑側廤抍丄巵懓丄晹懓偺娫偱暘梌偝傟偰偄偨偗傟偳傕丄摨偠嫟摨懱偵懏偡傞晹懓偺娫偱丄嫟摨偱峩嶌傪偟偰偄傞傛偆側忬懺偩偭偨偲偺偙偲偱偡丅偩偐傜丄偦傟偼擾嬈嫟摨懱偲偄偆傛傝傕杮尮揑強桳宍懺偲偟偰懆偊傜傟傞偲巚偄傑偡丅杮棃偺堄枴偱偺擾嬈嫟摨懱偑尰傟傞偺偼丄偦偺屻偱偡丅
丂娭楢偟偰丄僇僄僒儖偺帪戙偐傜僞僉僩僁僗偑昤偄偨傛偆側擾嬈嫟摨懱傊偺夁搉婜偲偟偰丄壠壆偑廤抍嫃廧偺応強偱偼側偔丄奺乆偺屄恖強桳偵側傞堦曽偱丄偍偦傜偔搚抧偺愯桳幰傪掕婜揑偵曄峏偡傞乽妱懼偊乿偺傛偆側偙偲傪偡傞擾嬈嫟摨懱傕憐掕偝傟偰偄傑偡丅偄偢傟偵偣傛丄儅儖僋僗偼僎儖儅儞揑宍懺偲尵偭偰傕慡偰摨堦偲偼尒偰偍傜偢丄僇僄僒儖帪戙丄僞僉僩僁僗帪戙丄偦偺師偺帪戙偲丄偝傑偞傑偵嬫暿偟偰偄傑偡丅
丂擾嬈嫟摨懱偺摿惈偲偼壗偐丅偙傟傕丄師偺巐揰偑嫇偘傜傟傑偡丅戞1偵丄寣墢娭學偐傜奜傟偰丄帺桼側恖娫偨偪偑宍惉偡傞幮夛廤抍偱偁傞丅戞2偵丄壠壆傗晘抧偵娭偟偰偼巹揑強桳偵側偭偰偄傞丅戞3偵丄搚抧偼埶慠偲偟偰嫟摨懱強桳偩偑丄峩抧偑掕婜揑偵暘妱偝傟丄妱懼偊偑側偝傟傞丅戞4偵丄奺壠懓偑暘妱抧傪屄暿峩嶌偟丄偦偺惉壥傪廂妌偟嫕庴偡傞宍偱丄壠懓偛偲偵晉偺拁愊傪壜擻偵偡傞忬嫷偑惗傑傟偰偄傞丅偙偆偟偨摿惈傪帩偮傕偺傪杮尮揑強桳宍懺偲崿摨偟偰偟傑偆偲丄儅儖僋僗偺媍榑偑傢偐傜側偔側傝傑偡丅
丂偦偟偰丄擾嬈嫟摨懱偼丄嵟屻偵戞擇師揑側峔惉偵帄傞丄偮傑傝丄怴偟偄嫟摨懱偵揮壔偟傑偡丅偙偺抜奒偱偼丄偡偱偵偝傑偞傑側宍偱巹揑強桳偑尰傟偰偄傑偡丅巹揑強桳偵婎偯偔幮夛偱偡偐傜丄奒媺娭學傕栤戣偵偝傟側偗傟偽側傝傑偣傫丅傕偪傠傫丄戞擇師揑峔惉傕傑偨擇師揑揮壔宍懺偲偟偰搝楆惂偲偄偆宍傪偲傝傑偡丅
仭儅儖僋僗偺楌巎峔憐
丂偙偆偟偰傒傞偲丄夵傔偰擾嬈嫟摨懱偺埵抲傪柧妋偵偟偰媍榑偡傞廳梫惈偑柧傜偐偵側傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 丂偙傟傑偱丄儅儖僋僗偺楌巎娤偵偮偄偰丄偄傢備傞乽巐敪揥抜奒愢乿偲偟偰懆偊傞棟夝偑捠梡偟偰偒傑偟偨丅偟偐偟丄埲忋偱尒偨傛偆偵丄偦傟傎偳扨弮側傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅妋偐偵丄亀宱嵪妛斸敾彉尵亁偱偼丄乽戝偯偐傒偵偄偊偽丄傾僕傾揑丄屆戙揑丄晻寶揑丄嬤戙僽儖僕儑傾僕乕揑惗嶻條幃偑丄宱嵪揑幮夛峔惉偺椵恑揑側彅帪婜偲偟偰昞帵偝傟偆傞乿偲弎傋傜傟偰偍傝丄偙偺巐敪揥抜奒愢偑楌巎偺婎杮揑側榞慻傒偲峫偊傜傟偰偒傑偟偨丅偟偐偟丄偦傟偼儅儖僋僗偺杮堄偱偼偁傝傑偣傫丅偙傟傑偱偺媍榑傪妶偐偟偰楌巎擣幆傪嶌傠偆偲巚偊偽丄廬棃偲偼傑偭偨偔堘偭偨峔憐偑偱偒忋偑傞偲巚偄傑偡丅
丂傕偟丄屆戙揑丄晻寶揑丄嬤戙僽儖僕儑傾揑惗嶻條幃偲偄偆偺傪奒媺揑峔惉偵婎偯偔傕偺偲峫偊傞側傜丄偮傑傝惗嶻條幃偲尵偆応崌丄柧傜偐偵奒媺揑側峔惉傪擮摢偵抲偒丄廬偭偰偦偺嬫暿偱宱嵪揑幮夛峔惉偑棟夝偝傟偰偄傞偲偡傟偽丄儅儖僋僗偺暥柆偐傜尒偰丄媍榑偺懳徾偼戞擇師揑峔惉偺彅宍懺偵側傞偼偢偱偡丅幚嵺丄晻寶揑丄嬤戙僽儖僕儑傾揑偲偄偆昞尰偵偼丄偦傟偑姶偠傜傟丄偦偺堄枴偱丄傾僕傾揑惗嶻條幃傕傑偨丄戞擇師揑峔惉偺揮壔偺宯楍偵埵抲晅偗傜傟傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅
丂偮傑傝丄乽宱嵪揑幮夛峔惉偺椵恑揑側彅帪婜乿偲尵傢傟傞傕偺偼丄尷掕偝傟偨楌巎揑抜奒傪巜偡昞尰偱偁偭偰丄楌巎偺敪揥抜奒傪偡傋偰曪妵偡傞傕偺偱偼側偄偙偲偑暘偐傝傑偡丅廬偭偰丄傾僕傾揑惗嶻條幃傪尨巒嫟嶻惂偲懆偊傞傛偆側棟夝偑岆傝偱偁傞偺傕柧傜偐偩偲尵偊傑偡丅
丂愭偵怗傟偨傛偆偵丄儅儖僋僗偼夞摎憪峞偱幮夛傪戞堦師揑峔惉偲戞擇師揑峔惉偵戝偒偔嬫暘偟偰丄擾嬈嫟摨懱傪椉幰偺夁搉揑側抜奒偲偟偰愝掕偟偰偄傑偡丅
丂慜幰偼杮尮揑強桳宍懺偵婎偯偔幮夛傪曪妵偟偰偍傝丄壗傜偐偺搚抧偺嫟摨強桳側偄偟嫟摨懱強桳偑懚嵼偟偰偄傞偲偡傞堦曽丄峩嶌偵娭偟偰偼乽嫟摨峩嶌乿偐傜乽屄恖乮壠懓乯偺峩嶌偲巹揑椞桳乿傑偱丄壠壆偲壆晘抧偵娭偟偰偼乽嫟摨壠壆偲廤抍強桳乿偐傜乽壠壆偺嫟摨強桳偲屄恖揑愯桳乿偍傛傃乽壠壆丒壆晘抧偺巹揑強桳乿傑偱丄偝傑偞傑側宍懺傪娷傔偰偄傑偡丅
丂傑偨丄擾嬈嫟摨懱偼嫟摨懱娭學傪婎慴偲偟側偑傜傕丄屄恖偵傛傞峩嶌偍傛傃巹揑椞桳丄偦偟偰壠壆傗晘抧偺巹揑強桳偑惉棫偟偨抜奒偲尒傜傟傞偲偟偰偄傑偡丅
丂懠曽丄屻幰偺戞擇師揑峔惉偼巹揑強桳偵婎偯偔幮夛偱偁傝丄奒媺幮夛偱偁傞偲尒側偟偰偄傑偡丅 丂巹偼丄偙偆偟偨媍榑偺寢壥偲偟偰丄師偺傛偆側楌巎擣幆傪儅儖僋僗偺楌巎峔憐偲偟偰昤偗傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傑偡丅乮壓偺峔惉昞嶲徠乯
丂堦椺傪帵偣偽丄乵1乶偼杮尮揑強桳宍懺偵懳墳偡傞尨巒揑幮夛峔惉偱偁傝丄戞1宍懺丄戞2宍懺丄戞3宍懺偲偁偭偰丄戞1宍懺偼壠壆偲壆晘抧偺嫟摨強桳偐傜巹揑強桳偵帄傞傑偱偺宍懺傪娷傫偱偄傞丅偙傟偑傾僕傾揑宍懺偵帄傞丅
丂偙偺3宍懺偺屻偵擾嬈嫟摨懱偑懚嵼偟丄偝傜偵偼乵2乶擇師揑揮壔宍懺偲偟偰丄傾僕傾揑惗嶻條幃偼峷擺惂偵婎偯偔儗儀儖偲偟偰搝楆惂丄擾搝惂偲懳墳偡傞丅偙傟傑偱偺儅儖僋僗棟夝偱偼丄偙偺擇師揑揮壔宍懺傪楌巎偺戞嶰抜奒丄戞巐抜奒偲懆偊偰偄偨傢偗偱偡丅
丂偦偙偐傜乵3乶岎姺壙抣揑悽奅偵帄傝傑偡丅偙偙偵偼丄岎姺壙抣偵婎偯偔僽儖僕儑傾揑側惗嶻娭學偩偗偱偼側偔丄慜僽儖僕儑傾揑側彜嬈傗彜昳惗嶻偺娭學傕娷傑傟傑偡丅変乆偺惗偒傞悽奅偱偡丅
丂偙偆偟偨宱夁傪偨偳偭偰丄儅儖僋僗偺峔憐偺拞偱偼嵟屻偵乵4乶巹揑強桳偺攑婞偮傑傝柍強桳偺攑婞丄偦傟傪捠偠偨帺桼側屄懱惈偺幚尰偲尵傢傟傞傛偆側抜奒偑偔傞丅
丂戝傑偐偵偙偆偟偨楌巎擣幆傪帩偰傞偺偱偼側偄偐丅偦傫側傕偺偼尰戙偱偼捠梡偟側偄偲尵傢傟傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偲偼偄偊丄戝榞偱偙傟偵庢偭偰戙傢傞媍榑偑偁傞傢偗偱傕側偄偲巚偄傑偡丅
丂傓偟傠丄偙偙偱拲栚偟偨偄偺偼丄楌巎擣幆偺栤戣偲偄偆傛傝傕彨棃幮夛偵娭傢傞栤戣偱偡丅愭偵尒偨傛偆偵丄杮尮揑強桳宍懺偑揥奐偟偰偄偔拞偱丄壠壆傗晘抧偼嫟摨強桳偐傜巹揑強桳傊偲恑揥偡傞偗傟偳傕丄偦傟偼惗嶻庤抜偺巹揑強桳偲偄偆栤戣偲偼堘偭偨柆棈偱尰傟偰偄傞丅偙傟偼戝偄偵拲栚偵抣偡傞偲巚偄傑偡丅偲偄偆偺傕丄偨偲偊偽彨棃丄壖偵幮夛庡媊偑惗嶻庤搳偺嫟摨強桳傪幚尰偟偨偲偟偰丄偦偺帪偵壠壆傗壆晘抧偺巹揑強桳偼巆偭偰傕峔傢側偄偙偲偵側傞偐傜偱偡丅
丂偙傟傑偱丄幮夛庡媊偱乽巹揑強桳偺攑婞乿偲偄偆偲丄偳偆偟偰傕巹桳嵿嶻傗屄恖偺惗妶嬻娫偑扗傢傟傞傛偆側僀儊乕僕偵側傝偑偪偱偟偨丅旕忢偵嫹偔棟夝偝傟偰偟傑偭偨傢偗偱偡丅偟偐偟丄儅儖僋僗偺杮堄偐傜偡傟偽丄偦偆偱偼側偄丅栤戣偼乽巹揑強桳偍傛傃柍強桳偺攑婞乿偱偁傝丄壠壆傗壆晘抧丄巹揑嬻娫偺巹揑強桳偵偮偄偰偼旕忢偵暆偑偁傞丅偙偺揰傪幉偵偡傟偽丄彨棃幮夛偵娭偟偰丄傕偭偲帺桼偐偮娚傗偐側峔憐偑偱偒傞偲巚偄傑偡丅
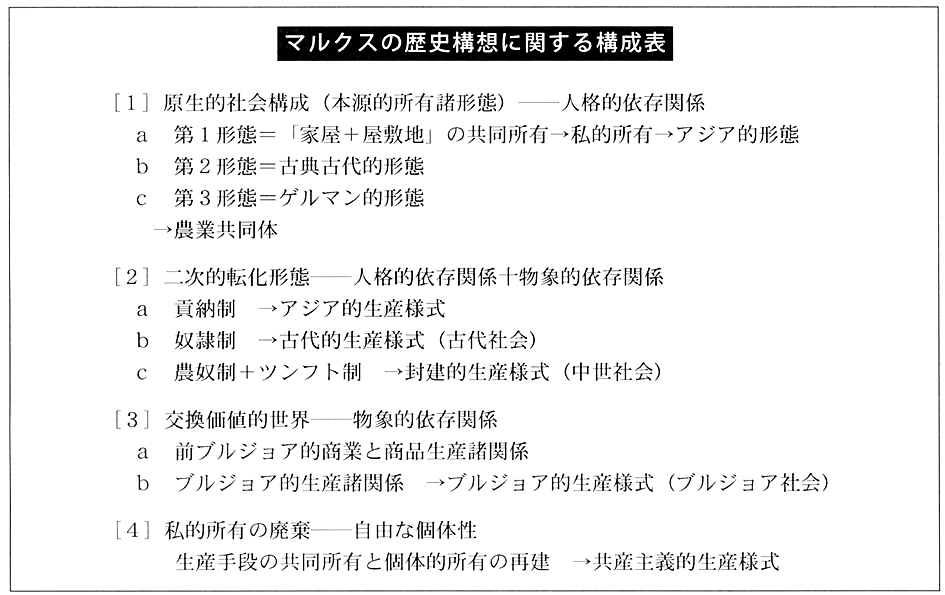
俁丏尰戙偺嫟摨懱庡媊偵偮偄偰
丂嵟屻偵丄尰戙偺嫟摨懱庡媊偵娭偡傞媍榑偵偮偄偰娙扨偵怗傟偨偄偲巚偄傑偡丅崱擔僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉丄曐庣庡媊丄僫僔儑僫儕僘儉丅偦傟偐傜巗柉幮夛榑丄岞嫟寳榑偲偄偆傛偆側偝傑偞傑側偐偨偪偱嫟摨懱庡媊偑暅妶傪偟偰偄傑偡丅偨偲偊偽丄僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉偺庡梫側榑幰偺堦恖偱偁傞儅僢僉儞僞僀傾偼乽巹偲偄偆懚嵼偼丄偝傑偞傑側嫟摨懱揑娭學偺拞偵梌偊傜傟偰懚嵼偟偰偄傞乿偲偐乽偦偺嫟摨懱偺暔岅偺拞偵杽傔崬傑傟偰偄傞乿偲偄偭偨尵偄曽傪偟偰偄傑偡丅偦偙偐傜儕儀儔儕僘儉偺戙昞揑側榑幰偱偁傞僲乕僕僢僋傗儘乕儖僘側偳偺媍榑傪斸敾偟偰丄斵傜偼乽幮夛偼屄恖偱惉偭偰偄傞乿丄偮傑傝屄恖偑戞堦偱幮夛偑戞擇偩偲偄偆偗傟偳傕丄偦偆偱偼側偔偰丄傓偟傠嫟摨懱偲偄偆暥柆偺拞偱丄傢傟傢傟偺娤擮傗惈奿丄傾僀僨儞僥傿僥傿偲偄偭偨傕偺偑宍惉偝傟傞偺偩丄偲偄偆媍榑傪偟偰偄傑偡丅
丂偙偆偟偨儕儀儔儕僘儉斸敾偵偼丄堦掕偺懨摉惈偑偁傝傑偡丅偮傑傝丄屄恖偲偄偭偰傕娫堘偄側偔摿掕偺幮夛偺拞偵惗傟棊偪傞傢偗偱偡丅嵟弶偐傜妋屌偲偟偨屄恖偑懚嵼偟偰丄偦傟傜偑帺桼偵幮夛傪偮偔傞偺偱偼側偔丄偁傞庬偺娭學丄偄傢偽屄恖偱偼偳偆偟傛偆傕側偄惗嶻條幃偺拞偵惗傟棊偪傞丄偦傟傪柍帇偡傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅
丂偲偼偄偊丄僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉偺尵偆傛偆偵丄屄恖偼嫟摨懱堦斒偺拞偱帺屓傪扠摼偡傞偐偲偄偊偽丄偦傟傕堘偆偲巚偄傑偡丅尰戙偵惗偒傞変乆偼丄嫟摨懱偺拞偱惗偒偰偄傞偲摨帪偵帒杮庡媊偺拞偱惗偒偰偄傑偡丅摉慠丄帒杮庡媊揑側彅娭學傕丄変乆偺屄惈傪婯掕偡傞戝偒側梫慺偵側傞傢偗偱偡丅偩偐傜丄嫟摨懱揑側拞偵偄傞偲偄偆偙偲傪扨弮偵嫮挷偟偰丄偩偐傜嫟摨懱揑懚嵼偱偁傝摼傞側偳偲尵偆偺偼丄偍偐偟側偙偲偵側傝傑偡丅
丂僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉偼丄屄恖偑嫟摨懱偺拞偵尰偵懚嵼偟偰偄傞偐偺傛偆偵榑偠偰偄傑偡偑丄偦傕偦傕嫟摨懱偺嵞寶偑栤戣偵偝傟傞偺偼丄尰戙偑嫟摨懱夝懱埲屻偺帪戙偩偐傜偱偟傚偆丅偲偡傟偽丄榑偢傋偒壽戣偼擇偮偁傞偲巚偄傑偡丅巹傕恖娫偑嫟摨懱揑懚嵼偱偁傞偙偲偼斲掕偟傑偣傫丅偟偐偟丄杮幙揑偵嫟摨懱揑懚嵼偩偐傜尰偵嫟摨懱揑側傫偩丄偱偼側偔丄傓偟傠丄杮幙揑偵偦偆偱偁傞偵傕偐偐傢傜偢嫟摨懱偑夝懱偝傟偨偺偼側偤偐丄楌巎揑偵愢柧偡傞昁梫偑偁傞丅偙傟偑堦偮丅
丂傕偆堦偮偼丄嫟摨懱偑夝懱偟偨屻偺巹揑強桳傪幉偲偟偨幮夛偺拞偱惗偒偰偄傞変乆偑丄偄偐偵偟偰怴偨側嫟摨懱偁傞偄偼嫟摨幮夛傪宍惉偱偒傞偺偐丄偦偺崻嫆傪採帵偡傞昁梫偑偁傞偲巚偄傑偡丅偦傟側偟偵嫟摨懱庡媊偼晄壜擻偱偡丅偲偙傠偑丄僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉偼偙偺偄偢傟偵偮偄偰傕愢柧偟偰偄傑偣傫丅
丂師偵尰戙曐庣庡媊偵偮偄偰丅偙偙偱偼丄壛摗揟梞丄嵅攲孾巚丄彫椦傛偟偺傝側偳偺媍榑傪庢傝忋偘傑偡丅斵傜傕嫟摨懱偺棫偪忋偘偵晠怱偟偰偄傑偡丅偲偙傠偑丄斵傜傕傑偨崻嫆偯偗偑偱偒偢丄嵟屻偵偼恖娫偺杮幙偺拞偵嫟摨惈傪媮傔偞傞傪摼側偔側傝傑偡丅
丂壛摗揟梞偼儅儖僋僗傪岆撉偟偰丄岞嫟惈偼巹棙巹梸偺忋偵抸偐傟傞偲庡挘偟丄巹棙巹梸傪墇偊弌偰岞嫟惈亖嫟摨惈偑壜擻偱偁傞偐偺傛偆側媍榑傪偟傑偟偨丅儅儖僋僗偼丄偦傟偼晄壜擻偱偁傞丄偁傞偄偼丄偦傫側岞嫟惈偼巹棙巹梸偲懳棫偡傞傕偺偱偼側偔丄偦傟偵揔崌偟偨岞嫟惈偵夁偓側偄丄偲尵偭偰偄傞偺偱偡偑丄壛摗偼偦傟傪岆撉偟偨丅
丂偙傟偵懳偟偰嵅攲孾巚偼丄壛摗偺偙偺娫堘偄傪偒偪傫偲斸敾偟偰偄傑偡丅巹棙巹梸偺憤榓偐傜岞嫟惈傪摫偔偙偲偼偱偒側偄丄偲丅偙傟偼傑偭偨偔惓偟偄丅偱偼丄偦偆偄偆嵅攲孾巚偼岞嫟惈傪摫偗傞偐偲尵偊偽丄巆擮側偑傜摫偗傑偣傫丅寢嬊丄岞嫟惈偑偁傞偲偄偆慜採偺忋偱丄巹棙巹梸偐傜敳偗弌偟偰丄偦偙偵旘桇偡傋偒偩偲偄偆偩偗偱偡丅
丂幚嵺丄嵅攲偑埶嫆偡傞偺偼丄屆揟屆戙偺惌帯揑嫟摨懱偵幚尰偝傟偨嫟摨惛恄偱偡丅摉帪偼柧敀偵嫟摨懱偑懚嵼偟偰偄傞傢偗偱偡偐傜丄嫟摨懱惛恄偑偁傞偺偼摉慠偱偡丅偟偐偟丄偦偺嫟摨懱偑夝懱偟丄晄嵼偵側偭偰偄傞偺偑尰嵼偱偡丅偵傕偐偐傢傜偢丄摉帪偺嫟摨懱惛恄傪偳偆傗偭偰暅妶偱偒傞偺偐丅崻嫆偑偁傝傑偣傫丅
丂彫椦傛偟偺傝傕摨條偱偡丅偮傑傝丄偄偢傟偺榑幰傕寢嬊丄乽岞乿偑偁傞偲慜採偟偰丄偦偺乽岞乿偺堄幆傪妎惲偡傞偲偄偆榖偵側偭偰偄傑偡丅恖娫偼傕偲傕偲嫟摨揑側懚嵼偩丄岞揑懚嵼偩丄偲丅偨偲偊偽丄彫椦偼乽偄傑丄偙偙偵偄傞傢偟偼慶晝偨偪偐傜偮側偑傞楌巎偺僞僥幉偲幮夛偺庬乆偺嫟摨懱偵懏偡傞儓僐幉偺岎嵎偡傞堦揰偲偄偆惂栺傪庴偗偰乽屄乿傪宍惉偡傞乿丅偦偟偰丄僞僥幉偲儓僐幉偺岎嵎揰丄乽偦偙偵偟偐惗偒傜傟側偄偲偄偆擣幆偐傜乽岞乿偵偮側偑傞巺岥偑尒偊偰偔傞乿偲偄偆傢偗偱偡丅僐儈儏僯僞儕傾僯僘儉偵帡偨暔尵偄偱偡偹丅偟偐偟丄偩偐傜偲偄偭偰乽岞乿偑弌偰偔傞偺偱偟傚偆偐丅僞僥幉偲儓僐幉偺岎嵎揰偵惗偒傞巹偼摨帪偵巹棙巹梸偵傑傒傟偨巹偱傕偁傝傑偡丅偦傟偑側偤乽岞乿傪棫偪忋偘傜傟傞偺偐丅
丂偟偨偑偭偰寢嬊偼乽岞乿偲乽巹乿偺嫟懚偑媍榑偝傟傞偩偗偱偡丅堦曽偱偼丄恖娫傪慡柺揑偵崙壠揑側懚嵼偲偟偰丄偮傑傝乽岞柉乿偲偟偰掕媊偡傞偙偲偼偱偒側偄丅偟偐偟懠曽偱丄偦偺師尦傪堦愗攔彍偟偨乽宱嵪恖乿傗乽巗柉乿偲偟偰掕媊偡傞偙偲傕偱偒側偄丅偦偙偱丄屄恖偲偼丄偦偺撪偵偁傞乽岞柉惈乿傗乽巗柉惈乿丄乽宱嵪恖惈乿側偳傪揔愗偵僶儔儞僗偝偣傞懚嵼偩偲偄偆奿岲偱丄偡傋偰偺梫慺傪嫟懚偝偣傞偙偲偵側傝傑偡丅偙傟偼丄乽巹乿偲懳棫偟側偄宍偱偟偐乽岞乿傪棫偪忋偘傜傟側偄丄嫟摨懱夝懱屻偺帪戙偵偍偗傞媍榑偺尷奅偱偡丅
丂嫟摨懱乛嫟摨幮夛偑夝懱偟偨屻丄嫟摨懱偁傞偄偼乽岞乿偺懚嵼偑梫惪偝傟傑偡丅偟偐偟丄偦傟偼尰懚偟偰偄側偄偙偲傪慜採偲偟偰偄傑偡丅尰懚偟偰偄側偄偐傜梫惪偡傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄媍榑偺夁掱偱丄偦傟偼杮幙揑偵懚嵼偡傞傕偺偲憐掕偝傟丄偦偺敪梘偑愢偐傟傞丅偡偱偵懚嵼偟偰偄傞偺側傜丄梫惪偡傋偒棟桼偼側偔側傝傑偡丅偙傟偼崻杮揑側柕弬偱偡丅
丂偮傑傝丄偨偟偐偵恖娫偼嫟摨懱揑懚嵼偩偲偟偰傕丄偩偐傜偲偄偭偰嫟摨惈傪幚尰偟側偗傟偽側傜側偄傢偗偱偼側偄丅尰嵼偱偼嫟摨懱偑懚嵼偟側偄偙偲傪慜採偲偟偰丄嫟摨惈傪幚尰偡傋偒偩丄偲尵傢傟傑偡偑丄杮幙揑偵偼恖娫偼嫟摨揑偩偲偄偆側傜丄偵傕偐偐傢傜偢丄側偤嫟摨惈傪憆幐偟偰偄傞偺偐傪愢柧偡傋偒偱偡丅偟偐偟丄偦偺愢柧偼偁傝傑偣傫丅
丂偱偼丄嫟摨惈偼晄壜擻側偺偱偟傚偆偐丅偦傟偼堘偄傑偡丅傓偟傠乽崱擔偄偐偵偟偰怴偟偄嫟摨亖嫤摨偼尰幚揑偵壜擻偐乿偲偄偆宍偱栤偄傪棫偰傞傋偒側偺偱偡丅偙傟偼丄恖娫偺杮幙榑傛偭偰婎慴偯偗傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅拲栚偡傋偒偼嵞惗嶻偱偁傞偲巚偄傑偡丅尰嵼偺僔僗僥儉偑変乆偺嵞惗嶻傪晄壜擻偵偟偮偮偁傞偲偡傟偽丄偙偺嵞惗嶻偲偄偆暔幙揑丄懚嵼揑師尦偵偍偄偰丄惗懚亖惗妶偺晄壜擻偲偄偆嫟捠宱尡傪捠偟偰懚嵼偺嫟摨惈偑惗傑傟傞偲巚偄傑偡丅
丂帒杮庡媊僔僗僥儉偼丄懚嵼偺嫟摨惈傪戝婯柾偵攋夡偡傞丅乽3丒11乿偺宱尡偼丄傑偝偵帒杮偲崙壠婡娭偑寢傃偮偄偰丄傢傟傢傟偺嵞惗嶻慻怐偺婎斦傪側偡恖乆偲偦偺懠偺惗暔丄搚丒悈丒嬻婥傪攋夡偟偨偙偲傪帵偟偰偄傑偡丅偲偡傟偽丄偙偺搚傗悈傗嬻婥偲偄偆惗妶帒尮偺嫟摨惈傪崻嫆偵偟偰丄変乆偼怴偟偔嫟摨惈傪棫偰傞偙偲偑偱偒傞丄偁傞偄偼棫偰偞傞傪摼側偄偺偱偼側偄偐丅偦傟偑巹偺棟夝偱偡丅
丂奆偝傫偑偝傑偞傑側妶摦偺拞偱峫偊偰偄傞偺傕丄嫲傜偔偦偆偟偨嵞惗嶻偵娭傢傞栤戣側偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅嵞惗嶻偑崲擄偲偄偆偐晄壜擻偵嬤偯偒偮偮偁傞崱擔偺忬嫷壓偱丄側偍偐偮丄偦偆偟偨尰幚偺宱尡偺拞偵嫟摨偺崻嫆傪尒弌偡偙偲丅巹偼偦傟偟偐偁傝摼側偄偲捝愗偵姶偠偰偄傑偡丅
仭尰幚曄妚偺崻嫆傊
丂儅儖僋僗偑壥偨偟偨巚憐巎揑側揮姺偼丄幚偼偙偺揰偵偁傝傑偡丅偦傟偼摨帪偵丄巹偺儗乕僯儞偵懳偡傞斸敾偲傕娭傢傝傑偡丅儗乕僯儞偼乽僇乕儖丒儅儖僋僗乿偺拞偱丄儅儖僋僗偼柉庡庡媊偐傜嫟嶻庡媊丄娤擮榑偐傜桞暔榑傊堏峴偟偨偲庡挘偟丄偙偺夝庍偑1970擭戙偖傜偄傑偱捠梡偟偰偒傑偟偨丅
丂儅儖僋僗偑柉庡庡媊偺棫応偵棫偭偨偺偼1843擭偺乽傊亅僎儖崙朄榑斸敾乿偱丄偦偺屻偵嫟嶻庡媊偺棫応偵棫偭偨偙偲偼娫堘偄偁傝傑偣傫丅偦偺堄枴偱丄柉庡庡媊偐傜嫟嶻庡媊傊偺曄壔偑偁偭偨偙偲偼妋偐偱偡丅傊亅僎儖揑側娤擮榑偐傜桞暔榑偵曄壔偟偨偙偲傕丄戝傑偐偵偼斲掕偱偒傑偣傫丅
丂偟偐偟丄崻杮揑側栤戣偼丄儅儖僋僗偺曄壔傪乽堏峴乿偲昞尰偟偨偙偲偱偡丅偨偲偊偽乽A偐傜B偵堏峴偟偨乿偲偄偆偲偒丄A偺抜奒偱B偲偄偆応強偑慜採偝傟偰偄傑偡丅尵偄姺偊傟偽丄婛抦偺懳徾偑側偗傟偽堏峴偱偒傑偣傫丅偲偙傠偑丄儅儖僋僗偵偲偭偰嫟嶻庡媊偼婛抦偺懳徾偩偭偨偐偲偄偊偽丄偦偆偱偼側偄偺偱偡丅
丂儅儖僋僗偼1843擭偵柉庡庡媊偺峔憐傪棫偰傑偟偨偑丄偦傟偼偡偖偵攋抅偟傑偡丅攋抅偡傞棟桼偼丄偦偺棟榑偑丄尰幚偺奜偵壗傜偐偺棟惈揑尨棟傪棫偰偰丄偦偙偐傜尰幚偺悽偺拞傪曄偊傞偲偄偆棫偰曽偱偁偭偨偐傜偱偡丅偦偆偟偨棟榑偱偼丄巹揑強桳傪幉偲偡傞巗柉幮夛偺偁傝曽傪挻偊傜傟側偄偲暘偐偭偨傫偱偡偹丅
丂偨偲偊偽丄惌帯傕朄傕摴摽傕廆嫵傕幚偵棫攈側偙偲傪尵偄傑偡丅偲偙傠偑丄寢嬊偺偲偙傠丄巹揑強桳偵傛偭偰巹棙巹梸偵傑傒傟偨偙偺幮夛丄昻崲偲楆懏偑墶峴偡傞巗柉幮夛偺偁傝曽傪崻杮揑偵斸敾偡傞偙偲偼偱偒側偄丅傓偟傠丄尰幚偺柕弬傪塀暳偟丄崌棟壔偡傞婡擻偝偊壥偨偟偰偄傞丅偦偆偟偨偙偲偵婥偯偔拞偱丄儅儖僋僗偼偦傟傑偱偺偁傜備傞棟榑傪攋抅偝偣傞偲摨帪偵帺暘偺棟榑傪傕攋抅偝偣偨偲尵偊傑偡丅
丂峴偒拝偔愭傕側偄偟丄棅傞傋偒棟榑傕側偄丅偦傫側忬嫷偺拞偱丄儅儖僋僗偑桞堦弌敪揰偵偱偒偨偲偡傟偽丄偙偺幮夛偺拞偵丄偙偺幮夛偱偼惗偒偰偄偗側偄恖偨偪偑朿戝偵偄傞丄偲偄偆帠幚乮嫟捠偺宱尡乯偩偗偩偭偨偺偱偼側偄偐丅偙偺幮夛偵偼丄偙偺幮夛偵傛偭偰棙塿傪摼偰偄傞恖傕摉慠偄傑偡偑丄敿柺偦傟偱偼惗偒偰偄偗側偄恖偨偪傕朿戝偵偄傞丅偦傟傪敪尒偟偨偲偒丄偙偺幮夛偼擇廳壔偝傟丄尰幚偺暘楐偑尒偊偰偔傞丅尰幚偵偼偝傑偞傑偵嶖憥偟偨帠忣偑偁傞偵偟偰傕丄偙偙偵懚嵼偡傞嫟捠偺宱尡傪崻嫆偵偟側偗傟偽幮夛偼曄傢傜側偄丅偁傞偄偼偙偺崻嫆偵婎偯偄偰偙偦曄偊傜傟傞丅偩偐傜丄昻崲偼昻崲偵廔傢傜偢丄昻崲傪暍偡崻嫆偵側傞傢偗偱偡丅
丂巹揑強桳偺尨棟傪傑偭偨偔嫕庴偱偒側偄丄偄傑偺幮夛偱偼惗偒傜傟側偄丄柍強桳偲偄偆愨懳揑昻崲偵偁傞楯摥幰奒媺偑懚嵼偡傞偙偲偼丄巹揑強桳偺尨棟傪挻偊偰偄傞丅儅儖僋僗偼偦偺偙偲傪敪尒偟偨偺偩偲巚偄傑偡丅偙傟偑曄妚偺崻嫆偲側傝偆傞丅巆擮側偑傜丄儅儖僋僗庡媊偺楌巎偼偦偺偙偲傪挿偄娫暘偐傜偢偵偒偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
丂巹偼儅儖僋僗偵弣偠傞婥側偳栄摢偁傝傑偣傫偑丄嶐崱偺忬嫷傪尒傞偲丄斵偑捈柺偟偨幮夛偺偁傝傛偆偼崻杮揑側偲偙傠偱曄傢偭偰偄側偄偲姶偠傑偡丅偦偺堄枴偱丄儅儖僋僗傪挻偊傛偆偲偡傟偽偡傞偼偳丄尰戙幮夛偺崻杮栤戣偵偳偆庢傝慻傓偐偑丄傑偡傑偡栤傢傟傞偙偲偵側傞偺偩偲巚偄傑偡丅乮廔丄暥愑丗杮帍曇廤晹乯

©2002-2011 抧堟丒傾僜僔僄乕僔儑儞尋媶強 All rights reserved.