農村・農民の自立を目指す晏陽初郷村建設学院
はじめに
中国農村ツアー3日目の訪問先は、北京から南南西へ3時間半、河北省定州市東亭鎮 城村に位置する晏陽初郷村建設学院である。北京から定州市までの車窓は、穀物地帯らしく、行けども行けども一面のトウモロコシ畑。北京に比べて10年ほど昔に戻ったような雰囲気の定州駅で下車し、マイクロバスに乗り換える。市街地を抜けて幹線道路をひた走ること、およそ20分。一行を乗せたバスはやがて農道に進路を変え、トウモロコシ畑をかき分けるように進んで行く。文字どおり牧歌的な光景(※1)の中、トウモロコシ畑の海に忽然と姿を現した建物こそ、晏陽初郷村建設学院だ。
郷村建設学院、その経過と概要
晏陽初郷村建設学院は03年7月、中国人民大学農業・農村開発学部の温鉄軍氏を中心に、 城村村民委員会、晏陽初農村教育発展中心、中国人民大学郷村建設中心、中国社会服務及発展研究中心(CSD香港)、国際行動援助中国弁公室、中国村社促進会現代化建設専業委員会の6者によって設立された。
後日、本ツアーの実務責任者にして学院の副院長でもある袁小仙氏(※2)にお聞きしたところでは、学院設立のきっかけは、農村における社会建設に関心を持っていた劉建芝氏(香港在住、本誌34号参照)が中国国内で連携できる知識人を捜していた際、温鉄軍氏に遭遇したことにある。
周知のように、中国では様々な制約から、現実を批判的に捉える研究者に出会うことは難しく、まして、批判的な視点を持ちつつ体制内で改革に取り組もうとする人は稀少である。この点で、三農問題について政府に各種の提言をし得る位置にあり、同時にNGO活動にも精力的に取り組んでいる温鉄軍氏は、打ってつけの人物と言える。
こうして温鉄軍氏と意気投合した劉建芝氏は、温氏が抱いていた農村復興のための学校づくりという構想を実現すべく、積極的に協力することになった。もっとも、香港のNGOを通じて資金援助を行なうといった当初の見通しは、実際に現場を訪問した後、むしろ現地に駐在しつつ、共に考え共に作業すべき、との考えに変化した。その際、常駐者として白羽の矢が立ったのが、当時CSDという香港のNGOで活動していた袁小仙氏である。
以上の経過から、また自らの性格を「非営利の原則に基づく公益事業」としていることからも分かるように、学院は形式上「国家985号計画:中国農村発展一級試験革新基地」という厳めしい名称を冠せられているものの、むしろ「NPOの自主学校」と言うべきだろう。(※3)
学院の所在地は、もともと1954年に建設され、90年代まで使用されていた 城村の中学校である。その後、生徒の減少により別の中学に統合され、廃校となった。しばらく民間に売却されていたが、学院の設立にあたって村民委員会が買い戻し、現在は学院に貸与する形になっている。修繕や改装の初期投資に50万元ほど要したとのことだが、使用目的がほとんど変わらないため建物の多くは転用でき、作業の多くはボランティアによって行われた。敷地の総面積は4ヘクタール(ha)で、そのうち1.4haが耕作地である(おそらく元は運動場と思われる)。村との相談で、建物のうち2棟は村の幼稚園として使用され、学院と村の日常的な接点となっているようだ。
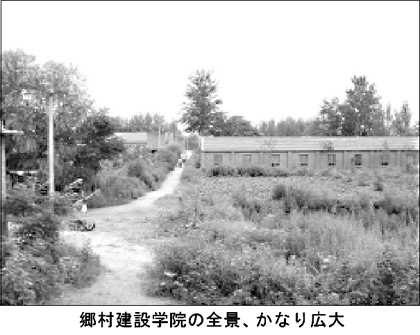
現在、学院の常勤職員は9名で、総務、作業、研究、教育計画、建築、循環農業、村民対応など、それぞれ担当が割り振られている。さらに、大学院生や学部生の実地学習、夏休みを利用した短期滞在など、十数名の学生ボランティアが在籍している。常勤職員のほとんどは、こうしたボランティア出身で、概ね30歳未満。そのほか、調理係、家畜係、実技係などとして、年輩の男性数人や、住み込み世帯の姿も見られた。
学院の問題意識と取り組み
2泊3日の学院滞在中、数度にわたる論議の場が設けられ、学院の問題意識や取り組み、直面する課題などについて理解することができた。
学院の基本原則は「人民生計為本、互助合作為綱、多元文化為根(民衆の生計を基本とし、互助協同を要とし、文化多様性を拠り所とする)」との簡潔な言葉で表現されている。これに基づいて中国農村の持続可能な発展を推進し、三農問題の解決を展望することが目的だ。具体的な活動領域は、以下のとおりである。
これは、学院の中心業務と言える。全国から参加者を募り、農業技術だけでなく、農村復興に関する考え方、農民の生計改善のための知識・諸情報を提供している。06年は4回(3・6・8・10月)、農繁期を避けて企画・実施したという。
中でも、研修参加者が各々の地元へ帰った際に、生産・消費の合作社(協同組合)や女性委員会などのアソシエーションを形成するための支援が柱である。合作社については、これまで中国全土で30ヵ所の実績があるという。また、初期投資を貸与するための信用機関の設立も促進している。
さらに、学院内にとどまらず、各地に出張して講座を開催するほか、研修参加者が地元に帰った後の「アフターケア」や、研修修了者が再び集まり、各自の実践について論議・交流する場の形成にも務めているという。
参加者は男女の別を問わず、熱意を長文の手紙にしたためてくる人、村民委員会の推薦を受けて代表参加する人、すでに一定の実践を行っている人など、まさに多様とのこと。ちなみに、学生を対象に、農村復興に関わるボランティア養成講座も実施している。
中国では改革開放から30年にわたり、生産性の向上を目的として、石油・農薬・化学肥料を多用する農業の「工業化」が押し進められてきた。その結果、収量増大の一方で土地は疲弊し、農民の健康にも大きな被害が生じている。投入財の購入に要する資金も増え、生産請負制の進展と相まって、農業・農村の市場化が急速に深化した。
学院では、こうした工業的農業の延長線上に三農問題の解決はあり得ないと考え、それに代わる持続可能な農業モデルを模索している。その中心となるのは、有機農業や無農薬栽培の実践であり、商品経済への依存度を低めるための農村環境の形成である。
前者については、農地およそ1haで有機農法、無(減)農薬栽培を試み、3年目になるという。研修講座や 城村との交流を通じて宣伝に務めてはいるが、当然ながら好意的な反応ばかりではない。農民にとっては、収入や労力などの面で懸念が多いからだ。
そこで学院では、労力軽減と収入維持を軸として、有機・無農薬に不安感なく移行できる仕組み作りが課題となっている。とくに、収入の維持には生産物の販路確保が重要なことから、日本の生協・産直運動なども参考に、消費者の組織化を考えていきたいという。
後者については、とくに石油への依存を減らすべく、家畜を使った耕作、バイオガスの利用、地元の材料や在来工法を利用した生態(エコロジー)建築など、地域循環型のシステムを試行している。
学院内には、台湾の生態建築家・謝英俊氏が設計した講堂やモデルハウス、「大」と「小」を分集する「生態厠所(エコトイレ)」など、興味深い建物がいくつかあるが、これらは材料が環境に則っているだけでなく、農民が人力で作りやすい工法が用いられている。実際の建築にあたっては、村の農民たちに工賃を払い労力の提供を受けたが、それは、農民自身の手で工法や利点を修得すると同時に、共同作業を通じて村民が一体感を得る、との狙いもあった。
中国内外における農村復興、農村自立の実践例に関する情報の収集、蓄積に基づき、学院の諸活動を踏まえ、講演会やシンポジウム、研究会などを開催している。とりわけ、学院長を務める温鉄軍氏の声望もあってか、海外の研究者や活動家の訪問も多く、その都度、交流・論議の場が設けられるという。06年には、今回のツアー一行のほか、ドイツの労働組合、インドのグループも訪れたとのことだ。
袁氏によれば、これまでの中でとくに印象深かったのは、ペルーで有機農法や農村コミュニティ活動に取り組む日系人との交流だったという。参加した職員やボランティアは、自らの活動について、中国内に限れば確かにマイナーではあっても、地球規模で見れば決して特殊なものではないことを再認識し、勇気づけられたらしい。そうした確信を持つ若者を育てることも、学院の目指すところと言えよう。
学院の特徴の一つに、その地理的な位置を挙げることができる。三農問題に取り組む団体やNGOは、中国内外を含めていくつかあるが、農民の当事者団体を除けば、それらは概ね外部(都市)から農村に関わる形をとっているという。これに対し、学院は農村の中に拠点を構えている。そのため、村との日常的な接触を通じて学院の問題意識や主張を伝え、直に村民の反応を得られるという点で、利点は大きい。
実際、学院と村との連携は、文化事業、スポーツ大会など村の行事への参加、女性委員会をはじめとする集団活動への共同の取り組み、農業や生活に関わる相談や論議、各種工事における作業分担など、多岐にわたって密接なものとなっているようだ。
そうした連携を形成するには、村の諸関係に内在する過程が不可欠だが、同時に内在するが故の困難さも存在する。現実の農村は、すでに何らかの形で市場化、工業化の影響を受けており、それを内面化した結果、都市と比較して自らを劣位に位置づける傾向が少なくない。工業的農業に対する批判や協同的な営みの再建など、伝統的な農村のあり方を参考に、小農を軸とした三農問題の解決を展望する学院の主張とは、齟齬を来す面も少なくないという。
晏陽初とその時代
ここで、学院の名称となっている晏陽初について、簡単に触れておきたい。
晏陽初は1890年に四川省で生まれ、長じて後、米国・欧州に留学した。その際、中国人出稼ぎ労働者に対する識字教育に関わった経験から、民衆教育の重要性に目覚めたとされる。
中国帰国後の1923年には、北京で「中華平民教育促進会」を創設し、実際に民衆教育を開始する。数年後には、同志や家族とともに現在の定州市 城村に移住し、識字教育を軸に衛生教育、女権向上運動など、生活改善運動に基づく「郷村建設運動」を実践した。彼のモットーは、次の言葉に集約されている。
「民の中へ/その中で生活し/彼らから学び/彼らと共に計画し/彼らが知っていることからはじめ/彼らがすでに持っているものを基礎として建設する」(※4)

当時の中国は、辛亥革命によって清朝から中華民国へ移行したものの、社会にはなお旧習が残存するとともに、軍閥の割拠、列強による侵略の拡大といった混乱要因が加わり、民衆の苦境は深まる一方であった。
しかしまた、日本による「対華21ヵ条要求」を契機とした「五四運動」(1919年)に象徴されるように、この時期の中国では、帝国主義列強への対抗的ナショナリズムが興隆してもいる。
こうした中、中国の現状を憂慮する梁漱溟、陶行知など先進的知識人の多くは、社会の基礎である農村の復興、教育による農民の自立を通じた中国の復興・再生を展望した。彼らの影響を受けた青年インテリも、数多くこの運動に参加している。晏陽初もまた、青年たちに大きな影響を与えた一人である。
もっとも、中国共産党は当初から、こうした農村復興運動に対して、農村における階層分化を軽視し、土地改革を要とする政治変革を回避した「改良主義」との批判を加えていた。事実、49年の革命後も大陸にとどまった梁漱溟は、50年代中期、毛沢東の進める農業集団化に反対して批判を浴び、長らく表舞台から姿を消すことになった。
晏陽初は革命後に海外へ移住したため、直接的な被害は受けなかったものの、国民党との関係もあり、長期にわたって批判対象とされた。しかし他方、その後もアジア、ラテンアメリカをはじめ、世界各地を訪れては農村開発事業に携わっており、60年の「マグサイサイ賞」受賞に見られるように、国際的な評価は高い。晩年には、フィリピンに「国際農村改造学院(IIRR)」を設立するなど、農村復興に生涯を捧げた。
中国でも、毛沢東路線からの転換、人民公社の廃止といった情勢変化に伴い、80年代中期に名誉回復を果たしたが、とりわけ今日、三農問題の解決が焦眉の急となる中で、本格的な再評価の機が熟してきたものと思われる。

「愚公移山(愚公山を移す)」
農民・知識人・学生の連携に基づく、平民教育(啓蒙)→生計教育(実利)→合作社による経済建設(システム)という段階を通じた農村復興(※5)は、かつて晏陽初が手がけて果たせなかった試みである(※6)。晏陽初郷村建設学院の実践は、その名の通り、晏陽初の構想を今日的な諸条件の中で刷新しつつ継承するものと言えよう。
本誌33号でも触れたように、胡錦濤政権はここ数年来、三農問題の解決を重視し、「社会主義新農村建設」の名の下に、財政支出の増大を進めている。旧来の農業政策からすれば急激な転換だが、袁氏によると、そもそも「新農村」の内容が漠然としているのに加え、転換が急な分だけ、農民側も歓迎の一方で混乱を来しているという。
もっとも、学院が実験区として承認されたのも、そうした状況なればこそ、と言える。党=政府の視点は基本的にマクロレベルに集中しており、目指す方向は「財政支出の増大→一層の市場化推進→小農の駆逐と営農の大規模化→産業としての農業の確立」である。
これに対して学院は、大規模化、産業化の追求はむしろ逆効果と捉え、市場化への対抗的視点から、農村・農民の自立を通じた農業の復興を目指している。その中心となるのは、農村における協同的な営みの復興・再生であり、生産や文化などにおけるアソシエーションの形成に向けた取り組みである。つまり、農民の自己組織化を通じた主体形成がなされてこそ、政府による財政支出は意味を持ち、農村復興も可能、との立場である。
いわば、中国における「主流派」の考え方とは正反対に近いが、主流派自身も確固とした展望があるわけではなく、幅広い試行・実験を許容せざるを得ない状況にある。学院としては、こうした趨勢に乗りつつ、農村における下からの動きを形成し、農村・農民の自立を通じた農業の復興という、一種の対抗的価値観を浸透させていく構えのようだ。
とはいえ、設立から未だ日が浅いこと、また中国の広大さからみれば、現状では、学院の活動範囲とその影響力は、非常に限定されている。
