儃儕價傾丒儌儔儗僗惌尃抋惗偺攚宨乮拞乯
偼偠傔偵
弶偺愭廧柉弌恎戝摑椞傪抋惗偝偣偨儃儕價傾偺忬嫷傪幉偵丄儔僥儞傾儊儕僇偵偍偗傞斀暷嵍攈丒拞摴嵍攈惌尃偺抋惗丄偦偺崻尮偵偁傞柉廜摦岦傪傔偖傞丄懢揷徆崙偝傫偺偍榖丅悽奅巎揑婯柾偱偺暘愅傪峴偭偨慜夞偵懕偄偰丄崱夞偼儔僥儞傾儊儕僇婯柾偐傜偺暘愅偱偁傞丅乮峔惉丒暥愑偼尋媶強帠柋嬊乯
儔僥儞傾儊儕僇偵偍偗傞怴帺桼庡媊
1960擭戙丄70擭戙偐傜80擭戙偺弶摢偔傜偄傑偱丄旕忢偵懡偔偺儔僥儞傾儊儕僇偺崙乆偑孯帠惌尃壓偵抲偐傟傑偡偑丄偙偆偟偨孯帠惌尃壓偱幚巤偝傟偨怴帺桼庡媊惌嶔偲偺娭學偱丄僄儃丒儌儔儗僗偺搊応傪峫偊偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅偙偺揰偵偮偄偰偼乽僼儕乕僪儅儞偲僺僲僠僃僩偼2搙巰偸乿乮亀楯摥忣曬亁2006擭1寧崋乯偱庒姳怗傟偰偄傑偡丅
儔僥儞傾儊儕僇尰戙巎偺拞偱旕忢偵戝偒側堄枴傪帩偮弌棃帠偼壗偐偲尵偊偽丄傑偢巚偄偮偔偺偑1959擭偺僉儏乕僶妚柦偱偡偑丄偙偺偲偒傾儊儕僇偼旕忢偵桘抐偟偰偄偨傢偗偱偡偹丅
偦傟傑偱傾儊儕僇偑巟偊偰偒偨僶僠僗僞撈嵸惌尃偼丄惌帯晠攕偲揙掙揑側抏埑偱丄枛婜揑側忬嫷傪掓偟偰偄傑偟偨丅偦偙偱丄庒幰偨偪偑拞怱偵側偭偰斀惌晎塣摦傪揥奐偟丄嵟廔揑偵偼59擭丄僇僗僩儘傗僎僶儔偨偪偑妚柦傪惉廇偡傞傢偗偱偡偑丄傾儊儕僇偼摉弶丄怺崗偵峫偊偰偄側偐偭偨丅僶僠僗僞偑埆偡偓偨偐傜巇曽偑側偄丄偲戝栚偵尒偰偄偨愡偑偁傝傑偡丅
偲偙傠偑丄妚柦惌晎傪庽棫偟偨庒幰偨偪偑崻杮揑側幮夛夵妚傪幚巤偟傛偆偲偡傟偽丄偄偢傟傾儊儕僇偑僉儏乕僶偵帩偭偰偄偨尃塿偵撍偒摉偨傜偞傞傪摼側偄丅擾抧夵妚傪峴偍偆偲偡傟偽丄僒僩僂僉價傗僞僶僐側偳丄傾儊儕僇帒杮偺尃塿偲傇偮偐傞丅嬥梈婡娭傪夵妚偟傛偆偲偡傟偽丄嬧峴傪偼偠傔懡偔偺嬥梈婡娭偑傾儊儕僇帒杮偺巟攝壓偵偁傞丅僯僢働儖側偳偺揤慠帒尮丄偙傟傕傾儊儕僇帒杮偑媿帹偭偰偄傞丅傾儊儕僇偺娤岝媞岦偗偺搎攷応傗攧弔奨傪堦憌偟傛偆偲偟偰傕丄僆乕僫乕偼傾儊儕僇帒杮偱偡丅
偮傑傝丄幮夛夵妚傪峴偍偆偲偡傟偽丄偙偲偛偲偔傾儊儕僇偺尃塿偲惓柺懳棫偟偰偟傑偆丅幚嵺丄妚柦惌尃偼師乆偲夵妚傪峴偄丄傾儊儕僇偺尃塿偵庤傪拝偗偰偄偔丅傾儊儕僇偲偡傟偽丄偦傫側偙偲傪偝偣偰偼側傞偐丄偲偄偆傢偗偱丄揋懳丄朩奞丄慾巭傪巒傔傑偟偨丅孯帠椡偵傛傞夘擖傕壗夞偐帋傒偰偄傑偡偑丄偦偆偟偨揋懳娭學偑埲屻48擭娫偵傢偨偭偰懕偄偰偄偔偙偲偵側傝傑偡丅
偙偙偱丄傾儊儕僇偼娫堘偄側偔乽戞2偺僉儏乕僶傪嫋偝側偄乿偲偄偆嫵孭傪捦傫偩丅偦傟偱丄崱屻偳偙偐偺崙偱幮夛晄埨偑婲偒偰丄斵傜偺棙塿偵側傜側偄惌尃偑偱偒偨側傜丄側傞傋偔憗婜偵丄揙掙揑偵捵偡丅偦偆偄偆曽恓偑妋掕偝傟傑偡丅
偦傟偑嵟弶偵峴傢傟偨偺偼丄僽儔僕儖偱偟偨丅1964擭丄僌儔乕儖偲偄偆柉懓庡媊嵍攈偺惌尃偑抋惗偟丄堦掕偺夵妚楬慄傪幚峴偟傛偆偲偟傑偟偨丅偛懚抦偺傛偆偵丄僽儔僕儖偲偄偆偺偼峀戝側崙搚傪屩傝丄恖岥偼摉帪偱傕1壄悢愮枩恖偄偨偼偢偱偡丅偮傑傝埨偄楯摥椡偑偁傞丅偝傜偵丄傾儅僝儞偵偼峼暔帒尮傪娷傔偨揤慠帒尮偑偁傞丅偦偺僽儔僕儖偑丄僉儏乕僶傑偱偼偄偐側偔偰傕嵍孹壔偟偨応崌丄傾儊儕僇偵偲偭偰偼怺崗側帠懺偱偡丅偦偙偱丄攚屻偐傜僥僐擖傟偟偰丄64擭偵僌儔乕儖惌尃傪搢偡孯帠僋乕僨僞乕偑峴傢傟偨傢偗偱偡丅
偦傟埲崀丄60擭戙屻敿偐傜70擭戙弶摢偵偐偗偰丄儔僥儞傾儊儕僇奺崙偱偼幚偵懡偔偺孯帠僋乕僨僞乕偑峴傢傟丄孯帠惌尃偑棎棫偟傑偟偨丅偦偺孯帠惌尃偼丄奜岎柺偵偼僉儏乕僶偲偺娭學傪抐偪丄幮夛庡媊僽儘僢僋偺塭嬁椡傪抐偮宍偱丄僉儏乕僶曪埻栐傪宍惉偡傞丅傑偨撪惌柺偱偼丄嵍梼僎儕儔傗嵍梼惌搣丄幮夛塣摦傪揙掙揑偵抏埑偟傑偡丅偲摨帪偵丄孯帠惌尃傪巟偊傞傾儊儕僇傗崙嵺嬥梈婡娭傗掗崙偵偲偭偰偼丄孯帠惌尃偑僉儏乕僶偵桪墇偟偰偄傞偲屩帵偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅幮夛庡媊傛傝偆傑偔偄偔偲偄偆幚愌偑梸偟偄丅偦偺巜昗偼宱嵪惉挿偱偡偐傜丄宱嵪柺偱偺僥僐擖傟傕峴偆偙偲偵側傝傑偡丅
偙偆偟偰傒傞偲丄偄傑悽奅傪惾姫偟偮偮偁傞怴帺桼庡媊宱嵪惌嶔偑丄側偤孯惌壓偺儔僥儞傾儊儕僇彅崙偱幚尡偝傟偨偺偐丄傛偔暘偐傞偲巚偄傑偡丅偮傑傝丄奜崙帒杮傪愊嬌揑偵摫擖偟丄惉挿帄忋庡媊傪娧偔偙偲偵傛偭偰丄偁偨偐傕摉奩崙偺宱嵪慡懱偑掙忋偘偝傟偨傛偆偵尒偊傞丅偦偙偑慱偄偩偭偨傢偗偱偡偹丅偙偆偟偨惌嶔偑堦斣揟宆揑偩偭偨偺偼丄儔僥儞傾儊儕僇偱偼僺僲僠僃僩惌尃壓偺僠儕丅偦偟偰丄傾僕傾偱偼杙惓鄦惌尃壓偺娯崙偱偡丅
儔僥儞傾儊儕僇偱偼丄僠儕偵揟宆揑側孯帠惌尃傪巟偊傞偨傔偵丄奜崙帒杮偺愊嬌揑側摫擖偑峴傢傟傞堦曽丄崙撪惌嶔偲偟偰偼丄偄傑杔傜偑宱尡偟偮偮偁傞傛偆側怴帺桼庡媊宱嵪惌嶔偑愭嬱揑偵嵦梡偝傟偰偄偒傑偟偨丅傑偝偵僼儕乕僪儅儞丄僔僇僑丒儃乕僀僘偺尵偆乽彫偝側惌晎乿偱偡丅岞嫟巟弌傪壜擻側尷傝嶍尭偟丄柉塩壔亖巹婇嬈壔偡傞偙偲偵傛偭偰丄嫞憟尨棟偺巗応宱嵪偺拞偵曻傝崬傫偱偄偔丄偦傟傪捠偠偰宱嵪傪妶惈壔偝偣傞丅偦偆偄偆帋傒偑揙掙揑偵峴傢傟丄岞柋堳偲偐暉巸梊嶼丄嫵堢丄堛椕側偳傊偺巟弌偑惁傑偠偄惃偄偱尭傜偝傟偰偄偒傑偟偨丅惉挿偺壥幚偼壗傛傝傕丄摫擖偟偨奜崙帒杮偺曉嵪偵廩偰傜傟偰偄偒傑偡丅偄傢備傞乽峔憿挷惍惌嶔乿偱偡偹丅
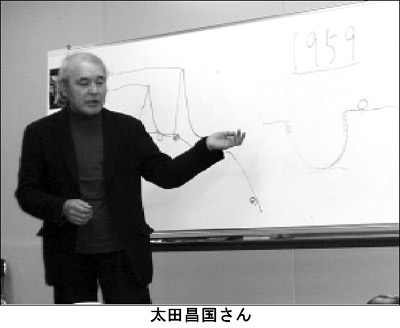
崙偵傛偭偰庒姳堘偄偑偁傝傑偡偑丄偩偄偨偄60擭戙屻敿丄70擭戙弶摢偐傜80擭戙慜敿傑偱丄栺15擭乣20擭嬤偔偺暆偱懕偔傢偗偱偡丅
婎憌偐傜偺栤偄捈偟
80擭戙屻敿偐傜90擭戙偵側偭偰丄儔僥儞傾儊儕僇偱偼柉庡壔偺帪婜傪寎偊傞傢偗偱偡偑丄柉庡壔偝傟偰乽偼偄丄傛偐偭偨乿偱偼嵪傑側偄丅孯帠惌尃壓偱朿傟偁偑偭偨庁娂丄朿戝側晧嵚偼丄柉庡壔偺帪戙傪惗偒傞恖乆偑曉偟偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅崅惉挿丄岲宨婥偲尵傢傟偨帪婜傕偁偭偨傕偺偺丄帺暘偨偪偺惗妶偼傑偭偨偔傛偔側傜側偐偭偨丄偁偺偲偒惗傑傟偨偍嬥偼偳偙偵巊傢傟偨偺偐丅宱嵪揑側恟偩偟偄晄暯摍偑懚嵼偟丄愨懳揑昻崲偑懚嵼偡傞幮夛偵偁偭偰丄偦傟傪惀惓偡傞偨傔偵偼價僞堦暥傕巊傢傟側偐偭偨丄偲偄偆尰幚偑暘偐偭偰偔傞丅柉庡壔偺夁掱偱帺暘偨偪偺堄尒傪帺桼偵尵偊傞傛偆偵側傞偲丄偁偺孯帠惌尃壓偺惗妶偲偄偆傕偺偼丄宱嵪惌嶔偲偄偆傕偺偼丄偄偭偨偄壗偩偭偨偺偐栤偄捈偟丄敪尵偡傞傛偆偵側傞傢偗偱偡丅
柉庡壔偺夁掱偲偄偆偺偼丄扨偵忋偐傜梌偊傜傟偨傕偺偱偼側偔丄戝偒側媇惖傪暐偭偰妉摼偝傟偨庡懱揑側夁掱偱偡丅帺暘偨偪偺惗妶傪巟攝偟偰偄偨孯帠惌尃偺偁傝曽傪栤偄捈偡拞偱丄柉庡庡媊傪偝傜偵揙掙偡傞夁掱傊偲偮側偑偭偰偄偔丅偦傟偼丄扨偵帺崙偺孯帠惌尃偩偗偱偼側偔偰丄偦偺攚屻偵偄偨傾儊儕僇丄偁傞偄偼宱嵪惌嶔偵愊嬌揑偵夘擖偟偨崙嵺捠壿婎嬥乮IMF乯傗悽奅嬧峴丄偦傟傜偑偄偭偨偄偳傫側栶妱傪壥偨偟偨偺偐傪栤偄偨偩偡丄偦偆偄偆応強偱傕偁偭偨偲尵偊傞傫偱偡偹丅
儃儕價傾偺応崌丄孯帠撈嵸惌尃偼僒儞僞僋儖僗弌恎偺僶儞僙儖偲偄偆戝摑椞偑拞怱偱丄1971擭偐傜80擭偔傜偄傑偱懚嵼偟傑偟偨丅偍傛偦10擭偱偡偐傜丄儔僥儞傾儊儕僇偺拞偱偼斾妑揑抁偐偭偨偲尵偊傑偡丅偙傟傪搢偡偨傔丄乽柉庡庡媊偺弔乿偲偄偆戝廜塣摦偑峴傢傟偨偺偑丄80擭偐傜82擭偵偐偗偰偱偡丅偙偺娫傕丄柉庡惃椡偺搊応偵懳偟偰偼巇曉偟偺孯帠僋乕僨僞乕偑偁偭偨傝偟偰丄梙傝栠偟偺懡偄悢擭娫偩偭偨偲尵偊傑偡丅
僂僇儅僂偺亀偨偩傂偲偮偺対偺偛偲偔亁偲偄偆僪僉儏儊儞僞儕乕嶌昳偼丄偙偺夁掱傪嶣偭偨傕偺偱偡丅僪僉儏儊儞僞儕乕側偺偱丄夋柺偵搊応偡傞恖乆偺惗偺惡傪暦偔偙偲偑偱偒傞丅儃儕價傾偱偼僶僗傗僩儔僢僋偑庡梫側岎捠庤抜側偺偱丄峈媍峴摦偲偟偰摴楬傪晻嵔偡傞偙偲偑傛偔偁傝傑偡丅亀偨偩傂偲偮偺対偺偛偲偔亁偱傕丄擾柉偲偐峼嶳楯摥幰偑丄愇傪塣傫偩傝丄摴楬偵崅偔愊傒忋偘偨傝偟偰摴楬晻嵔傪峴偭偰偄傞丅偦偺斵傜偑岥乆偵岅偭偰偄傞偺偑丄偙偺尰幚傪傕偨傜偟偰偄傞偺偼崙嵺捠壿婎嬥乮IMF乯偱偁傝悽奅嬧峴偩丄偲偄偆偙偲側傫偱偡丅偨偟偐1981乣2擭偺応柺偩偭偨偲巚偄傑偡丅
僂僇儅僂偺亀偨偩傂偲偮偺対偺偛偲偔亁偲偄偆僪僉儏儊儞僞儕乕嶌昳偼丄偙偺夁掱傪嶣偭偨傕偺偱偡丅僪僉儏儊儞僞儕乕側偺偱丄夋柺偵搊応偡傞恖乆偺惗偺惡傪暦偔偙偲偑偱偒傞丅儃儕價傾偱偼僶僗傗僩儔僢僋偑庡梫側岎捠庤抜側偺偱丄峈媍峴摦偲偟偰摴楬傪晻嵔偡傞偙偲偑傛偔偁傝傑偡丅亀偨偩傂偲偮偺対偺偛偲偔亁偱傕丄擾柉偲偐峼嶳楯摥幰偑丄愇傪塣傫偩傝丄摴楬偵崅偔愊傒忋偘偨傝偟偰摴楬晻嵔傪峴偭偰偄傞丅偦偺斵傜偑岥乆偵岅偭偰偄傞偺偑丄偙偺尰幚傪傕偨傜偟偰偄傞偺偼崙嵺捠壿婎嬥乮IMF乯偱偁傝悽奅嬧峴偩丄偲偄偆偙偲側傫偱偡丅偨偟偐1981乣2擭偺応柺偩偭偨偲巚偄傑偡丅
杔偼偦傟傪尒偰丄旕忢偵嬃偄偨婰壇偑偁傞丅偨偲偊偽丄擔杮偱堦斒弾柉偑帺暘偨偪偺惗妶忬嫷偵偮偄偰榖偡偲偒偵丄偄偒側傝乽崙嵺捠壿婎嬥偑偳偆偟偨乿偲偄偆榖偵偼側傜側偄偼偢偱偡丅偲偙傠偑丄儃儕價傾偱偼傑偝偵丄帺傜偺捈柺偡傞栤戣偵偮偄偰丄弾柉偑偦偺傛偆偵岅傜偞傞傪摼側偄忬嫷偵偁偭偨傢偗偱偡偹丅偙傟偼傗偼傝丄70擭戙偺10擭娫丄孯帠惌尃壓偵偍偗傞宱嵪偺偁傝曽偑丄偄偐偵夁崜側傕偺偩偭偨偐丄傑偨丄偦偺攚宨偵偮偄偰丄斵傜偑偄偐偵惓妋偵攃埇偟偰偄傞偐丄偦傟傜傪帵偡傕偺偩偲峫偊傜傟傑偡丅
傕偪傠傫丄偦傟帺懱偼堦偮偺僄僺僜乕僪偐傕偟傟傑偣傫偑丄偝傑偞傑側暥專傪捠偠偰丄傑偨崱夞偺椃偱弌夛偭偨恖乆偲偺夛榖傪捠偠偰丄扨側傞僄僺僜乕僪偱偼側偄偙偲偑暘偐傝傑偡丅孯帠惌尃壓偺旕忢偵夁崜側惗妶備偊偵丄偦傟偵懳偡傞斀敪椡偺拞偱丄夁崜側惗妶傪傕偨傜偟偨攚宨傪棟夝偡傞幮夛堄幆丒惌帯堄幆偑宍惉偝傟偰偒偨偙偲偼柧傜偐偱偟傚偆丅
乵幙媈墳摎嘆乶
亂幙栤亃儌儔儗僗惌尃抋惗偵偮偄偰丄屄暿儃儕價傾揑攚宨偲摨帪偵丄儔僥儞傾儊儕僇偵嫟捠偡傞抧堟揑側攚宨偵怗傟傜傟傑偟偨偑丄怴帺桼庡媊側偄偟暷崙偺巟攝偐傜棧扙偟傛偆偲偄偆摦偒偼丄儔僥儞傾儊儕僇慡懱偵嫟捠偡傞巙岦偩偲峫偊傜傟傞傢偗偱偡偐丅
亂懢揷亃05擭11寧丄傾儖僛儞僠儞偱暷廈庱擼夛媍偑峴傢傟傑偟偨偑丄偦偺嵺僽僢僔儏偼丄杒暷偲僉儏乕僶傪彍偔慡儔僥儞傾儊儕僇傪娷傓丄傾儊儕僇戝棨婯柾偺帺桼杅堈巗応丄乽暷廈帺桼杅堈寳乮FTAA乯乿傪偮偔傠偆偲屇傃偐偗偨丅94擭偵惉棫偟偨杒暷帺桼杅堈嫤掕乮NAFTA乯傪戝棨婯柾偵偟偨偐偭偨傢偗丅偲偙傠偑丄偦傟偵懳偟偰丄摉慖偡傞慜偺僄儃丒儌儔儗僗偲偐儅儔僪乕僫偲偐丄偄傠傫側恖乆偑儔僥儞傾儊儕僇拞偐傜廤傑偭偰丄偦偺栚榑尒傪姰慡偵捵偟偰偟傑偭偨丅奺崙偺戝摑椞傕斀懳偟偨傫偱偡丅偦偺堄枴偱偼丄暷崙偺尵偄側傝偵側傝偨偔側偄丄偲偄偆巙岦偼摉慠偁傞丅
偨偩偟丄奺崙偺惌尃偵偼傗偼傝壏搙嵎傕偁傞丅嫀擭偩偭偨偲巚偄傑偡偑丄僽儔僕儖偺儖儔惌尃偲傾儖僛儞僠儞偺僉儖僠僱儖惌尃偑IMF偐傜偺庁嬥傪孞傝忋偘偰慡柺曉娨偡傞偲寛傔偨嵺偵偼丄椉崙偺NGO丄幮夛塣摦偐傜斸敾偑暚弌偟傑偟偨丅乽IMF偵孞傝忋偘曉娨偡傞偔傜偄側傜丄傕偭偲愭偵傗傞偙偲偑偁傞偩傠偆乿偲偄偆傢偗偱偡丅
傕偪傠傫丄崙撪惌嶔偱傕旝柇側堘偄偑偁傞偙偲偼帠幚偱偡丅巗応尨棟傊偺懳墳傗幮夛庡媊偵懳偡傞嫍棧偺庢傝曽側偳偱偡偹丅崱夞傕丄徻偟偔尒偨傢偗偱偼偁傝傑偣傫偑丄儌儔儗僗惌尃偵懳偟偰丄暿偺嵍攈偐傜乽懨嫤楬慄偩乿偲偄偭偨斸敾傪栚偵偟傑偟偨丅
偙偺揰偱偼丄峀悾弮偝傫偺亀摤憟偺嵟彫夞楬亁乮恖暥彂堾丄2006擭乯偑旕忢偵嶲峫偵側傝傑偡丅斵偺暘愅偱偼丄儌儔儗僗惌尃偲帺棫揑側幮夛塣摦偺娫偵傕偦傟側傝偺堘偄丄嬞挘娭學偑偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅
乽恀幚榓夝乿偺摦偒
偙傟偼丄擔杮偺愴屻巎偺弌敪揰偲斾妑偟偰傒傞偲丄旕忢偵偼偭偒傝偟傑偡丅偙偺娫丄懡偔偺儔僥儞傾儊儕僇彅崙偱偼丄乽恀幚榓夝乿偲偄偆尵梩偑摉偨傝慜偺傛偆偵巊傢傟偰偄傑偡丅儔僥儞傾儊儕僇偩偗偱側偔丄柉庡壔傪彑偪庢偭偨娯崙傕丄傾僷儖僩僿僀僩懱惂傪懪搢偟偨撿傾僼儕僇傕偦偆偱偡丅偮傑傝丄帺暘偨偪偑旕忢偵恏偄丄夁崜側忬嫷傪夁偛偟偰偒偨帪戙偵壗偑峴傢傟偨偺偐丄偦傟偼扤偺愑擟偩偭偨偺偐丄恀幚傪抦傞偙偲丄偁傞偄偼愑擟傪捛媦偡傞偙偲偵傛偭偰偟偐丄嫋偟偲榓夝偵帄傞偙偲偑偱偒側偄偲偄偆偙偲偱丄恀幚傪偲偵偐偔捛媮偡傞丅愑擟幰偑惗偒偰偄傞応崌偵偼丄嵸敾偵偐偗傞丅嫋偟偑昁梫側傜偽嫋偡丅偦傟傪摜傑偊偰丄嵟廔揑偵偼榓夝偑昁梫偵側傞丅偦偆偟偨抜奒傪丄尰嵼丄偦傟偧傟偺幮夛偑宱偮偮偁傞傢偗偱偡偹丅
撿傾偺応崌偼摿堎偱丄昁偢偟傕張敱偼敽傢偢丄偍屳偄偑帺暘偺傗偭偨偙偲丄庴偗偨巇懪偪傪愻偄偞傜偄榖偡丅偦傟偵傛偭偰榓夝偺応傪嶌傞偲偄偆帋傒偑峴傢傟傑偟偨丅偄偢傟偵偣傛丄偦偆偄偆宱尡傪宱偰尰嵼偑偁傞傢偗偱偡偹丅偦傟偵斾傋丄杔傜偺幮夛偱偼62擭慜偺抜奒偱丄杔傜偺晝曣傗慶晝曣偺悽戙偑偁偺愴憟偺愑擟偵偮偄偰丄偦偆偟偨宍偱嵸偔偙偲偼側偐偭偨丅愴彑崙偵傛傞嵸偒丄偮傑傝嬌搶孯帠嵸敾乮搶嫗嵸敾乯偙偦偁傝傑偟偨偑丄愴憟偺嵟崅愑擟幰偱偁傞桾恗偼柶嵾偝傟丄怴寷朄壓偱徾挜偲偟偰89擭傑偱惗偒偨丅柉廜偺懁偼1壄憤滒夨偲偄偆宍偱丄愴憟悑峴偺恀幚偼偆傗傓傗偵偝傟丄愑擟幰偼偮偄偵張敱偝傟側偐偭偨丅
姱椈傗惌帯壠傕偦偆偱偡丅娸怣夘偺傛偆側愴憟斊嵾恖傕惗偒墑傃丄屻偵偼庱憡偵傕側偭偨丅偄傑傗偦偺懛偑庱憡偱偡丅偦偆偄偆擔杮偺愴屻巎偲斾妑偟偰丄恀幚榓夝偲偄偆楌巎夁掱偑偄偐偵廳梫偱偁傞偐丄偝傑偞傑側嬯擄傪宱偨戞嶰悽奅偺楌巎丄偲傝傢偗儔僥儞傾儊儕僇傗撿傾偺楌巎偼暔岅偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅崱擔丄儔僥儞傾儊儕僇偱惌帯曄妚丒幮夛曄妚偺戝偒側僄僱儖僊乕偑暚弌偟偰偄傞偺偼丄偦偙偵堦偮偺崻嫆偑偁傞偲峫偊傜傟傑偡丅
孞傝曉偟偵側傝傑偡偑丄孯帠惌尃偺帪戙傪栤偄捈偡偙偲偼丄扨偵捈愙揑側愑擟幰傪嵸偔偩偗偱偼偁傝傑偣傫丅嵟廔揑偵偼丄捈愙揑側愑擟幰偺攚屻偵塀傟丄偁傟偙傟偺宱嵪惌嶔傪墴偟晅偗偰偒偨傾儊儕僇傗崙嵺嬥梈婡娭傪嵸偔丄偦偆偄偆撪幚傪娷傫偱偄傞偲尵偊傑偡丅傕偪傠傫丄偩偐傜偲偄偭偰60乣70擭戙偺傛偆偵丄僎儕儔傗晲憰摤憟偵傛偭偰偦傟傪幚峴偡傞偲偄偆帪戙偱偼偁傝傑偣傫偐傜丄堦斒慖嫇傪捠偠偰帺暘偨偪偺堄巙傪昞尰偡傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偺寢壥偑尰嵼丄怴偨側惌尃偺抋惗偲偄偆宍偱丄偄偔偮偐偺崙偱尰傟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偟傚偆丅儔僥儞傾儊儕僇婯柾偵偍偄偰儌儔儗僗惌尃抋惗偺堄枴傪峫偊傞応崌丄埲忋偺傛偆側娤揰偐傜懆偊傜傟傞偺偱偼側偄偐丄偲峫偊偰偄傑偡丅亖偮偯偔亖
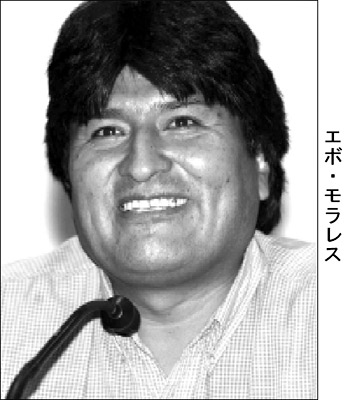
乵幙媈墳摎嘇乶
亂幙栤亃儔僥儞傾儊儕僇偱偼丄偐偮偰偼柉懓夝曻摤憟偺僎儕儔慻怐傕偁偭偨偟丄偄傢備傞乽妚柦惌搣乿傕偁傝傑偟偨傛偹丅嵟嬤偺僯僇儔僌傾偱傕丄僒儞僨傿僯僗僞偺惌帯慻怐偑枹偩偵巆偭偰偄偰丄偦傟偑僆儖僥僈曉傝嶇偒偺尨摦椡偵側偭偨偲暦偒傑偟偨丅偦偺揰偱丄儃儕價傾偺応崌偼惌搣儗儀儖偱偼偳偆側傫偱偟傚偆偐丅尰忬偱偼丄惌搣偦偺傕偺偑乽媽懱惂乿偲偄偆帪戙偵側偭偰偟傑偭偨偺偐丅
亂懢揷亃儃儕價傾偺応崌偼丄僯僇儔僌傾偺僒儞僨傿僯僗僞丄偁傞偄偼僄儖僒儖僶僪儖偺僼傽儔僽儞僪丒儅儖僥傿偺傛偆偵丄偐偮偰晲憰惃椡偱丄忬嫷偺曄壔偵傛偭偰惌搣偵惗傑傟曄傢偭偰慖嫇偵傕嶲壛偡傞偲偄偆丄偦偆偄偆慻怐偼偁傝傑偣傫丅僎僶儔偨偪偑60擭戙偵摤偭偰偄偨摉帪偺僎儕儔塣摦偼丄夡柵偝偣傜傟傑偟偨丅
儌儔儗僗惌尃偵傕暃戝摑椞偵僈儖僔傾丒儕僱儔偲偄偆恖偑偄偰丄斵偼偐偮偰乽僩僁僷僋丒僇僞儕丒僎儕儔孯乿偲偄偆慻怐偵懏偟偰偄傑偟偨丅偨偩丄偦傟偼婯柾傕彫偝偔偰丄儃儕價傾惌帯傪摦偐偟偨偲偄偆傎偳偺惃椡偱偼側偄丅偦傟偵斵帺恎偼丄偢偄傇傫慜偵偦偙傪敳偗偰丄偦偺屻儌儔儗僗偲慻傫偩偲偄偆宱堒偑偁傞丅偩偐傜丄僩僁僷僋丒僇僞儕偑娵偛偲惌搣偵側偭偰丄崱夞偺摦偒偺堦梼傪扴偭偨偲偄偆傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅
偦傕偦傕丄儌儔儗僗惌尃偑埶嫆偟偰偄傞MAS乮Movimiento al Socialismo乯偵偟偰傕丄擔杮偱偼乽幮夛庡媊塣摦搣乿側傫偰栿偝傟偰偄傑偡偑丄梫偡傞偵乽幮夛庡媊偵岦偐偆塣摦乿偱偡偐傜丄偄傢備傞惌搣偱偼側偄偱偡傛偹丅偦偺堄枴偱偼丄儃儕價傾偺応崌丄偲偔偵尰嵼偱偼丄偙傟傑偱巟攝揑偩偭偨塃梼惌搣偲偐拞娫惌搣偼偁傞偗傟偳傕丄偄傢備傞乽嵍攈惌搣乿偲偄偆懚嵼偼側偄偱偡偹丅椺偊偽丄擔杮偱乽柉懓妚柦塣摦搣乿偲栿偝傟傞MNR偼丄拞摴塃攈偱偡丅摨偠偔丄乽嵍攈妚柦塣摦搣乿偲栿偝傟傞MIR傕丄幮夛庡媊僀儞僞乕偵壛柨偟偰偄傞偙偲偐傜暘偐傞傛偆偵丄拞摴嵍攈側傫偱偡偹丅
