HOME>過去号>32号
【研究会報告】「農」研究会;
対抗する現実的な「地域」を対置していく実践が重要だと思う
―内山節著『農の営みから』第2篇・新しい哲学の方向性―
先回はテキスト前半の報告でしたが、今回はテキスト後半の報告です。
「半商品」の思想(第四章)
「半商品」とは、市場では商品として通用し流通しているけれど、それを作る過程や生産者と消費者との関係では、必ずしも商品の合理性が貫かれていない、そんな商品のこと。「多職の民」としての江戸時代の農民の姿から、農村共同体の中で暮らしながら、傍らでは職人労働や賃労働をとおしてもう少し広い世界で暮らしていた百姓像が浮かんでくる。「半賃労働」「半商品」であったゆえに、商品経済の合理性が貫徹されなかった。「半商品」は具体的な関係のなかでつくられたり、流通したりする商品であり、「使用価値」は関係的価値だから、文化的価値でもあり、さまざまな条件やつくり手と受け取り手の関係によって変化していく。
今の時代でも「半商品」の世界が成立する例として“産直”がある。大規模化すると「半商品」による共同世界を失うが、自然との関係、村との関係、消費者との関係が農民の主体をつくりだす。農業には有用性をつくりだす農業の規模の限界があるが、農の営みの中に労働の総合性を回復させ、その全体のなかで半商品の世界をつくることも可能なのではないか?
無事な「場所」についての想像力(第五章)
普遍的な近代思想というのは、実はヨーロッパのローカル思想であり、そして日本的に理解されたヨーロッパ思想でしかない。空間的普遍性は近代的な産業技術の発想であり、「場所」のない拡大系の社会として成立した近代社会。生産力も富も無限に拡大するものと錯覚し、「場所」の制約を受けない思想や技術が確立されてきた。しかし、土地の生産力は飛躍的に拡大しない。「場所」と結びついた、安定した循環を保障する技術や思想の再構築が必要。
経済と違って人間の存在は「場所」から離れられない。すべてのものは地域による変形を受けざるをえないし、思想も政治システムも労働感も同様。循環系の社会を成り立たせる単位としては、共通の精神や風土をもつ「地域」が根源にある。「地域」とは、自然との関係や人間同士の関係、さらには歴史や文化との関係などが安定した状態、循環をつくりだしているところだと思う。農山村の人々と都市の人々との、産直をはじめとするさまざまな交流・交通は、関係がつくりだす共同の生活圏。多元的な「場所」、つまり「場所」が重なったところで、関係を調和させ、うまく折合いをつけていく中に、人間存在がある。
貨幣と「時間価値」(第六章)
貨幣経済は順風満帆で発展してきたのではなく、歴史的に強まった時期も弱まった時期もあり、それは共同体の安定度と関係している。価格という等価の基準がないところの等価交換は、習慣・慣習を目安にしていた。不足と過剰をならしていく共同体の「贈答」、お米で町に「お金」を買いに行った江戸時代の農民。価格とは異なる共同的な交換上の価値基準が、共同体の中でつくりだされていた時代があった。
資本制商品経済は、ものをつくって、それを売って利益をあげる、というかたち成り立っているわけではない。生産や物づくりに目的があるのではなく、それらは貨幣の増殖のための手段でしかない。テイラー、フォード主義以来、何をつくったかでなく何時間働いたかだけが労働の目安となり、労働が時間の消費に変わっていった。わたしたちは、産直を通して共同的で文化的な交換ルールを創造していく必要がある。
新しい思想の方向性(第七章)
思想は、地域自然の性質が反映した、もともとローカルなもの。空間的意味で語られてきた普遍的な思想などありえない。「進んだ地域の思想」として、ヨーロッパの生みだした思想が、発展の末の普遍的思想としての地位を獲得したにすぎない。しかし、歴史全体をみれば、発展していくものもあるし、逆に後退していくものもありながら、その時代がつくりだした価値が展開しているだけなので、歴史に発展という概念は成立ない。私たちは近代的な思想的合意を捨てるべき。思想とは共同的価値であり、その共同性の中では絶対的価値をもつもの。思想も真理も「場所」とともにあり、思想は他者との交流・交通とともにある。
現実的な「地域」を対置する必要性
以上、かなり省略しましたが、「農の営み」というテキストの後半部分の紹介でした。前半と同様に「情緒的で主観的な内容」だという声が出ていましたが、「守田志郎さんのあとを受けた、東北の農家の勉強会での講演だから、省略した表現になっているのは仕方ない」という意見もありました。何にしても「農」研究会にとって検証しづらい主張であることは間違いないようです。以下、少しテキストへの見解をまとめてみました。
「小さな単位の連帯の中に世界をみる」発想が、内山さんが構想する「地域」の中に自然発生的に芽生えてくる(再生産される)とは思えません。多元的な「場所」の重層性のうえに循環系社会を展望するだけでなく、非ヨーロッパでありつつ、「つながっていくこと」の普遍的な思想が必要だと思います。ヨーロッパで生まれた「普遍的な思想」や「発展史観」だけが問題なのではなく、新自由主義による市場競争のグローバル化を通じて、さらに「普遍的な思想」や「発展史観」が増殖・再生産されている社会全体を思想の対象とする必要もあるように思います。
「近代」に思想の個別性・ローカル性を対置するだけではなく、対抗する現実的な「地域」を対置していく実践が重要だと思います。また、農村と都市を固定化して捉え、農業を農村だけのものとして考えていこうとするところにも限界があるのではないでしょうか。「農への直接的なかかわり」を都市部も含めた社会全体にひろげていく可能性を模索していくべきだと考えています。変革の過程では統一的・普遍的な思想が必要であり、変革後のビジョンとしては多様でローカルな思想が共存できる社会のイメージが必要なのかもしれません。ちょっと乱暴な表現ですが、無色透明で演繹的な「アソシエーション」理論と、個別限定的で帰納的な「内山式ノスタルジー」理論の中間あたりに、何か見えてきそうな気がします。
今回の目的は、内山節さんの本そのものではなく、この本を題材にお互いの問題意識を出し合い、今後の研究会のテーマを絞り込んでいくことでした。議論の結果、次回のテキストは、ハンス・イムラー著『経済学は自然をどうとらえたか』(農文協、1997年)の第1部第6章「カール・マルクス―自然と価値理論」に決まりました。「自然の使用価値」「使用価値の源泉は自然の中にある」という考え方は、内山節さん固有のものではなく、重農主義者と呼ばれたケネーにまで遡ることになります。「マルクスがその理論体系の中で使用価値を捨象した」と言われる問題と絡んで、イムラーがこの問題をどのように考えたのか勉強することになりました。チューターはアソシ研事務局の山口さん、9月28日(木)午後6時半からです(終了しています)。興味のある方は是非ご参加ください。(T)
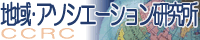
©2002-2011 地域・アソシエーション研究所 All rights reserved.
