HOME>過去号>32号
研究会報告−「よつばらしさ」の根源を探る
第3の経済学―「生命系の経済学」の必要性
はじめに
研究会第4段階の題材は、中村尚司氏の『地域自立の経済学』(第2版、日本評論社、1998年)。本書で一貫して語られているのは、「生命系」という考え方。地球全体を一つの生命系として捉え、さらに循環性・多様性・関係性という異なる性質が三重の層を成して生命系全体を構成しているという。ここに、「エントロピー論」を援用することで、生命の活動を全体として捉え、社会科学と自然科学の双方に生命の把握の手がかりが得られる。かくして、経済学の分野でも、「生命系」を基礎にした「第3の経済学」なるものが提唱されることになる。
このあたりのくだりは研究会のテーマとはずれてしまうので、興味のある方は独自に読んでいただきたい。要するに、市場経済システムや計画経済システムという既存の経済学の発想の中には、生命過程が維持・再生産されることの本質的な意味が盛り込まれていない。したがって、既存の経済学は環境破壊や人間関係の荒廃、市場経済の暴走といった社会問題を解決することができない。しかし、あらゆる学問は生命過程の維持・再生産にとってプラスに働くべきものである。それゆえ、経済学においても「生命系」という考え方を取り込むことで、これまでのさまざまな問題を解決できるはずだ。これが著者の主張である。
経済的自立の意味
著者は本書の冒頭部分で、経済的自立を課題としている。しかしながら、経済的自立を目指す人の目標は必ずしも一致していない。それは、経済的自立には主に三つの意味があり、各々のおかれている立場や環境や利害の違いによって、その範囲や性格を変えるからであるという。その三つの意味とは、
(1)自給自足としての自立
(2)自己決定権としての自立
(3)経済過程が支配的な社会システムからの自立
である。
そもそも、この世の中に完全な自立など存在するはずはなく、他者との関係の中においてのみ人も物も存在可能なのだから、自立とは他者との関係を一定の目標の状態に保つことと言える。となれば、自立の主体に応じて自立の意味は変化するという訳である。こうした多様な経済的自立への要求に対して、市場経済システムも、計画経済システムも明確な答えを用意していない、というのが著者の主張である。
経済の主体としての地域
経済過程は本来、生命過程の一要素に過ぎない。人が生きるために経済があるのであって、経済のために人が生きるわけではない。にもかかわらず、高度に発達した経済過程が生活過程に対立し、生命系の破壊を引き起こしてしまうのはなぜか。本書での答えは、かつて経済過程と生活過程を重ね合わせることができた経済主体が、人間としての統合力を失い、法人機関や行政機関に分断されているからであるとしている。
市場経済システムの場合、巨大な私企業の存在が経済の巨大な発展を可能にし、企業が人を支配する構造を生み出したと言える。企業で働く人間は、当然のことながら生命系のリズムから離れられないのに対し、法人としての私企業は生命過程の制約に挑戦し、乗り越えようとする。計画経済システムにおける公権力もまた、生命系のリズムに左右されない権力機関となり、個々人の感性を越えてしまっているのが現状である。
著者は、私企業や公権力がそれぞれの経済システムにおいて、中心的な経済主体として重要な役割を果たすことに異論はないとしながらも、それらが生命過程を破壊したり解体したりする場合に対抗できる経済主体を見出すことの必要性を主張する。
その経済主体とは、生活過程と経済過程の二重の過程を生き、生身の人間の活動として両者を統合できる存在でなければならない。それは、生活の本拠をともにする者が協力して新たに形成する経済主体であり、そこから「地域」が新たな経済主体となるべきである、との結論が導かれる。つまり、「地域自立の経済学」とは、生活の本拠から出発し、新しい経済学を構築する試みだと言える。
地域自立への主体形成
今回の研究会で取り上げたのは、本書の終章にあたる「地域自立への主体形成」である。生命系に対立する、既存の経済システムに対抗しうる経済主体としての「地域」が、いかにして形成されるのかが論じられている部分である。
経済活動は、さけようもなく共同主体的な営みである。個人で営業する自営業者も、多くの人々の協力なくしては存続することができない。江戸時代の日本において、そのような共同主体の中心的な単位は「むら」であった。庶民の日常的な暮らしは、おおむね「むら」の中で営まれ、そこから外へ出ることは例外的なことであった。
しかし「むら」は、明治以降の近代化・工業化を担う経済主体にはなれなかった。資本主義に不可欠な土地・労働力・信用といった社会関係の商品化に「むら」は馴染めなかったのである。こうして、「むら」にかわる経済主体として、「会社」が登場する。
会社は生命過程の制約を乗り越え、地域を捨て、命に限りがある人間に代わって不死身の存在として発展した。現在では会社に限らず、さまざまな組織が会社モデルによる運営を基本としている。会社という言葉なしに日本人の暮らしは語れなくなっている。
しかし、生命系の維持・再生産という点からみれば、「会社モデル」は「むらモデル」より優位に立てない。効率競争において優位に立つだけである。著者としては、歴史的に「むら」を乗り越えた存在として「会社」があり、さらに「地域」が「会社」を乗り越える、と考えているように読み取れる。
この点については、研究会の中で、「むら」が果して乗り越えられるべき存在か、との批判が出された。「むら」すなわち農村を再評価することは、これからの社会を構想する上で不可欠なのではないか、という意見である(ただし、これについては、あくまでテキストから受けた印象であり、後日行われた中村氏を交えた討論会において、その主張に大きな違いはないものと受け止めた)。
地域の中に作られるべきもの
会社にかわる経済主体としての地域は当然、生命系の維持・再生産を基本とすることになる。生活の本拠の基本単位は家族であり、親子・兄弟・配偶者という家族の三重の基本関係を支えることが、経済活動の基礎となるはずである。
しかし、既存の経済学は、これらの経済的関係をいずれも説明することができない。というのも、生命系の維持・再生産には、経済効率や金銭的利害を超えた関係が必要になるからであり、また、乳幼児から高齢者までの異なった世代が相互に助け合わなければならない地域の協議システムが不可欠だからである。
逆に言えば、市場経済や計画経済ではなく、親子・兄弟・配偶者間に見られる関係を地域の中に持ち込むことが、地域が経済主体となりうる道だということになる。それは、最小限の食糧供給、子育て、老人の養護、医療、災害時の救援活動、地域用水の管理、地域エネルギーの供給、廃物・排水の処理とリサイクルなどの活動を、競争関係や計画目標とはまったく別に、能力に応じて住民が協力し合える社会関係を作り出すことである。
研究会での議論点
ここまで、本書の内容をかいつまんで紹介してきたが、研究会では次のような議論がされた。
ますは、「地域の定義」をめぐって。地域という言葉を改めて考えてみると、人によって捉え方にずいぶん違いがあることがわかった。「生活を共同できる範囲」「生活圏内」「食べ物を手に入れられる範囲」「国家に対する地域」など。世代によっても違いがあるのではないか。都市で暮らすものには、地域を実感できるものは少ない。「ローソン」が地域の象徴だったりする。地理的限界があるかどうかも議論となった。
次に、市場経済に対する著者の捉え方について。著者は市場経済システムを明確に批判せず、ある程度は許容可能としている。その背景には、人間の長い歴史の中で営まれてきた商売・交易などは、優れたものを持っているという主張がある。商品経済を一律に否定せず、部分的に許容する立場は、たしかに現実的主張であり、説得力を持つ。一方、商品化可能なものと不可能なものを分けたとしても、あらゆるものを商品化する現実の動きに対して、どう歯止めができるのか、原理としては商品経済を否定すべきではないか、との意見も出され、議論となったが、見解の一致にはいたらなかった。
さらに、「地域づくり」について。地域づくりとは、まさに人との関係作り。社会関係が解体されている状況を認識し、関係性を取り戻していく活動を、経済活動といかに結び付けていくのか。よつばの現場で、こうしたことが意識できているか。
あるいは、目的に基づくつながりと「地域」との関係、空間的な括りの必要性について。一定の空間的括りの中で活動していくことは、社会変革を目指すうえで不可欠なのではないか。地域を考える際、空間的括りは重要な意味を持つ。
次の時代を創造するために
本書を読んで非常に印象的だったのが、経済や社会の問題を考えるときに、「生命系」という概念を基礎におくという、本書の基本的な考え方である。「人間らしく」、「環境を守る」など、われわれは日常の中でさまざまな課題に取り組んでいるが、その際、環境なら環境という個別的な側面で捉えることが多い。それを生命系という一つの科学的な理論で整理し、エントロピー論という手法で解決の糸口を探る。こうした試みは大変興味深く、実践的であるように思う。
一方、研究会での議論にもあったが、商品経済を完全に否定せずに変革を目指すという姿勢は、たしかに中途半端な印象もあるものの、私自身としては、より現実的で評価できるのではないかという印象も持った。このことは、よつば自身も商品経済から逃れられない中で活動している現状を踏まえ、どういった社会を構想し、実現に向けていくのかを考える際に、突き当たる課題に違いない。
研究会はこの第4段階から、これまでの学習内容を踏まえて、自ら考え構想するという段階に入ってきているようである。次の第5段階で最終段階に入るが、「よつばらしさの根源」に触れ、次の時代を創造するために少しでも役に立つよう、研究の成果をまとめていきたい。(能勢食肉センター・Hさん)
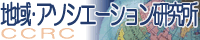
©2002-2011 地域・アソシエーション研究所 All rights reserved.
