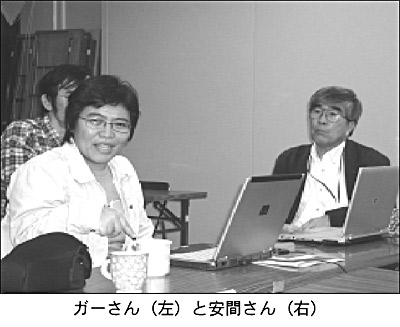重ねられる不平等・不公正な関係
はじめに
11月23日の企画に至る過程で、当研究所を含む実行委員会は二度にわたる事前学習会の機会を持った。その一つが、10月30日(火)に行った「タイ民衆から見た日本・タイ経済連携協定(JTEPA)の問題点」である。翌11月1日の協定発効を前に、改めて問題点を明確化する機会となった。
日タイ経済連携協定(EPA)の問題点
今回の学習会には、タイにおけるJTEPA反対運動の中心となっているNGO「FTAウォッチ」のガンニガー・キティチャクーンさん(通称・ガーさん)をお招きした。ガーさんはジャーナリストを本業とする傍ら、「国境なき医師団(MSF)」タイ支部の活動家として、民衆の医療を受ける権利を保障すべく取り組みを行っている。この間は、日本における地域医療の現状について学ぶため、日本に長期滞在されている。
さらに、ガーさんの通訳兼世話人として、日本国内でタイやフィリピンの諸団体と連携しながら、廃棄物輸出の問題を軸にFTA/EPA反対運動を中心的に担っておられる、化学物質問題市民研究会(東京)の安間武さんからも報告がなされた。
EPA交渉と日本・タイの社会運動
まず安間さんから、JTEPA交渉の経緯、日本とタイにおける市民側の取り組み状況について紹介があった。JTEPA交渉が開始された2003年12月、当時のタクシン政権の下、タイはアジア諸国の中でもFTA/EPAを先駆けて推進し、市民から「FTA症候群」と揶揄されながらも、豪州、インド、中国などと矢継ぎ早にFTA/EPAを締結していった。
中でも、04年6月に開始された米国とのFTA交渉は、締結された場合、その内容が他のASEAN諸国にとっては一種の「基準」として機能するため、東南アジア諸国の市民団体やNGOは会議を重ね、反対行動を起こした。タイ国内でガーさんの所属するFTAウォッチが形成され、活動が活発化していくのも、この時期である。
一方、JTEPAは、すでに05年9月、大筋合意がなされている。農業国であるタイとの貿易自由化は、本来なら大きな話題を呼ぶところだが、影響の大きい品目は予め交渉から除外されたため、全般的に反応は薄かった。
周知のように、その後、反タクシン政権を掲げる軍事クーデターが勃発し、交渉は一時停止した。軍政は当初、反タクシン路線の観点から、急速な貿易自由化にブレーキをかけるかの動きを匂わせ、タイの運動側も一定の関心を持って見守っていた。ところが、国際的認知を求める軍政は、程なく積極姿勢に転じ、今年4月には協定に調印、11月1日に発効、という形で事態は推移した。
安間さんによれば、JTEPAが市民団体やNGOの間で本格的に問題とされ始めたのは、昨年12月だという。協定内容に有害廃棄物の輸出に関する条項が含まれていることが判明したからである。
日本の家電ゴミや産業廃棄物は確かに、再利用可能な「資源」でもある。しかし、処理方法によっては、環境や人体に対して計り知れない汚染をもたらす。それ故、本来ならば、生産・消費国の責任において最終的な処理が行われるべきだろう。ところが、現状ではそうした責任が省みられることなく、「商品」としてアジア諸国に輸出され、実際に少なからぬ被害を招いている。JTEPAの関連条項は、そうした現状をさらに促進するものだ。
こうした問題点を踏まえ、それ以降、タイでは抗議行動が活発化していく。日本の市民団体もまた、政府・財界による「廃棄物輸出」戦略の見直しを求め、反対運動を立ち上げるとともに、タイ側の運動との連携を進めてきた。その中心こそ、他ならぬ安間さんである。
JTEPAの問題点
「JTEPA:不快な協定であり、現状をさらに悪くするプロセス」と題し、ガーさんからの報告が行われた。先に触れたように、ガーさんは国境なき医師団の活動家として、エイズ患者が50万人以上いるタイで、知的所有権を盾にした多国籍製薬資本の圧力と闘い、エイズ治療薬の大衆的な供給に取り組んでいる。そうした活動を通じて、WTO(世界貿易機関)の「知的所有権の貿易関連措置に関する協定」(TRIPs協定)やFTA/EPAにおける特許権条項の問題点に関心を持ち、FTAウォッチの中で情報収集・分析・発信を担当することとなった。
今回の報告も、そうした内容が中心だが、医療や特許にまつわる問題は、日本ではほとんど知られていないため、極めて有益な情報と言えよう。
問題点1 知的所有権とバイオパイラシー多国間交渉たるWTOと比べ、基本的に二国間交渉のFTA/EPAは、協定内容に国力の差がモロに反映される。知的所有権でも、FTA/EPAではWTOのTRIPs協定に比べ、過剰な自由化が行われがちだ。この点で、ガーさんは「バイオパイラシー」の危険性を訴えた。バイオパイラシーとは、「植物品種や土壌中の微生物等の生物資源を、本来の保有者から無断で収集する行為」である。
すでに、先進国の製薬会社やバイオ企業が、途上国において自然資源を無断で収集し、特許を取得する事例が相次いでいる。そうなると、これまで自然資源を利用してきた現地住民は、知的所有権の保護を理由に使用を制限されてしまう。
ところが、JTEPAには、日本企業によるバイオパイラシーを助長する条項が含まれているのだ。
問題点2 医療格差の助長国民皆保険制度のない米国では、民間の医療保険に任意で加入する人がほとんどだ。もちろん、掛け金は高額だし、保険があっても医療費は高い。そのため、治療費が安い途上国に医療ツアーに出かける人々が後を絶たない。行き先はインド、メキシコ、タイなど。それらの国では、医療関係者が儲かる私立病院へ集中している。
ガーさんによると、タイでは、儲からない農村部の病院に勤める医師の割合が全体の5~8%である一方、外国人を含む富裕層向けの割合は16%と、すでに明確な医療格差が生じている。実際、タイに医療ツアーで訪れる日本人は、外国人患者数の約15%を占める、毎年20万人に上るという。
ところがJTEPAには、日本人がタイで受けた医療について、日本の健康保険が適用されるべきだとする内容の文言が含まれている。仮にこれが実現すれば、日本人患者が激増することは間違いない。と同時に、タイにおける医療格差もこれまで以上に激化し、農村医療は崩壊に瀕するだろう。
問題点3 不平等な関係を拡大する投資タイの貿易全体に占める対日貿易の割合は、輸出で14.2%、輸入で24.1%に上る(03年)。日本からタイへの直接投資は、外国投資額全体のおよそ半分を占めている。
問題は、投資条項に国対投資家の紛争解決手続きが入っていることだ。日本の企業の投資が、タイの政策によって不利益をこうむった場合、補償を求め国を訴えることができるようになっているのだ。その手続きには異議申し立ての手続きがなく、三人のパネルによって判断されるという。日本は、タイにとっては最大の投資国であるため不利な訴訟がまかり通る可能性もある。
問題点の本質は何か
以上の問題点を指摘した上で、ガーさんは最後に、日本側の課題について、次のように提起した。
すなわち、①日本の企業が有害廃棄物を他国に輸出しないよう規制・監視する、②他国の資源に対する搾取を行わないよう規制・監視する、③高齢化や医療費高騰など自国の問題を他国に押し付けないよう規制・監視する~である。
こうした提起は、本来タイ側から行われるものではなく、日本側からなされるべきものだろう。JTEPAで懸念される諸問題は結局のところ、大量生産・大量廃棄といった日本人の生活様式に、あるいは新自由主義の浸透における医療・福祉の切り捨てや「外部化」といった状況に突き当たらざるを得ない。
こうした現状を具体的に、広範囲に伝えると同時に、私たち自身が「いま・ここ」から、生活のあり方を見直していく責任がある。そう切実に感じた次第である。(松平尚也:研究所事務局)