ともに生産⇔消費の有機的統一を目指して
はじめに
本誌第39/40合併号で紹介したように、今年3月、韓国ドゥレ生協連合会と交流し、韓国と日本、生協と産直会社という違いはあれ、規模や組織構成、考え方などの点で共通性を感じた。いずれ本格的な現地訪問を、と考えていたところ、今回、ドゥレ生協側から訪問の申し入れがあり、去る10月24日から26日まで、全行程に同行することとなった。その模様を簡単に紹介したい。
よつ葉訪問の経緯など
今回、日本を訪れたのは、総勢20名。そのうち17名は、同生協が組織する生産者組合「ドゥレ生産者会」のメンバーであり、残り3名のうち1人は生産者会の専従事務局員、2人は生協連合会の職員という構成である。
よつ葉グループにも、「安全食品事業協同組合」という組織があったが(今年11月に活動停止)、これは各配送センターや直轄の生産会社(PB=プライベート・ブランド)含んでいたため、これらを除いたような組織と考えられる。
味噌・醤油、海苔、緑茶、惣菜、食肉加工、韓牛肥育など生産品目は多様であり、韓牛肥育の「ドゥレ畜産」以外は、基本的に独立の経営体である。そのため、ドゥレ生協に全量を卸しているところもあれば、部分的な関係の会社もある。それら個々の関係を組合としてまとめ、取り引きの一定割合を会費に充てて専従を置き、課題の共有、質的な連携の深化を追求しているという。
関西空港で出迎えた時点で、一行にはすでに打ち解けた雰囲気が漂っていたため、てっきり年来の関係かと合点していたところ、聞いてみると、各々が社長や責任者クラスながら、まったく初対面だったり、面識はあっても会議で言葉を交わしただけだけだったり、といった人々がほとんどらしい。言い換えれば、今回のような訪問は、単に見聞を広めるという直接的な教育効果だけでなく、行動の共有を通じて互いの関係を密にするという、戦略的な教育効果をも睨んだものとして位置づけられているようだ。
ところで、日本との関係としては、ドゥレ生協はこれまで、生活クラブ生協やグリーン・コープなど大手生協との訪問・交流を行ってきた。それが今回、生協でもなく規模も小さいよつ葉グループを訪れることになったのは、以下の理由によるという。
すなわち、この間の訪問は主に農業生産者を中心に行ってきたが、それだけではなく加工生産者を中心にした日本訪問も必要ではないか、との要望が寄せられ、その内容を煮詰めていく中で、訪問対象を、小規模で、かつ生産密着型の加工、または生産者による付加価値型の加工、あるいは生産者の意識を強く持った加工業者に絞り込んだ、とのことだ。
確かに、よつ葉のPB各社はいずれも生産密着型であり、また、各社で働く人々は必ずしも固定されておらず、直接生産・加工・流通が相互に往来する関係が形成されている。さらに、会員の規模に応じて小規模である。なおかつ、地域的にある程度まとまっており、交通の面でも利便性が高い。いずれにせよ、よつ葉の特徴をうまく捉えた選択と言える。
時間と人数のせめぎ合い
訪問スケジュールは、次の通りである。
【24日】ハム工場/能勢農場/交流会
【25日】食肉センター/別院食品/アロン/大 北食品/物流センター/よつば農産/よつば水 産/よつ葉ビル/交流会
【26日】丹但酪農(酪農農家、丹但牛乳工場)/ 山名酒造
一見して、かなり密集した日程の強行軍であることがお分かりだろう。そのため、各社での見学は平均して、せいぜい1時間強を限度とせざるを得ない。
ところが、さすがに直接生産や加工に携わっている一行だけあって、設備の具合や原料の調達方法、品質管理に関する留意点など、分野は違っても次から次へと質問が飛び出してくる。
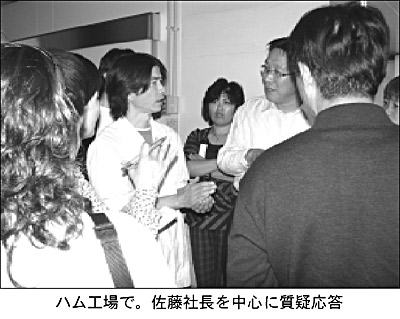
何しろ、総勢20人にも及ぶ大所帯、5人が3分ずつ質問したとしても、応答を含めて軽く30分を超える。通訳兼実質的な世話役の
ところが、その鄭さんも、物流部長の血が騒いだのか、物流センターのピッキングラインではその場に釘付けとなってしまい、案内役の森川さんに怒濤の質問攻撃を繰り返す展開。そんなこんなで、時間は常に押し気味を余儀なくされた。
質問が出るからには、善かれ悪しかれ、何か心に残るものがあるのだろう―。そう思いつつも、各社を見学する中で一行が何を感じているのか、非常に気にかかる。
ようやく意見交換の機会が持てたのは、25日の夕方、よつ葉ビルにおける交流会の席上である。ここで初めて、よつ葉グループの来歴と現状、基本的な考え方、将来展望などを紹介するとともに、訪問団各々から見学の感想をうかがった。
もちろん、これまた時間と人数のせめぎ合いの中で、一言二言が精一杯のところ、それでも、率直な印象が聞けて嬉しかった。以下、かいつまんで紹介する。
「狭い立地条件の中で、効率よく作業をしているように感じられた。」
「韓国では、第一次産品の生産や加工に携わる若者は少ないが、よつ葉には多くの若者がおり、感動した。」
「働いている人たちが皆、誇りを持って働いてるように感じられた。」
「老若男女、障害のある人もない人もいっしょに働いていたことに感心した。」
「各社の社長、責任者も現場の第一線で働いていることがよくわかった。」
「能勢や別院のあたりの風景を見て、自分の故郷にいるような気持ちになった。」
「『モノより人』など、よつ葉の目指しているものと自分たちが目指しているものとの間に、大きな共通性を感じた。」
生産・消費の分断超克に向けて
後日、鄭さんからの御礼のメールには、次のように記されていた。
「帰国の後、研修参加者から感想を聞きました。共通した意見として、暖かい人々と会えて本当によかったということと、次は皆さんに訪韓してほしいということでした。…今回の研修で皆さんが見せくれた笑顔、忘れないようにします。」
また、常務理事の
「今年は、韓国に有機農業とその消費者組織が作られて大よそ20年、当会が創立されて10年目になります。有機農産物が商品の一つになりつつあり、世界的な市場経済が生活の隅々にまで影響を強めているような今日の内外状況から、私たちの運動も一種の転換期を向かえています。
そして、その転換方向の一つに、今までの生産と消費の分断に基づく連結から脱皮して、生産には消費を、消費には生産を、そして生産と消費の役割分担という機能組織からプロシューマーの生活組織に、当生協と生産者組織を交差させ、連帯を強めようとしています。その中で、貴会への研修は、きっと大きく役に立ったと思います。」
「プロシューマー」とは、

それ故、この間よつ葉グループもまた、生産と消費の分断をどう超克するか、そこにおける流通の新たな役割は何か、といった問題意識を、折に触れて表明してきた。その意味で、金さんの提起は、今後の相互交流を深めるに当たり、軸となるべき内容を示したものと言える。お隣の韓国にも、こうした問題意識を持ちつつ、生産・流通・消費に取り組む人々がいること、そうした人々と直に触れ合えたことは、訪問先の各社にとっても大きな財産になったと言えるだろう。
ともあれ、よつ葉農産の
※ ※
【ドゥレ生協連合会の基本方針】
◆ドゥレ生協連合会の行動理念
①食糧自給率と食料安全性及び生態系保全のために努力する。
②生協の食べ物を通じて、市場経済の世界化(グローバル化)戦略に対する問題提起と生活変革を追求する。
③情報公開と参画を通じ、民主的運営を実践する。
④より多くの地域市民に向け、より強化された組合員間のコミュニティ(共同体)回復のため、多様な事業方式を定着させていく。
⑤生産者間のコミュニティをより強化させ、協同セクター形成のための交流と連帯に積極的に寄与する。
◆新しい生協運動のアイデンティティ:地域生命運動
-ドゥレ生協連合会は「生命価値」を中心に据えます。
-ドゥレ生協連合会の「生命価値」を実現する主体は、「大地の母親」とも言える組合員です。
-ドゥレ生協連合会の組合員同士は、生命を中心に「連帯」します。
-その連帯は「大地の母親-町の集まり-地区-単協一連合」という多元的な拡充の関係網(ネットワーク)として創造されます。
-この関係網に支えられるドゥレ生協連合会の事業は、組合員の私的生活領域が組合員同士の横の関係づくりを通じて組織化、構造化、経済化された形態です。
-ドゥレ生協連合会は、「大地の母親」の社会的自己実現のため、多様な生活領域で、地域を舞台に多様な「対案(オルタナティブ)」を創っていきます。
※ドゥレ生協の紹介資料から抜粋。
