「よつ葉の地場野菜」研究会シンポジウム 報告
今後も「食べものを分かち合う」関係を
よつ葉の地場野菜、その現状と課題
関西よつ葉連絡会では「地場と旬」を軸に農産物を扱っている。その象徴が「地場野菜」の取り組みだ。前史も含めると40年近く、中山間地農業の維持発展を目指して、4地区数百軒の農家との間で市場による需給調整とは異なり、協議に基づく野菜の集荷を続けてきた。その結果はどうなのか。地域の農業、農家はどんな状況なのか――。当研究所では現状を把握するために研究会を組織し、これまで足かけ3年にわたって生産、流通、消費の各領域でアンケートを実施してきた。今回そのまとめとして、研究会の成果を報告し論議するシンポジウムを開催した。以下、その概要を紹介する。(文責:当研究所)
今回のシンポジウムは、もともと農家や消費者会員も含め、広く参加を呼びかける公開企画として、今年4月に開催を予定したが、新型コロナウイルス感染症の流行拡大によって延期を余儀なくされた。その後、状況を見ながら8月に再開を試みたが、折悪しく流行のぶり返しと重なり、最終的に公開シンポジウムとしては断念に至った経緯がある。
とはいえ、せめて関係者の間だけでもまとめの報告に基づいた議論の機会が必要だと考え、去る10月14日に非公開の形で実施した次第である。
当日の流れとしては、まず、研究会のとりまとめ役としてアンケートの作成と分析に尽力いただいた大阪市立大学の綱島洋之さんによる報告を受け、関西よつ葉連絡会の外部からの観点として、㈲やさか共同農場の佐藤隆さん、㈱坂ノ途中の小野邦彦さんにコメントをいただいた。
続いて、研究会参加者からは、研究会での議論をを通じて感じたこと、考えたことをそれぞれ語ってもらった。
その上で、地場野菜の取り組みについて基本的な考え方と仕組みを設定し、長らく牽引されてきた、㈲アグロス胡麻郷の橋本昭さん、㈱北摂協同農場元代表の津田道夫さんに、これまでの総括などを提案していただいた。
本来なら、各々の発言を踏まえてさらに議論を深める予定だったが、時間配分を誤り、ほとんど議論の時間が取れずに終わったのは、返す返すも残念だ。
とはいえ、地場野菜の取り組みに対する客観的なデータの集積と分析、それぞれの発言を通じて示された論点は非常に貴重なものである。当日の発言順に基づいて紹介したい。
まずは綱島さんからの報告である。
よつ葉の地場野菜研究会 調査結果報告
綱島洋之(大阪市立大学都市研究プラザ)
生産者アンケートの結果について
まず、地場野菜生産者アンケートの結果から見ていきます。2018年8月に、地場野菜を出荷している4地区に対してアンケートを実施し、計157名から回答をいただきました。ここで驚いたのは、主たる従事者の年齢として、最高92歳で現役の方がおられたことです。一方、最低は31歳で、平均は67.9歳になります。
それから「就農した経緯」について、①生家の跡継ぎ、②農家出身で新規参入、③非農家出身――の三つに区分し、年齢別に集計してみたところ、①は全体の50.3%で、平均年齢は回答時72.0歳、就農時53.4歳、②は22.2%を占め、回答時の平均年齢は76.4歳、就農時は49.8歳、③は26.1%で、回答時の平均年齢は55.5歳、就農時は44.2歳――との実態が分かりました。
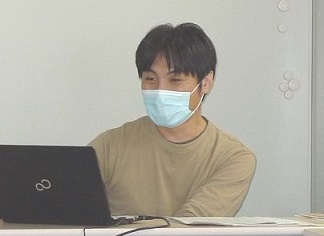 |
| ■綱島洋之さん |
ちなみに、いまも農業を続けている動機について、いくつか選択肢を挙げて訊いたところ、農家出身者とくに生家の跡継ぎの中では「先祖伝来の土地を守らなければならない」との回答が圧倒的に多く、非農家出身者では「自分自身の生計を維持しなければならない」が最も多かったのが特徴的でした。この点でも高齢者と比較的若い生産者との立場の違いがよく現れていると思います。高齢者の場合は基本的に年金を受給している方が大半(生産者全体のうち68.9%)で、収入を得るために農業する動機付けは低い一方、若い生産者は農業で収入を得ないといけないからです。
実際、家計に占める農業収入の割合について尋ねたところ、「50%未満」との回答が71.5%、「95%以上」との回答が12.5%でしたが、前者の平均年齢は72.0歳、後者は46.4歳と鮮明に分かれています。しかも農業収入の中での地場野菜の割合を見てみると、農業で生計を立てようとしている若手ほど農業収入に占める地場野菜の割合が多いことが分かりました。一方で高齢者にとっては、地場野菜からの収入は大きな割合を占めていないようです。
言い換えると、ほとんどの地場野菜生産者の中では、地場野菜が農業収入に占める割合はそれほど高くはないけれども、ごく一部に家計のほぼ全てを農業収入で賄い、地場野菜を主たる収入源としている若手生産者が存在するという構図が浮かび上がってきます。つまり、地場野菜で稼ぐ人とそうでない人に二極化されているわけですが、おそらく今後は少数の若手が地場野菜の主力を担うことになるだろうと考えられます。
こうした構図は、作付け品目を選択する基準にも表れています。生産者が作付けの際に最も重視している基準を集計したところ、第1位は「自分たちが食べたいもの」、第2位が「自分の農法に合うもの」でした。回答者の平均年齢は前者が69.1歳、後者が67.1歳です。では、若手はどうかといえば、回答者の平均年齢が若い順に見ると、「単価が高いもの」「需要が確実なもの」「労働生産性が高いもの」が上位になっています。やはり、稼がないとけない現実が反映していると思います。
ちなみに、こうした事情は営農規模の分布でも、高齢者と若手の差異として反映されています。高齢者の営農規模が10a前後に集中しているのに対して、若手の場合は1ha前後に集中しています。
それから、「農作業で譲れないこと」との設問について、最も多かった回答は「美味しいものを出品する」で36.3%、次いで「減農薬」が34.2%、「特になし」が28.3%でした。ただし、それぞれの回答について年齢の違いは関係なさそうです。関連して、自由記述欄では「無農薬で通せない品目があり農薬を使用せざるを得ない時は心を痛めます」とか、予備調査では「無農薬で通せる作目を追求したら作付け品目が限定された」という回答もありました。つまり、無農薬で作りたいけれども妥協して「減農薬」にせざるを得ない人が一定いることが窺えます。
また、「地場野菜に出荷するメリットをどう感じているか」との設問では、最も多い回答は「少量でも出荷できる」、次が「全量引き取りがあるので収入の見通しが立つ」、さらに「見栄えが悪くても出荷できる」となりました。この点では、例えば農協などへの出荷とは異なるメリットが窺えます。ただし、これらの選択肢を選んだ回答者の平均年齢は回答者全体よりも少々高いことが分かります。
逆に若手はといえば、「価格が安定しているので、作付け計画を立てるときに収入の見通しが立てられる」との回答が際立って平均年齢が低く、若手の関心が集中していることが窺えます。
一方で、一般に産消提携運動では「消費者からフィードバックがある」ことが大きな特徴のはずですが、これをメリットと捉えている生産者は少ないことが分かりました。
消費者アンケートの結果について
続いて、消費者アンケートの結果について見てみたいと思います。2019年3月から8月にかけて行い、計226名の方に回答いただきました。回答者の平均年齢は現在58歳、入会時42歳とのことで、会員歴20年近い方が少なくないことが分かります。また、アンケートの依頼や受け渡しは基本的に、配送センターの職員を通じて配送時にお願いしましたが、そうなると対面でやりとりすることが多いそうです。つまり、平日昼間の時間帯に在宅されているわけで、ということは、回答者の年齢層は消費者会員全体に比べて比較的高めだと考えられます。そうした偏差があることを予め含みおきいただければと思います。
その上で、「会員になろうと決めた理由」(複数回答可)についての設問に対する回答は、「商品の質が良さそうだから」77%、「宅配が便利だから」43%、「配送費が無料だから」27%などとなっています。つまり「質」と「宅配」がキーワードと言えるでしょう。
また、ふだん野菜や果物を購入するときに重視していることについて、アンケートの選択肢ごとに順位付けをお願いし、それを点数化して集計したところ、第1位から順に「旬のもの」「健康に良さそうなもの」「作りたい料理に必要なもの」「美味しそうなもの」「お買い得なもの」などとなり、一般的な消費者に比べてとくに旬と健康を重視していることが窺えます。
さらに、地場野菜に絞った設問の中で、地場野菜を購入している会員が、商品を選ぶにあたって重視している点を尋ねたところ、選択肢で回答の多かった順に「減農薬」60%、「無農薬」58%、「季節感」51%、「鮮度」43%となっています。驚いたのは、「見栄え」「荷姿」という選択肢を選んだ方はいずれもゼロだったことです(ただし、これを真に受けていいのかどうか、議論の余地があるとは思いますが)。
これについては、実は生産者に対しても同じように、「地場野菜の出荷の際に重視している点」について尋ねています。選択肢で回答の多かったのは「美味しいものを出品する」が最も多く、次いで「無農薬・減農薬」、「特になし」という順番になりました。ただし、消費者に比べれば「無農薬・減農薬」に対するこだわりはそれほど強くないように見えます。また、少数ですが「荷姿」や「見栄え」にこだわりを持っている方もいました。いずれにしても、消費者と生産者の間で、こだわりの持ち方が違うことが分かると思います。
地場野菜は一般小売店に比べて割高だといった評判もあるそうです。実際に消費者会員はどう感じているか、その点を質問しましたが、「そもそも値段が違うとは思わない」との回答が15%くらいありました。「いつも納得できないくらいに割高である」との回答、「納得できないくらいに割高なときがある」との回答もありますが、合わせても全体の1割くらいです。むしろ、割高だとしても「品質が良いので納得できる」69%、「生産者を支えるためなら納得できる」44%との回答が多勢を占めました。
関連して、どんな点で品質が良いのか分類して集計したところ、「安全・安心」が78%、「美味しい」が37%、「新鮮」が26%、「無農薬・無化学肥料」が12%となりました。「安全・安心」が消費者の最大の関心事であり、値段は割高でも相応の価値があると考える会員が多いと言えるでしょう。
別の角度から見れば、生産者のこだわりは広く浅く、生産者自身・流通側・消費側それぞれに配慮している傾向が窺えるのに対して、消費者のこだわりは「安全・安心」「無農薬・減農薬」といったあたりに狭く深く集中していることが分かります。
いずれにせよ、地場野菜が消費者から「割高に感じられるけれども納得できる」と受けとられていることは、ある種のブランドが確立されていると見ることができます。
とはいえ、地場野菜のような産消提携の取り組みにとって、需給の調整は大きな課題です。例えば、豊作で大量に入荷する野菜をどう捌くのかという問題があります。地場野菜では一つの対応策として、野菜セットを組むことで対処しています。
消費者アンケートでは、野菜セットを注文する方、しない方、双方に回答いただいていますが、注文しない理由として多かったのが、「単品の方が注文しやすい」とか「何が届くか分からない」などです。一方、「ほぼ毎週」といったように頻繁に注文し続けている会員の場合、注文する理由としては、「お買い得」「注文の手間が省ける」などに加えて、少なからず「食べたり調理したことがない野菜」「全く知らない野菜」との遭遇を期待しているとの回答もありました。
ちなみに、知らない野菜が入っていた際の対応としては、「レシピを本やインターネットで調べる」が61%、「適当に食べる」が42%となっています。実際には、珍しい野菜が入る時には、よつば農産が簡単な説明やレシピを添えているそうです。
また、季節の変化による野菜セットの内容量の変動については、回答の多かった選択肢の順に「多い時に助かる」が39%、「少ない時は割高に感じる」が32%となっています。
ただし、「多い時に困る」も14%にのぼります。野菜セットを食べきれない場合、その対処法としては「保存食を作る」が41%、「お裾分けする」が33%、「ふだん作らない料理に挑戦する」が22%となり、「廃棄する」は4%にとどまっています。
他方、季節や天候条件によっては、逆に入荷が少なく欠品が生じる場合もでてきます。そこで、欠品にかんして尋ねたところ、「他産地の代替品でも構わない」が68%でしたが、「他産地の代替品が届くくらいなら欠品でも構わない」も19%ありました。後者については、例えば「無農薬と減農薬を混同しないで欲しい」というように、代替品として認められないものが届けられているという意見もありました。欠品時の対処法についても、小売店など「他業者から買う」が36%、「ふだんから届く野菜に合わせている」が48%と、二分されています。
よつば農産では、野菜セットなどでも捌ききれないほど大量入荷した際には、配送時に配送員が手売りする「引き売り」も行っています。これをめぐる回答としては、「買うか買わないか実物を見て判断できるので有難い」が48%で最多、次いで「生産者を応援したいので、できるだけ買いたい」46%、「配送員を応援したいので、できるだけ買いたい」31%、「値引きされているので有難い」30%となりました。全般的に否定的な回答は少ないですが、すべての配送センターで頻繁に実施しているわけはなく、また在宅の会員しか対象にできないため、「経験したことがない」との回答も少なからず見受けられました。
さらに、商品に対する不満についての設問です。カタログに掲載されている写真と実際に届いたものが違うと感じる頻度を尋ねたところ、「全くない」が45%、「数か月に1回くらいある」が32%という結果になりました。
商品に不満があった際の対応としては、「よつば農産や産直センターにクレームをつける」が24%、「配送員にクレームをつける」が26%ですが、「我慢する」も40%にのぼりました。「我慢する」頻度は、「数か月に1回くらいある」が39%で最多です。
クレームをつける理由では「お互いのためになるから」との回答が多勢を占め、我慢する理由では「次から買わない」「自然のものなので仕方がない」など複数の回答が見られました。
どんなときにクレームをつけるのか尋ねたところ、最多は「腐れ」でした。一方で、トウ立ちやス入りといった自然現象については、クレームよりも我慢するとの回答が多勢を占めました。
最後に、生産者や配送員に伝えたいこと、そして会員以外の一般消費者に訴えたいことを、自由に記述していただきました。前者については、感謝、慰労、評価、提案などがほとんど、後者については、「食品を主体的に選択して欲しい」との意見が最多で、よつば農産の野菜を勧める意見が続いています。
いずれにしても、記述の中で「安全・安心」「美味しい」「子ども」などのキーワードが頻出した点が特徴的です。すなわち、「安全・安心」かつ「美味しい」から、とくに子育て世帯に相応しく、だからこそ生産者を応援する必要があるんだと、そういうロジックが読み取れるのではないかと思います。
配送・事務担当者アンケート結果
2018年10月から翌年3月にかけて実施し、計91名に回答いただきました。平均の勤務年数は10.3年となっています。
職員とはいえ、地場野菜について「よく知っている」は37%、「漠然と知っている」は58%で、これをどう考えるか、一つ論点になると思います。
関西よつ葉連絡会が地場野菜に力を入れていることについて尋ねたところ、①「今のままで良い」が53%、②「強化すべき」が38%に対して、「他の商品に力を入れるべき」はわずか8%にとどまりました。地場野菜について肯定的な回答が多いと言えるでしょう。
ただ、それぞれの回答に関する理由を記述してもらったところ、①では、現状に妥協せざるを得ない諦観の側面が見受けられ、②では、早急に解決すべき課題が提起されているといったように、裏表があるものと思われます。とりわけ早急に解決すべき課題としては、欠品が多いこと、野菜セットの内容に偏りがあることが問題視されています。この点に関連して、自由記述の中では、「自然のものなので仕方ないという説明は、もう今の時代、通用しなくなってきている」といった厳しい指摘もありました。
また、「引き売り」についての評価は、「このままで良い」が55%で、他の選択肢(いずれも15%未満)を大きく引き離しました。その理由は「会員との話がはずむから」44%、「過剰野菜の存在をアピールすることで地場野菜についての理解が得られるから」39%、「会員が実物を見て買えるから」32%となっています。これらは、会員の評価とも合致しています。
一方、地場野菜の特性上やむを得ない欠品などのトラブルに際して、対応で心がけていることとしては、「申し訳ないという気持ちを伝える」75%、「会員に地場野菜の特性を理解してもらうよう理性的に説明する」50%という順になっています。
ただし、クレームを受けること自体については、大部分が「貴重な情報源」62%と捉え、「時間の無駄」と考える回答はまったくありませんでした。むしろ、消費者から何らかのフィードバックを受けて参考になった、あるいは嬉しかったという回答の方が多く寄せられています。
産地野菜の生産者の意見
以上、地場野菜に携わる関係者へのアンケートと並行して、地場野菜以外の産地野菜の生産者(よつば農産に出荷する北海道と九州の野菜生産者3団体)にも、「よつ葉の地場野菜」をどのように評価するか、お話を聞いています。それをまとめると、次のようになります。
・理念に基づいた需給調整の必要性
全量引き取りを前提とした需給調整の方法は、組合員が世代交代していく中で単なる売るツールになってしまっている。
個々の生産者には取り引きの全体像が見えず、各自が作りたいものに走ると、需給のミスマッチが生じる。
今の生産者がそういうことに意義を見出すのか否かについては、疑問の余地がある。見出さないとしたら、生産者組合とは何なのか。流通ルートを作った人の熱い思いを次世代に受け渡すためにはどういうビジョンが必要なのかという問題である。
地場野菜の目標や到達点が、生産者と消費者で共有できているか。お互い理解し合うための距離感が必要である。やらなければならない理由付けがなければ、有機認証がついた輸入品でもいいことになる。
・後継者育成の取り組みについて
出荷先が確保されていれば、新規の生産者が最初から競争に曝されることにならずに済む。しかし生産者組合の価値は若手に理解されているのだろうか。
有機農業の組織は、今の社会にないものを作り出そうという思いのような、自分なりの目的意識がなければ背負えないが、それさえあれば技術は工夫次第で身に付く。関心とやる気が最も重要である。
・供給量の調整をめぐる産地間の関係について
よつ葉の地場野菜の取り組みは、生産者の顔が見えるという意味では良いと思う。欠点は品不足に陥るリスクを分散できないこと。離れた地域と地元の産品を組み合わせる方が良いのではないか。当組合では出品を止めるよう言われたこともあれば、品薄のときに出品できないかと声がかかることもある。それでは生産者も大変である。地元産を各地の消費者に届けられれば最高だが、ある程度は常に他地域産のものを入れて危険を分散すべきである。
まとめ
以上のアンケート結果、産地野菜生産者からの御意見を踏まえ、私の考えを述べたいと思います。
まず、今後は少数の若手が地場野菜の主力を担うことになるのは明らかです。その一方で、今のところ消費者は地場野菜や生産者に相当程度の理解を示していると言えます。
ただし、今後何らかの形で齟齬が出てくることが予想されるのは、「自分自身の生計を維持しなければならない」若手生産者の一部が、無農薬栽培が困難だと訴えている点です。この点では、自らの「安全・安心」のために、あくまで無農薬にこだわる消費者がいるのも現実です。
そうした場合、消費者が自らの嗜好に合う生産者を選ぶようになり、生産者同士が競合に曝される可能性が出てきます。そうなると、何のための地場野菜かという話にならざるを得ません。
その意味では、生産者と消費者がそれぞれのこだわりを互いに摺り合わせる余地が残されているのではないかと思います。その際、配送・事務担当者が地場野菜について消費者に丁寧に説明する契機として、「クレーム」がむしろポジティブ機能を発揮する可能性があると考えられます。
つまり、生産者と消費者の間に未だ残されている溝は、これから「クレーム」をきっかけとして積極的に取り上げられるべき話題として、ポジティブな意味でとらえ直すことができるわけです。
それから、今回アンケートの結果をまとめた後で、研究会参加者の感想や意見を聞く機会がありましたが、その際に印象に残ったのが、「よつば農産で働き始めたころは、地場野菜に関する自分の考え方に確信が持てなかったが、生産者と消費者の間で働いていくうちに確信が深まっていった」という意見でした。そうしてみると、よつば農産や各配送センターは消費者だけでなく、配送・事務担当者にとっても農業について理解を深めるきっかけを提供している、一種の教育機関でもあると言えるのではないでしょうか。
ただし、今回アンケートという手法とりましたが、当事者に会ったこともない人間が回答を分析するやり方には限界があります。その意味では、今回の調査結果は確固とした「事実」としてではなく、むしろさらなる議論のための叩き台として利用していただきたいと思います。
さて、全体的な状況ですが、「食と農をめぐる環境教育」における未解決の課題として、いかにして「食べ物の安全」と「農業の安定」を両立するのか焦点になっています。「食べ物の安全」が単に消費者の安全を意味するのであれば、生産者同士が競合に曝され、「農業の安定」が脅かされる可能性があるからです。
「食の安全」を追求する実践は、大きくは提携型と認証型に分けられます。提携型の産消提携運動では生産者と消費者が「顔の見える関係」を築くことで、認証型のJAS有機などでは第三者の視点を仲介させることで、生産者は消費者の信頼を得たり、消費者は生産者を選択したりしてきました。よつ葉の地場野菜が提携型に属するのは明らかです。
ただし、「顔が見える」からといって信頼は形成できるのでしょうか。実際の経過から言えば、よつ葉の地場野菜のように認証制度に頼らない産消提携運動は、生産者と消費者が「同じ物を食べる関係」をつくりながら進めてきたし、それは「顔が見える関係」よりももっと深い関係だと言えるのではないでしょうか。生産者が食べているものなら自分たちが食べても安全に違いない。もし危険だとしても、生産者と分かち合えるのなら、そうすべきである――。こちらの方が「顔が見える関係」よりも産消提携運動の本質を示しているし、よつ葉の地場野菜が目指してきたのも、こうした「同じ物を食べる関係」だったと思います。
いずれにせよ、さきほど触れたように、長年にわたる取り組みの中で地場野菜がブランドを確立しつつあることは確かです。ただし、その際のブランドとは何なのか、考えてみる必要があるでしょう。誰かと競争するためのものか、それとも競争以外のところに本当の目的があるのか、だとしたら本当の目的とは何なのか。そのあたりを改めて問うことが、地場野菜の今後を考える契機になると思います。
よつ葉の外から地場野菜を見る
生産者自ら「地場」をつくる
報告に続いて、関西よつ葉連絡会の外からよつ葉の地場野菜はどのように見えるのか、御二方にコメントをいただいた。以下、かいつまんで紹介したい。
まずは、㈲やさか共同農場の佐藤隆さん。広島県尾道市に生まれ育った佐藤さんは18歳の時、自分たちの理想とする共同体をつくるため、仲間とともに島根県弥栄村(現:浜田市弥栄町)に入植した。それから40余年、メンバーの離脱、農産加工への着手などを経て、全国の生協や消費者組織との間に販路を開拓し、営農面積は30ヘクタールを超え、30人以上の従業員を擁するまでになった。関西よつ葉連絡会との関係は長く、広島で共同事業を手がけたこともある。
 |
| ■佐藤隆さん |
そんな佐藤さんは綱島さんの報告、とくに産消提携運動の総括に触れた「まとめ」に対して、次のように評価された。
「とくに、地場野菜の原点として生産者と消費者(農家と都市住民)が「同じ物を食べる関係」「同じ食べものを分かち合う関係」と指摘しておられるのは、まさにその通りだと思います。仮に無農薬だったはずのものが減農薬になったとしても、つくる側がそれを食べているのであれば、受けとる側も同じものを食べようよ、分かち合うんだ、と。それはまったくその通りだと思います。
私は「共同体」を作ろうとして農村に入った人間ですが、「共同体」というのは要するに同じ釜の飯を食べることです。利益の分配ではなくて、ともに暮らす、分かち合う。そこを農業の柱として持たないといけないということをきちんと指摘されていたのは、非常に大切なことだと思います。」
一方で、都市から農村に入植し、長らく暮らしてきた経験から、以下のようにも指摘された。
「(地場野菜に出荷する農家の動機として)自家用の野菜をつくる時に、どうしても余計にできてしまうから出荷すると言われても、きれいごと過ぎると感じてしまう。農家の本心としてはやっぱり食べてほしいんですよ。お金云々よりも。お裾分けも含めてね。ほめてほしいとか。そういう他人との関係の中でやっていると思います。」
「アンケートでは、農業を続ける理由として「先祖からの農地を守る」との回答が多かったようですが、私の地元の農村で言えば、むしろ「我が田地はオレのモンや」という所有意識が強いように思います。いい悪いじゃないですよ。農地解放の歴史があって、ようやく自分の農地を手に入れた、それを手放したくないという思いが強いんではないか。」
「つまり、農村の現状を把握する時には、歴史も踏まえて中からと外からときちっと見ないといけないと思います。」
さらに、自ら生産者として苦闘を重ねてきた実体験から、同じ生産者に対して厳しい指摘を隠さない。
「全量引き取りについて言うと、これは生産者がだらしないと思うんですよね。確かに、いろんな生産者が消費者と関係をつくる第一段階という点では非常に有効な仕組みだと思います。ただ、それがあるから地場野菜の生産者を続けるというのは、あまりにも(システムに)胡坐をかいている。食べものの世界というのは、そんな何かに保証されてできているものではない。全量引き取りを長く続けていこうとするなら、生産者としてもっと努力しないといけないし、提案しないといけない。」
厳しい言葉は、生産者としての主体性、プライドを尊重するが故でもある。生産者を優遇するかのような仕組みが結果的に生産者としての自主性を損なってしまう可能性もあるからだ。
「だから、全体的に見て僕が思うのは、もうちょっと生産者が頑張らないといけないということですね。とくに若手はね。
何を頑張るかというと、技術的なこともあるだろうし、生産量もあるだろうけど、それこそ「地場」というのは自分たちの地域や自分たちの仲間を表しているわけだから。地場野菜を括っているのがよつば農産で、生産者はバラバラで言いたい放題、そんなのは地場野菜と言いませんよ。生産者自らが「地場」(の中身)を作って表現できないと。もっと生産者一人一人顔が見えるようにならないと。」
世代交替のストーリーはあるか
次にコメントいただいたのは、㈱坂ノ途中代表の小野邦彦さん。京都に拠点を置き、ネット通販を使って飲食店や個人宅に野菜などを届ける同社は、「100年先もつづく、農業を」との合言葉の下、環境負荷の少ない農業の拡大を企業目的としている。現在、関西を中心に300軒ほどの農家と関係を持ち、そのほとんどが新規就農者だという。新規就農者の多くは有機農業など環境負荷の少ない農業と親和的であるため、新規就農者を支援することで持続可能な農業の普及が展望できるからだそうだ。
そんな小野さんは、地場野菜が対象とする生産者の範囲について、次のような感想を示された。
「僕が思うのは、農業で生計を立てていこうという人に対して全量引き取りで応えるというのは、いい関係性だと思いますが、別に売れても売れなくても生きていけるという人に対して全量引き取りするというのは、優しさがすごいな、と思いましたね。」
 |
| ■小野邦彦さん |
「やっぱり気になるのは、(報告にあった)これから新規就農の方が(地場野菜の)主力を担っていくんだろうというのは、あくまで希望的観測であって、そのための対策、つまり新規就農の人たちにどうやって世代交替していくのか、そのためのストーリーはあるのかというところです。そこがこれから議論すべきところではないかと思いました。」
小野さんからはその他にも3点ほど、今後の地場野菜を考える上で重要な指摘をいただいた。一つは、これまで地場野菜が築いてきた中身をどのように対象化・可視化するかである。
「このアンケートで定量化され、数字で分析された部分と、自由記述の間のギャップに鍵があるように思います。自由記述の部分は、消費者のコメントを見てもすごい共感性があるじゃないですか。それがたぶんよつ葉が蓄積してきた無形の資産で、そういう定量評価しづらい価値を本当に増やしてきたのか、そのあたりが考えられるようになればいいんじゃないか、そんな風に思いました。」
もう一つは、いかにして生産者と消費者の距離を縮めるかという課題だ。現在では都市と農村の間に共通言語がなくなってしまい、そのままでは産消の交流が成り立たないと考える小野さんは、果たすべき仲介の役割を次のように考える。
「だから、僕らは自分たちの役割として翻訳業務のようなものが大事なんじゃないかと思っていて。たとえば大根のスとか、トマトの割れといった品質の不具合に対して、お客さんが楽しめるような形で説明することで、スの入った大根のが届いたら「ほんまや、スが入ってた」と、当たりを引いたような感覚になってくれることを目指していて。予めそういう説明しておくようなことをしています。」
さらにもう一つ。これは坂ノ途中の事業目的とも関わるが、よつ葉の地場野菜にとっては一種の盲点かもしれない。鋭い指摘である。
「不思議に思ったのは、環境の話が出てこないことです。これはアンケートの項目設定の問題かもしれませんし、よつ葉の会員さんが環境よりも自分の安心・安全に注目する人が多いのか分かりませんが、僕らのお客さんはかなり環境に関心が強い人が多いし、世の中のトレンドとしても環境に関心を持つ人が増えてきていると思うので。うちの嫁さんもよつ葉の会員ですが、彼女に「何でよつ葉を選んだのか」ときくと、「おいしいから」の次に「環境コンシャスなものが多いから」みたいに答えると思うんです。報告では、消費者アンケートの回答者が全体よりも上の年齢層に集中したようですが、その影響で拾い損ねている消費者ニーズとして、そういうところがあるのかなと思いました。」
研究会参加者から
さらに、研究会参加者からも、研究会での議論を通じて考えたことなどを述べてもらった。紙幅の都合上、かなり圧縮して紹介する。また、よつば農産の横井代表には、社としてのまとめと展望を語ってもらった。
辻本静男(元高槻地場農産組合)
よつ葉で配送に携わった後、2004年から2018年まで高槻の原地区で農業をした。原は中山間地で農業が主業になり得ないところ。佐藤さんの言われた「生産者が自ら『地場野菜』の中身について考え、打ち出していく必要がある」というイメージより、野菜作りを楽しんで田んぼ畑を荒らさずに守っていこうという方たちが中心。そういう人たちから、たくさんのことを学んだ。そういう人たちが今後も農業を続けていくことも非常に大事だと思う。
野口博文(よつ葉ホームデリバリー東大阪代表)
生産者の作ったものを消費者に届ける最前線の配送現場で働いている。一番大切にしているのは消費者と直接話をして売るところ。食卓に並んだ野菜を見て、野菜をつくった人のことや配送担当者が話していたことを少しでも思い浮かべてもらえればと思っている。2~3年前に全量引き取りの条件が変わった際には、高齢の農家が農業を止めてしまうきっかけにならないかと心配した。
表木崇(㈱よつば農産、地場野菜担当)
4年目になるが、野菜がいつ出てくるか、どれだけ出てくるかが分らない、必要なときに野菜がなかったり、同じ時期に出荷が集中したり、地場野菜のシステムに翻弄されている。現状では、これまでの枠組みの中に入り込んでいるだけなので、今後は自分で新たに生産者と関係を築いていきたい。入社したのは農業に興味があったというより、ここに入ったら人間としてのあり方を鍛えることができるかなと思ったから。今後も、さまざまな人との関わりを通じて自分を磨いていけたらと思う。
笹川浩子(㈱よつば農産、地場野菜担当)
調査結果を受けて、「やっぱりそうやったんや」と思ったのは、農家の構成だったり、消費者アンケートで野菜や果物がダントツで支持されていること。「意外やな」と思ったのは、消費者アンケートで見栄えや荷姿にこだわる人がゼロだったこと。クレームに関しても我慢する方がそんなに多いとは驚き。消費者、生産者、配送現場からの要望をすべてかなえるのは難しいが、やれることからやっていく。農家と会員の架け橋になれるように、よつば農産としての発信を強めていきたい。
宇野幸子(㈱よつば農産、地場野菜担当)
もともとよつ葉の会員で、入社して3年経ったところ。地場野菜の目的に共感するが、農家の生活がかかっているのでプレッシャーを感じる。野菜セットを組んでいるが、とくに夏場は毎日大量に入荷する野菜を、とりあえず捌いていく状態。今日は綱島さんの報告をはじめ、さまざまなお話を聞き、地場野菜の取り組みを客観的に捉えられたような気がする。とくに佐藤さんのお話では、よつば農産だけの責任ではないと聞いて、少しほっとした。
安原貴美代(㈲北摂協同農場代表)
生産者にとって、作付け前に収入の見通しが立つ地場野菜の取り組みは大きな励みになっている。発注なしで出荷できるのは、改めてすごいことだと思う。生産計画に従って出荷する若手農家もいれば、一日の出荷が5束や10束の高齢者もおり、トータルで地場野菜を支えてもらっている。今回、生産者にアンケートを書いてもらうのに苦労したが、こんなに分かりやすく分析され、職員や会員さんの意見と関連づけられていて驚いた。この結果をどう生かしていけるのか、生産者と一緒に考えていきたい。
横井隆之(㈱よつば農産代表)
よつ葉の配送を15年した後、よつば農産に移って11年。地場野菜は当初、小規模な多数の農家によって入荷量を賄っていたが、ここ数年、品目によって数名の新規就農者が入荷の大半を担う事例も増えた。農家の高齢化は止められず、今後は新規就農者が地場野菜の軸になるだろうが、事情は地区ごとに違う。それぞれの事情に合わせ、当事者とともに対応を考えていきたい。
この間、作付け品目と数量の厳格な運用、特定品目で入荷が集中した際の価格変動など、地場野菜の集荷システムをいくらか変更してきた。農家にとっては一種の出荷制限だが、あくまで地場野菜の取り組みを続けていくために、お互いに譲れるところは譲り合うということ。今後も出荷予定の調整や需要の緻密な予測などに取り組みたい。
配送の経験から言うと、生産者と同じく会員も高齢化が進んでいる。よつ葉は会員による紹介で入会する率が高いが、親から子に継承される事例も多かった。要因の一つは、配送職員と会員の関係だ。消費者アンケートの記述も、それを反映している。今後ますます配送現場を通じた会員に対する働きかけが重要になってくる。
よつ葉の生産者憲章には「私達は……家族の食べ物をつくる心でつくり上げることをめざします」と書かれている。綱島さんの報告にあったように、自分の家族が食べるのと同じものをつくり、それを会員と分かち合うことで「安心・安全」が生まれる。それがよつ葉の言う「顔の見える関係」だと思う。
地場野菜の原点に立ち戻り、農家、会員、配送現場を巻き込んで、新たな産消提携の方向性を考えていきたい。
地場野菜のこれまで、これから
「反グローバル」としての「地場」
最後に、よつば農産の設立も含めて地場野菜の取り組みに当初から関わり、基本的な考え方や仕組みを確立してきた御二方から発言をいただいた。
まずは、京都府南丹市日吉町胡麻にある㈲アグロス胡麻郷の橋本昭さん。地場野菜の生産地4地区で作る「摂丹百姓つなぎの会」の代表を長らく務めてこられた橋本さんは歴史的経緯を踏まえ、「基礎になっている言葉が、(よつば)農産を作った時から、じわじわと変わってきたのではないか」と言う。
「全量引き取りという言葉をずっと引きずっていて、とにかく出てきたものはすべて受けとらないといかん、明日何が出てくるかは問うべきでもない。とりあえず朝、野菜室にあるものを捌かないといけない。それを引き受けるのが全量引き取りなんだ、というようになってしまったのか、という話。」
橋本さんによれば、産消提携運動が生まれた背景には、「近代化」の名の下に化学肥料や農薬を使った農業が主流を占める中、志ある人々が問題提起を行うと同時に、農家とつながろうとする安全な食べ物を求める消費者たちの運動があったという。
「だから、農家も消費者も自分の利害だけを持ち出すことなんて起こりようもなかった。それが当時の雰囲気、産消提携という言葉に託された内実だったと思います。
それがいつの間にか抜けていって、みんな合理的な頭の人ばかりになって、エクセルで数量と値段をいじるようなこと多くなって、産消提携や全量引き取りが重荷になって、それが(よつば)農産の仕事であるかのようになっているのではないかと心配もしています。もしそうだとしたら、本来の意味とはかなり違うので、ぜひ年寄りの記憶も参考にしていただければと思います」
では、「本来の意味」とは何か。
「僕が思うに、地場というのは簡単に言えば「反グローバル」だと思います。何でもグローバル化する中で、対抗的に「地場」というコンセプトを打ち出して、消費者の方も詳しく定義するよりは「へぇ、地場ってええやん」みたいな直感的なところで受けとめられた。それはいまも続いていると思います。
でも、いまやっているのは本当の地場なんかいという話になると、確かに地域から出てきているけれども、考え方としては非常に合理的でグローバル化にも通じるものが重なってもいる。果たして先人たちが地場に託した思いが実現されているのか、将来が描けるのか。単に“何時、何を、どれくらい出せますよ”という合理性ばかり追求していったら、もともと「地場」の中にあった「反グローバル」という発想にはつながらないのではないかと、そんなことを思いました。」
「モノ」の背後には生産・流通・消費それぞれの思いがある。と同時に、それら関係のあり方もまた、何らかの思想を作り出す。橋本さんの言うように、それが「反グローバル」だとすれば、いまそれぞれにどう受けとめられているのか、そこからどう展開していくのか、地場野菜に関わるすべての人々に問われている課題だと言えるだろう。
よつ葉全体で地場野菜を考えてほしい
最後の発言は、これまでよつば農産や北摂協同農場の代表として地場野菜に関わり、この研究会の呼びかけ人でもある津田道夫さん。
「研究会を立ち上げようと思った動機は、橋本さんたちとつくってきたよつ葉の地場野菜の取り組みが、実際にどんな状況を生み出したのか、よつ葉で働く人たちがどう受けとめ、理解しているのか、都会の消費者会員がどんなふうに理解してくれているのか、一度客観的に調べてみたいと思っていたからです。でも、そんな作業は僕らにはできないので、やってくれる人を探した末に綱島さんに行き当たったのが、研究会の構想から2年目ぐらいです。」
そうした立場から、津田さんは研究会の終結に当たって次のような希望・期待に言及した。
「僕としては、この研究会の成果をぜひよつ葉にきちっと受けとめて考えてほしいのが一番です。
これからのよつ葉の地場野菜をいったいどんなふうに発展させていくのかという観点で、この研究会の成果をよつ葉全体としても受けとめてほしい。よつば農産が矢面に立って、一番負担がかかるのはその通りだけれども、同時に、それ以外のよつ葉で働くさまざまな立場の人にも考えるきっかけになってほしいと思います。」
「時代は大きく変わっていて、いろんなところで、これまでのやり方ではダメだと、技術的なところで対応しないといけないというのも確かだけれども、それだけではなくて、どう変えていくのか、よつ葉全体で考えていただきたいと思います。
地場の4地区も(よつば農産の設立から)20年経って大きく変わったと思います。4地区それぞれ、決して同じではない。その特色に見合った取り組みに変えていかないと、これまでと同じように括ったままというわけには行かない。摂丹百姓つなぎの会も、地場野菜の生産地区として、この先どうしていくのか、現状を踏まえてどう変えていくのか、もう一度考えてほしい。そういう取り組みが、よつ葉がよつ葉としてあるための取り組みだと思います。」
食べものは単なる「モノ」に限定されない。食べものの作られ方、届け方、食べ方、いずれもその社会のあり方と密接に関係している。むしろ、社会のあり方の反映と言えるだろう。とすれば、関西よつ葉連絡会は、どのように食べものと関わるのか、食べものを通じて何を目指すのか――。
そうしたことを考える上で、地場野菜の取り組みは依然として重要な課題を提供し続けている。これこそ地場野菜の、もう一つの意義なのかもしれない。
