自分の頭で考えるためのテツガク茶話会
緊急企画 報告
2020年パンデミックと生活過程論
コロナ禍を思想として捉えるために
新型コロナウイルス感染症のパンデミック(世界的流行)は現在も進行中だ。状況は一進一退を繰り返しながら、事態終息の見通しは依然として不透明である。コロナ禍に伴う生活危機、グローバルな覇権をめぐる抗争など、深刻な問題も山積している。しかし、だからこそ視野を広く長くとって考える必要がある。目前の出来事に一喜一憂するだけでなく、この事態を「思想」として捉えてみれば、私たちの現状そして今後の方向性が垣間見えるのではないか。そんな問題意識から、哲学者の田畑稔さんに、今回の事態を思想として捉えるための問題提起をお願いした。以下、その概要を報告する。(文責:当研究所)
「生活過程」論という視座
今日は現状分析というより、今回のコロナ危機をめぐって思想は何を問うべきなのか、その点についてお話ししたいと思います。
この間、私は「マルクスと生活過程論」というテーマに取り組んでいます。これは、これまで出した『マルクスとアソシエーション』『マルクスと哲学』に続くマルクス再読の3冊目になる予定ですが、今日のお話も生活過程論の観点からコロナ危機を考えるものとなります。
では、なぜ生活過程論に着目するのかということですが、私としては、全体像を射程に入れずに専門分野だけを見たり、逆に大ざっぱに全体像を掴もうとするだけでは、現在のような過渡期を捉えきれないと考えるからです。
たとえば、「生活」について、釈迦は「人生は苦である」と言っています。あるいは、ニーチェなら「生きることは闘うことであり、支配することだ」と一言で言います。しかし、それらは全体直感であって、対象を限定して言明しているわけではありません。求められるのは、対象をさまざまな側面に限定した上で、それらが相互に媒介しあいながら全体過程が進んでいく、そのありさまに対してアプローチをしていくことです。
現状を見ると、システムの安定期を過ぎていることは間違いありませんが、現在がどのような来歴を持ち、今後どのような方向へ向かうのかと考えた時には、やはり全体像が問われます。そうした意味での全体像を、マルクスは「総過程」と呼んでいます。総過程の中にはいくつかの過程がさまざまに分節化しながら、それらが相互に媒介しあっている。これがマルクスの総過程の考え方です。
私は暫定的に、マルクスは総過程を下図のように見ていたと考えています。分節化したものが相互に媒介しあっている、その全体の進行、これをマルクスは現実的生活過程、社会的生活過程、歴史的生活過程という言葉で捉えています。
マルクス生活過程論の暫定全体図 I. 総過程 Ia. 現実的生活過程:現に作動中の存在様相で見られた総過程 Ib. 社会的(gesellschaftlich)生活過程:単位社会における総過程 Ic. 歴史的生活過程:マクロな変容過程としての総過程 II. 生命過程:地球環境下の生命史的生態学的過程、ヒトおよび生理学的身体過程 III. 部分諸過程 IIIa. 物質的生活過程:生活手段の生産、分配、交換、消費の行為、構造、過程 IIIb. 社会的(sozial)生活過程:相互諸行為、その構造と過程 IIIc. 政治的生活過程:社会の公的総括、その構造と過程 IIId. 精神的生活過程:認識、価値判定、行為コントロール、想像、学習、表現 の諸活動、その構造と過程 IV. 個人的生活過程:総過程を織り込みつつ織り上げられる人格的な生活過程 |
そうした総過程を構築しているのが、まずは生命過程ですね。これは自然過程とも言い換えられます。人類の場合は長く見つもっても600万年ぐらい、現生人類では16万年ぐらいに過ぎませんが、生命過程そのものは40億年ほどの時間幅になります。もちろん人間も自然過程としての生命過程をベースに生きています。それなしに「文明」も「階級闘争」も成立しません。
次に、経済領域としての物質的生活過程、それから人間同士の関係としての社会的生活過程、さらに社会を公的に総括するさまざまな活動が集まったものとしての政治的生活過程、最後に認識、価値判定、行為コントロールなどを中心とする精神的生活過程――これらが部分諸過程として位置づけられます。
さらに、別枠として個人的生活過程が位置づけられます。というのも、個人的生活過程は総過程を織り込みながらも、当事者の一回きりの人生として織り上げられるものであり、固有の存在位置を持つからです。
ちなみに、マルクス自身は直接こうした分類を行っているわけではありません。私なりにマルクスの主張を解釈した結果、こうした分類ができるということです。
いずれにせよ、こうしたさまざまな過程が相互に媒介しあいながら全体が進行している、そんなイメージで今回のコロナ危機を見たらどうなるか、考えてみましょう。
生命過程としてのコロナ危機
その際、まず前景に出てくるのは生命過程ですね。コロナ危機で死者の数が注目されるのは、生命過程を前景に置いて事態を見ているからです。しかし、他の諸過程はまったく無関係、純粋に生命過程としてコロナ危機を語れるかというと、そうではありません。実際、総過程を意識しながら生命過程を前景に置く形で捉えているはずです。
演劇でも主人公や各場面で重要な役回りの人が前景に出てきますが、同時に後景の脇役も含めて、全体として演劇が行われています。それと同じです。総過程を問題にする場合でも、いつも全体を問題にするわけではなく、前景と後景の関係、スポットライトをどこに当てるか、メリハリをしっかりしないといけません。そうでないと、先ほど触れたように全体直感に流し込んで、中身はなくてイメージだけ残ることになってしまいます。
その意味では、前景に何を置くかを問題にしないような総過程論は意味がありません。常に全体像を意識しながら、いま前景に置くべき過程を捉え、同時に後景として諸過程の相互媒介の姿を想定する、そうしたアプローチになると思います。
新型コロナウイルス感染症は生命に関わる事態なので、生命過程が前景に出るのは当然です。とはいえ、生命過程も総過程の内部で動いています。「パンデミックは自然過程だ」などと言っている人がいますが、見当違いも甚だしい。
今回の事態は象徴的ですが、歴史的に見て感染症が新航路の開発や植民地の征服など文明と自然の衝突から出現してきたのは明らかです。今回だと、経済のグローバル化や巨大都市武漢の存在といった条件が後景にあるからパンデミックになったのです。
自然過程として見た場合でも、これまでは新型コロナウイルスが宿主(コウモリと言われる)との間で安定した寄生関係を持っていたと見られていますが、それが市場で野生肉として売られ、世界の自動車産業の先端となった武漢で感染症が発生し、中国の権威主義体制が初期対応に失敗するといった、一連の事態を伴ったわけですね。
つまり、パンデミックはこうした全体を通して進んだのであって、自然過程だけで済ますことなどとうていできません。自然過程だけで捉えた場合、コウモリに寄生していた新型コロナが変異を起こした末に、人間の肺に達して自分を複製し、人間を死に至らしめる――、そう捉えられると思います。
しかし、それはあくまでパンデミックの可能性でしかなくて、パンデミックの現実性とは違います。現実性を捉える際には、やはり総過程を意識しながら、つねに後景と前景との相互媒介に注目していかないといけない。これが第1点です。
生命過程に関わる第2点として、文明と自然の衝突、つまり人間による自然破壊について指摘されるわけですが、私としては自然破壊について、大まかに三つに区別する必要があると思っています。一つ目は核反応レベルの破壊。これは原爆投下や核実験、原発事故、オゾン層崩壊による宇宙線災害などです。
二つ目は化学反応レベルの破壊。農薬汚染、水俣病などの公害、化石燃料の大量使用による地球温暖化などですね。マルクスが『資本論』で、資本主義農業は「物質代謝」に「回復できない亀裂を生む」と指摘したのは、この領域です。
三つ目が、いま問題になっている「生態系(エコシステム)」レベルの破壊です。地球全体を一つの生息地として、様々な生命種がお互いに棲みあい、生きている。食物連鎖、宿主/寄生関係、共棲、相互適応、ニッチや生殖機会をめぐる競合といった、無数の生物種内、生物種間の相互諸関係が一つの安定したシステムを作っている。これが生態系です。現在、こうした生態系に対する破壊がすさまじい状況になっています。膨大な量の絶滅種、絶滅危惧種が想定されるほどです。今回のパンデミックについても、まずはそうした生物種間の相互関係の問題として捉えないといけません。以上が第2点です。
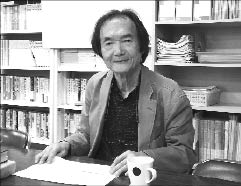 |
| ■田畑稔さん |
第3点として、生命過程については今日、全体論的(ホリスティック)アプローチと要素論的アプローチの深刻な分裂があると思います。
資本主義は圧倒的に要素論的アプローチですね。例えば、ウイルスが人間の肺に潜り込んだとき、どのように自らを複製していくのか、それに対する人間の生体反応はどうなるのか。ミクロの視点で研究し、ワクチンの開発につなげていこうとする。
しかし、私たちはそういうわけにはいきません。もちろん、ミクロのアプローチそのものを否定するわけではありませんが、パンデミックは長い歴史幅の文明史的な過程の中で生じているわけですから、それを捉えるには全体論的なアプローチも必要です。ところが、大変な危機が迫っているのに悠長なことなんか言ってられるかということで、資本主義はミクロのアプローチ一本槍になってしまう。それではまずい。
こうした全体論的なアプローチと要素論的なアプローチの深刻な分裂は、実は人類史の将来展望において一番大事な問題になっています。後でまた紹介したいと思います。
コロナ危機と国家
以上、コロナ危機が生じて最初に前景に現れたのが生命過程だとすると、次に前景に出てきたのは、国家権力です。国家権力は、「そもそも論」で言えば「社会の公的総括」としての政治、その制度と言うことができます。公権力、政府機関と言い換えられるでしょう。こうした領域を、マルクスは「政治的生活過程」と捉えています。
今回、個人や企業などでは対処できない危機的状況の中で、国家権力の「正統な」権力掌握者たちが非常事態宣言などを通じて、営業や移動といった市民の自由権の一部を制限しました。同時に、医療崩壊の阻止やワクチン開発などへ社会資源を動員するとともに、一時金給付や休業補償など分配の経済による生活危機への応急措置を行いました。こうしたことは権力がなければできません。
もっとも、どの国の権力掌握者たちも最初は事態にうろたえ、混乱した対応を余儀なくされました。急展開する事態に対応が遅れたり、専門家の判断と政治権力者の判断が食い違ったり、感染症対策と経済活動再開の判断が衝突したり、ひどい事例では大統領の愚かな判断で死なずに済んだ大量の死者が出たことなども厳然たる事実です。
しかし、最大の問題は、事態が国家を越えてグローバルに進んでいるにもかかわらず、国家権力は国民国家の範囲に留まらざるを得ない、このギャップです。今回のパンデミックに限らず、温暖化、核拡散、人口爆発、大量の難民や貧困、グローバル資本の規制といったように、グローバルな問題が山積している。にもかかわらず、国民国家の権力掌握者たちのほとんどが自国のこと、もっと言えば自らの権力しか眼中にない。今回、そうした実態が改めて明らかになりました。
こうした傾向は、「アメリカ・ファースト」を叫ぶトランプ大統領の米国、習近平政権下で権威主義体制が強化されている中国で顕著ですが、それに対して国際協調に基づく対応を主導すべきWHO(世界保健機関)も信頼を大きく失墜しました。
こうした深刻な状況に対しては、単に実態について云々するだけでなく、「そもそも論」で考えないといけません。私はこの点で、マルクスの政治過程や国家論の端初規定で強調した「社会の公的総括」という視点、そこから「民衆の自己統治で公権力を社会に再吸収する」という方向性が非常に重要だと思っています。
「人間たちの生活過程」と「資本の生活過程」
それから、経済過程つまり物質的生活過程で見れば、非正規雇用労働者や外国人労働者が職を失ったり、封鎖や営業自粛要請で自営業者が廃業や営業危機に追い込まれたり、多くの人々を生活危機が直撃しています。企業の倒産、整理、統合、合理化、解雇はこれから本格化すると見られています。
物質的生活過程についても、やはり「そもそも論」が問われます。こうした危機に際しては、個別資本ではなく国家が前に出るわけです。1人10万円の特別定額給付金を出したのは国家です。あのトヨタといえども、私的企業はこんな時は役に立ちません。
私的企業が経済過程つまり物質的生活過程を牛耳っているというのは、平時の安定した経済システムでの話です。危機の局面では国家が前に出てくる。国家を媒介にして、初めて経済過程も成り立つわけですよね。
先ほど、自然過程としての生命過程に着目する場合でも、パンデミックを捉えようとすれば総過程、つまり巨大都市武漢とかグローバル企業といった問題を媒介にして初めて理解できると言いましたが、それと同じです。危機局面では経済領域でも国家が前景に出てくるわけです。
ここで「そもそも論」が問われてきます。そもそも経済とは何のためにあるのか。マルクスは「食・住・衣」と言っています。つまり、生活手段の生産、分配、消費です。あくまでも生活がベースなんです。生活するためには、まずは食べものが必要だし、雨露をしのぐ家も必要だし、着るものも必要だ――ということで、人間たちは生活手段を作って、分配して、交換して、消費するわけですよね。これが、そもそもの経済領域です。
ところが、そうしたそもそもの経済領域、つまり人間たちの生活過程が資本の生活過程にひっくり返ってしまっているというのが、マルクスの批判です。自分たちの生活手段を一生懸命作っているつもりが、実は資本の生活過程になっているんじゃないか、というわけです。
逆に言えば、物質的生活過程の中での対抗的な運動も、資本の生活過程に転倒させないような形態が中心になります。たとえば、労働者協同組合などアソシエーション型の社会的連帯経済とか、エコロジー志向の地域循環型経済圏の構築運動とか、社会民主主義政府樹立による生活保障や社会的サービス形態での分配経済とか、生産性上昇による労働時間短縮=自由時間拡大とか――、どれも「生活」中心の形態ですね。
ただし、そのためには当事者が自らのライフスタイルについて不断に自己吟味したり、知的文化的な対抗ヘゲモニーを展開してくことが欠かせません。そうでなければ資本側の欲求操作と余暇商品の消費などによって、容易に転倒されてしまうからです。
いずれにせよ、そもそも論として、あくまで生活手段の生産、分配、交換、消費が経済のベースであるはずなのに、資本の生活過程になってしまっている。そこにパンデミックが重なりあってくるのが物質的生活過程の重要なポイントです。ただ、今回のような危機の際には分配経済が前に出てくるわけで、商品売買の形でだけ経済を考える必要はないことが明らかになったとも言えます。だから、生活手段に立ち戻って、共同で生産し、分配するような経済の規模をさらに大きくしていく可能性もある。
ちなみに、この間ベーシックインカムについて論議が浮上していますが、マルクスの観点からすると消極的にならざるを得ない側面があります。というのも、ベーシックインカムで想定されているのは、基本的には現金給付ですよね。現金給付を否定する必要はないけれども、現金給付だけで済ませていいのかという話になるわけです。
繰り返しになりますが、マルクスの経済に対するそもそも論は生活手段が中心、つまり生活手段の経済学ですから、イロハのイは生活手段なんですね。そして、生活手段は財とサービスから成り立っています。だから、現金だけ給付して、あとは投資でもなんでもやって下さいというのは筋が違うことになると思います。
深化する「相互行為の脱身体化」
社会的生活過程つまり人間同士の関係で言えば、端的には「相互行為の脱身体化」が深化したと言えるでしょう。感染拡大を防ぐには、感染者を隔離し、直接の接触を遮断するしかありませんが、今回の場合は未発症の感染者も多いわけですね。そこで、人と人との関係を、できるだけ身体的ではない形で置き換えようとする動きが前景に出てきました。テレワーク、遠隔授業、電子決済、オンライン診断、ネットショッピング、新型コロナ接触確認アプリ――、全部そうですね。
もちろん、こうした脱身体化のプロセスはこれまでも進んでいましたが、今回の事態を契機に決定的に深化しつつあります。現実に対して批判的な問題意識を持った若者でも、こうしたプラットフォーム型の社会に希望を託す人は少なくありません。
しかし、ここで考えてほしいのは、ベースがあってこそ可能だということです。プラットフォーム型の社会にしても、グローバル市民のネットワークにしても、確かに大事ですが、人と人との関係のベースがあってこそ成り立つわけです。その意味では、人と人との関係が変容を迫られている現在だからこそ、むしろベースを問題にするべきだと思います。
たとえば、人と人との「関係」と言っても、最初から関係があるわけではありません。まずは行為、相互行為があって関係が成立します。どんな関係でも、まず自分が行為を積み上げて作らないと、関係なんてできませんね。だから、行為論なしに関係を論じるのは間違いです。
その意味で、まずは人と人との相互行為に着目しないと社会は解けない。相互行為をベースにして見たら、最初に来るのは身体と身体の直接行為です。母子関係やパートナー関係は、その最たるものです。抱き合ったり、母乳を飲んだり、セックスしたり、喧嘩でドツキあったり、そういう直接的で身体的な相互行為がベースとなるのは間違いない。
それから言語行為。たとえば、約束をするのも面と向かって(face to faceで)するからできます。顔も見ないで相手を信用するのは難しい。これまで私と相手の間に築かれてきた長い相互行為の歴史があって、それが信用という関係になるわけです。だからこそ約束とか説得とかができるので、口先だけで説得なんかできませんね。そうした意味で、「相互行為の脱身体化」が急速に深化しつつある現状は、まったく楽観視するわけにはいきません。
たとえば、ネットワークと権力の関係はどうか。国家でも経済でも権力システムで動いていますから、権力システムとネットワークとの関係が問われなければいけない。実際には、この間、安定した雇用関係が崩壊して、一部に富裕層が形成される一方、膨大な貧困層が蓄積されています。これは端的に図式化して言えば、権力は中枢部分だけ、つまり戦略的な部分、イノベーション部分だけは直接抱え込むけれども、それ以外はネットワークでそのつど調達する。雇用も非正規を拡大する。そんな状況が今後さらに進む可能性が高い。
古代の文明に鉄が果たした役割のように、またマルクスの時代に産業革命が世界を変えたように、情報革命が歴史を大きく変える力を持っていることは間違いありません。ただし、産業革命で言えば、巨大な生産力は同時に巨大な破壊力としても立ち現われてきたわけで、当然ながら情報革命の力も同じように明と暗の両義性を含んでいます。それらを腑分けせず、明の部分だけ着目して楽観論に安住することなど、とうていできません。
この点に関連して、中国に象徴されるような監視社会と権威主義体制の問題もありますが、ここでは問題の提示にとどめます。
コスモロジー危機と制度イデオロギー
さらに、私たちの認識や価値判断といった精神的生活過程を前景に置いて今回の危機を考えると、宗教的コスモロジーが過去のものになったことが改めて明白になりました。
コスモロジーとは宇宙論や世界観を意味します。人間の精神は、何であれ世界が秩序立っていないと安心できません。秩序立っているから、現状を辛抱すれば次の展望が開けると考え、努力もできます。逆に、そうした秩序が崩れてしまい、何がどうなっているか分からなくなると、現状に耐えられません。その意味で、今回のパンデミックは私たちに一種のコスモロジー危機を招いたと言えるでしょう。
歴史的に見ると、顕微鏡ができたのは16世紀、ウイルスの発見は19世紀ですから、それまでは疫病の原因も分りませんでした。だから、疫病神や厄神や「神の怒り」というように疫病の原因を人格化し、祈祷や祭祀によって疫病神や厄神を鎮めたり、怒った神に謝るといった努力目標を作って対処しました。言い換えると、宗教的コスモロジーを作り上げることで疫病に対応したわけです。
しかし、現在は科学知の時代ですから、新聞やテレビでは毎日「エヴィデンス」や「サイエンス」といった言葉が叫ばれ、感染症の危険性、対処、現状認識、克服の条件などが解説されます。科学知は膨大なデータを集めて、整合的な仮説を立て、実験を通じた検証と反証のプロセスですから、宗教とは違って「絶対」なんてことは言いません。昔のように原因が分らないことで恐れおののくこともありません。宗教コスモロジーの時代は明らかに過去となりました。
しかし、だからコスモロジー危機はないのかといえば、そうではありません。新しいコスモロジー危機はどこにあるのか、いま問われています。それは端的に言えば、世俗化したコスモロジーとしての制度イデオロギーです。
宗教的コスモロジーが世俗化する過程で宗教イデオロギーのような全体イデオロギーがなくなった結果、制度イデオロギーが跋扈したわけですね。その最たるものは、国家主義とか民族主義、国民主義です。安倍さんは典型的です。国民国家を基礎にして、天皇を前景に置いて、愛国心を強調する。宗教コスモロジーが世俗化して、全体イデオロギーがなくなった後に、こうした制度イデオロギーが跋扈したということです。
制度イデオロギーの中心はおおむね国家主義が担っていますが、とくに戦後の日本では80年代の末ぐらいまで会社主義も絶大な力を持っていましたね。それから近代家族(マイホーム)主義と科学技術の権威。科学知といっても、人々は科学知を裏付けて信じているわけではなくて、科学の権威、専門家の権威を信じているわけです。これらが世俗化後の今日のイデオロギー、コスモロジーの中心です。
そうした制度イデオロギーの弱点は、制度そのものが危機の局面を迎えた際に、新たな方向性を語れないところにあります。端的に言えば、ワクチン開発を待望し、嵐が過ぎるのを待ち、早く元へ戻れるように願望・確信することしかできません。だから思想が必要なんですね。宗教に戻れというのは時代錯誤であり、権威を受容するだけの科学も批判しないといけません。制度イデオロギーの制度そのものを超え出る努力が問われてきます。
ここで重大な問題となっているのが、先ほど言ったように、生命観や生命研究をめぐって全体論的(ホリスティック)な生命観と要素論的なミクロの生命観に分裂していることです。大まかに、前者は進化論やエコロジー(生態学)の流れで、フィールド調査、歴史研究、環境保護運動を志向し、文明と自然の関係のラディカルな反省を強調しています。
一方、後者は文明と自然の関係といった大きな枠組みを問題にすることなどなく、ウイルスや生命についてミクロの視点で技術的に取り組むことが中心です。現代文明は明らかに後者です。というのは、資本主義と親和的だからです。文明と自然の関係を問い直すことなど考えず、当面は国家が前面に出て分配経済で持ち堪え、その間にワクチンや新薬の開発、究極的には遺伝子操作へ向かって競合しながら突進しているわけです。
果たしてそれでいいのか。いずれにせよ、両者の分岐は実に根深い。人類史の未来展望にも関わってくると思います。このあたりが精神的生活過程論の問題と言えるでしょう。
個人レベルで語ることの固有性
個人的生活過程について一言だけ言うと、統計上の死者数などでは現れてこない、一人一人の無残な死があるということです。中国やイタリアなどでは、大勢が病院に殺到して、治療にまで至らずに野たれ死んだような事例が少なくないそうです。
個人の人生は二つとなく、しかもたった一回きりです。これは、他の生活過程にはない個人的生活過程の特質です。そんなかけがえのない人生なのに、なぜこの状況で、なぜこのように死ぬことになってしまったのか。そこが問われないといけません。パンデミック危機の局面は一般的な危機ではなく、当事者個々人にとって現れるからです。
米国で言えば、トランプのような愚かな大統領のおかげで、死ななくてもいい人まで生命を失った。中国でも、権威主義体制が隠蔽しなければ助かった人もいたわけです。だから、必ず個人レベルでこの危機を語ることが必要です。戦争を問題にする場合でも、原発を問題にする場合でも同じです。
もちろん、すべてを個人的生活過程で済ますわけにはいきません。これまで述べてきたようなさまざまな生活過程を含めて考えなければいけないわけですが、同時に個人的生活過程には欠かすことのできない固有の意味があることも押さえておく必要があると思います。
「実践としての歴史」に立脚する
最後に歴史的生活過程ですが、これはマクロな変容過程としての総過程と位置づけられます。一般に歴史と言うと歴史学を想定されるかもしれません。歴史学で考えると、まずは歴史的事件に示されるような「出来事としての歴史」があり、それから当事者の証言に示される「物語としての歴史」があります。さらに、さまざまな形で歴史的事実を再構成する「再現としての歴史」もあれば、歴史に指針を見出す「教訓としての歴史」もあります。
しかし、これらは歴史学の話です。歴史的生活過程は、端的に言って「実践としての歴史」です。言い換えると、私たちは現にこの場で実践的な変容過程や自覚的な変革過程を生きているということです。もちろん、その際には「教訓としての歴史」も、専門家による「再現としての歴史」も、「物語としての歴史」も必要になってくるでしょう。ただし、実践を中心に置かなければ歴史的生活過程として総括はできません。
総括は、たとえば一つの事件があって、予兆があって、開始があって、展開があって、一定の結末があって、総括に至ります。一つの事件をとってもさまざまな局面がある。では、いまコロナはどの局面にあるのか、分かりませんね。つまり、私たちは現在どの局面にあるのかさえ分からない段階で現実に関わっている。それが歴史的実践なんです。
ギリシア神話では、プロメテウスという予知能力を持った神様が出てきますが、予知能力というのは実は「後知恵」なんですね。皆さんも私も少なからず「後悔先に立たず」を実感した経験があると思いますが、後知恵を先取りしたいという共同幻想から生まれたのがプロメテウスだと考えられます。たしかにその気持ちは分かりますが、現実には後知恵で勝負することはできませんね。あくまで現に進行しているプロセスで勝負しないといけない。そこが歴史的生活過程の重要なポイントです。
たとえば、マルクスを見ても、実際には時代や局面に応じてさまざまな歴史的実践を転々と行っています。別に超人でもなんでもない思想家であり革命家ですから、転々と変わるのが当たり前です。その意味で、焦点を当てるべきなのは、彼の歴史的実践のあれこれではなくて、歴史的実践の諸条件について一般的にあれこれ語っている、そうした部分だと思います。
私の場合、その中心はまさに総過程を意識するということです。つまり、全体直感ではダメであって、総過程つまり全体を分節化したものの相互媒介のプロセスとして捉える。
ただし、そのように分節化した各々の部分過程についても、ドミナント(支配的)なもの、補完的なもの、対抗的はものへと分節化していて、それらが複雑に重なりあい相互に媒介しあいながら総過程が進んでいくことには注意が必要です。たとえば、物質的生活過程つまり経済領域を見ても、資本主義的なものもあれば、協同組合的なものもあれば、国家による分配経済もあるわけで、ドミナントな経済システムだけ完結しているわけではありません。
さらに今回のような危機の局面では、安定して相互に媒介しあっていた状況が切断されます。複雑に重なりあっていただけに、一つが切れると次々に切れる。営業や移動の権利が制限され、生産が停止し、対面コミュニケーションができなくなる。こうした局面でこそ歴史的実践が問われてくるわけです。
この点でマルクスが言っているのは、そうした局面を表面的に捉え、体験だけで語るのではだめで、深いところで総過程を構成しているさまざまな媒介が次々と切断されていることを把握するような知的努力が必要だということです。そうした知的努力を踏まえてこそ、次の時代を開くような変革論、変革の運動が生まれる条件ができてくるわけで、私としては、こうした点が現在もマルクスを参照すべき魅力の一つだと考えています。
「宗教コスモロジー」と「制度イデオロギー」
【質問】そもそも生活過程論に着目されたきっかけは、いわゆる「土台・上部構造」に基づく土台決定論への批判からですよね。
【田畑】たしかにマルクスは『経済学批判』(1859年)の序言で「土台・上部構造」について述べていますが、他のところでは別の言い方もしています。ところが後年、いわゆる「マルクス・レーニン主義」の公式として、それがマルクスの中心的な主張とされ、土台=経済、上部構造=政治と分けられてしまいました。その結果、まともな国家論もできない状態が長く続きました。
当たり前ですが、国家は社会を離れては存在しないし、国家を再び社会へ埋め戻さないといけないというのがマルクスの基本的なモチーフです。ところが土台と上部構造を静止状態で捉えてしまっては、ほとんど現実を説明できません。
そうした問題意識から、私はマルクス国家論の端初規定として「社会の公的総括」という視点を提起したわけです。
【質問】今回のパンデミックが何をもたらしたのか、一番鮮明なのは、私たちが生きている現実のありよう、その由来や構造を逆照射したことだと思うんです。その点で、まさに総過程として掘り下げることの必要性がよく分かったような気がします。
その上で質問ですが、精神的生活過程のところで、宗教的なコスモロジーが退場して、それが世俗化して制度イデオロギーになっていくと言われました。そうだと思いますが、同時に制度イデオロギーにしても科学知にしても、すぐに全体性が与えられるわけではない。それが逆に、宗教的コスモロジーの劣化版みたいな形で一種の陰謀論まで現れる原因かもしれません。また、個人的生活過程の固有性を誰が保証してくれるのか、という欲求にもつながってくると思います。そのあたりはどうでしょうか。
【田畑】私は反科学主義はナンセンスだと思いますが、科学知批判は必要不可欠だと思っています。実態を暴く形での科学知批判ですね。それは先ほど言ったように、人類史の未来展望にも関わってくるし、それから情報革命の明暗両用を腑分けする際にも、非常に重要になってきます。
宗教と科学知の差異について考えるべきことはたくさんありますが、とりあえずおおざっぱにいくつかの特徴を上げてみます。
たとえば「原理主義」があります。原理主義は世俗化できないマイナーな宗教集団として現在も残っており、世界の秩序に対する脅威と見られています。しかし、原理主義集団が世界を牛耳っているわけではありません。実際、中東で石油や権力を握っているのは世俗化した宗教集団です。そこを間違わないようにしないといけない。
要するに、宗教原理主義を批判すれば現代の水準でコスモロジーを論じられるなんて大間違です。先ほど制度イデオロギーに触れた際に、その最たるものは国民国家における政治権力の安定、それから生産力だと指摘しました。現実に、アメリカも中国もロシアも、すべてそれで自己正当化しています。
会社主義でも、古いモデルは力を失いましたが、会社主義そのものがなくなったわけではありません。たとえば、橋下徹のやったことはまさに会社主義ですよね。株主総会で決まれば経営陣がトップダウンで経営するように、選挙で勝てば首長が自由にトップダウンでやる。それが「決定できる民主主義」だと言っています。これは会社主義のモデルチェンジですが、現実に人々が構築しているコスモロジーとして、非常に根強いものがあります。
いずれにせよ、こうした制度イデオロギーを正面からどう克服するのか、今日のコスモロジー危機を考える上で非常に重たい問題だと思います。
ついでに、6月に出た『アフター・コロナ:見えてきた7つのメガトレンド』(日経BP)というムックを紹介しておきます。同書では、まだコロナ禍の行く末も分らない状況で、コロナ後に7つのトレンドがあるとして、生き残るにはそれに乗るべきだと説いています。先ほど私の言った「相互行為の脱身体化」なども「ニュー・リアリティー(新たな現実)」というように、口当たりのいい言葉で言われています。新たな現実なんだから良いも悪いもなく、それに乗っかる以外ないというわけです。
結局、制度イデオロギーの下で生存競争しようとする人たちは、所与の前提に対してポジティブに構える以外ない。歴史的なレベルで、もう一度新しい全体的なコスモロジーを考え直そうとか、そんなことを言っていたら現在の制度の中で生き残れない。制度の枠組みの外に出るような議論なんてネガティブで、トレンドだから抗ったらダメ、乗っかって竿をさす以外に語ることがないわけです。
逆に言えば、こういう危機の局面では、皆さんや私のような、いつも枠組みの外で冷や飯を食っている人間ががんばらないといけないと思います。
生活レベルからグローバルな連携を
【質問】グローバリズムが結果的に現在のような感染状況を招いたとすれば、国民国家では対応できず、対応するには世界的規模の政治や人々の連携が必要なのは確かです。ただ一方で、対応不能な国民国家の政治を変えるための基礎は、地域や自治体といったローカルな単位で考える必要があると思います。10万円の給付金でも、決定したのは国ですが、具体的に実行するのは地方自治体だし、実際に現場レベルで大変な作業がなければ実現しませんでした。それは逆に、本来の地方自治の役割が現状では形骸化し、ほとんど空洞化している実態を浮き彫りにしたと思います。やっぱり、地域とか地方自治というレベルでどう対抗していけるのか、改めて考えることも大事じゃないかと思います。
【田畑】おっしゃる通りです。先ほどは時間の関係で触れませんでしたが、今回のコロナ危機に即して、私なりの「ポスト・コロナ社会」への変革構想を考えました。自分の力の範囲を越えていますが、あえていくつか挙げるとすれば、こうなるでしょう。
①生活危機に対処するためアソシエーション型の社会的連帯経済の諸形態の展開
②エコロジー型の地域内循環経済圏構築運動を活性化すること
③生活保障、子供手当などの現金給付と医療や教育の無償化などの社会的サービスの両面にわたるベーシックな分配の経済の画期的な前進
④直面する人類史的課題(温暖化、パンデミック、人間の安全保障、脱原発、少数民族や難民問題、グローバル企業規制など)では、国民国家的ネグレクトや資本主義的歪曲を抑止するために、危機に立つ当事者たちと繋がりつつ、グローバルな市民運動や専門家集団がイニシャティブを発揮し、国際機関、各国政府やメディアを動かす歴史的運動形態
皆さんが長年やってこられたのは①と②に該当するでしょう。いずれにしても、生活ベースから運動を構築していくことは絶対に必要ですよね。私が「思想が大事だ」と言うのは、決して地域とか生活ベースの運動はいらないという意味ではなく、思想そのものが地域や生活ベースの思想にならないといけないということです。現在の制度イデオロギーでは、国民国家や会社、マイホーム主義からの思想になってしまっているからです。
地域あるいは生活ベースの連帯組織が思想とつながり、さらに運動化していくことで、グローバルに連携する条件ができる。④にも挙げましたが、今回の事態を見れば、国民国家レベルを超えた課題に直面していることは明白ですから、国民国家や資本が手に負えない状況を突破していくにはグローバルな連携しかないわけですよね。ところが、私たちがグローバルな課題についてなにがしか展開しようとしても、国民国家が中間で邪魔をしているわけです。
その意味で、私としてはとりあえず生活現場と思想がつながって陣地ができる、生活世界に近いところに陣地ができることがポイントだと思います。ただし、思想とつながらないと陣地はできません。
それから、社会の公的総括つまり政治プロセスへの対応も避けて通れないと思います。この点では、市民運動の中でネガティブな感情も多く見られます。政治に手を出すとロクなことがない、絡め取られてしまう、市民運動だけでやっていればいい――。それではまずい。やはり社会の公的総括のレベルでも勝負を挑まないといけない。もちろん、いまどういう形で挑むべきかについては議論もあるでしょう。一般論で言えば、たとえば③に挙げた分配の経済の領域はかなり重要になってくると思います。
また、おっしゃるように、公的総括の形式を生活世界に近づけていく試みは必要不可欠です。これは言い換えれば、国家権力を社会へ再吸収するというマルクスの基本的な観点でもあります。この点で言うと、ドイツでは社会の公的総括の規模を生活世界に近づけて、コミュナール(市町村)、州、連邦、EU(欧州連合)、国連といった多段階な形でさまざまな取り組みを行う形になっています。あいかわらず東京中心の日本とは、かなり違いがあります。
いずれにしても、あくまでも当事者たちが思想とつながって生活世界に陣地をつくる。そこからすべての歴史的実践が始まることを改めて強調しておきたいと思います。
【質問】生活ベースの陣地形成と市民のグローバルな連携が国民国家を挟撃していくというモチーフはポスト冷戦後しばらく将来展望として語られたと思います。それが、とくにこの10年ぐらいは逆風にさらされています。
【田畑】そうですね。大変な逆風ですが、大きな禍根を残すと思います。とくに地球温暖化は早急に対応しないと大破局になる可能性が非常に高い。こうした課題に対して、もちろんベースは生活現場で思想とつながって陣地をつくっていくことがイロハのイですが、果たしてそれだけで阻止できる力になるのかどうか、これは別の話です。
ただ、私は、思想としてはそれをめざす以外ないと思います。既存の力、たとえば国連に依存したり、EUの“よりまし路線”に期待したり、そんな他人頼みでは仕方がない。むしろ、既存の力を機能させるためにも生活現場における陣地形成、それを基礎としたグローバルな連携、同時に社会の公的総括のレベルにおける挑戦――、そうした多様な構えが必要だと思います。
(おわり)
※マルクスの「生活過程」論に関する田畑さんの専門研究は『21世紀のマルクス―マルクス研究の到達点』(伊藤・大藪・田畑編、新泉社、2019年)をご参照下さい。
