農福連携シンポジウム 参加報告
農福連携と産消提携
そのつながりを模索する
去る12月14日(金)、エルおおさかにおいて「第25回釜ヶ崎講座講演の集い 仕事づくり集中講座5 農業分野の仕事づくりを釜ヶ崎で!~農福連携と産消提携の先進事例に学ぶ~」と題するシンポジウムが行われた。主催は釜ヶ崎講座、NPO法人・釜ヶ崎支援機構、大阪市立大学都市研究プラザである。以下、シンポジウムの簡単な報告および主催者の一人への追加インタビューを紹介する。
農福連携」をめぐって
「農福連携」とは、農業分野と福祉分野の連携を指す。一般的には、福祉団体と農家や農業法人が連携して、障害者や高齢者などが農業分野で就労するのを支援したり、自ら農業生産によって一定の収益を得たり、農作業を通じて体力増進や生活リズムの確立を目指すといった取り組みが基本だ。
耕耘や畝立てなどの力仕事、草とりや水やり、収穫や袋詰めなど、農業には多様な作業があり、工場労働などに比べて作業のペースも自由度が高いため、各々の適性や能力に応じて働くことが可能である。なにより、自然を相手に身体を動かしたり、必要に応じて共同作業や単独作業を行うことで、リハビリや癒しの効果も期待できる。
そんなこともあって、実態として農福連携は以前から各地で行われてきた。かつて本誌で紹介した、京都市山科区の社会福祉法人「オリーブの会」の事例も、その一つだと言えよう。
とはいえ、農福連携という言葉が社会的に広まったのは、実はここ数年のことらしい。日本農福連携協会の顧問を務めるJA共済総合研究所の濱田健司主任研究員はこう指摘する。
「一気に動いたのは、2014年に農林水産省が「農山漁村振興交付金」をつくった頃ではないでしょうか。農林水産省の交付金なので、最初は福祉系の中間支援団体や施設まで情報が届きにくかったのですが、厚生労働省が広報したことで徐々に知れ渡り、農福連携をはじめる施設が増えてきました。」(「農福連携はここまで進んだ!成功事例と課題から見る未来」『マイナビ農業』2019年10月3日)。
いずれにせよ、高齢化と人口減少を背景に耕作放棄地や担い手不足といった問題を抱えた農業の側、地域社会で暮らしていくために就労の機会を求める福祉の側、両者の需要が重なる形で、この間、農福連携の取り組みに注目が集まっているようだ。
関西圏での活動紹介
さて、当日のシンポジウムでは、まず「釜ヶ崎にゆかりがある事例の報告」として、大阪と京都の計四ヶ所の取り組みが紹介された。(もっとも、釜ヶ崎と直接関係があるのは、その内の二つ)。
1つ目は、大阪府柏原市の雁多尾畑(かりんどおばた)地区にある「雁多尾畑 土と緑の谷 未来農園」である。長らく耕作放棄地となっていた谷筋の棚田を借り受けて畑に再生するとともに、釜ヶ崎で仕事にあぶれた労働者や路上生活者、就労支援機関に通う若者などに対して農作業への参加を呼びかけてきた。
この取り組みを中心で牽引してきたのが、今回のシンポジウムの主催者の一人であり、当研究所で「『よつ葉の地場野菜』研究会」のとりまとめ役をお願いしている綱島洋之さん(大阪市立大学都市研究プラザ特任講師)だ。綱島さんには、後日さらにお話をうかがったので、後でまとめて紹介したい。
事例報告の2つ目は、釜ヶ崎を拠点とする「ひと花センター」である。同センターは、釜ヶ崎で活動する5つのNPO(非営利組織)と西成区役所の協働による「ひと花プロジェクト」に基づき、釜ヶ崎の単身高齢生活保護受給者の社会的孤立を防ぐことを目的に2013年7月から実施されている。
活動内容は、公園の草むしりや道路清掃、お祭りやイベントの手伝いといった地域参加、文化やレクレーション、健康教室など。農業もそうした活動の一環として位置づけられ、近隣の広場で畑をつくり農作業を行うとともに、参加者で作物を調理して会食したり、地域にふるまったりしているという。
かつては日本最大の日雇い労働者の街として知られた釜ヶ崎だが、建設需要の低迷や労働市場の変化に伴い、現在では高齢化した元日雇い労働者が集住し、介護や福祉事業の割合も高まっている。「ひと花センター」の活動も「街かどデイハウス」とよく似た内容を持っている。
3つ目は、やや遠方になるが、兵庫県豊岡市を拠点とする企業組合労協センター事業団但馬地域福祉事業所の取り組みである。同事業所は、労働者による協同組合(ワーカーズコープ)づくりを進める日本労働者協同組合連合会の傘下団体として、但馬・丹後地方を対象に活動を展開している。
事業としては、いわゆる「ニート」や「引きこもり」など、一般的な労働市場に馴染みづらい若者を対象とした厚生労働省の支援事業「地域若者サポートステーション」を受託し、若者に就労に向けた各種のセミナーや体験訓練を行っている。その一環として、京都府京丹後市で2014年に農業体験セミナーを開催、2015年からは「就労体験による居場所づくり事業」と形を変えて、農作業を通じた就労体験・訓練、自己肯定感の獲得、地域社会との交流など、いくつかの成果を得ているという。
一方、課題としては、未だ事業を通じて農業での就労につながった事例はないこと、今後の展望として、加工などを組み合わせた仕事おこしの模索などが述べられた。
4つ目は、大阪府八尾市にある障害者の作業所「はばたき作業所」である。同作業所は就労継続支援A型施設、すなわち現状では一般企業での雇用が難しい人を対象に、雇用契約を結んだ上でさまざまな就労支援事業を行っている。
利用者21名の障害区分は、身体2名、知的6名、精神10名、発達3名。主な事業内容は、軽作業、清掃・洗浄作業、便利屋、そして農業などだが、全員が農業に携わっているわけではなく、現在は身体、知的2領域の利用者に限られ、実質的には意欲のある1名を中心に回しているという。
農業に関わるきっかけは偶然らしい。近隣の農家からミカンの皮むきや畑の草取り、作業小屋の修理といった仕事を請け負う中で体調の良くなる利用者がいたことから農業の効用に気づいたとのことだ。その後は、役所などに問い合わせたり、近隣の農家に研修をお願いしたり、試行錯誤を重ねた。その過程で綱島さんと面識ができ、綱島さんの紹介で関西よつ葉連絡会の㈱東大阪産直センターともつながりができたという。
ちなみに、同作業所では便利屋仕事として、利用者が農作業を行う以外に、作業所が管理する畑で利用料を払い、短時間の農業体験を行う「1畝オーナー」、休耕地・耕作放棄地での除草や畝たてなど圃場管理の仕事も行っている。
先に触れた「オリーブの会」の事例によく似た取り組みと言えるだろう(オリーブの会は就労継続支援B型施設である)。
野菜を育てながら自分を育てる
続いて行われたのは、シンポジウムのタイトルにある「先進事例」二例の講演である。
一人目は、神奈川県藤沢市の㈱えと菜園およびNPO法人農スクールの代表を務める小島希世子さん。1978年、熊本県合志市の教師の家庭に生まれた小島さんは、農村地帯で過ごす中、幼少期から農業への憧れを抱いていたという。小学校の時、飢餓に苦しむアフリカの子どもたちを描いたドキュメント番組を見て衝撃を受け、将来は農業関係の職に就きたいと思うようになったそうだ。
その後、大学入学を機に上京するが、生まれてはじめて路上で寝ているホームレスに遭遇し、「日本にも飢えている人がいる」と気づかされたという。
大学在学中から農業系の会社でアルバイトをはじめ、卒業後はその会社に就職、別の会社に転職するなどした後、独立し起業に至る。最初にはじめたのは、熊本の農家と全国の消費者をネットで結ぶオンラインショップだ。
| ㈱えと菜園の事業領域 ■つくる 少量多品種(年間30種類)栽培 雑草、虫、鳥と共存 直売とオンライン通販 ■食べる 農家直送のオンラインショップ 熊本の農家16軒が参加 市場流通とは別のしくみで市場の影響を回避 無農薬無化学肥料の米や小麦粉、雑穀など 「人から人へ」を感じられるように ■学ぶ 7坪の貸し農園で農業体験 年間20種類を播種から収穫まで 利用者の7割は地元在住者 起業の社員研修も活用 毎週日曜日に野菜作り講習会を行う 地域の交流の場づくりも展望 |
その一方、取引先の農家と関係が深まる中で、年を追うごとに耳にするようになったのが、人手不足や耕作放棄地、空き家をめぐる困りごとだ。
農村では人手が足らない一方、都会では働きたくても職のない人が路上生活を強いられる。双方をうまくつなぐことができれば、お互いの利益になるのではないか――。そう考えた小島さんは、農園を媒介にした新たな試みに踏み出す。それがNPO法人農スクールだ。
設立は2009年、参加者はリーマンショックの影響で職を失った日雇い労働者が多かったという。それまで肉体労働に従事していただけに、体力もあれば農作業に必要なスキルもある。もちろん働く意欲もある。路上生活が続く中で自信や自尊心を失っていた人もいたが、ともに農作業をする中で、徐々に元気を取り戻していった。そうした中で「農家になりたい」と言い出す人、実際に就農につながった事例も現れてきたという。
それを踏まえ、小島さんは農業の効用を次のように指摘する。
・種から生長し収穫に至る野菜の栽培は一つの成功体験であり、それが自信の回復につながっている。
・自分の手で自分の食べものを生み出すことは生きる力の実感であり、それも自信の回復になる。
・虫や動物、植物など人間以外の生き物に触れることで、生きていることを実感できる。
・青空の下での共同作業は、コミュニケーション圧力が比較的低く、対人関係の形成が容易である。
農スクールでは現在、ホームレスだけでなくニートや引きこもりの若者も受け入れている。就農に向けた「野菜作り挑戦プログラム」の年間スケジュールは3段階に分かれ、「導入編」は週1回・2時間を全10回。すべて畑での実習だ。自然のなかで身体を動かし、土と触れ合うことによって自分自身に向き合う。それを通じて自己肯定感を取り戻したり、コミュニケーションの力を養うのが狙いだ。
 |
| ■小島さんの著作 |
続く「基礎編」も週1回・2時間を全10回。ここでは、生きる上での目標や働くことの意義を模索しつつ、メンタルヘルスを自己管理することが課題となる。終了時には、就職の意思を確認する口頭試問があるという。
最終段階の「就職準備編」の期間は2ヶ月程度。就職先の模擬面接を行い、そこで現れた課題を解決したり、筆記試験に向けた学習を行う。
なにやら極めてシステマティックに感じられるかもしれないが、あくまで基本に置いているのは、農作業の持つ多様性を媒介に、本人がもともと持っている能力を再発見する機会の提供だ。
というのも、小島さんによれば「人は野菜を育てながら自分を育てている」からである。
「お茶を飲むことが仕事になる」ように
もう一人の講演者は、埼玉県熊谷市で埼玉福興株式会社およびNPO法人グループファームの代表を務める新井利昌さん。1974年生まれの新井さんは1993年、それまで縫製業を営んでいた両親が自宅で障害者施設(生活寮)をはじめたことから、福祉の道に足を踏み入れることになった。
当初は、それまでと同じく縫製の下請け作業が中心だったが、国内での生産が次々に海外へと移転していく中で工賃は切り下げられ、仕事自体も少なくなっていった。そうした状況を受け、農業への業態転換を考えはじめたのは2000年代初頭だという。その背景には“食べものをつくる農業なら仕事がなくなることはない”との展望、また“農業にはさまざまな作業を通じて障害者の関わる余地が大きい”との期待があったという。
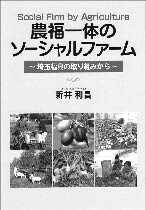 |
| ■新井さんの著作 |
同時に、“農業をやるならスローライフで生きていこう”との考えでオリーブの栽培を思い立ち、小豆島まで見学に行き、株を分けてもらったこともあるという。
新井さんによれば「一通りの失敗は経験した」とのことだが、退路を断つつもりで取り組んだこともあってか、いずれも現在につながっている。これについて、新井さんは「一人では農業の担い手になれなくてもチームなら可能です」と言及する。
現在の主な栽培品目は、水耕栽培による葉物、地元特産の深谷ネギを中心にしたハウスでの野菜苗、玉ネギや白菜に特化した露地栽培、2ヘクタールのオリーブなどとなっている。圃場は埼玉と群馬にあるという。
52名の社員のうち障害者雇用は7名で、利用者は障害者(知的・精神・身体・発達)、ニート、引きこもり、シングルマザー、難病者、若年性認知症、触法障害者(元受刑者)など広範囲に及ぶ。その背景には「人を選んだら福祉ではない」という新井さんの持論がある。
とはいえ、各自の状況はまったく一様ではない。想像するだけでも大変そうだが、事前に農作業全体のレイアウトを組み立てたり、作業工程を単純化し、一人でやる仕事、ペアでする仕事、チームでする仕事に分けることで、適性や状況に応じて利用者を配置したり組み合わせたりするという。また、作業に応じた治具の開発も行っている。
| 埼玉福興の営農面積 水耕栽培ハウス(埼玉) 2,241㎡ 苗・花卉栽培ハウス(埼玉) 1,432㎡ 野菜苗育苗ハウス(埼玉) 360㎡ グリーンケア農園(埼玉)0.3ha 露地栽培(埼玉)4ha 露地栽培 (群馬)1ha オリーブ栽培(埼玉)1ha オリーブ栽培(群馬)1ha |
今後の展開としては、農を「業」として成り立たせていくことと同時に、理念をつくっていく農業にも取り組みたいとのことだ。それは、最後まで人生をともにするための居場所づくりであり、新井さんの言葉では「お茶を飲むことが仕事になる」ような関係づくりである。そうした関係を地域に広げていくことができれば、持続可能な地域がつくられていくだろう。
ちなみに、新井さんの著作のタイトルにある「ソーシャルファーム」のファームとは、農園のfarmではなく会社のfirmであり、ソーシャルファームは社会的企業を意味する。社会的な目的をビジネスの手法で行うものであり、障害者をはじめ一般の労働市場では雇用が難しい人々に雇用を、あるいは支援を伴った雇用の機会を提供するビジネスである。
釜ヶ崎と農福連携をめぐって
以上、ごく簡単にシンポジウムの概要を紹介した。その上で後日、主催者の一人である綱島さんにうかがったお話を付け加えたい。
かつて本誌(第104号、2012年10月)でお伝えしたことがあるが、網島さんは学生時代に農学部で学ぶ傍ら、大阪市内の公園などに暮らす野宿者の支援活動にも取り組んでいた。その中で、次第に都市の貧困問題と農村における耕作放棄地の増大との間に関連があると考えるに至り、この点から農業を捉え返すようになったという。
その後、活動の過程で耕作放棄地の有効活用を希望する地主の面識を得たこともあり、耕作放棄地の再生と雇用創出とを結びつけた形で、2011年に「雁多尾畑 土と緑の谷 未来農園」を開くことになった。
まずは未来農園のその後についてを皮切りに、今回のシンポジウムについてお話をうかがった。
――その後、未来農園はどうなっていますか。
綱島:さまざまな人と作業をする中で、当初思い描いていた想定とは違う現実に突き当たることがいろいろありました。
参加者が農作業に習熟していく中で、やがては農園の管理を担う人も育ってくるものと期待していましたが、現時点ではそうはなっていません。候補者は何人かいましたが、そういう人は行政が用意する新規就農支援の仕組みを使ったりして、外へ出て行く形になりました。それはそれでいいんですが、結局うまくいかなかったようです。
いま釜ヶ崎で月一回、子ども食堂の大人版「おとな食堂」をしていますが、農園はそこで使う食材を供給する場として機能しています。釜ヶ崎で働く労働者、生活保護受給者などを対象に呼びかけ、収穫作業に参加した人には食堂の無料券を配布するといったやり方です。
 |
| ■綱島洋之さん |
はじめた当初、農園の運営資金には研究費を充て、作業に参加した労働者には日当を支払っていましたが、現在は基本的に止めました。農作業に興味はないのに、他に仕事もないという理由だけで参加する人も少なくなく、それを続けても次につながらないと思ったからです。そこで、日当はなくても農業に興味を持つ人を集める方向に転換しました。それなりに来てくれますが、高齢の人ばかりですね。
未来農園の活動の中間総括については研究報告書にまとめたので、詳細は参照していただければと思います。(網島洋之『生態資源利用による社会的包摂―自然と向き合う労働観と観察眼の再生―研究成果報告書』、URP Report Series,No.46、2018年11月、大阪市立大学都市研究プラザ)
――今回のシンポジウム開催にあたって、釜ヶ崎と農福連携を結びつけた背景をお願いします。
綱島:この数年間で「農福連携」に関する社会の認知はずいぶん進みした。そこで、一般的に農福連携をテーマとしたものではなく、釜ヶ崎で農福連携を行う際の課題に絞って議論する場をつくろうと考えました。現状、釜ヶ崎では農業で仕事づくりにつながっている事例はないけれども、興味を持っている人がたくさんいるのは実感してきました。そうした人たちが集まり、外部の人も交えて議論する場が必要ではないかと思いました。
シンポジウムでは釜ヶ崎での事例として「ひと花センター」を紹介しましたが、ここは高齢者中心で、仕事づくりを課題にしているわけでもありません。
一方で、釜ヶ崎では若者を対象とした仕事づくりに対する関心がかなりあります。ただし若者と言っても、かつてのような若手の日雇い労働者というわけではなくて、通常の地域社会や労働市場では包摂が難しい人々です。象徴的なのが矯正施設からの出所者です。出所したばかりの若者が釜ヶ崎にきて、そのまま未来農園にくるといったことが何回もありました。
僕は前から、ひと花センターのような高齢者対象の取り組みに若者も加われるようにすべきだと考えてきました。実際、未来農園では、意識的に釜ヶ崎の労働者、高齢の野宿労働者と就労支援対象にある若者との協働を追求してきました。両者の出会いを通じて、若者がこれまで釜ヶ崎の労働者、高齢の野宿労働者に対して抱きがちだった否定的な先入観が変化したり、労働者の側が肉体労働を通じて得たスキルを若者たちに伝えたりする関係も見られたんです。こうした関係を釜ヶ崎で復活できないかと考えています。
――シンポジウムの中で印象に残った点をお願いします。
綱島:新井さんは「人を選んだら福祉ではない」とか「一人では難しくてもチームならできる」と仰っていました。そうは言っても実際には困難ではないかと思い、その点について質問したところ、生活寮やグループホームを通じて24時間共同生活をしており、仕事と生活が一体化しているので、いろいろなことが可能になる、とのことでした。
小島さんの場合は、取り組みの中で「ワークノート」を活用している点に注目しました。農スクールでは、農作業を通じて自分や他者を発見してほしいということから、作業を終えた後に参加者は「ワークノート」に感想を記入するそうです。作業内容に応じて書式があり、体力やメンタル、知識などに関する自己評価を記入したり、共同作業では仲間に対する評価の設問も加わるとのことです。その中で印象的な点について尋ねると、うまく就農したり、他の業種で就職したりした人は、仲間について心配りが細やかだという特徴があったそうです。
あと、小島さんはもともと農業が好きで、出発は農業だった。それが、大学入学で上京した際に街中でホームレスの姿を見て衝撃を受けたのをきっかけに農福連携に広がっていった。それに対して、新井さんは福祉施設を運営する中で農業に出会い、やがては農業を軸とする農福連携に広がっていったわけです。ある意味で対照的です。
農業のやり方も、小島さんの場合は多品種少量生産で、そこに福祉的なものを噛ませていく。逆に新井さんは、できるところに絞って大規模にやり、その中で人に応じた関わり方を噛ませていく。たしかに規模が大きければ一つの仕事でも同じ作業を長時間繰り返すことができるので、そういうメリットはあると思います。
いずれにしても、出発点の違いがはっきり現れていたと思います。
農と福の両立で可能になる領域とは
――今回のシンポジウムで得た成果を、今後どのように研究や活動に生かしていく予定でしょうか。
綱島:そのあたりはこれからの課題で、未だ印象レベルに留まりますが、新井さんの言われた「仕事と生活の一体化」ということについて、改めて考えています。
考えてみれば、もともと農業というのは仕事と生活が一体となった営みだったはずです。しかし現在では、労働者の権利という問題も考えなければなりません。これまで労働運動では、基本的に労働と生活をいったん切り離した上で、そのバランスをどうとるかを問題にしてきたと思います。
しかし、農業について真面目に考えると、そうした前提を再び問い直さなくてはならないという気もしています。ひょっとすると、労働運動がこれまで勝ち取ってきた成果と対峙する可能性すらあるのではないかとも思っています。
たとえば小島さんの場合、農スクールの部分では収益はほとんどないようです。みんなで作業して、収穫して、持ち帰るというのが活動の基本ですね。どこで収益を得ているのかと言えば、主には一般向けの貸し農園とのことです。会員が何百人もいたり、企業の研修なども受け入れ、ソーシャルビジネスとしてうまく回しているようです。
――今回のシンポジウムのタイトルに「農福連携と産消提携の先進事例に学ぶ」とあります。産消提携の部分はどうだったんでしょうか。
綱島:今回は「農福連携」で手一杯だったのが実際で、「産消提携」については論議する時間もありませんでした。ただし、僕自身としてはやはり農福連携と産消提携を重ね合わせて考えていきたいと思っています。
というのも、農福連携を具体化する際にハードルになるのが、都市住民の農業に対する理解の薄さだと思っているからです。そう考えた時に、実は産消提携こそ、早くから同じようなハードルに取り組んできたはずだと気づきました。
そこで、農福連携が自らのハードルを克服していくに当たっては、産消提携運動がこれまで積み上げてきた財産をうまく継承すべきだろうと思ったんです。
産消提携運動を担ってこられた方もすでに高齢になられています。そうした方々の持つ知恵を現在の農福連携を実践している人たちと共有するための橋渡しができれば、と考えています。
――その際、農福連携の「農」の部分に力点を置くのか、あるいは「福」の部分に力点を置くのかによって、産消提携との関わり方も変わってくると思いますが。
綱島:そうですね。ただ、僕が最近学会などで議論しているのは、どちらに力点を置くのかというよりも、むしろ農と福が両立して初めて可能になる領域とは何か、ということなんです。
たとえば、農業と言ったら基本的には農産物の生産が軸になります。そこでは生産性ということが一つのキーワードになります。ところが、逆に福祉では、能力主義の意味を含んでしまうがゆえに、生産性という概念には慎重にならざるを得ません。
しかし、せっかく農と福を連携させるのであれば、生産性を高めようとすることで初めて実現できるようなwell-being(幸福・福祉)があるのではないか、そこを追求すべきではないかと考えています。
作物学者の津野幸人さん(鳥取大学名誉教授)によれば、農業技術というのは人間の死に対する恐怖によって形成されたとのことです。つまり、作物を育てないと自分が死んでしまうという恐怖心から、さまざまな技術が生み出されてきたのであり、そうした恐怖と裏腹に形成されてきた技術を抜きにしては、農作業の面白さもなくなってしまうのではないか、と。ごく簡単に言うと、そういうことらしいです。
そこで僕が考えているのは、たとえばたくさん収穫できるとか、よりおいしいものをつくるとか、そういう生産性を上げる努力をして、はじめて実感できるものがあるのではないか、ということです。
僕たち人間が身体や頭脳を使って自然に働きかけ、それを通じて自然の摂理を実感する。それも一つのwell-beingだと思うんです。農と福とが両立することで可能になる領域というのは、ひょっとしてそういうところにあるのではないか。そんなことをいま考えているところです。
(聞き手・文責/山口協:当研究所代表)
