HOME>過去号>124号
−講演学習会報告−
ウクライナ情勢から見た「地域と国家」
講師:塩川伸明さん(ロシア政治史、比較政治学)
石油価格の下落がロシア経済を直撃し、ルーブルの為替相場下落が止まらない。アメリカがサウジと組んで仕か
けた陰謀だとの指摘が流れ始めた。ウクライナをめぐる対立が、ここにも見え隠れしているようだ。当研究所では、ウクライナ情勢の底流をなす、この
地域の歴史的背景を探る試みとして10月3日、塩川伸明氏をお招きして、「地域と国家を考える―ウクライナ情勢をめぐって―」と題する講演学習会
を開催した。以下はその抄録であ
る。
(文責は当研究所)
歴史と文脈
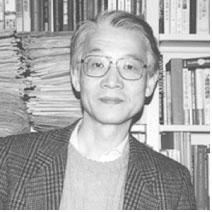
ここ数ヵ
月、ウクライナで大変な事態が起きているのは、皆さんご承知でしょうが、どうしてこんなことが起きたのか、これをどう考えるべきかという問題にいきなり入
る前に、歴史をさかのぼって、その文脈を考えてみたいと思います。
古い歴史のことを詳しく話していると切りがありませんが、大事なのは、民族というのは、ある一つの決まった形でずっと固定しているものではないというこ
とです。日本は島国であるために、なんとなく日本人という一つの民族がずっとあるような気がしてしまいますけれども、大昔にさかのぼると、大陸やら南方の
島々やらいろんな方面から来た人々がまじりあってきたのでしょうし、戦国時代以前には東日本と西日本では相当違っていたでしょう。全国統一後も、北海道や
沖縄はどこの国に属しているかがはっきりしない状態があったりしたわけです。というわけで、民族というものはずっと長いこと固定した状態であるということ
はないわけですね。
そういうことを念頭においてロシアやウクライナについて考えると、今では、はっきりと形をとった「ロシア人」「ウクライナ人」というものがあるのが当た
り前と思われていますけれども、もともと非常に近い間柄にある人たちですので、数百年前にさかのぼると、いろんな流動的な関係があったわけです。たとえば
言語ですね。ロシア語とウクライナ語は非常に似通った、お隣同士のような言葉です。ある言葉がお隣の言葉とどれくらい似通っているか、違っているかという
のは、厳密な測り方がないんですけれども、たとえば日本本土の通常「日本語」と思われている言葉と沖縄の言葉は、意思疎通がむずかしいくらいの差がありま
すね。それでも、「沖縄方言」という言い方をしています。ロシア語とウクライナ語の関係は、それよりは近いでしょう。ですから、それぞれが別々の言葉にな
るのか、一つの言葉の中の方言になるのかというのは、あまり明確な基準で決まるものではないということです。
宗教というのも、民族を考えるうえで非常に大事ですけれども、これはロシアとウクライナで基本的には同じです。厳密にはちょっと留保が必要なんですけれ
ども、あまり細かいことを言っても切りがないので、「基本的には同じ」という言い方をしておきます。具体的には、キリスト教のうちの東方正教会です。「東
方」というのは、西のカトリックに対して東方という意味です。
歴史と文化について言うと、ロシア文化の先祖をたどるとウクライナに根っこがあるということがよく言われます。キエフというのは今のウクライナの首都で
すけれども、そこが、ロシアとかウクライナとかがはっきりと確立する前の最初の国家の中心地でした。日本の場合にたとえるなら、いまは東京に首都があるけ
れども、昔の中心は京都だったというようなものです。空想的な話ですが、仮に西日本と東日本が別々の国家になったとすると、東日本の人は平安文化とか源氏
物語とかを自分たちの文化と言ってはいけないと京都の人から言われるかもしれない。こういうことを考えると、なかなかに簡単に関係を切ることはできないと
いうことです。
リーベンというイギリスの歴史家が、この関係をイギリス人に分かり易く説明するため、「ソ連が解体した時にバルト三国だけでなくウクライナやベラルーシ
も独立したのは、ちょうど大英帝国の末期に海外植民地だけでなくスコットランドやウェールズも独立したようなものだ」と言っています。ウクライナはスコッ
トランドにあたり、ベラルーシはウェールズにあたるというわけです。
リーベンがこう書いたときには、スコットランド独立という可能性はあまり現実的でなかったのですが、つい最近、スコットランド独立問題がニュースになっ
たのはご存じの通りです。もっとも、独立が当事者に有利かどうかはよく分からないところがあって、揺れているということが、住民投票の結果からも分かりま
す。たしかに独立運動はあるけれども、ずっと一貫して独立を願い続けてきたというわけでもないんですね。スコットランドとイングランドは隣接していて、互
いに行ったり来たりしていて、スコットランドの人がイギリスの中心でエリートとして活躍するというはたくさんあるわけで、常に必ず独立しようとしてきたこ
とでもない。これと同じことはウクライナにも当てはまります。
要するに、ロシアとウクライナは非常に近い間柄だということです。もっとも、近いからといって必ず親しいということにはなりません。なまじ近いからこ
そ、ぎくしゃくした関係も生じるわけで、そこがデリケートなところです。
次に、歴史的背景の一つとして、「ポーランド・ファクター」について考える必要があります。ロシアとウクライナの西に位置するポーランドはカトリックの
国で、東方正教とは宗派が違います。そして、ポーランドは元来非常に大きな強い国でした。この点は、日本の多くの人にはわかりにくいかもしれません。ポー
ランドというのは小国だ、「昔からロシアに蹂躙されて、かわいそうな国だ」といったイメージが、日本にはありますね。たしかに18世紀末以降はそうなので
すが、もっと昔にさかのぼると、ポーランドのほうが大きくて強い国だったんですね。今日のウクライナ、ベラルーシの大半はポーランドが支配していたわけで
す。それどころか、一時は勢いに乗ってモスクワまで攻め上ったこともある。ロシアから見ると、ポーランドは見下すことのできる弱小国ではなく、むしろ恐ろ
しい強敵だったわけです。
ともかく、ウクライナは長いことポーランドに支配されていた歴史があります。ですから、ポーランド文化とかポーランド語の影響がウクライナにかなり浸透
しました。ウクライナがロシアと共有するものを多数持つ半面、ポーランドと共有するものも多いのは、そういう歴史的事情によります。西ウクライナにカト
リックとロシア正教の中間のような「ユニエイト」という独自の宗派があるのは、そのあらわれです。
18世紀末以降、ポーランドの領土はロシアとプロイセンとオーストリアに分割されましたが、今日のウクライナが大部分ロシア領になってからも、土地を
持っているのはポーランド人貴族で、ウクライナ人はその下で農民として働いている、つまりポーランド人が支配者でウクライナ人が使われている関係がありま
した。こうした事実がウクライナの歴史を複雑にしています。
ソ連時代

ソ
連時代の歴史は入り組んでいて、一言で説明しきれるものではありませんが、民族問題に関して重要なのは「現地化」という政策がとられたことです。「現
地化」あるいは「土着化」とも訳されますが、「現地に根を下ろさせる」ということです。
ロシア革命の時、共産党がまずロシア帝国の中心部で政権を取って、それから周辺地域に徐々に勢力を伸ばしていく。そのときに、最初は軍事力で制圧してい
く。しかしそれだけでは、ただの占領とか征服と変わらないわけですが、共産党は「帝国主義反対」を一枚看板にしていますから、帝国主義と同じようなことを
したのではまずいわけですね。そこで共産党政権を現地に根を下ろさせるための政策が必要だったということです。どうやって根を下ろさせるかというと、それ
ぞれの地域ごとの民族言語、民族文化を尊重して、盛り立てるということが中心的な要素です。
たとえば、ウクライナ民族、ウクライナ語というものがロシア民族、ロシア語とは別個に存在するという観念は、ロシア帝国時代にはなかったんですね。ロシ
ア語に似ていて、ちょっと劣るものというぐらいの感覚でしかなかった。それを、ウクライナ語というものがあり、ウクライナ文化というものがあって、ウクラ
イナ共和国はウクライナ人が統治する国である、という形を作ったのはソヴェト政権です。それ以外にも、グルジア共和国とかカザフ共和国とか、いろいろな共
和国ができて、それらの連合としてソ連というのが作られたわけですけれども、こんなことは帝政ロシアの時代には全く考えられなかった。それぞれの地域には
それぞれの民族がいるんだ、という体裁を整えたのが「現地化」政策です。
これだけ聞くと、なかなかいいことをやったという話のように聞こえるかもしれません。しかし、実際にはそう簡単な話ではありません。
この問題に切り込んだ本として、テリー・マーチンの『アファーマティヴ・アクションの帝国:ソ連の民族とナショナリズム、1923年〜1939年』(明
石書店、2011年)という本があります。アファーマティヴ・アクションというのはアメリカで、アフリカ系とか女性などのマイノリティ、これまで活躍する
機会のなかった人たちに、できるだけ活躍の場を与えるために積極的に登用する制度を指します。日本でも最近、「女性の輝く社会」なんていって、それを実現
するためにクォータ制を導入してはどうかなどという話が出ていますが、これもアファーマティヴ・アクションの一種です。人為的な割り当てをすることで、そ
れまで活躍する機会のなかった人たちに活躍の場を与えようということですね。
これは理念として考える分には、なかなかいいことのように思えるのですが、いざ実際にやろうとすると難しいところがある。実際、アメリカでは、アフリカ
系の人とか女性を優遇することに対して、白人の男性からものすごい巻き返しがあって、こんなことをやるからアメリカがダメになったんだという議論が現れ
て、大論争になったんですね。差別をなくそうというのはいいけれども、それに伴ってこういう軋轢が現われるというのは非常に深刻な問題です。
ロシア革命後のウクライナでは、徹底してウクライナ語を使おうという政策を20年くらいとりましたけれども、ウクライナのインテリ自身が、日用語はウク
ライナ語であっても公共のことを扱う際にはロシア語だという使い分けが当たり前になっていたので、急にウクライナ語で全部やれといっても難しかったわけで
す。日本語の例でいうと、日常会話では関西弁を使っている人でも、地方行政に携わって条例を関西弁で書いてみろとか、大学に入って修士論文や博士論文を関
西弁で書いてみろといわれても、これはなかなか難しいのではないでしょうか。こういう風に、いざ実際にやろうとすると、かえって軋轢が生じて民族間の紛争
を強めてしまったというのが、ソ連の民族政策を考えるうえで重要な点です。
もう少し現代に近いところに話を移します。第二次大戦のときにウクライナの領土が広がりました。さっき言ったように、ウクライナはポーランド分割のとき
に大部分がロシア帝国領になったんですけれども、ロシアではなくオーストリア領となり、それが第一次大戦後にポーランド領となったところもありました。ウ
クライナの一番西の部分です。これが第二次世界大戦期にソ連領になりました。これはスターリンとヒトラーの密約の産物ですが、ウクライナからすれば、その
おかげで領土が広がったということになります。
それから、クリミアの移管が1954年にありました。それまでクリミアはソ連の中のロシア共和国の一部でしたが、ロシアとウクライナの友好の印として、
ロシアからウクライナにプレゼントされたわけです。これ以降、クリミアはウクライナ共和国の一部となり、ごく最近までそうでした。1954年というのはフ
ルシチョフの時代ですが、このクリミヤ移管のことを「フルシチョフの気まぐれ」として批判する考えがロシアにはあります。それをどう評価するかは微妙です
が、この移管がどれだけ正当な手続きを踏んだのかという疑問を出す余地は、あるといえばあるわけです。
少し話題を変えますが、ウクライナは「ソ連第二の共和国」だったとよく言われます。ウクライナ人はロシア人に次いで人口が多く、経済力その他の点でもナ
ンバー2です。ウクライナは多数のソヴィエト・エリートを輩出し、共産党幹部も多数いました。
これはソ連時代の民族関係を考える上で微妙なところですが、ソヴィエト政権というのは、特定の民族が上に立って他の民族を支配するのはいけないことだと
いう建前を掲げていましたから、ロシア人だけがエリートになるという構造にはなっていませんでした。もちろん現実には、人口の多数派がロシア人ですから、
支配層の中でもロシア人は高い比率を占めていましたが、だからといって、ロシア人だけがトップにいるという構造ではないんですね。特にウクライナ人はロシ
ア人に次いでたくさんのエリートを生み出してきました。
その他の民族の例として、グルジア人とかユダヤ人とかアルメニア人とかも、かなりたくさんのエリートがいました。スターリンはグルジア人だったし、ス
ターリンの片腕と言われたカガノビッチはユダヤ人だったし、レーニンは普通ロシア人と言われていますが、実際にはさまざまな民族の混血で、ロシア人の血は
ほとんど入っていないような感じです。というわけで、ソ連時代の統治エリートはロシア人だけだったわけではなくて、他のいろんな民族も関与しており、その
中でもウクライナ人の比率は結構高かったわけです。今日、過去を振り返るときにも、ここのところが重要な論点になります。
ペレストロイカからソ連解体へ
ソ連時代の末期にゴルバチョフという人があらわれて、いろんな改革をやって、国全体が大きく変わったということは皆さんご存じの通りです。
この時期のウクライナでは「ルーフ」という運動体が出てきました。人民戦線とも訳されます。これは最終的には独立運動になるんですが、最初から独立を掲
げていた運動ではありませんでした。共産党員も大量に入っていて、純然たる反体制運動とも言い切れない運動だったのです。というのも、ゴルバチョフのペレ
ストロイカというのは、共産党のトップが「これまでの我が国の在り方はよくなかった」、「どんどん改革しよう」と号令を発したわけですから、それに呼応す
る形で人民戦線がつくられたわけです。ルーフというのは略称で、「ペレストロイカを支持する人民戦線」というのが当初の正式名称でした。ある意味では体制
内での改革を目指す運動でした。
最初から独立論が出ていなかったのは不思議だとお感じになるかもしれませんが、そうでもなかったのです。先ほどからお話ししているように、ロシアとウク
ライナは非常に近い関係で、相互交流もあるし、お互いに結婚して血が混じっている人もたくさんいる。そういう密接な関係を切って、分離独立しようといった
議論は、少なくとも最初のうちは一般的ではありませんでした。
ですが、政治運動というのはえてして過熱し、極端な意見が強まるもので、1990年ごろから独立論が高まってきます。ルーフに入っていた共産党員は、
ルーフをとるのか共産党をとるのかという選択を迫られ、ルーフの正式名称にあった「ペレストロイカ支持」という言葉も削られるようになります。こうやって
ウクライナ独立論が高まったのですが、ゴルバチョフが登場した85年よりも5年ほど遅い時期です。
もう一つ触れておかなくてはならないのは、クリミアの自治共和国化です。さっき言ったように、クリミアは54年にロシアからウクライナに移管されました
けれども、そのときはウクライナの中の一つの州、単純な行政区分にすぎませんでした。ところが、ウクライナで独立運動が高まると、クリミア住民の多数派で
あるロシア人は不安を感じるわけです。そこで、ウクライナの中の自治共和国という地位を持ちたいということになってくる。91年1月に住民投票をやりまし
て、圧倒的に自治共和国に賛成という結果が出て、2月にこれをウクライナ中央も認めて、正式に自治共和国化しました。
いよいよソ連時代の最後ですが、91年8月にクーデター事件が起き、その直後にウクライナは独立宣言を採択しました。そのときにエリツィンは報道官を通
じて、「どこかの共和国がソ連から独立するのであれば、国境を再調整する必要がある」という発言をしました。これは明らかにウクライナのことを念頭に置い
たもので、要するに「クリミアをロシアに返せ」ということです。この発言はウクライナでものすごい反発を食らって、大騒ぎになりました。
あわてたエリツィンはこの発言を取り消して、とりあえずは穏便に処理されたのですが、一度大騒ぎになったことは、完全に忘れさられるものではありませ
ん。ですから、クリミア問題はプーチンになってから急に問題になったと勘違いする人が多いのですが、実は91年8月、ソ連時代最末期のエリツィン発言が出
発点だったということを指摘しておきます。
ソ連解体後の20年―ウクライナ内政
ソ連時代の話はこれくらいにして、1991年12月にソ連が解体した後の時期に入ります。内政、ロシア・ウクライナ関係、国際的文脈と分けて、順々にみ
ていきます。
ウクライナの内政において東西の分岐が重要だというのは、多くの人が指摘しているところです。隣との関係でいうと、ウクライナの東にはロシアがあり、西
には西欧があって、それぞれからの影響がある。言語についていうと、主にロシア語をしゃべる人は東部に多く、もっぱらウクライナ語を使う人は西部に多い。
そのため、西に行くほどウクライナ民族主義が強くなる。こういうわけで、ウクライナの西と東ではかなり肌合いが違うわけです。
このように東
西問題が重要だというのは大勢の人が言うとおりですが、私はちょっと別の面を付け加えたい。というのは、「東部と西部」という言い方をすると、どこかに線があって、西と東
がはっきり分かれているという印象を持ちやすいのですが、実際にはそういう線はなく、ゆるやかにつながっているということです。自然の障壁のない平原の国
ですから、自由に行き来しているわけです。言語も純粋なロシア語やウクライナ語があるわけではなく、口語では両方の要素がいろんな形で混じり合っている。
そういう連続性があるわけですから、どこかで割るというのはあまり現実的ではないのです。ときどきケンカをする、悪口を言う、ということはあっても、死に
物狂いの闘争をするということは滅多にないのです。
日本でいうと、関西には関東への対抗意識があって、タイガースを応援してジャイアンツが大嫌いな人が多い、とよく言われます。だからといって、武装闘争
で相手をやっつけてしまおうなんてことはまずないですね。ウクライナもごく最近までそうでした。たしかに論争や紛争はある。けれども、だからといって「あ
いつらをやっつけてしまおう」ということはまずなかった。どの州の住民の何%がロシア人で、何%がウクライナ人かという統計を見ても、100対0とわかれ
ているのではなく、90、70、50%というふうに、なだらかにつながっているスペクトル状なわけです。
ただ、大統領選挙の時は別です。一位と二位で決選投票をしますから、東部に基盤をおく候補と西部に基盤をおく候補のどっちが勝つかが大きな問題になるこ
とがあります。だから、大統領選挙に着目すると、西と東が割れるような感じに見えますが、これは選挙時だけの特殊情勢で、それ以外のときにも通用するわけ
ではないんですね。
人口分布についてデータを補足しておくと、ウクライナ民族主義が強いのは西部と首都キエフであるのに対し、わりと親露派が多いのは東部と南部、その中間
が中部となりますが、2001年の数字で、東部と南部をあわせておよそ48%、西部とキエフをあわせて28%、中部が24%となります。もちろんこれは非
常に大雑把な計算で、この数字がそのまま親露派とウクライナ民族主義派の勢力を示すということではありませんが、それにしても東部と南部の重みというのは
相当なものがあります。ですから、90年代には、常に東部・南部を基盤とする大統領候補が勝ってきたわけです。
けれども、東部や南部の人たちがみんな同じ党派に属しているわけではなく、いろんな政党の離合集散の中で、だんだんバラけてきたわけです。そうやってバ
ラけていくと、ウクライナ民族主義寄りの勢力が東部や南部にも支持を伸ばして、選挙で勝つ可能性も出てくる。これが起きたのが2004年の大統領選挙で、
「オレンジ革命」と言われた出来事でした。西寄りの政策をとるユーシェンコという人が大統領になったわけです。ところが、この時代にウクライナの政治は非
常に混乱して、国内の対立が激しくなりました。ユーシェンコは政権末期には人気が急落し、2010年の大統領選挙に立候補したものの、まるで振るいません
でした。このとき勝ったのが、ヤヌコビッチという人です。ユーシェンコとヤヌコビッチを比べると、一般に前者は西欧志向で後者はロシア志向だと言われるの
で、大逆転に見えます。しかし、実際には、ウクライナ政治はあまり極端にはならないのが普通で、真ん中が重く、その時々の微妙なバランスであっちに揺れた
り、こっちに揺れたりという方が実態に近いのです。
ヤヌコビッチが当選したときの選挙は決してでたらめな選挙ではなくて、西欧諸国からやってきた監視団が自由で公正な選挙だというお墨付きを出しました。
ですから、民主的政権として発足したはずなんですが、次第にいろんな問題が指摘されるようになり、末期には政権批判が非常に高まったわけです。ただ、少な
くとも政権発足時には、不法選挙で政権を握ったということではなかったし、ロシアの介入で親露派が勝ったというような話でもありませんでした。
ソ連解体後のロシア・ウクライナ関係

さきほ
ど、クリミア問題が1991年の段階でいったんクローズアップされ、とりあえずは穏便に処理されたということをお話ししました。この問題がソ連解体の直後
に再浮上することになります。
91年まではソ連という国がありましたから、その中のウクライナ共和国とロシア共和国のどちらにクリミアが属するかという問題があっても、大きな意味で
は一つの国じゃないか、と考えることができたわけです。ですが、92年以降、クリミアの属するウクライナはロシアとは別の国になってしまいましたから、多
くのロシア人としては、これは耐えられないということで、ロシア国内で“クリミアを取り戻せ”という機運が高まりました。“そもそも54年まではロシアに
属していたのに、ウクライナに移したのがおかしかった。だから、それを取り消せ”というわけです。これは特定の政治家だけのことではなく、わりと国民全体
の中でそういう機運が高まってきたわけです。
象徴的な例として、ソルジェニツィンという人を取り上げましょう。かつて、彼はソ連体制を厳しく批判して「反権力の闘士」と言われた人で、ソ連時代に国
外追放され、ソ連解体後にアメリカから故国ロシアに凱旋した人です。同時に、実は熱烈なロシア民族主義者です。彼に代表されるロシア民族主義者の観点から
すれば、歴史はどう見えるのか。彼は次のようなことを言っています。
“我々ロシア人はスターリンをはじめとするソ連共産党指導部に酷い目にあってきた。ソ連共産党指導部を牛耳っていたのは誰か。ロシア人もウクライナ人も
グルジア人もユダヤ人もいる。それなのに、ウクライナがスターリン時代の犯罪的所業をロシアの責任としているのはおかしい。そして、ロシアのものであるク
リミアをウクライナに渡したのも共産党指導部の恣意的な行為であり、それは取り消されるべきだ”と。
これは日本では分かりにくい議論だろうと思います。けれども、ロシアではわりと自然に受け入れられる発想です。そういうことがあって、90年代前半にロ
シア・ウクライナ関係はクリミヤ問題をめぐってかなり緊張したわけです。
ただ一方で、政治家は歯止めなく緊張をエスカレートさせることの危険性も知っていますから、緊張がある程度高まったところで和解することも考えたわけで
すね。万が一ロシアとウクライナが戦争することにでもなったら大変だと、世界中の政治家たちが非常に懸念したわけです。
そこで97年にロシアとウクライナが友好条約を結んだわけです。この条約でロシアは、クリミアをウクライナ領と認め、その代わりに、クリミアの一角にあ
るセバストポリという海軍の軍港をロシアが租借できるということになりました。これで長年の懸案が決着したんです。これはとても重要なことで、今日では忘
れられる傾向が強いんですけれども、そういうことがあったという事実は確認しておくべきだろうと思います。
ただ、細かいことを言うと、わずかに決着し残した問題がありました。地図を見ていただくと分かりますが、クリミア半島の東の先端にケルチ海峡という細い
海峡があります。この海峡を隔てて、ロシアとクリミアは向かい合うような位置関係にあります。この海峡のどこに国境線を引くのか、海峡に点々と存在してい
る小さな島々の帰属はどうなるか、海峡を船が航行する権利や海底資源を開発する権利をどうするのか、こういった点が最後の問題として残っていました。
これも実は2012年に決着しました。領土的にはロシアが譲って、この海峡およびそこに点在する島々の大部分をウクライナ領とする。その代わりに、ロシ
アは海峡の自由航行権を認められ、海底資源は共同開発とする。こういう形で平和解決ができたわけです。
ロシアは一貫して領土拡張を目論んでいる国だというイメージが、わりと広まっていますけれども、実はそうとは限らないのですね。平和的な外交交渉で領土
問題を解決する、しかもその際に小さな島は譲る、その代りに経済的な実利はもらう、というプラグマティックな対応をしていたわけです。ケルチ海峡の例だけ
でなく、中国やノルウェーとの国境でも、同様の対応が見られます。クリミヤ問題が起きてしまった今日では、ちょっと想像もつかないんですけれども、ほんの
二年前まではそういうことだったんです。
もう一つ別の問題として、「ホロドモル」というものがあります。これは「飢饉」を意味するウクライナ語です。特にユーシェンコの時代に、世界的に宣伝す
るためにウクライナ語の表現を広めました。“1933年に非常に大規模な飢饉が生じた。これはウクライナ民族に対するジェノサイドである”と非常に激しく
糾弾し、ロシア国家の責任を問う態度を打ち出したわけです。これは大変デリケートな問題です。先ほど、ソ連時代の権力エリートはロシア人だけではなかった
と言いましたけれども、その問題と絡むわけです。
飢饉は単純に自然条件だけで起こるわけではなく、政府が農村をないがしろにする政策をとったことの結果だという意味では、政治の責任であることは明らか
です。けれども、そうした政策を実施した統治エリートはロシア人だけではなく、多民族的なエリートだった。それから、この飢饉のとき、ロシアもカザフスタ
ンもベラルーシもたくさんの餓死者を出したのであって、決してウクライナだけを狙い撃ちにしたわけではない。数百万人もの死者が出るというのは、とても悲
惨な出来事であり、政治に責任があるというのはその通りです。しかし、それを「ウクライナ民族へのジェノサイド」と言うのは暴論だと私は思います。
私はスターリン時代のソ連政府を免罪しようとは決して思いません。誤った政策あるいは不適切な政策によって、多くの人々にものすごい被害を与えたことは
事実です。しかし、それを特定の民族だけの責任である、あるいは特定の民族だけが被害者であると捉えるのは、やはり無理があると思います。ゴルバチョフの
ペレストロイカの時代には、ソ連全体で、スターリン時代の悲劇を究明する動きが高まりましたが、それは特定の民族だけが加害者とか被害者という話ではな
く、ソ連国民全体の悲劇としての取り組みでした。
ところが、ユーシェンコは「ウクライナ民族へのジェノサイドだ」という捉え方を強烈に押し出して、国内で猛烈に宣伝しただけでなく国際的にもアピール
し、ジェノサイド認定を求めました。欧州審議会は、“非常に悲惨な出来事であり、それは共産党政権の産物として糾弾すべきだ”との決議を採択しましたが、
「ジェノサイド」という言葉は認めませんでした。にもかかわらず、ウクライナでは「ジェノサイド」という見方が圧倒的に流布されました。これはロシアとの
関係を悪化させただけでなく、ウクライナ国民の間でも感情的な対立を煽りたてる結果になったと思います。
国際的文脈
次に、ロシアと欧米諸国との関係について考えてみたいと思います。もっとも、「欧米」と一口に言っても、「欧」つまりヨーロッパと、「米」つまりアメリ
カは、かなり似通っているけれども完全に同じではありません。EU(欧州連合)とNATO(北大西洋条約機構)の関係も同様です。EUに加盟している国々
とNATOに加盟している国々は大部分重なりますが、微妙に違いますね。最大の違いは、アメリカはNATOで主導的な位置を占めているけれども、EUの一
員ではないということです。そしてNATOは軍事同盟ですが、EUは軍事色が薄いという違いがあります。
そういう違いを念頭におくと、ロシアとして、NATOには強い警戒心を持つけれども、EUに対してはそうではない、という違いが見えてきます。EUはロ
シアの最大の貿易相手なので、EUとの仲がこじれたら一番困るのはロシアなんですね。ごく最近は違ってきましたが、少し前までのロシア人の感覚としては、
“EUはいいけれども、NATOは困る”というのが普通の感覚でした。
そこで、まずNATOから考えていきます。NATOは冷戦後、何回かにわたってだんだん東に範囲を拡張してきました。古い話ですが、1990年のドイツ
統一の際、統一ドイツが丸ごとNATOに属するのかどうかが最大の論点となりました。ゴルバチョフは、「ドイツが統一するのは当然である。しかし、もう冷
戦は終わったのだから、NATOもワルシャワ条約機構もいらなくなったはずだ。統一ドイツがどちらに属するかという問題もなくなるはずではないか」と主張
しました。しかし、アメリカはこの主張に見向きもしませんでした。力関係でアメリカのほうがソ連よりも強かったため、統一ドイツはNATOに入るという結
論を押し通したわけです。それでもゴルバチョフは最後まで抵抗したので、当時のアメリカの国務長官ベイカーらがゴルバチョフを説得するための口約束に、
「東ドイツは名目上NATOに入るが、実質上はNATOの軍事管轄下には入らない」と言いました。しかし、この口約束はすぐに反故にされ、その後NATO
はポーランド、ハンガリー、チェコへ、さらに東へ東へと広がっていきました。ゴルバチョフは欺されたわけです。
NATOの東方拡大は、ロシアから見れば脅威以外の何物でもありません。最近まで敵対していた軍事同盟がどんどん自分たちの方に近寄ってくるわけですか
ら。NATO側は「われわれは昔のNATOではない。決してあなた方を敵視しているわけではありません」と言いますが、ロシアとしては信じられないわけで
す。ややもすれば、ロシアが反NATOなのはプーチンのせいだと思われがちですが、実はゴルバチョフであれエリツィンであれ、この点では基本的に同じなの
です。一般的な国民の意識としても、NATOは非常に怖い脅威だという感覚があります。そのことを欧米諸国はあまり分かっていないように思います。
かつてジョージ・ケナンというアメリカを代表する外交官、歴史家がいました。第二次大戦直後に活躍したロシア通で、学者としても優れた、アメリカ外交の
大御所ともいうべき人です。彼が90年代末に遺言ともいうべき発言として、「NATOの東方拡大は危険である。それはロシアを追い詰め過ぎることになる。
それはけっして国際平和のためにならない」と警告しました。しかし、この警告は無視されました。最近の情勢を見るにつけ、私はこのケナンの警告が当たって
しまったという気がしてしようがありません。
以上のようなNATOに比べると、EUはそれほど露骨に反ロシア的ではなく、貿易をはじめとする交流も盛んです。特にフランスやドイツは比較的ロシアに
友好的ですね。
とはいえ、完全に友好的かというと、そうでもなく、「文明の序列」観という問題があります。文明というのは西へ行くほど高くなり、東へ行くほど低くな
り、野蛮だ、という発想は、西ヨーロッパの人には非常に根強くあります。つまり、ロシアを見下す意識があるわけですね。これはロシアからすると屈辱的で
す。ロシアにとって、EUはNATOほど嫌う相手ではないけれども、やはり面白くない面があるといえばあるんですね。
それからポーランドやバルト三国がEUに入りましたが、これらの国々は歴史的事情からして反ロシア意識が非常に強い国ですから、その反ロシア意識がEU
全体に影響を及ぼすところがある。そうするとEU全体が反ロシア的になるかもしれない。そのことにロシア側は神経過敏にならざるを得ない。こういう不幸な
関係があります。
最近の状況
以上、歴史的背景について述べてきましたが、強調したいのは、この間のウクライナ危機は、そうした背景から直接生じたのではなく、ある種の飛躍があった
のではないかということです。
2013年の暮れからウクライナで反政府運動が盛り上がりました。これはいろいろな理由がありますが、外交政策も批判の的になりました。またヤヌコビッ
チ大統領が特権をほしいままにして、相当に乱脈を極めていたことも事実のようです。そのため、元来はヤヌコビッチを支持していた人々も、もうあんな奴には
ついていけないということで、一斉に離反したんだろうと思います。
しかし、それだけでは、こんな大ごとになる必然性はなかったんです。腐敗した政府があり、その外交政策も気に食わない。だから反政府デモが起こる。ここ
までは、当たり前のことです。そして、2015年には任期切れで大統領選挙という予定になっていましたから、普通に合法的に引きずりおろすことができたは
ずなんです。
ところが、突然暴力革命のような様相を呈してきたんですね。これが一番分かりにくいところです。おそらくは少数の過激派のようなグループがいて、暴力に
訴えはじめたのでしょう。そういう過激派は、それ自体は少数の動きであって、全体を左右するほどのものではなかったはずです。ところが、ここはまだあまり
はっきりしていない部分ですが、そういう過激派ではない、反政府運動の多数をなしていた人たちも、「同じ反ヤヌコビッチだから」ということで、過激派と一
線を画することなく、ある程度まで容認してしまったのではないかという気がします。
そのあとクリミア、そしてドネツク州とルハンスク州に飛び火するわけです。ドネツクやルハンスクは、いわゆる「親ロシア派」の強いところですが、従来は
“ウクライナから独立したい”という要求はほとんどなかったと思います。クリミア問題については97年の条約でもう決着していて、それを蒸し返そうという
動きはありませんでした。ですから、少し前まで、クリミア独立運動とかドネツク独立運動とか、あるいはロシアに併合を求めるとか、そういうことはなかった
んです。ところが、首都のキエフで暴力革命が起こってしまった。そうすると“大変だ。あんなやつらに支配されるのはごめんだ”ということで、クリミアでも
ドネツクでも急に独立論が高まった。それをキエフの新政権は許さないということで、軍事作戦を発動した、というのが最近の流れです。
以前から東西の肌合いの違い、産業構造の違い、国際的な志向の違いはありました。ただウクライナ全体としては、どちらか一方だけをとることはあまり考え
られず、ほとんどすべての政治家が“バランスをとるしかない”と考えていたわけです。ときどき、どちらか一方に傾くことはあっても、必ず元に戻ろうとする
のがウクライナ外交の基本的なパターンでした。東西の分岐が武力衝突に至るようなことはなかったのです。
ソ連解体後あるいはユーゴスラビア解体後、あちこちで内戦が起きましたが、ウクライナではこの20年、流血の惨事はありませんでした。旧ユーゴスラビア
の場合、クロアチアとセルビアが第二次大戦中にお互いに殺しあったことがある。旧ソ連でいえば、アゼルバイジャンとアルメニアは何十年か前に殺しあったこ
とがある。しかし、ロシアとウクライナはそういう経験はありません。
じゃあ、どうしてこんな事態になったのか。これは大きな謎です。多くの人がいろいろ言っていますが、どれも納得できるものはありません。ただ、とりあえ
ずこんなことが言えるのでは、といういくつかの仮説を出してみたいと思います。
一つは、かなり漠然とした話ですが、独立から20年を経る中で、ウクライナ政府が国民形成を進めてきたという事実があります。「君たちはウクライナ人な
んだ」「ウクライナ人としての誇りを持て」という教育を進めてきたわけです。そういう教育を受け、若い人の中ではウクライナ人意識を持つ人の比率がだんだ
ん高まってきて、親ロシア的な傾向の比率が低くなるという傾向が、じわじわと進行したのではないかと考えられます。そうなると、親ロシア派は孤立感と不安
感を強めていきます。そんな中で、どちらも心理的に強硬になってきたのではないか。
もう一つは、ユーシチェンコ政権期における歴史論争とその後遺症です。これは私たちにも関わってくる問題です。中国でも韓国でも反日運動がありますね。
戦前・戦中に日本が悪いことをしたのは確かですから、それを非難すること自体は正当なことですが、ときどき行き過ぎがないわけではない。しかも、中国や韓
国で行き過ぎがあると、それは日本の中の右翼、ナショナリストを非常に元気づける。“あいつらがあんなひどいことをやってるんだから、俺たちもあいつらに
仕返ししていいんだ”という傾向を強めて、非常に悲しい状況が生じているわけです。
歴史問題は非常に微妙な問題で、“自分たちはこんな被害にあった”と主張するのは正当なことですが、それを政治の道具として利用し、過度に政治化しよう
とすると、かえって相手を刺激し、さらに悲惨な結果をもたらす可能性が高い。ウクライナ問題でいうと、「ホロドモル(飢饉)」を「ジェノサイド」として大
宣伝するのがその一例で、過度の政治化によって国民が割れていく。国民の中で、そうした捉え方に「賛成するのかしないのか」「お前は敵か味方か」という分
岐が生じるという事態が進行したように思います。
さらに、このところ世界的に経済不況が広がっており、ウクライナも非常に厳しい状況になっています。その結果、人々の中で寛容の精神がだんだん失せてい
く。そして、“自分がいま苦しいのは、どこかに悪い奴がいるからではないか、そいつをつるし上げてしまえ”という雰囲気が高まってくる。これは、世界的な
風潮だと思います。
ウクライナ人というのは本来、ロシアを好きな人と嫌いな人と真っ二つに分裂しているのではなく、ある面では好きだけどある面では嫌いだ、というごちゃま
ぜな状態が多数派だったはずなんですけれども、“そんな中途半端な状態は許せない、お前は敵なのか味方なのか”と問いかけるような風潮が広まり、「味方」
と「敵」とに割れる条件が拡大しているような気がします。
ロシアとヨーロッパとの間でも、似たような関係が見られると思います。もともと友好関係にあったはずロシアとヨーロッパで、ここにきて急に対抗感情が高
まってきているように見えるのも、世界的な不況の中で不寛容の心理の広まりが作用しているのではないかということです。
いろいろと話してきました。あまりすっきりした結論がなくて、かえって混乱させてしまったかもしれません。とにかく言えるのは、ウクライナの東部と西部
にせよ、ロシアと欧米諸国にせよ、対抗要因があるのは事実だとしても、それが爆発する必然性があったわけではないということです。むしろ、あまり爆発せず
に済みそうだというのが、少し前までの素直な見方でした。ところが、いったん爆発してしまうと、大変な規模の犠牲が出て、収拾の展望もなかなか出てこな
い。ナショナリスティックな対抗感情を煽りたてることの恐ろしさをしみじみ感じさせられます。これは私たちにとっても他人事ではないように思います。

©2002-2019 地域・アソシエーション研究所
All rights reserved.

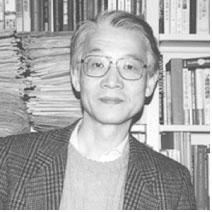 ここ数ヵ
月、ウクライナで大変な事態が起きているのは、皆さんご承知でしょうが、どうしてこんなことが起きたのか、これをどう考えるべきかという問題にいきなり入
る前に、歴史をさかのぼって、その文脈を考えてみたいと思います。
ここ数ヵ
月、ウクライナで大変な事態が起きているのは、皆さんご承知でしょうが、どうしてこんなことが起きたのか、これをどう考えるべきかという問題にいきなり入
る前に、歴史をさかのぼって、その文脈を考えてみたいと思います。 ソ
連時代の歴史は入り組んでいて、一言で説明しきれるものではありませんが、民族問題に関して重要なのは「現地化」という政策がとられたことです。「現
地化」あるいは「土着化」とも訳されますが、「現地に根を下ろさせる」ということです。
ソ
連時代の歴史は入り組んでいて、一言で説明しきれるものではありませんが、民族問題に関して重要なのは「現地化」という政策がとられたことです。「現
地化」あるいは「土着化」とも訳されますが、「現地に根を下ろさせる」ということです。 さきほ
ど、クリミア問題が1991年の段階でいったんクローズアップされ、とりあえずは穏便に処理されたということをお話ししました。この問題がソ連解体の直後
に再浮上することになります。
さきほ
ど、クリミア問題が1991年の段階でいったんクローズアップされ、とりあえずは穏便に処理されたということをお話ししました。この問題がソ連解体の直後
に再浮上することになります。