活動報告:アソシ研懇話会
グローバリゼーションと日常からの変革(上)
従来の講演学習会に加え、さらに専門的な話を聞き、論議することを主旨とした「アソシ研懇話会」。その第二回目として、昨年11月8日、斉藤日出治さん(大阪産業大学、社会経済学)にお願いし、「グローバリゼーションと日常からの変革―金融危機と食糧危機」と題して報告いただいた。以下は、その概略であり、今号と次号の二回にわたって掲載する。文責はすべて研究所事務局にある。
はじめに
地域・アソシエーション研究所の機関誌を送っていただき、拝見しました。農や食の問題を、単にそれを重視するだけではなく、そこから社会を形成していくという視点が感じられます。とくに、野田公夫さんの学習会の報告(本誌第53号、08年6月)を興味深く読みました。その中で、野田さんは「所有の重層性」として、所有を「私」と「村」と「天」という三層の構造で捉え、そうした所有の重層性を「生きられる法」という視点から捉えるよう提起されています。これに関連して、私は最近、金菱清さんの『生きられた法の社会学』(新曜社、2008年)という本を読みました。伊丹空港の周囲に、戦前、空港工事に従事させられた在日朝鮮人が、その後、国有地を「不法占拠」していた地域がありましたが、2002年には国と市が土地と住宅を提供する「移転補償」が決まった。つまり、国が「不法」としたものを「合法」と認めたわけですが、それについて研究した本です。
私たちは「法」と言えば、実定法や成文法を思い浮かべます。しかし、所有という概念は人と人との交通・コミュニケーションを媒介にして自然に働きかけ、自然からさまざまなものを領有する、我が物として獲得するという実践に裏付けられています。伊丹空港の場合も、まさにそうした長い歴史にわたって自らの生活を築いてきた中で獲得された知識とか論理を通じて「不法占拠」が合法化されていった、つまり「法」を成立させていったわけです。これは、野田さんの言う「所有の重層性」と重なる部分があるように思います。
今日の私的所有の概念には「私」しかありませんが、歴史的に見れば、実際の所有には「村」というコミュニティ、あるいは関係性がある。それから「天」つまり自然との関わり、自然との物質代謝もある。そうした総体において所有が捉えられてきたわけです。この視点はまた、マルクスが『経済学哲学草稿』で私的所有を批判する際に、五感を駆使した世界の実践的領有として所有を位置付け、それを実定法における私的所有権に還元してしまうような近代の所有概念を批判していることとつながってきます。
私の先生だった平田清明さんがマルクスを読む場合も、『資本論』を所有理論として読んでいます。所有は、一つには生産活動の概念。それから交通概念、つまり人と人との関係の概念。もう一つは法や道徳、政治や倫理といった上部構造。そういう総体の構造として押さえています。まさに『資本論』は、生産過程、流通過程、分配過程という三段階の構造になっていますが、こうした重層的構造のなかで所有を捉えていく視点と野田さんの提起とが連なってくる気がして、非常に興味深く読ませていただきました。
消費者運動と商品形態批判
以上を前置きとして、本日の話を始めます。最初に「消費者運動と商品形態批判」について触れますが、たぶん皆さんの産直運動とも関連があるものと思います。実は、先ほど挙げた平田清明さんが、日本の社会運動のなかで一番注目したのが生活クラブ生協の運動なんですね。合宿など、さまざまな形で生活クラブの運動に参加しています。平田さんがどういう意味で関心を持ったかといえば、要するに、日常の社会運動の中で商品社会に対する批判意識を持っていたところです。

私は一昨年、生活クラブ生協系の市民セクター政策機構の機関誌で、生活クラブ生協の創設者の一人である岩根邦雄さんと、「平田清明と生活クラブ」と題して対談しましたが(月刊『社会運動』第321号、2006年12月)、その際の中心テーマもこの点でした。経済学者は言葉では「商品批判」と言うものの、実際の経験や感覚の中では理解していない。それ以上に理解しているのは、実は生活クラブ生協の運動だ、と。言い換えれば、商品批判というのは単に経済的なレベルの問題ではなくて、社会闘争・文化闘争の課題であって、それを実践的に遂行していることに注目したわけです。
たとえば、生活クラブ生協には「消費材」という言葉があります。一般には貝偏の「消費財」と書くところですが、貝偏の「財」を使うことは貨幣による価値規定を受けていることを意味します。今日の商品社会は「消費材」を、つまり使用価値をサカナにして交換価値の獲得を自己目的とする市場経済の社会ですね。金儲けのために素材を利用するわけです。そうした事態に対する批判意識があって、木偏の「消費材」を使う。この批判意識は、まさに今日の金融危機に見られるように、金融の投機の中で実体経済が翻弄されている事態に対する批判意識にもつながると思いますが、この点は後で触れましょう。
マルクスで言うと、商品論の冒頭にある商品のフェティシズム(物神崇拝)に対する批判に当たります。商品は、労働生産物に数字、つまり値段・価格がついた形で現象します。その価格は、あたかもその物の自然的な属性のように、商品に内在する力として、人々の日常意識に映ります。しかし、実はそれは特殊な社会関係ですね。私的所有者の社会的関係が物に内属して、あたかも物の力であるかのように日常意識に思念される。マルクスはそういう事態をフェティシズムとして批判していますが、平田さんは生前、こうした批判感覚を日常的に持っているのは経済学者でなく生活クラブの社会運動だ、と常に強調していました。
グローバリゼーションと市民社会
次に、私の研究テーマである「グローバリゼーションと市民社会」について紹介します。いま進展しているグローバリゼーションを市民社会の概念で捉え返そうという問題意識で、これまで三冊ほど書いています(1)。来年には、新泉社から『社会的個人とヘゲモニー』という本を出す予定ですが、今日の話と関連するところで、その主題について大きく三点ほど触れておきましょう。
一つは、グローバリゼーションという現象を古典思想の市民社会の概念で批判的に捉えることです。その際、代表的な思想家として、カール・マルクスとアンリ・ルフェーブル、そしてアントニオ・グラムシの三人を取り上げています。
マルクスについては、とくに彼が『資本論』執筆前の1850年代に作成した『経済学批判要綱』と言われる草稿を題材にしています。そこでマルクスが、19世紀の半ばに資本の循環運動が国境を越えて世界的に広がる中で、そのダイナミックな資本の運動が社会的生産過程の最後に何を生み出すのかというときに提起したのが、「社会的個人(social individuality)」という概念です。
平田さんは1980年代に『経済学批判要綱』を読みながら、この概念に注目するわけですが、実は同時期にイタリアでも「社会的個人」に注目した人がいました。それがアントニオ・ネグリです。彼は日本でも『〈帝国〉』(以文社、2003年)の著者として、また「マルチチュード」という集団的主体の提唱者として知られていますが、『マルクスを超えるマルクス』(作品社、2003年)という本を書いています。要するに、『資本論』を超えるマルクスは『経済学批判要綱』のマルクスだ、ということですが、彼もやはり「社会的個人」に注目し、そこから「マルチチュード」という概念を出しているわけです。
アンリ・ルフェーブルはフランスの社会学者、哲学者です。「日常生活批判」つまり日常生活に対する批判意識と「都市革命」という二つの概念を継承して、今日のグローバリゼーションを考えるということ。そして、グラムシに関しては「ヘゲモニー」という概念です。いずれも後で説明しますが、こうした古典思想を通してグローバリゼーションを読んでみようというのがこの本の大きなテーマの一つになります。
グローバリゼーションと日常生活批判
ところで、現在のグローバリゼーションは新自由主義的な、市場における自由競争を最優先するようなもので、その破綻が世界の金融危機として現れているのは、ご存じの通りです。しかし実は、現在の危機の前、90年代ぐらいから、かなり行き詰まりが出てきており、その中ですでにグローバリゼーションの転換が始まっていたと見るべきだと思います。
今年(2008年)9月、日本の経済産業省が出した『新経済成長戦略2008改訂版』という本の中では、これまでの日本は、グローバルな競争に耐えられる企業を育成すべきだということで、グローバリゼーションにのめり込むような戦略を立てていたけれども、今後は同時に地域の活性化が重要だ、というようなことが書かれています。もちろん、グローバリゼーション戦略はいまも柱の一つですが、それだけでなく、日本国内の地域でどうやって事業を掘り起こすかが大きな課題になっているわけです。これまでトヨタやソニーのような日本の大企業は、多国籍企業戦略の下で工場をどんどん海外に移転し、安い労働力を活用し、外国で販売することによって多大な利益をあげてきたけれども、その一方で、国内ではワーキングプアが増えて消費は冷え込むことになってしまった。「戦後最長の好景気」などと言われながら、実感は全然ない。今回の危機はそうした矛盾をいよいよ露呈させたと思いますが、それを踏まえて、政府がこういう提言を出してきた。
しかし実際、世界的レベルではかなり以前から、新自由主義的なグローバリゼーションの行き詰まりという問題が浮上していました。80年代から、IMF(国際通貨基金)や世界銀行は「構造調整政策」というもの展開していきます。つまり、先進国の資本がラテンアメリカやアフリカなどの途上国に自由に投資できるように、規制緩和を通じて環境を整備する内容の政策をグローバルに推進してきたわけです。もちろん、それは非常に深刻な貧富の格差や不平等の拡大を招くといった批判を浴びますが、IMFや世界銀行は「経済成長を推進していけば、水滴が上から下に落ちていくように、やがて貧困層にも恩恵が及ぶんだ」(2)と強弁して成長一本槍を進めていきます。しかし、90年代になると、いよいよ行き詰まりが明らかになる。そうすると、今度は貧困対策を課題に掲げるようになります。

たとえば、世界銀行のアジア版とも言えるアジア開発銀行(ADB)は90年代に出した報告書の中で、アジアの農村における貧困の救済について言及し始めます。そして、産業インフラ、経済生活インフラの整理が必要だ、そのためにはNGO(非政府組織)やNPO(非営利組織)といった団体の協力が必要だ、というようなことを言い出します。この段階で「市民社会」というものが注目されるようになってくるわけですが、そうした形で、一つのグローバリゼーションの転換がすでに始まっている。これはグローバリゼーションの今後を考える上で非常に重要な問題だと思います。
それから、先に触れたアンリ・ルフェーブルの日常生活批判について。これはある論文の中で提起したことですが(3)、ルフェーブルは人々の日常意識について「神秘化された意識」というふうに批判しています。この問題意識は戦前の1930年代から戦後まで、30年ぐらいにわたって引き継がれ、『日常生活批判』という本を何冊も書いています。その際どういう意味で「神秘化」されているのかと言えば、私的所有の意識を、コミュニティや共同労働といった共同性を奪われた意識として捉えるわけです。「私的」という言葉はフランス語で「privee」と表現しますが、これは「共同性を奪われた」という意味を含んでいます。言い換えれば、労働者は富や力や幸福と同様に意識も文化も奪われている。そのように奪われていることを、自分が所有していることと混同する、と。ルフェーブルはそう言っています。
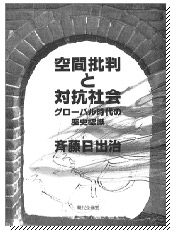
私的所有が共同性の剥奪であるにも関わらず、それを意識せずに私的、排他的な利益だけを追求する。人々が互いに分断され、孤立化させられ、排他的な競争関係に押し込められている。本来なら、そこで共同性に目を向けなければならないのに、そうした視点を欠落していく。そうすると、最終的に何が起きるか。1930年代で言えば、ファシズムやナショナリズムといった新しい集団主義が生まれ、そうした集団的な幻惑状態に向かって人々が突然走り出したわけです。
これも現在の状況に重なると思います。新自由主義的なグローバリゼーションが金融危機を引き起こして、社会の危機をもたらしたとすれば、次に出てくるのは排外主義的なナショナリズム、あるいは戦争の問題ですね。そういうルフェーブルの問題意識は、今日のグローバリゼーションの中でもう一度受け止める必要があると思います。
食糧危機の要因
以上、グローバリゼーションに対する私の問題意識を示した上で、今日の本題「食糧危機と金融危機」に入ります。先ほどのルフェーブルによると、日常意識というのは私的な意識で、即時的な感覚で物事を捉える。食糧の問題で言えば、私たちは日常的には、穀物価格や食品価格が急騰したという形で食糧危機を意識しますが、その背後には国境を越えたトランス・ナショナルな社会関係や複合的なメカニズムがあるわけです。そういうものを手繰り寄せながら、私たちの共同的な関係を再建していかなければならないと思います。
さて、いま起きている食糧価格高騰については四点ほどの原因が考えられます。一つはBRICs(ブラジル、ロシア、中国、インド)と呼ばれる新興工業国の急成長によって、穀物の需要が急増したことです。とりわけ、長らく農産物の輸出国だった中国が2004年以降、穀物や大豆の輸入国に転換する。農産物の貿易収支も赤字になります。ところが、その中国は日本にとって、米国に次ぐ第二位の食料輸入元です。今後、アジアの経済共同体といった問題を考えた場合、日本と中国という二つの主要国がともに食料輸入国であることは、食の安全保障という問題が非常に重要にならざるを得ないことを物語っていると思います。
ラテンアメリカでは現在、ブラジルとアルゼンチンで大豆の増産が進んでいます。21世紀に入ると、とくにブラジルで大豆の増産が顕著になります。これについて、以前NHKが特集していましたが、アメリカの穀物メジャーや丸紅のような日本の商社、それから中国の穀物商社がアマゾンの熱帯雨林地帯で凄まじい大豆の争奪戦をやっている。中国の商社もブラジルの大豆を大量に買い込んで食用油にしています。そういう動きがいま急速に進展しています。
そして第二にバイオ燃料。トウモロコシやサトウキビからエタノールをつくったり、大豆からバイオディーゼルをつくったりして、バイオ燃料の生産が急増しています。とくにアメリカでは、21世紀に入ってエタノール生産が急増しています。日本のトウモロコシ自給率は0%で96.3%をアメリカから輸入していますが、そのアメリカでトウモロコシによるバイオ燃料の生産が行われるようになった。ブッシュ大統領が中東の石油からの自立戦略を提言する中で、GM(ゼネラル・モーターズ)のような自動車メーカーが、ガソリンの代わりにバイオ燃料を使うという動きが急速に高まりました。これが、日本の飼料用穀物価格の高騰を引き起こし、畜産農家に深刻な危機をもたらした一つの大きな原因です。
同時に、バイオ燃料の生産が急増したことで、それまで食用穀物を生産していた農家が、バイオ燃料向けの穀物生産に切り換える動きが拡大したことで、途上国における食用穀物の不足という問題が生じています。この点については、ラテンアメリカ諸国の左翼政権が、バイオ燃料によって食用の穀物が不足して、非常に深刻な飢餓の問題を引き起こしている、と批判したこともあります。
第三に原油の急騰です。原油価格は90年代、1バーレル20ドルほどで比較的安定していましたが、21世紀に入って急騰します。これも中国など新興工業国の需要増大と関連していますが、2007年には7倍の140ドルに上がります。1973年の第一次オイルショックでは原油価格が4倍になりましたが、それを遥かに上回る原油価格の高騰が起きた。これが穀物の輸送用燃料、輸送コストを引き上げ、穀物価格の高騰に影響を与えています。
そして第四に、供給側の条件として、地球環境の悪化によって穀物の生産量が伸び悩んでいることが挙げられます。干ばつ、水害、異常気象によって生産が減退していく。水問題も深刻化する。これらによって、穀物の需給バランスが大きく崩れていきます。「期末在庫率」(4)という指標で見ると、20世紀の間は世界全体でおおむね生産量が消費量を上回っており、在庫率が比較的高かった。最高で36%ぐらいありました。ところが21世紀に入ると、消費量が生産量を上回るようになって在庫率が急減し、2006年度には14.5%まで下がります。70年代の初めにも在庫率が減少し食糧危機が叫ばれましたが、それでも15.3%あった。現在は、それよりさらに在庫率の低下が起きている。
食糧危機とグローバリゼーション
こうした要因は、すべてグローバリゼーションと関連しています。とくに新興工業国における穀物需要の増大については、その背景には、新興工業国の工業化を生み出した多国籍企業のグローバルな戦略が存在しています。多国籍企業が先進国から途上国に工場を移し、低賃金労働力目当ての投資を進めることで、ラテンアメリカや中国、東南アジア、東ヨーロッパなど一部の途上国の急成長、工業化が生み出され、以前は「南の停滞と北の成長」という形で焦点化されていた南北問題の構造を大きく変えていったわけです。昨今の穀物価格の高騰という現象も、こうしたグローバリゼーションの動きの中で生じていることに注意する必要があるでしょう。

いずれにせよ、その結果として、食糧危機のグローバル化という、21世紀的な食糧危機の現象が起きてくる。それに対して、食糧価格の高騰に伴う食糧暴動や抗議デモが世界で、とくに中南米や東南アジア、それからアフリカなどで同時多発的に生じています。また他方で、食糧の輸出を禁止したり、高い関税をかけたりという輸出規制という動きも出てきます。とくに、基礎食糧になるような主要穀物については、各国が自給を中心とする方針を明確化しています。日本の場合、ご存じのように自給率は39%ですから、こういう状況の中で、果たして耐えられるのかという問題が深刻化するわけですね。
もちろん、食糧危機が深刻化するのは先進国以上に最貧国です。とくにアフリカの場合、植民地経済の名残でカカオやバナナなど輸出用作物のモノカルチャー化が進み、そのために住民が確保すべき穀物を生産する土地が少ない、農業国でありながら自分たちの基礎食糧を自給できないという矛盾がある。そこに加えて、先ほど触れたように、バイオ燃料に穀物を使うという事態が生まれれば、途端に飢餓が深刻化してしまう。つまり、グローバリゼーションの中で、食糧危機が地球的な規模で深刻な問題として出てくる、と言えるでしょう。
食糧危機と金融危機
実は、食糧危機と金融危機は密接に関連しています。現在の金融危機の発端となったアメリカにおけるサブプライムローンの破綻ですが、サブプライムは「二流の」という意味で、低所得者層向けの住宅ローンを意味しています。当然、リスクが非常に高い。だから本当は金利が高いけれども、最初は安くして2年〜3年後に引き上げるわけです。住宅価格が上がり続けている限り、金利が高くなる前に借り換えをして、また低金利で借りる。住宅価格が上がり続ける限り、それを繰り返していればローンは破綻しない。しかし、そんなことがいつまでも続くわけはありません。実際、去年の秋ぐらいから住宅価格が下がり始めます。借り換えもできなくなり、ローンの不良債権が急激に増えていきます。
では、この住宅ローンがなぜ世界の金融危機を引き起こしたのか。住宅ローンは30年ぐらいの長期ローンですが、リスクが非常に高いので、ローンの債務を証券化して短期の金融商品(債務証券)を仕立て、それを世界全体に売りさばいて、リスクを回避使用としたわけです。もちろん、そのままではリスクが大きいため、誰も購入しません。そこで、サブプライムローンの証券を優良な証券と組み合わせて、どこにサブプライムローンの証券があるか見分けがつかなくしてしまった。加えて、格付け会社というものが、そうした金融商品に対して、実質以上の高い評価を与える。そうなれば、今度は誰もが買いたがるわけですね。そういう形で世界中にバラまかれました。
ところが、住宅バブルが崩壊してサブプライムローンの不良債権が増えると、こうした金融商品もたちまち紙くずになります。リーマン・ブラザーズが破綻したのも、そのためです。その上、どの金融商品にサブプライムローンの証券が入っているのか分からないため、金融機関は疑心暗鬼にならざるを得ない。当然、信用全般も収縮してしまう。それがこの間の状況です。
今日では、投機を目的に膨大なお金が短期の金融市場で取引されています。いわゆる「ヘッジファンド」の運用資産額は1.9兆ドル、機関投資家の運用資産額は60兆ドルと言われていますが、生産や消費という実体経済の何倍ものお金が投機目的で売り買いされ、それが株式市場や債券市場に流れ込んでいるわけです。しかし、金融危機に陥って株が暴落すると、もはや株式市場や債券市場に注ぎ込むわけにはいかない。その結果、そのお金が新たな儲け口を探そうとして、原油や金や銅、トウモロコシや大豆や小麦といったコモディティ(商品)を取引する先物市場に一挙に流れ込みました。ある新聞で、海を泳いでいた象が片足をプールに突っ込んだようなものだ、と表現していましたが、実際、株式市場や債権市場の規模と商品先物市場の規模はケタ違いです。それほど巨大な株式市場や債権市場に溢れていたお金が小規模な商品先物市場に急激に流入すれば、先物価格は急騰するに決まっています。こうして、現実に穀物価格が急騰してしまったわけです。
このように金融が実体経済から離れて一人歩きする、暴走するような、そういう状況が生まれていますが、それこそが新自由主義に基づくグローバリゼーションの最終的な帰結として生まれ、この金融主導型資本主義が行き詰まって破綻したというのが、まさに私たちが今日直面している現状だろうと思います。=つづく=
(1)『国家を越える市民社会―動員の世紀からノマドの世紀へ』(現代企画室、1998年)、『空間批判と対抗社会―グローバル時代の歴史認識』(現代企画室、2003年)、『帝国を超えて―グローバル市民社会論序説』(大村書店、2005年)。
(2)「トリクルダウン理論(trickle-down theory)」と呼ばれる考え方。
(3)「日常生活批判と神秘化批判」、季報『唯物論研究』第95号、2006年2月。
(4)一定の期末に、在庫量を同期の消費量で割った数字。数字が低ければ、それだけ消費が多く安定確保が難しいことを意味する。国連食糧農業機関(FAO)が示す安全在庫水準は17〜18%。
