対症治療と原因治療|げんきDASで治そう!010
トップへ戻る
慢性の痛みを、お医者さんはどう考えているでしょう?
どうして慢性の痛みは治らないのでしょう?
患者さんにも、柔道整復師、鍼灸師の先生方にも楽しんで読んでいただけるように、「そこだけ先生とえだね先生」の話として、なるべくわかりやすく工夫しています。
各ページは、4~5分で読める文章量でまとめています(文庫本2ページ分くらいの文量です)。
それぞれの章は読み切りになっていますが、順番に読んでいただくとさらにわかりやすくなると思います。
慢性痛の原因は、ぜんぶわかっているんでしょうか?
わかっているなら、保険でぜんぶ治せるはずなんじゃ…?
治療と施術
「先輩、『治療』は医者が使うことばで、鍼灸や接骨は『施術』とか『療養』とかだっていうっスよね?」
「医師でなければ治療ではない、という考えですね。鍼灸院や接骨院では、治療という表現は用いないように指導されていますね。」
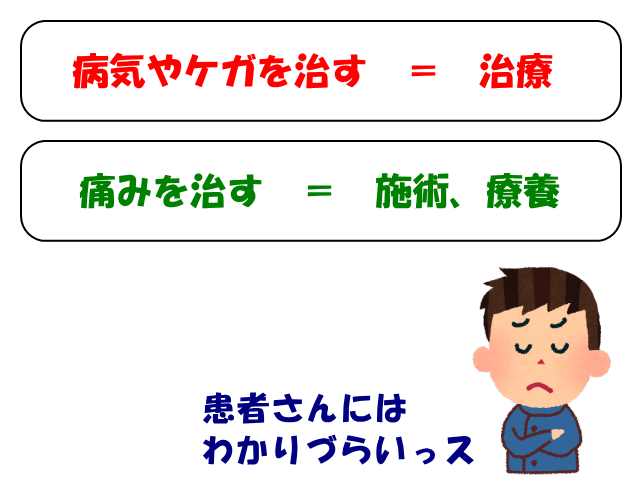
「でも、それじゃ患者さんにはわかりづらいっス。治してもらえば、治療っス。」
「治療と施術の違いがあいまいなままだから、患者さんは整形外科と鍼灸、接骨の使い分けができないんですよね。」
イメージの間違い
「原因がよくわからない慢性痛の人数と、整形外科で受療する人数の割合が、10対1くらいなことはさっき説明しましたね。」
(前回の「鍼灸、接骨と病院」を参照。)
「でも、整形外科の先生は、そんな風に考えていないと思います。治すといったら病院でするもの、というイメージでしょう。」
「症状を和らげるだけの対症治療(左側)と、原因から治す原因治療(右側)にわけたら、医師はこんなふうにイメージしているかもしれません。」
(赤い点線が、整形外科の先生が考える、鍼灸、接骨とのさかい目。)
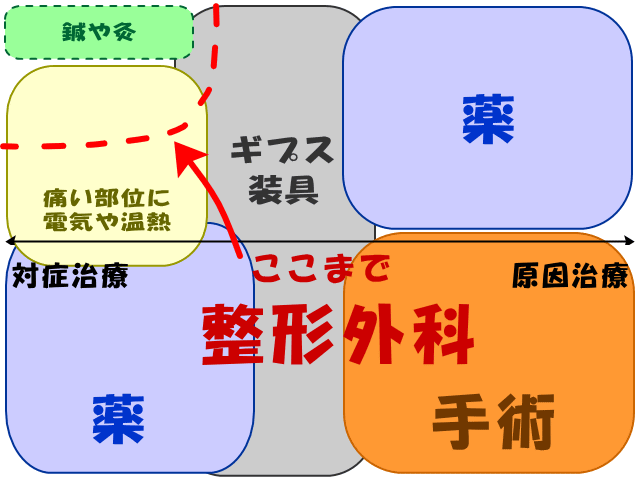
「ほとんどが、薬で治療できるような炎症や、手術で治す骨の変形などで、その間をギプスなどの固定が埋めているようなイメージでしょう。」
「なんでスか?整形外科の治療ばっかじゃないっスか?」
「痛み≒病気やケガ、と考えればこうなると思います。患者さんでも、そう考えている方は少なくないでしょう。」
「それじゃ現実に合ってないっスよ。鍼灸や接骨、ムチャクチャ扱いが小さいっス。これじゃ、すみっコぐらしっスよ。」
「鍼灸や接骨は、痛みの症状を和らげるだけ、原因となる病気やケガを治す治療はできない、という考えもあるからでしょうね。」
「統計でみると、そういうことになりますよね。鍼灸、接骨と、整形外科の境目は、実際の人数で考えるとこんなふうになるでしょうね。」
(下図のようなイメージ。)
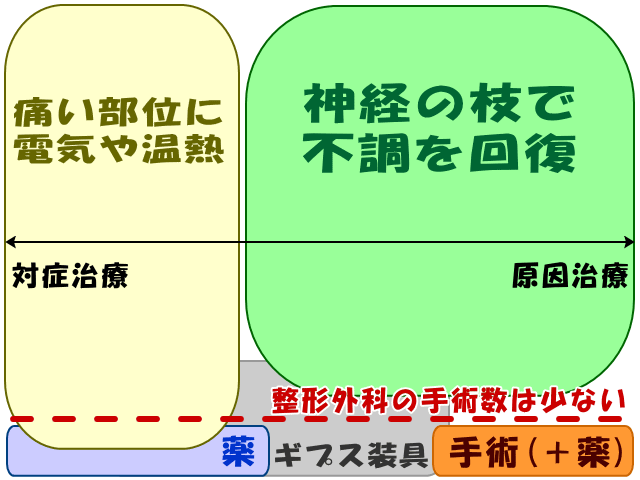
「お医者さんの手術がとても重要で、知識が高度なことは確かなんです。でも、実際に手術が必要な人はごく少数ですよね。」
「それに、鍼灸院や接骨院で痛みが治ってしまうので、実際には原因から治せているだろうと考えると、こっちの図のようになると思うんですよ。」
「慢性痛をもつ人は、病気やケガの人の10倍くらいいます。こうした実際の数を無視したイメージだと、痛みの原因ってわからなくなると思います。」
患者さんの混乱
「先輩は、慢性痛の原因って、なんだと思ってるんスか?」
「単なる不調=働きが弱いだけ、ということが多いと思いますよ。」
「えっ?ちょっと、何いってるかわらならいっス…。」
「たとえば、胃が重い人っていますよね。胃がもたれるから、胃カメラで調べても、何にも悪くないといわれるとか。」
「あんがい多いと思うっス。」
「お医者さんは、胃潰瘍や胃がんがないと、なんともないという、腱胃剤をくれるけれど、なかなかスッキリしない。」
「でも、『胃の六つ灸』という胃腸の自律神経の根もと付近のお灸をすると、元気になっちゃう。」
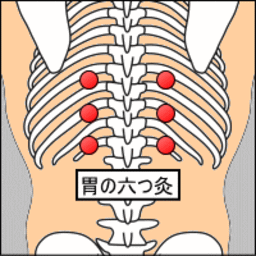
「あっ、それは知ってるっス。学校でやったっス。」
「同じように、腕や脚も、自律神経の根もとを刺激すれば、痛みとか不調が治っちゃう。」
「でも、不調なだけなら、病気じゃないじゃないスか。」
「そうそう。たいていの患者さんは痛みがあるだけ。病気じゃなくて痛みを治して欲しい。」

「患者さんにとっては、痛みの原因なんて関係ない。不調か病気かなんてわからない。だから、鍼灸、接骨と整形外科を混同しちゃうんです。」
「お医者さんに、病気やケガがないか調べていただくのはとても大切です。でも、痛みだけだとわかったら、痛みの原因となる不調を治さないと。」
不調を説明しよう
「解剖学からすれば、神経にそった痛みは、神経が絞めつけられていると考えがちです(神経絞扼(こうやく)といいます)。」
「でも、絞めつけられていないのに、神経の枝自体が調子が悪いことがあるんだと思います。胃腸や呼吸器が弱いような、体質のようなもので。」
「それが、げんきDASの痛みルートっスね?」
「そうなんです。お医者さんで異常なしといわれて、でも痛い、不調だというときには、げんきDASで測ってみるといいと思います。」
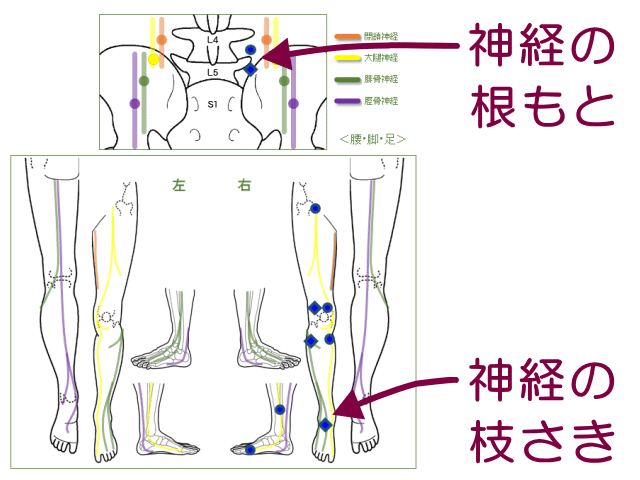
「そうでないと、オレみたいに、痛いところに電極はって、タイマー回して終わりになるっス。」
「それが普通ですよね。」
「でも、それじゃ慢性痛にあんまり効かないっスよ?治療器って、慢性痛には効果がないなって感じてる先生が多くないスか?」
「神経の根もとと神経の枝さきに電極を貼って、神経にそって刺激すると、違った効果があると思います。」
「もったいないですよね。痛いところに当てるだけだと、痛み止めの湿布と同じ考えのままです。慢性痛にはあまり効かないと思います。」
「慢性の痛みなら神経の不調、代謝の不調が原因だろう、という考えをちゃんと説明しないと、鍼灸や接骨の存在価値が伝わらないでしょう。」
「痛みルートの反応があるか調べるのって、オレたちの存在価値に関わるんスね。」

鍼灸、接骨でも原因治療
「整形外科の先生は、神経の絞めつけや炎症が無ければ、異常はない、異常がないんだから痛みもないハズ、という考え方かもしれません。」
「それって、痛みだけなら無視ってことっスね?」
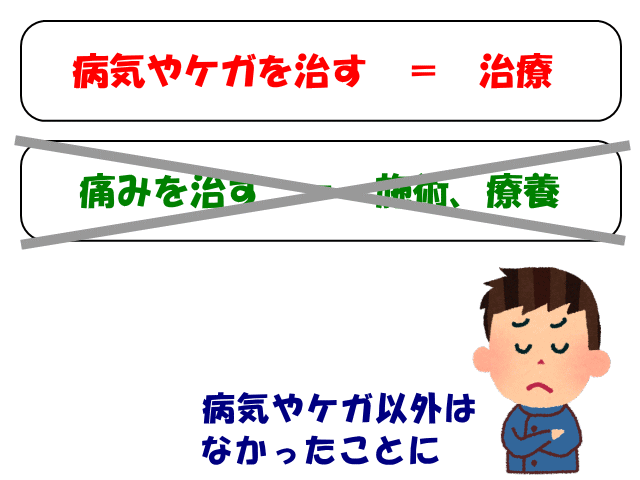
「そうかもしれません。げんきDASのような、不調のようすを把握する方法がないんですね。たいていの鍼灸師も同じですけどね。」
「それがわかれば、原因から治せるってわけっスね?」
「そうですね。鍼灸や接骨の先生は、自分達が症状を和らげる対症療法しかできないと思い込んでいる方が少なくありません。」
「でも、痛みの原因が病気ではなくただの不調なら、私たちが治すべきものだと思います。その方がずっと、患者さんも増えるはずです。」
「そうなるっス。薬や手術でなくても治るなら、患者さん増えるっス。」
「大事なのは、原因となる不調のようすを調べることですよ。」
具体的な使い方は?
「それで…、先輩、実際のトコ、何をするんスか?」
「えっ?」
「オレたち治療家の存在価値とか、よくわかったんスけど、何をしたらいいかぜんぜんわからないっス。」
「あっ、それはすみません。」
「具体的なところを教えて欲しいっス。たとえば、古里さんの肩こりはどうしたらいいとか、具体的に教えて欲しいっス。」
「治療器をどう使うんスか?根もとはわかるっスけど、枝さきってどう選ぶんスか?」
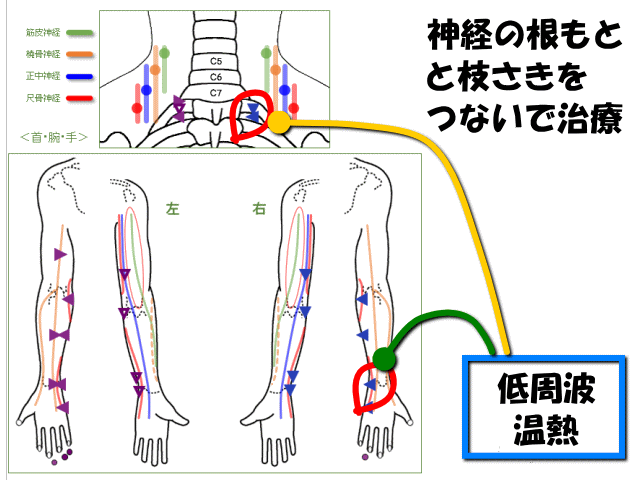
「そうですね、じゃぁ、げんきDASの画面について、一つ一つ説明しましょう。」
「それっス、それがイイっス。難しいのは、簡単な話の後でお願いしたいっス。」
そこだけ先生は、奥さんがおみやげに持たせた饅頭を自分で頬ばりながら、元気そうにいいました。
(2019年01月04日 公開)
次のお話
いよいよ具体的なげんきDASの使い方
