
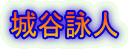
3
「おかえりなさい。今、おかず温めなおすから」
自宅のマンションに帰り着くと、いつもの通りに妻の響子が僕を迎えてくれた。
妻と子供はすでに食べ終わっている。
一人息子の修一は、テレビのバラエティ番組を見て笑い声を上げていた。
食卓の硬い椅子に座って待っていると、響子が皿をレンジから出して並べてくれた。
「そうだ。明日、飲み会が入ったから夕食は要らない。新人の歓迎会なんだ」
箸を持ちながら、僕が言うと、響子は一口お茶をすすって、言った。
「変な時期に新入社員が入ったのね。まだ3月にならないって言うのに……」
疑っている雰囲気は無かった。
「まあね。正社員じゃなくて、一時的な手伝いの契約社員だから」
すんなり嘘が出てくる。
罪悪感はほとんど感じなかった。
「それでさ、私言ってやったのよ……」
妻の言葉は僕の耳を通り過ぎていくだけだ。
適当に相槌を打ちながら、考えるのは明日の事だった。
適当な居酒屋で飲食したあと、二次会は昨日の店に行くのがいいかな?
それとも、二人きりの方がいいだろうか。
僕の気の無い返事に慣れっこになっている妻は、不機嫌になる様子も無く延々と話を続けている。
「修一、風呂は入ったの?」
僕が妻に聞くと、話の腰を折られた彼女は、ちょっと眉間にしわを寄せて、二人ともはいってるわよ、もう。
と言った。
ベッドの中で、僕が久しぶりに響子の背中をなでたのは、言い訳を作りたっかたらか。
時計はまだ12時を回っていない。
修一は自分の部屋で、とっくに寝息を立ててる頃だから、気になるものは何もないはずだ。
「どうしたのよ」
僕のいつもと違った雰囲気を察して、響子は振り向いた。
「久しぶりにどうかなって思ってさ」
オレンジ色のナイトライトの下で、響子の顔は一瞬不思議そうな表情になった。
「僕がもうそんな気無いって思ってた?」
「そうは思わないけど、私の気持ちはもうわかってるものと思ってた」
「男は時々どうにも我慢できなくなるんだよ」
「今までは自分で処理してたんでしょ」
その通りだ。
響子は、隣で横になる僕の振動をとっくに気づいてるはずなのだ。
「君は、もう全然その気がないって言うのか?」
僕の声には少しとげが含まれていたはずだ。
男の気持ちを理解しない妻に今までも何度も腹を立てていた。
その気持ちが不意によみがえったのだ。
「今はそんな気になれないのよ」
「じゃあ、口か手でしてくれないかな」
いつになく粘ってみる。
「勘弁してよ。疲れてるんだから」
いつもの台詞だった。
「僕が浮気してもいいのか?」
これも何度目かの台詞を言ってみる。
「家庭を壊さない程度ならいいかもね。そんな器用なことができればだけど」
ため息と共に響子が言う。
どうせできる訳が無いとたかをくくってるのだ。
男が家庭を壊さない気でも、相手のあることだから、そううまくいくとは限らない。
家庭を壊さない浮気なんてできないと思ってるのだ。
そう、男女の恋なら無理な話かもしれない。
しかし男同士なら?
どうせ結婚なんてできないのだから、家庭を壊すことはないだろう。
響子には想定外のことだろうな。
僕はべッドを出ると、キッチンに向かい、食器棚から取り出した小さめのグラスにウイスキーをたっぷり
注ぎ込んだ。
NEXT
![]()
![]()