
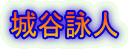
1
青いネオンサインの店の階段を一段ずつ上っていく。
ときめく胸を押さえながら、この店に初めて入った一ヶ月前を思い出した。
インターネットの同性愛関係を見ているうちに、自分の生活している街中にこのバーがあることを知って、
強く好奇心をかきたてられていた。
初めて異世界の門に踏み込んだのは、去年の忘年会の帰りだった。
酔った勢いと、胸に秘められた欲求不満で、何度か店の前を行きつ戻りつした後、意を決してこの黒い階
段を上ったのだった。
BAR-ローズビーズのドアは無愛想な黒いドアだった。
そこには店の名前も出ていない。
古びてきしむドアを押し開けて、僕は生まれて初めての世界に足を踏み入れた。
いらっしゃいませという言葉は、良く耳にするが、男の声で、女のようにシナを作った
その言葉は異様に聞こえた。
五分刈りに髭の彼のことを、マスターと呼んだ方がいいのか、ママさんといった方がいいのかわからない。
二十人も入れば満員になる程度の狭い店だったが、先客が三人ほどしかいなかった。
その三人が、一斉に僕の方を見る中、空いているカウンターに腰を下ろした。
「お客さん、初めてですよねえ 」
マスターは、そう言いながら僕の方に近寄って来た。
「ここに来るのは初めでだし、この手のお店に来るのも、実は初めてなんです」
用意していた言葉をすんなり言えたのが少し嬉しかった。
「へえ、初めてなの、お飲み物は何にします?
それとお通しはどうしましょうか。お腹は減ってるかな」
にこやかに聞いてくるマスターの印象は、一瞬感じた違和感を少し消してくれる。
「ウイスキーのロックをお願いします。食べてきたので……」
お通しにどういうのがあるのかわからないから言いよどんでいると、じゃあサラダにしましょうね、とカウンター
に置いてある笊の中から、切り野菜を皿に盛りだした。
奥では、一瞬こちらに興味を持った客達もすでに自分達の会話に戻っていた。
生で聞くオネエ言葉が耳をくすぐる。
静かに時間が流れる中、マスターが僕の前にオンザロックとサラダを並べた。
オンザロックを口に含んでゆっくり飲み込む。
「今迄で男の経験とかあるの?」
コップを拭きながらのマスターに聞かれた。
「いえ。全然無いんです。いろいろと想像はしてたんですが」
正直に答える。
「どういうタイプが好みなのかな? いい人がいたら紹介したりできるわよ」
いきなり核心をつくようなことを言われて、返答に困る。
好みのタイプなんて考えていなかった。
「ええと、まだ良くわかんないんですけど、痩せてる人はパスかな。それとあまり太ってる人も」
「じゃあマッチョがいいのかな?」
マッチョといえば、ボディビルダーみたいな筋肉質の男の事か。それもあまり好きじゃない。
「まあ、普通な感じがいいですね」
答えた後ロックを一口流し込んだ。喉を熱い液体が通り過ぎる。
「まだ右も左もわからないって感じね。雑誌でも見てみる?」
マスターはいったんカウンターから出て、店の奥にある棚から数冊のゲイ向け雑誌を持ってきてくれた。
目の前に二十センチくらい積まれた中から一冊を抜き出して開いてみた。
髭の生えた坊主刈りの太った男が、上半身裸で、腕組みしてこっちを見つめている。
横のページではふんどしをした、これも似たような体型の男がうっすらと毛の生えた背中を見せながら振り
向いていた。
こういうタイプが好きな人向けの雑誌なのだろう。
こっそりため息を吐いて別の雑誌を見てみた。
背広姿の男達が抱き合っていたり、さらに別の雑誌の中では若い長髪の男の子が裸で仰向けに寝てこっち
に悩ましい視線をよこしていた。
どれを見ても僕の感覚を呼び覚ましてくれるようなものは無かった。
そうしているうちに、数人が帰り、数人の客が入ってきた。
僕を入れて、五人の客だ。
週末だというのに、これくらいの客しかいないで、店はやっていけるのだろうか。
それとも、今日は偶然客の少ない日に当たったのか。
「どう? 好きなタイプいた?」
他の客と話していたマスターが近づいてきた。
「いや、なんかすごいですね。考えてみたら、タイプって無いんですよね。あえて言えば外見よりも中身かな。
頼りになる人がいいですね」
「なるほど。セックスより精神的なものが優先って感じかな?」
「あ、そうかもしれない。実はあまり性的な欲求って無いんですよ」
「まあ、まだお若いのに。ストレスのたまる仕事なのかな?」
「そうかもしれません。確かに」
マスターは僕をいくつくらいだと思ってるんだろう、と少し思った。
いつも僕はかなり若く見られる。
二十代半ばくらいに思われることが多かった。今年年男の三十五歳だというのにだ。
その日はその後少しだけマスターと話をして帰った。
いろんな淫靡な想像をしながら入った店だったが、思いのほかどうという事は無い、しかし他の騒々しいス
ナックなんかと比べて断然居心地のいい店の雰囲気を楽しんで、僕は階段を下りて帰路についた。
その後、その店のクリスマス会というのに出席してみた。
その日は前回とは打って変わってほぼ満員状態。こんな地方の都市のゲイバーに、これほどの客が集まる
なんて思ってもいなかった。
カウンターに席をひとつ見つけて座った後、水割りを飲みながら三千円で食べ放題の料理を軽くいただいた。
カラオケが絶えずかかり、隣の人と話すのも難しい状況だった。
マスターもさすがに忙しく、僕の相手などしてる暇は無い。
僕は適当に切り上げる事にした。
そして今夜が三回目だった。いったい僕は何を求めてこの店に来るんだろう。
好奇心は満足させられたはずだ。男に対して特に性欲を掻き立てられる事がない以上、ここに来るのは不要
なはずなのに。
きしむドアを開けて、見慣れた店に入ると、マスターが嬉しそうな笑顔を寄越してくれた。
「あら、エイト君いらっしゃい。久しぶりね」
この店では僕はエイトと名乗っている。愛車から取った名前だった。
常連さんも大体仮名を名乗ってるようだった。
先客が三人いた。
奥の方に年の離れたカップルが一組。手前には中年の背の高い男が、カウンターに肘かけてビールを飲んで
いた。
その男の奥に、ひとつ席を空けて座ると、オンザロックとサラダを注文した。
「ウイスキーのロックか。若い人には珍しいな」
左側に座ってる中年男が言った。
彼を見ると、人懐っこい笑顔をしていた。
「そうですか? 普通だと思いますけど」
「いや、最近はビール飲む人がほとんどだろ、ウイスキーにしても水割りがほとんどだから」
彼の声は聞いていて耳に心地よかった。低音でもなく、かといって高いわけでもないが、シャープな感じの声
だった。
サラダを口に含んでかむと、ドレッシングの酸味がさわやかに広がった。
「こっちに来いよ。ゆっくり話そうよ」
彼は僕との間の空席を叩いて言った。
ひょっとしてナンパされてるのかな? 気恥ずかしさとともに、僕は席をひとつ横にずらせた。
「若いね。二十代後半くらい?」
まあそんなところですと答えながら、この人はいくつ位だろうと考えた。
この店に来る客には珍しく長髪にしている。適度に日焼けした顔は精悍で、目じりのしわも似合っていた。
四十代半ばというところだろうか。
「結婚してるんだね」
彼が僕の左手の薬指に視線を送って言った。
「ええ、一応」
と答えると、マスターが聞きつけて、うっそー信じられない。と叫んだ。
「ええ? ばればれだと思ってましたけど」
マスターに見えるように左手を掲げて見せる。
「エイト君って、バイなわけ?」
マスターの問いに、かも知れませんと答える。
本当に僕はそうなのか? 自分では良くわからなかった。
普通に女性が好きで、恋愛をして結婚。
ここまでまったく普通の生活をしてきたのだ。
でも、心の中に何か満たされないものをずっと感じていたのは事実だ。
性的に満たされないものだった。
それが知りたくてこの店に足を運んでみたのだったが、今の所収穫はゼロだった。
「エイトって言うんだ、ひょっとして車の名前から?」
マスターが僕をそう呼ぶのを聞いた彼は、コップに残っていたビールを飲み干した。
自然と僕は彼のビール瓶を持って、そのコップに継ぎ足してあげる。
「ええ、良くわかりましたね。世界唯一の生産中のロータリーエンジン車ですよ」
「いい車に乗ってるんだな。俺は荒木って呼んでくれよ。近くにおでんの美味しい店があるんだが、行かな
いかい?」
おお、お誘いがきた。心臓の鼓動が早くなるのを感じる。
これは完全にナンパじゃないか。自分が女の子にでもなった気分だった。
でも、さっき会ったばかりの男について行くのは、なんだか尻軽な気がする。
それに、帰る時間も迫っていた。
午後七時に始まった同僚の厄入りの会が終わったのが、9時半、いまは10時半を時計の針はさしている。
家には11時過ぎ程度に帰り着きたかった。
宴会などがあっても最近はあまり二次会まで行くことがなくなっていた。
妻に変に思われるのは避けたい。
だから、いつもそんな宴会の後に此処によっても一時間程度で帰るようにしていたのだ。
それを告げると、彼はすんなり引いて、メモ用紙を取り出した。
ボールペンでなにやら走り書きしている。
多分電話番号か何かだろうと思っていたら、予想通り、そのメモにはメールアドレスが書かれていた。
「また飲もうよ。よかったらメールくれよ」
彼はメモを僕に押しやると、するりと席を立った。
店の入り口近くにあるコート掛けから、カーキ色のモッズコートを茶色のジャケットの上から羽織った彼は、マス
ターにまた来るよ、と声をかけてカウンターの上に千円札を二枚のせ、店を出て行った。
引き際が鮮やかだ。
「荒木さんって、格好いいですよね。もてるんでしょうね」
心の中に燈った灯りをいとおしむ様にしながらマスターに話しかけてみた。
「女にはもてるみたいだけど、あまり男と付き合ってるのって見たこと無いなあ」
「女に? 荒木さんってバイなんですか?」
「良くわからないわね。でも奥さんがいたのは事実。数年前に亡くなっちゃったらしいんだけど」
「でも、ここの常連さんなんでしょ。じゃあ男好きなんですよね」
僕は何でこんな事を聞いてるんだろう。
「君も自分の事良くわかってないって言ってたじゃない? 彼もそうなのかもね」
マスターが僕のグラスを指差した。
「おかわりは?」
いえ、もういいですと答えて、N2Bジャケットから財布を取り出すと、僕はお勘定を済ませた。
NEXT
![]()
![]()